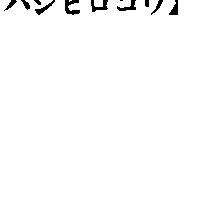ハシビロコウ (嘴広鸛)
shoebill
whale-headed stork
Balaeniceps rex
コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。この科はハシビロコウ1種だけからなる。全長約1.2m。形態,大きさともコウノトリ類に似ているが,大きな頭と木靴のような形の異常にぶ厚いくちばしが特徴。英名は,いずれもこの奇妙なくちばしと頭に由来する。羽色は全身スレート灰色で,背は光沢のある緑色を帯びている。雌雄は同色,幼鳥は褐色に富む。アフリカ中央部の奥地に分布し,主として白ナイルの上流や熱帯東アフリカの人跡まれな沼沢に生息している。ふつう単独かつがいですみ,習性はかなり夜行性である。昼間はヨシやパピルスの間で休み,夕方出て魚,カエル,小型のヘビ,その他の水辺の小動物をあさる。ハシビロコウのくちばしは,とくにハイギョやナマズを捕食するのに適応しているといわれている。飛ぶときは,サギやペリカンのように,首をZ字形に縮めて飛ぶ。鳴管の筋肉が退化しているため,鳴声はほとんど出さず,かわりに上下のくちばしをたたき合わせてカタカタと鳴らす習性がある。巣は湿地の中の草の間に水生植物を積み上げてつくり,大きなものは外側の直径2.5m,産座の直径1mに及ぶ。1腹の卵はふつう1~2個(まれに3個)。ただし,雛として育てられるのは,ほとんどの場合1羽だけである。抱卵期間は約30日。雛は少なくとも3ヵ月間巣にいて,両親が主としてオタマジャクシを与えて育てる。この鳥の類縁関係についてはいろいろな意見があるが,原始的なコウノトリという説が有力である。
執筆者:森岡 弘之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ハシビロコウ
Balaeniceps rex; shoebill
ペリカン目ハシビロコウ科。全長 1.2m。木靴のような形をした厚い巨大な嘴をもつ鳥で,1種で 1科を構成する。羽色は濃い灰色で,背中は緑色を帯びる。アフリカ固有種で,中央部のスーダンから南のジンバブエまでの沼沢地にすみ,ホワイトナイル川とその支流域にもっとも多く生息する。おもに夜間活動し,普通は単独かつがいでいる。巣はアシ原の中などに草を積み上げてつくり,白色の卵を 1~2個産む。ハイギョやナマズをはじめ,魚類,トカゲ,ヘビなどなんでも食べる。コウノトリと同じく上下の嘴をたたき合わせてカタカタと音を出すが,鳴くこともある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ハシビロコウ
はしびろこう / 嘴広鸛
shoebill
whaleheaded stork
[学] Balaeniceps rex
鳥綱コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。この科Balaenicipitidaeの唯一種で、形態、大きさともにコウノトリ類に似ているが、大きな頭と木靴のようなかっこうの巨大な嘴(くちばし)が特徴である。全長約1.2メートル。羽色は全身スレート灰色で、背には緑色光沢がある。雌雄は同色、幼鳥は褐色に富んでいる。白ナイル上流地方の人跡まれな沼沢に分布しているが、数は多くない。昼間はアシやパピルスの間に隠れていて、夕方出て魚、カエル、小形のヘビなどを捕食する。魚類では肺魚やナマズ類をよくとる。巣は湿地の地面に枯れ茎や枯れ葉を積み上げてつくり、1腹1、2個の卵を産む。抱卵期間は約30日。雛(ひな)には主としてオタマジャクシを与えるといわれている。世界の動物園での繁殖例はない。国内では上野動物園、千葉市動物公園、伊豆シャボテン公園で飼育例がある。
[森岡弘之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ハシビロコウ
学名:Balaeniceps rex
種名 / ハシビロコウ
目名科名 / ペリカン目ハシビロコウ科
解説 / 単独でいることが多く、水辺に何時間もじっと立ち、ナマズやハイギョが近づくと、体ごとたおれこんでとらえます。くちばしをカタカタいわせるクラッタリングをして、なかまとコミュニケーションします。
全長 / 152cm
食物 / 魚、両生類
分布 / 中央アフリカ
環境 / 川、湖沼、湿原
絶滅危惧種 / ★
出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報
Sponserd by