よし(読み)ヨシ(その他表記)reed grass
精選版 日本国語大辞典 「よし」の意味・読み・例文・類語
よし
- 〘 感動詞 〙 承知や承認、また、決意、命令などの意味を表わして、相手のことばに応じて発することば。わかった。
- [初出の実例]「はづかしくさへ有りて泣くをみて、『よし、いかがはせむ。女知り侍らば、物なおぼしそ』」(出典:宇津保物語(970‐999頃)俊蔭)
よ‐し
- 〘 間投助詞 〙 ( 間投助詞「よ」「し」の重なってできたもの ) 文節末に添えて詠嘆を表わす。
- [初出の実例]「はしき予辞(ヨシ) 我家の方ゆ 雲居立ち来も」(出典:日本書紀(720)景行一七年三月・歌謡)
改訂新版 世界大百科事典 「よし」の意味・わかりやすい解説
ヨシ (蘆/葭/葦)
reed grass
(common)reed
Phragmites communis Trin.
いたるところの水湿地に群生するイネ科の多年草。地下に長くはった根茎を縦横に出し,茎は直立して高さ1~3mになり,円柱形で多数の節がある。葉は茎の節につき,幅の狭い披針形で,やや硬く,灰白色を帯びた緑色で,先がとがり,上部は垂れる。夏から秋にかけて茎の頂に長さ40cmに及ぶ大型の円錐花序を抽出し,その上部と多数の長い枝はやや下向きになる。小穂は小枝上に多く密生し,淡い褐色で,長さは10~17mm,2~4個の小花が有り,最下の小花は雄性,他は雌性で,長い白い毛が生えている。北海道から琉球まで日本全土に多く見られ,全世界の湿地にくまなく分布している。別名をアシというが,発音が〈悪し〉と同じであるため,その反対の意味の〈良し〉に古くに言いかえられたといわれる。またハマオギともいう。日本ではヨシに似た種類にツルヨシP.japonica Steud.とセイタカヨシP.karka Trin.がある。前者は砂地や河川の縁に生え,地上に長い走出枝を出すので良くわかり,後者はヨシより丈が高く,ヨシが枯れる初冬まで緑色をしており,小穂の状態も異なる。
ヨシ類の茎は葭簀(よしず)や簾(すだれ)にするほか,屋根や編んで壁などにも使われることがある。若芽は食用になり,アイヌ人が用いるほか中国でも蘆筍(ろしゆん)と呼ばれ用いられた(ただし,近年台湾で蘆筍といって缶詰にして輸出するものはアスパラガスである)。茎は他の大型のイネ科植物,例えばムラサキススキやススキ等のそれとともにパルプ原料に用いられ,良質の紙ができるが,解離がややむつかしいという。和楽器の笙(しよう),ひちりきにも使われる。また漢方薬の蘆根(ろこん)はヨシの根茎で,健胃・利尿・消炎剤とされる。
執筆者:小山 鐵夫
神話,伝説
ギリシア神話では,ニンフのシュリンクスSyrinxが牧神パンに追われヨシに変身したといわれる。追ってきたパンがこれを折って笛を作り,彼女を悼んで吹き鳴らしたことから,ヨシは音楽の象徴となった。エフェソスにはパンが最初にこの笛を収めた洞があり,処女か否かを判定する場所に用いられた。真の処女はシュリンクスの調べが聞こえて扉があき,松の冠を戴いて出てくることができるが,偽りの処女は帰還できなかったと伝えられる。またオウィディウスの《転身物語》には,ロバの耳を持つミダス王の秘密を知った髪結師が,穴を掘って〈王様の耳はロバの耳〉とささやき,あとを埋めて安堵したところ,穴の上に生えたヨシが風にそよぐたびに秘密を口外したという話がある。そのために告げ口や無分別のたとえに使われるが,他方《イソップ物語》では弱々しいヨシが実は嵐に最もよく耐えるという,日本の諺の〈柳に雪折れなし〉と同様の寓話も語られている。このイメージはパスカルの名言〈人間は考えるヨシ(アシ)である〉につながっているものかも知れない。
執筆者:荒俣 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「よし」の意味・わかりやすい解説
ヨシ
→関連項目蕪栗沼|渡良瀬遊水地
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「よし」の読み・字形・画数・意味
【
 】よし
】よし
字通「 」の項目を見る。
」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「よし」の意味・わかりやすい解説
ヨシ
よし
→アシ
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「よし」の意味・わかりやすい解説
ヨシ
「アシ(葦)」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のよしの言及
【リード】より
…植物のアシ(蘆)の意。またそこから転じて気鳴楽器を鳴らすための振動体のこと。アシやダンチク(暖竹)などの茎には適当な弾力があり,これを加工した小薄片がある種の管楽器の音源に古くから用いられたが,素材の名である〈リード〉がいつか振動体の意味にもなり,材質と無関係に使うこともできる用語になったのである(たとえば金属製,合成樹脂製などの振動体もリードと呼んでいる)。諸型式のものがあるが,普通は管の入口に付けられていて気流の通過で振動し,気流にパルス状の断続を与える。…
【湿原】より
… 沼沢湿原は,湖沼の岸や河川の排水の悪い氾濫(はんらん)原などにみられ,栄養物質に富んだ水に涵養(かんよう)され,泥炭は集積しない。ヨシ原に代表されるが,オギはヨシよりも浅いところに,マコモ,ヒメガマは深いところに出現する傾向がみられ,沼沢植物の分布は水深と関係する。 泥炭湿原は,植物遺体の分解量が生産量を下回るためヨシ,スゲ類,ミズゴケ類などの植物遺体が集積し泥炭化するところに形成されるので,寒冷な亜寒帯・冷温帯に多い。…
※「よし」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...


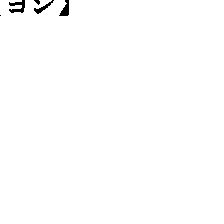
 】よし
】よし