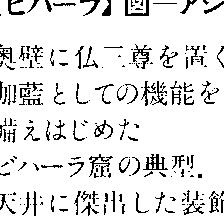ビハーラ
vihāra
サンスクリットで散策すること,およびその場所をさす原義から,仏教やジャイナ教の出家者の住房,さらには僧院,精舎を意味し,音訳して毘訶羅(びから)という。出家修行者は元来は遊行を続け定住せず,遊行が不可能な雨季には仮設の住房で共同生活を送った。しかし釈迦の在世中から定住する傾向が生まれ,やがて常設の僧院が出現した。さらに主として在家信者が崇拝していたストゥーパと僧院とが結びつき伽藍が成立した。その定型化した形式は,窟院では方形の広間の三方に小部屋を,構築した僧院では中庭の四方に小部屋を並べ,広間や中庭は比丘たちの集会に用いられた。さらに後には,3~4世紀のナーガールジュナコンダに見られるように,僧院内にストゥーパや仏像をまつる祠堂を設けたり,5~6世紀のアジャンター窟院のように,奥壁中央の仏堂に本尊をまつって,僧院のみで伽藍の機能を備えるものも現れた。しかし僧院は比丘たちのみの閉鎖的な空間として,ストゥーパの区域とは隔離されていた。
→寺院建築
執筆者:肥塚 隆
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ビハーラ
vihāra
古代インドにおける仏教またはジャイナ教の僧や尼僧が,修行のために集団生活をした宿舎もしくは道場。僧堂,僧房,僧坊,精舎などと訳される。狭義には寺院内の居住用施設をさし,共存するストゥーパ (仏塔) ,チャイティヤ (祠堂) などと区別されるが,広義には寺院全体をいう。煉瓦造,石造,木造などによって地上に建造されたほか,石窟として山や丘に開掘されたものもある。ビハーラを含む石窟寺院はアジャンタ,エローラ,カールリーをはじめ,中西部インドで前2~後8世紀頃数多く造営され,その影響は中央アジアや中国にまで及んだ。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ビハーラ
インドの僧房。方形の中庭をとりまく僧房列からなり,僧房の前に回廊がある。石窟寺院では2〜3層のものもあり,エローラ石窟のものが名高い。
→関連項目アジャンター
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のビハーラの言及
【寺院建築】より
…やがて定住者の修道院としての機能や組織がととのえられてゆくが,この傾向はすでに釈迦在世中から見られるらしい。[ビハーラ]とは比丘の住房を指し,後に語義が拡大されて僧院とか精舎を意味するようになった。釈迦在世中の僧院として[祇園精舎]や竹林精舎などの名が文献上知られるものの,その実態は明らかでない。…
【精舎】より
…サンスクリットの[ビハーラ]の漢訳語で,仏教寺院のこと。仏道に精進する者が住む舎という意味。…
※「ビハーラ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by