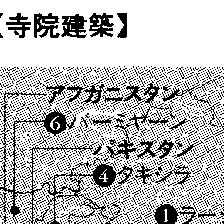改訂新版 世界大百科事典 「寺院建築」の意味・わかりやすい解説
寺院建築 (じいんけんちく)
仏教のための建築群で,本来は僧尼の組織を伴う。仏教がインドで成立した当初は,仏陀を中心とした僧団の住舎に大衆集会の広場をもち,サンガーラーマsaṃghārāma(僧園,衆園(しゆおん)),アーラニヤāraṇya(寂静処)などと呼ばれた。後,仏陀の墓を示すストゥーパstūpaを中央に置き,周囲に僧房がある形となる。さらに中央堂の上をストゥーパとし,室内に仏像をまつる形ができた。これが中央アジアを経て後漢代(1~3世紀)に中国に伝えられた。塔殿と僧房その他を有する建築群に官衙(かんが)や宮宅の形が応用されて,官庁の意である寺という呼び方が使われ,外来宗教(今日ではキリスト教を除く)の施設が寺と呼ばれた。院は障壁で包まれた一部の意で,寺の一部分を指したものである。迦葉摩騰(かしようまとう)が白馬に経典を積んで来って初めて漢に仏典をもたらし,外客接待施設の鴻臚寺に入り,後に仏寺を建立して白馬寺と呼ばれたという説話がある。仏陀をまつるところを指す浮屠祠(ふとし)の名は後漢代から,学舎の意の精舎も魏・晋代(3世紀)から用いられた。南北朝(5~6世紀)ころから浮屠は仏塔のみを指すようになり,寺院全体はsaṃghārāma,āraṇyaの音を移した僧伽藍(そうぎやらん)(僧伽藍摩ともいう),阿蘭若などとも呼ばれ,また伽藍,蘭若などと略称されることが多くなった。
形態と機能の変化
インドは乾季と雨季が明確で,乾季には広場で儀式や集会が行われ,雨季には僧房で安居の行をし,また仏陀を礼拝するのが伽藍のおもな機能であったが,中国では雨雪や極寒期もあって,一山大衆を屋内に収容し儀式や教学の集会を行う必要が生じた。そのため大面積の建築をもつ官衙(寺)や宮宅の建築群が教団に応用されるようになった。
伽藍配置の原形
官衙や宮宅は南面し,中心部に内庭があり,その北に正殿を置いたり,3方から内庭を囲む三合院形をとった。内庭中央に高層の塔殿を置くことが初期伽藍の通例となったと思われる。やがて塔殿が仏塔と仏像をまつる殿堂に分離し,塔を中心前面に置く配置の先駆となったであろう。複数の塔をもつ伽藍も南北朝には現れたらしい。仏に対する儀式は塔や仏殿前の広場で庭儀として挙行され,僧の集会は大殿の中で開かれた。時刻や法事を告げる鐘鼓の楼,経典を安置し拝礼する経楼を置く。これらの聖域をめぐって回廊や築地塀を造り,四方に門を開いた。最外周に頑丈な塀をもつのは中国の官衙,宮宅の通例をうけたものである。全体にも個々にも宗教建築としてのシンボル性,崇高性,威厳,華麗さが求められた。
教団の建築
寺院の教団としての財政基礎が,個々の僧の乞食行によらず寄進された荘園領経営によることになると,管理機構が大きくなり,政所,倉庫が設けられる(政所院)。当然,施入物,什物,資財の倉や監理所(正倉院)も置かれ,仏寺機構は官衙と類似する。食作法や炊事の食堂院,清浄のための浴室(温室)や厠(かわや),法衣や建築物の維持管理,仏像仏画の製作や経典書写の作業所,花果蔬菜の苑院や花園院,雇民や奴婢の賤院など,寺地と施設を備えるようになった。このような多角的機能を備える内容と形式が朝鮮三国を経て日本に伝えられた。一方,インドでは塔の基壇が階段状に拡大する傾向も生じ,これらを別の堂や僧房で取り囲む形式ができて南方諸国などに伝わった。曼荼羅など中心性強調の構図と互に影響して発達し,ヒンドゥー教寺院にも影響を及ぼした。
→寺院
執筆者:沢村 仁
インド
仏教の比丘,比丘尼は遊行僧とも呼ばれるように,元来は定住せず伝道の旅を続けたため,住房を必要としなかった。ただし旅行が不可能な夏の雨季には仮小屋を建て,一時的に共同生活を送った。都市の近郊では富裕な信者が林園を提供した。これが衆園(しゆおん)saṃghārāmaであり,音訳の僧伽藍摩は伽藍の語源となった。衆園には仮小屋とともに常設的な建物も寄進された。やがて定住者の修道院としての機能や組織がととのえられてゆくが,この傾向はすでに釈迦在世中から見られるらしい。ビハーラとは比丘の住房を指し,後に語義が拡大されて僧院とか精舎を意味するようになった。釈迦在世中の僧院として祇園精舎や竹林精舎などの名が文献上知られるものの,その実態は明らかでない。ただラージギル(ラージャグリハ)では,釈迦時代の名医ジーバカが寄進したというマンゴー園の精舎の遺構とされるものが発掘された。これにはストゥーパや祠堂(チャイティヤ堂)はもとより比丘の個室にあたるものもみられず,後世の僧院とはまったく様相を異にする。
僧院とともに伽藍を構成するもう一つの基本要素はストゥーパである。ストゥーパは仏教以前の墳墓に起源し,仏教徒のそれは仏滅直後に釈迦の遺骨をまつるために造立されたのにはじまる。やがて仏教徒の専有物であるかのごとくその造立が盛んになるが,それを推進したのはもっぱら在家信者であった。このようにストゥーパと僧院とは,元来別個に発生したものである。
やがて比丘たちもストゥーパを受容するようになり,ストゥーパと僧院よりなる伽藍が成立するが,その初期の形態はガンガー(ガンジス)平原の古い例が知られていないため不明である。前2世紀後期から盛んになる西部インドの石窟寺院は,内部にストゥーパを安置した祠堂窟1窟と比丘の住房である僧院窟数窟とを基本単位とする。僧院窟は紀元前後までには広間の3方に数個ずつの房室を並べる整然とした形式をとるようになる。初期の石窟には木造建築を忠実に再現した形跡があり,それ以前の寺院形式を推測する手がかりとなる。野外の建築寺院としてはタキシラの諸遺構が最古の例であり,古いものは1世紀にさかのぼる。2世紀には方形の囲壁の内側四辺に多数の房室を並べ,内庭を比丘たちの集会堂とし,一方にのみ狭い入口をもうけるという広大な僧院が現れた。このような四面僧坊はナーランダーやナーガールジュナコンダその他にも見られるように,ガンガー平原や南インドにまで普及し,以後ながく僧院建築の典型となった。仏像が一般化するとともに仏堂も出現するが,伽藍配置の上からはあくまでもストゥーパと僧院とが二大基本要素であることは,インド亜大陸の全時代を通じて変わることはない。しかもストゥーパの区域と僧院とは厳格に区画され,僧院は比丘たちのみの閉鎖的な区域であった。僧院内にストゥーパを造立する場合もあるが,それは比丘たちのみの礼拝所であり,別に信者たちも参拝するストゥーパが必ず造られた。なお,伽藍は都市の近郊や通商路に近いところ,山岳寺院も比較的登りやすい山腹が選ばれ,日本の密教寺院のように深山に位置するものはない。また方位については明確な規定がなかったようにみえる。構築寺院の用材は,石材が主で煉瓦もあり,木材も古くは用いられたが現存しない。
インド亜大陸の南に浮かぶスリランカへは,前3世紀に仏教が伝えられた。スリランカの寺院建築は南インドの影響を濃厚に受けながらも独自の展開を示し,やがて東南アジアに強い影響を及ぼした。スリランカの寺院建築に最も顕著な特色はストゥーパである。ダーガバdāgabaと呼ばれ,インドの覆鉢塔の初期の形式をながく保持し,傘蓋は円錐形の相輪となっている。大規模なものが多く,欄楯(らんじゆん)に代えて列柱をめぐらすなど独自の特色も備えている。アヌラーダプラのアバヤギリ塔,ジェータバナ塔,ルワンウェーリ塔など基壇径が70~100mに及ぶ巨大な煉瓦造のストゥーパがある。また仏堂としてはポロンナルワのランカーティラカ寺(12世紀)がある。煉瓦造でボールト(穹窿)天井をもち,創建時(前1世紀)は9層であったと伝える。現在もその初層の石柱1600本が残されている。
→ヒンドゥー教美術
執筆者:肥塚 隆
東南アジア
東南アジアの歴史時代の建築(遺構)はほとんどが宗教建築であり,インドの宗教であった仏教とヒンドゥー教の伝来にともない,その両宗教に奉仕するものとして建てられた。したがって,古ければ古いほど,インドの建築からの影響を強く受けており,時代がたつにつれて,東南アジア各国固有の建築様式を生みだしていった。これが東南アジアの建築に見られる歴史的な展開の特徴である。ただし,インドの南にあるスリランカ建築からの影響も忘れることはできない。スリランカは東南アジアに流布した上座部仏教の発祥地であり,その信仰とともにスリランカ風の仏教建築が東南アジアの各地域に伝わった。特にスリランカ様式の仏塔の形体は,ミャンマーとタイの建築に著しい影響を与えた(パゴダ)。ミャンマーでは特に11世紀以降のパガン朝(11~13世紀)に出現し,タイでは13世紀以降のスコータイ朝(13~15世紀)に現れる。
東南アジアの過去の建築で現在も残っているものはほとんどが石造建築で,切石ブロックの積上げによったもの,あるいは煉瓦建てである。木造建築は朽ちやすいため,19世紀以降に建てられたものしか残っていない。インドと同様,東南アジアの石造建築は寺院,霊廟などに限られ,一般の民家や王宮でさえも木造建築であった。この石造建築で古いものは5世紀ころのものが発見されているが,ほとんどが基壇の部分だけしか残っていない。しかし,9世紀以降のものはその基壇のみならず,上部までよく残った建築が各地で発見されている。その代表的なものとしては,インドネシアの中部ジャワに見られるボロブドゥールやプランバナン遺跡群などの霊廟(チャンディ)建築である。ヒンドゥー教の遺構には南インドのパッラバ朝(3~9世紀)の建築と類似した点が多く認められる。また仏教建築には東インドのパーラ朝(8~12世紀)に見られる密教建築のプランを思わせる点が認められている。
カンボジアの古代寺院建築でも,7,8世紀を中心に,南インドのパッラバ朝の建築を思わせる様相が見られる。これらの遺構はヒンドゥー教のもので,先述のインドネシアの場合と同様に,その起源はおもに南インドに発していた。このカンボジアのクメール族の建築の代表的なものにはアンコール・トム,アンコール・ワットの遺跡群があり,これらは隣のベトナム中部のチャンパ王国(2~15世紀)の建築と類似し,また11世紀以降のタイ建築に大きな影響を与えている。その主軸はクメール語で〈プラサート〉と称する塔堂で,上へ上へと高く積み重ねた砲弾状の塔である。このように,インドシナにおいてはクメール建築のおよぼした影響は大きい。
執筆者:伊東 照司
中国
中国の宗教建築には,国家自身が挙行する祭祀儀礼のための壇や,政治教理に直接かかわりをもった儒教の廟を別として,仏教の寺,道教の道観,イスラムの寺院(モスク),および各種の民間信仰の祠廟などさまざまなものがある。また,実例はすでに失われたが,歴史上には景教(キリスト教ネストリウス派),マニ教,祆教(けんきよう)(ゾロアスター教)などの寺院が建てられた時期もあった。
仏寺
仏教は漢代にインドから伝来した。〈寺〉の語は本来官署を指したが,後漢明帝の感夢求法説に,インドから初めて仏像・経典が将来されたという地を,のちに仏寺に改めたのがその始源であり,白馬寺の前身と伝えられる。文献にインド系の建築様式がみとめられる最古の例は,後漢時代末に笮融(さくゆう)が徐州に建てた〈浮屠祠(ふとし)〉で,金色の仏像をまつる九重銅槃(どうばん)の相輪をいただいた楼閣建築であった。浮屠は浮図とも書き,のちに〈塔〉の名で呼ばれる中国独自の仏教建築の類型の基型をあたえたが,初期における機能はむしろ仏殿に近いものであった。南北朝時代にはいり,仏教が社会的に普及するようになると,数多くの仏教建築がつくられ,500以上の仏寺を擁した南朝の建康(南京)や,1000をこえる仏寺が林立した北魏の洛陽のような都市も出現した。なかでも梁の武帝がしばしば捨身した同泰寺や,塔刹(とうさつ)に30重の承露盤をそびえ立たせた北魏洛陽の永寧寺九重木塔などは,歴史上に名高い仏教建築である。
初期の伽藍は仏陀を供奉する建物を中心に構成されたが,仏舎利信仰の高揚とともに,仏舎利をまつる塔と仏を安置する仏殿とがそれぞれ独立分離し,形態的には塔を中心とする伽藍から仏殿中心の配置へ変化したようである。南北朝時代には,貴族住宅を喜捨して仏寺とするものが数多く現れ,仏殿と講堂を前後にならべる配置で,塔を有するものは少なかった。また,これらの中国化された寺院建築のほか,インド直系の形態を色濃く反映した石窟寺院も当時さかんに開鑿(かいさく)され,いまも雲岡,敦煌,竜門などの各地に遺構が現存する。隋・唐時代にも都城の大興(長安)に数多くの仏寺が建てられたのをはじめ,各地にさかんに寺塔が建設された。唐代以前の寺院建築は,会昌の廃仏(三武一宗の法難)や火災などでほとんど失われ,今日に伝わるものはきわめて少ないが,晩唐以降の木造寺院建築遺構は,都城,宮殿,壇廟の古い実例が残存しない中国建築の,様式,技術的発展を知るうえでの限られた貴重な資料である。現存する木造の遺構では,小規模ながら南禅寺大殿(山西省五台山。唐,782),広仁王廟大殿(山西省芮城。唐,831)が古く,これに次ぐ仏光寺大殿(山西省五台山。唐,857)は間口7間,寄棟造の本格的規模をもつ。くだって独楽寺観音閣(天津市薊県。遼,984)は楼閣建築の代表的遺構。また,華厳寺(山西省大同),善化寺(同),隆興寺(河北省正定)には遼・金・宋時代の遺構が数棟ずつ現存する。塔は,塼造(せんぞう)に最古の嵩岳寺塔(河南省登封。北魏,520)をはじめ多数,石造に神通寺四門塔(山東省歴城。東魏・隋)ほか多数,木造に仏宮寺釈迦塔(山西省応県。遼,1056)などの遺構がある。このほか,元代以降に盛行したラマ教の建築は,チベット族のもの以外では河北省承徳の外八廟の建築群が代表的で,一般の仏教建築とはまったく様式を異にする。
道観
道教の寺院は一般に〈観〉と呼ばれ,遺構の数では仏寺に遠く及ばないが,随所に広範な影響をとどめる。ただし,史上に名高い前漢の壇祠や北魏,隋,唐の各祠観,北宋の玉清照応宮などはいずれも失われ,建立年代の古いものは少ない。現存遺構に関する限りでは,伽藍配置,平面構成などの面で仏寺との著しい差異は希薄である。木造最古の遺構は晋祠(しんし)聖母殿(山西省太原。北宋,1023-32)で,飛梁という十字形石橋を架けた方池を前面に掘った東向きの自由な配置をとる。永楽宮(山西省永済。現在は芮城に移築)は唐の呂洞賓の祠に建てられた典型的な道観遺構で,かつての壮大な規模は失われたものの,無極門,三清殿,純陽殿,重陽殿と中軸線にならぶ元代1262年から建立の建築群が現存し,とくに華麗な壁画で知られる。
イスラム寺院
イスラムは唐代に伝えられたといい,とくに元代以降はさかんになり,各地に漢名を清真寺という礼拝寺院が数多く建てられた。年代の古い遺構としては広東省広州の懐聖寺光塔が,年代に諸説あるが,ミナレットの原型を忠実に伝えた,螺旋階段をもつ塼造尖塔として代表的。福建省泉州の清浄寺(本来は聖友寺)にはモスク直系の半球ドームを塼積みにした大門とドームの失われた礼拝殿がある。また,明代建設の西安の清真寺には木造の省心楼(ミナレット),礼拝窰龕(ミフラーブ),宣喩台(ミンバル)を設けた礼拝堂などがあり,北京,成都,昆明など各地の清真寺もまた平面,配置,用途を教義に従いながら,漢式の木造建築を採用した例が少なくない。
執筆者:田中 淡
朝鮮
朝鮮半島への仏教の伝来は三国時代にはじまる。高句麗に372年,百済には384年に相ついで伝えられ,新羅にも同じころに僧侶の個人伝道によってもたらされたが,迫害を受けたのち527年(法興王14)に国教として受容される。
三国時代
高句麗では〈平壌九ヶ寺〉をはじめ多くの寺院が記録にあらわれ,寺院址には平壌清岩里廃寺,大同郡上五里廃寺などが知られる。伽藍配置は中央に平面八角形の塔を据え,三金堂を東西北面に配置する。この形式は漢代の天文占星思想に由来するものとして,初めは宮殿址と考えられたが,日本の飛鳥寺の伽藍配置と同形式であることが明らかになって寺院址とされた。百済では公州と扶余に寺院址を残し,遺構には扶余定林寺址五重石塔,益山弥勒寺址多層石塔がある。伽藍配置は中門,塔,金堂,講堂を一直線上に置いた百済式伽藍で,日本に波及して四天王寺式伽藍と呼ばれる。定林寺址,金剛寺址,軍守里廃寺は中門と講堂を回廊で結び,金堂を囲う四天王寺式伽藍であり,弥勒寺址は回廊が金堂と講堂の中間で閉じる日本の山田寺伽藍と同形式である。東南里廃寺は塔がなく,金堂を中心にして中門と講堂を回廊で結ぶ形式で,日本には紀寺に例がある。古新羅はその固有の文化,伝統の強さから仏教の受容は遅れたが,その後の寺院造立は最も盛んであった。興輪寺,皇竜寺,永興寺,祇園寺,実際寺,三郎寺,霊妙寺,芬皇寺などが知られ,芬皇寺に塼塔に倣った石塔と幢竿支柱を残す。皇竜寺址は発掘調査によって,566年竣成から統一新羅時代にわたる大伽藍の全容と変遷が明らかにされた。創建伽藍は百済式で,三面僧房が中門の東西方まで延びて中門とは回廊で連結する。この形式は唐の西明寺を模したと伝えられる日本の大安寺伽藍と類似する点で興味深い。
新羅
新羅は唐と結んで660年に百済を,668年に高句麗を滅ぼして半島を統一した。寺院址は慶州を中心に四天王寺址(699),感恩寺址(682),望徳寺址(684),千軍里寺址(8世紀),仏国寺(752)があり,僻遠の山地にも太白山浮石寺,智異山華厳寺,伽倻山海印寺などが創建された。統一新羅時代の伽藍配置は金堂前方の左右に2基の塔を置く二塔式伽藍で,日本の薬師寺と同形式である。四天王寺,望徳寺址は木造双塔址で,感恩寺,仏国寺,千軍里寺等の石塔が現存する。石塔は8世紀に入って流行し,9世紀以降方形多層塔が全国的に普及する。
高麗
高麗時代に入って半島北部の開城に首都が遷り,仏教は国教として厚く保護され,全国各地に多くの寺院が建てられた。しかし,度重なる外寇,とくに高麗末期の倭寇の侵入によってその多くは焼失した。高麗時代後半の建築には強い胴張りをもつ柱,斗栱(ときよう)形式に三国時代以来の古い要素をなおも残しているが,三国統一前後から唐文化の影響を強く受けて統一新羅時代に定着した唐様式を継承している。例えば,現存最古の木造建築である鳳停寺極楽殿(12世紀)や浮石寺無量寿殿(13世紀)の斗栱形式や,二重虹梁蟇股(かえるまた)を基本とする構造形式に唐様式が根強く生きている。しかし,鳳停寺極楽殿の頭貫(かしらぬき)木鼻を垂直に切った形式や,母屋(もや)桁下架構の発達などは,中国華北の遼時代建築細部を受容したものであり,また,肘木(ひじき)下端の繰形は12世紀ころに南宋から伝わった様式(日本でいう大仏様=天竺様)の影響と認められる。新羅以来の伝統様式の上に新しく中国の建築様式を採り入れて折衷様化を図り,日本の折衷様式と同じ経過をたどっている。この様式は斗栱の組み方から柱心包様式と呼ばれ,前記2例に続く例に修徳寺大雄殿(1308),江陵密舎門(14世紀),成仏寺極楽殿(1320ころ),浮石寺祖師堂(1377),道岬寺解脱門(1473),無為寺極楽殿(15世紀),松広寺国師殿(15世紀)などがある。
高麗時代末期には元の支配を受け,元の建築様式を導入して多包様式が成立した。この様式は柱と柱の間にも斗栱を置く詰組(日本の禅宗様=唐様と同じ),尾垂木形の肘木鼻,柱上斗栱の梁頭形拳鼻などに特色をもつ。柱心包様式に比べると内外への手先も多く,彫刻を多用して装飾的にも豪勢・華麗を尊ぶ宮殿建築にまず採用されたが,14世紀末には盛行して仏教建築にも採り入れられた。黄州心源寺普光殿(1374),安辺釈王寺応真殿(1386)がその初期の遺構例である(高麗美術)。
李朝
李朝時代は元の滅亡とともにはじまり,太祖は仏教を信仰して造寺造仏を行ったが,3代太宗以降は儒教を奨励し,仏教を厳しく排斥して首都漢城から締め出したため,高麗時代に隆盛を極めた仏教も,山間に旧寺院を復興して命脈を保つ状況であった。李朝後期に入って多包様式が木造建築の主流となり,装飾の多い外観や大きな空間を構成する合理的な架構法に,最も民族的な色合いが濃く表現されている。この時代の代表例として,法住寺捌相殿(1625),金山寺弥勒殿(1635),華厳寺覚皇殿(1697)などがある。
執筆者:宮本 長二郎
日本
伽藍の興隆
6世紀中ごろ,仏教公伝直後の日本には寺院建築はなく,宮殿や邸宅の一部が仏堂とされた。《日本書紀》や《元興寺縁起》は崇峻1年(588)に,百済から寺工や鑪盤博士,瓦博士等が来り最初の本格的伽藍,法興寺(飛鳥寺)を着工したと伝える。発掘によると飛鳥寺は,中央の仏塔を北・東・西の三金堂で囲む配置で,先例は高句麗にあり,中国の三合院配置から生まれたとみられる。塔の心柱は掘立式で,仏舎利を奉安する心礎は地下2.5mに据えられ,東西金堂は朝鮮の清岩里廃寺や定林寺址に例を見る,周囲の低い基壇上にも柱を建てる特殊な構造で,配置,技術のすべてにわたり,百済の工匠の指導を受けたものである。中国の建築技術では,基壇上に礎石を据え,太い柱に複雑な組物を用い,彩色を施し厚い土壁と深い軒のある本瓦屋根をもつ。講堂や食堂(じきどう)は大面積で,寺内大衆を集会させた。従来の日本建築の掘立柱,板壁,茅(かや)または檜皮(ひわだ)葺きとはまったく異なるもので,講堂のような大面積の建築も寺院が最初とみられる。石や塼(せん)の建築は,日本では内部空間のない記念碑的なものしか造られなかった。斑鳩寺(いかるがでら)(若草伽藍)や四天王寺など7世紀初頭に発願された寺は,中軸線上に中門,塔,金堂,講堂を縦に順に並べ,回廊は中門から講堂を結び堂塔を囲む。造営に長年月を要し四天王寺の完成は7世紀後半であった。飛鳥時代に着工された寺院は東海から山陽にかけ40余寺ほどあり,大多数は奈良,大阪,京都にある(飛鳥美術)。
白鳳から奈良へ
白鳳時代には奥羽南半から九州中部まで数百の寺が建立され,政府の官寺も定められた。天智天皇発願の川原寺(かわらでら)は中金堂の前庭に東塔と西金堂を置き,背後に講堂と三面僧房があった。中金堂は母屋(もや)のみ壁と扉で囲む聖域とし,四周は吹放しだったらしい。斑鳩寺は焼けて7世紀後半に法隆寺として再建され,これが現存世界最古の木造建築として金堂,五重塔,中門,回廊,東室を伝える。塔と金堂を左右に並べ,胴張りのある太い円柱に雲斗(くもと),雲肘木(くもひじき)を用い,軒を深く出す。人字形蟇股(にんじがたかえるまた)や卍崩し(まんじくずし)高欄など中国六朝建築の細部を伝えている。これら初期の仏殿は平面は比較的小さく,外観は二重屋根とし,内部は閉鎖的で,塼仏,壁画,仏具で荘厳された〈仏の聖域〉で人の立入りを許さなかった。7世紀末に藤原京で造営された本薬師寺は回廊内に両塔をもつ最初の伽藍で,金堂は正面幅が大きく,重層のそれぞれに裳階(層)(もこし)を付し,母屋は閉鎖的な聖域であった。三重塔も各重に裳階のある華麗で異国的な姿とされた。大官大寺(だいかんだいじ)(百済大寺)は九重塔と巨大な金堂を建てた。このころから朝鮮三国だけではなく唐の直接の影響が大きくなった。
平城京が定まると官私大小の寺が相次いで遷り,金堂前庭を回廊で囲み,塔は回廊外に置く寺が多くなった。大安寺は東西七重塔を南大門外に置き,金堂院の外周を2列の僧房で囲み,唐天竺の寺を模したといわれた。そのなかで薬師寺のみが旧寺(本薬師寺)と同形とされた。これら官大寺は令外官である造寺司によって,国家予算で造営された。741年(天平13)聖武天皇は詔で全国に国分僧寺と尼寺を置き,僧寺には七重塔を建てた。743年には大盧遮那仏(だいるしやなぶつ)をまつる大寺が発願され,745年平城京東郊で着工された。東大寺と呼ばれ,盧遮那仏が仏教世界の中心仏であるのになぞらえて,国分寺の中心とされた。大仏殿の桁行は86m,高さ44mの巨大なもので,前面東西に高さ98mの七重塔がある,規模も意義も空前絶後のものであった。奈良の大寺は中心伽藍のほか,各種の機能を果たす院や本尊以外の仏菩薩などをまつる別院が寺内に置かれ,広大な寺地をもった。東大寺内も別院が多く,羂索院法華堂(三月堂)は双堂(ならびどう)形で建てられ,鎌倉中期に礼堂を再建して1棟とした西大寺は2棟の華麗な金堂をもち,多数の院ごとに仏堂と僧房を有した。唐から律を伝えた鑑真の唐招提寺は私寺ながら4町の寺地を有し,当時の金堂,講堂を存している。また聖徳太子をまつる法隆寺東院が発願され,中心に八角円堂の夢殿を置いて塔廟を表現した。法隆寺には大講堂,経蔵,鐘楼,東西僧房,食堂等,古代寺院の各種建物をよく残している。奈良時代は唐のさまざまの形式の一部を選択摂取し,宮殿,官衙,邸宅にもその建築様式が普及したので,これらの建築を寺院にも転用しやすかった。各地の神社で仏教に帰依して神宮寺を造るものも増加し,山中で定形の配置をとらず,檜皮葺きの塔や床張りの堂も建てられた(奈良時代美術)。
平安時代
平安時代には初期に密教が伝えられ,中期には浄土信仰の興隆があって特色のある寺院建築が求められた。平安京の京内は,東寺,西寺の2官寺のみとして他に官私の寺は建立させず,京郊外に多数の私寺ができた。唐から密教を伝えた最澄は比叡山に天台宗の延暦寺を,空海は高野山に金剛峯寺を建てる。山上なので一定の伽藍配置をもたず,宝塔などを中心に講堂,灌頂堂,常行三昧堂,法華三昧堂などを院ごとにまとめて置き,100余年後に完成した。宝塔以外は堂内に僧ら多勢を入れて儀式を行うため,土間による仏の座と床張りの人の場を分離するよう広庇(ひろびさし)や礼堂の応用と発達をみるようになり,初期仏殿とは異なる性格と形式をもった。平地の密教伽藍として醍醐寺なども造営された。平安初期の寺院建築は現存するものが少ないが,室生寺金堂や当麻寺西塔などがあり,中期初めには醍醐寺五重塔がある。
浄土信仰と末世思想は,貴族たちに浄土曼荼羅を具体化した苑池をもつ伽藍を流行させ,鎌倉初期まで続いた。藤原道長の法成寺,八角九重塔を有した白河天皇の法勝寺は失われたが,藤原頼通の宇治平等院は苑池と阿弥陀堂(鳳凰堂)が今も残る。伽藍跡と苑池がよく残るのは平泉の毛越寺である。また阿弥陀堂などの三間堂が日本全国に普及し遺構を伝えている。これらは組物も簡単で床張りとし,小組格天井(ごうてんじよう)を用いて落ち着いた室内とされた。墓堂に用いられた中尊寺金色堂は金銀螺鈿(らでん)の装飾で知られる。このような絢爛(けんらん)多彩な装飾は他寺でも用いられた。九品の阿弥陀如来像を並べる九体阿弥陀堂は,六勝寺などから建立されるようになり,京都府加茂の浄瑠璃寺に実例が残る。他にも長大な堂が要求され,京都三十三間堂の前身は法住寺殿に建てられた。一方,貴族邸に持仏堂を置くことから,邸宅と寺院の両性格をもつものもあった。堂内を内・外陣に分け仏と人に別の空間を造る中世本堂形式も平安末からでき,当麻寺曼荼羅堂が知られる。観音信仰や修験道の山寺には,鳥取県三仏寺奥院など懸造(かけづくり)の堂も造られた。本地垂迹などの思想から,神宮寺や神社に堂塔や鐘・経楼を置くものも増えた(和様建築)。
中世--新様式の展開
中世の寺院建築は南都復興に宋の新技術が導入されたことから始まる。やがて禅宗渡来にともなう新様式の成立があり,新宗派の要求する個性的な仏堂や,中世密教本堂形式の全国普及がみられた。遺構数も奈良時代,平安時代とも約30例ずつなのに対して,鎌倉時代だけで160棟におよぶ。東大寺再建のため俊乗坊重源が中国江南から学んだ新様式は,後に天竺様(大仏様)といわれ,挿肘木(さしひじき)と貫(ぬき)による豪壮・単純な軀体に,細部の装飾性をもたせている。重源生前にだけ遵守され,後世には貫による構造強化と木鼻や桟唐戸(さんからと)などの装飾的要素として応用される。大建築の場合だけ当初の天竺様に近い形式を用いた。
禅宗は思想,芸術,生活様式の総合体系として移入され,寺院の環境として南宋の五山のような境地を実現することが重視されたので,伽藍配置や建築構造と細部の表現が後までよく守られ,かつ日本的な精緻なものに消化され再形成された(禅宗寺院建築)。配置は古代伽藍の中軸線を重視する方式に帰り,中心の仏殿は,外観は重層に見え,柱が高く内部空間も見上げるような高さを志向する。木割の細かい複雑な組物を柱の間にも使って装飾を兼ねる。床はふたたび土間となった。主要伽藍のほかに高僧の住院を墓所とした塔頭(たつちゆう)ができ,開山塔と昭堂(しようどう),方丈(ほうじよう),庫裡(くり)などを配し小僧院の形をとる。これは後に一般の小寺院の原型となった。禅宗寺院は建仁寺,建長寺,東福寺,円覚寺,南禅寺など京と鎌倉を中心に五山十刹の制ができたが,当初の建物はすべて失われ,後世再建のものとなっている。仏殿の実例は功山寺(下関市),不動院(広島市),永保寺(多治見市),円覚寺舎利殿(鎌倉市)など,母屋規模が方三間の堂のみ残る。塔は伽藍後方に建てられ,安楽寺塔(上田市)は唐様(禅宗様)による八角三重裳階つきの珍しい例である。座禅修行の場である僧堂(禅室)や清浄のための浴室,東司(とうす)(便所)は東福寺に実例がある。書院などに二階建ての楼もできた。
密教寺院の本堂には仏のための内陣と人の場の外陣を同一建物内に設け,間に結界をつくり,新技術を応用して柱を減じたものが全国に普及した。天竺様や唐様の細部や組物が意匠として使われ,折衷様と呼ばれる。新宗派である浄土宗や一向宗では,本堂に集会と説法ができる住宅風の室内をもった奥行きの深い堂が造られ,宗祖をまつる祖師堂を本堂に並べて配したり,あるいは庫裡や書院と並べられた。貴族の邸宅と寺院を兼ねた別邸も造られ,後に寺院となった鹿苑(ろくおん)寺や慈照寺などがある。
衰退と変容
近世になると,桃山時代には装飾彫刻や彩色で華麗さを競うようになるが,江戸初期に禁止される。禅宗の一派である黄檗(おうばく)宗に中国明朝の形式が移入されるが,配置は禅宗様そのままで,細部意匠に明様を用いるものとなる(黄檗美術)。幕府の禁令で一般の寺院では簡素な塔頭形が全国に多くなり,本堂,庫裡,鐘楼がどの寺にもみられるようになる。本堂は禅宗方丈形の六室取りに類似し,宗派によって内陣の構成に違いがみられる。明治維新直後,神仏分離令で仏寺と神社は完全に別組織に分けられて多数の寺院が破壊され,寺院建築は衰退の方向をとる。古建築のすぐれたものは文化財として保存されるが,大規模な木造建築の新築や維持は,大寺院以外はしだいに困難になる。鉄筋コンクリート造の新様式が東京築地本願寺などにみられ,外観は古典的でも内部をホール風とするものや,まったく現代的外観の寺院(静岡大石寺など)も建てられる。さらに広い墓地をやめてコンクリート造の納骨堂が流行するほか,堂内の儀式形態も椅子式などに変化しつつあり,現代は寺院建築の形態,内容とも変革期にある。
→伽藍配置 →教会堂建築 →社寺建築構造 →塔
執筆者:沢村 仁
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報