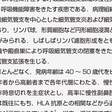内科学 第10版 「びまん性汎細気管支炎」の解説
びまん性汎細気管支炎(気道・肺胞疾患)
びまん性汎細気管支炎(diffuse panbronchiolitis: DPB)は,臨床的に慢性副鼻腔炎と慢性の下気道感染症を主徴とし,病理学的には両側びまん性に存在する呼吸細気管支領域の慢性炎症所見(図7-3-10)を特徴とする炎症性疾患である.DPBの疾患概念は1960年代にわが国において確立されたもので,欧米にはDPBにあたる疾患が存在しないため,長く認知されてこなかった経緯がある.しかし,1983年に本間らによってChest誌に発表(Hommaら,1983)されて以来,欧米においても徐々に理解が深まり,現在では主要な欧米の教科書では必ず触れられる有名な疾患となっている.
原因・病因
明らかな病因は不明であるが,病態は,慢性副鼻腔炎を伴う慢性下気道感染症であり,この病態を示す副鼻腔気管支症候群(sinobronchial syndrome: SBS)には何らかの気道・全身の免疫低下を示す疾患が多いことからDPBにおいても,そういった異常の存在も考えられている.また,DPBで注目されるのは,親子兄弟などの家族発生例が多いことと,家系内での副鼻腔炎のみの例が多発していることである.これらのことから,遺伝的素因がきわめて濃厚な疾患と考えられ,HLAの検討が行われ,患者はHLA-B54を有意に多く有していることが判明している(Sugiyamaら,1990).HLA-B54は日本人を中心とした東アジアの諸民族のみが有する抗原であり,このこととDPBが欧米・アフリカには存在しないこととの関連が推測されている.
疫学
1980年代以前には,ごくありふれた疾患であったDPBも,近年はきわめてまれな疾患となっている.この間の経緯について最近,JR東京総合病院より職場健診のデータを用いた約30年間の疫学データが発表(Konoら,2012)され,1976~1980年には10万人対13.8人であった有病率が1989~1993年には6.6人,1999~2003年では0人となったことが示されている. この理由として,日本人全体の栄養状態の改善と,後述する1980年代半ばからのマクロライド療法の導入の効果が考えられている.
臨床症状
最も大きな特徴は,本疾患がきわめて長期にわたる慢性的な経過をたどることである.多くの例で,膿性鼻汁,鼻閉といった慢性副鼻腔炎症状が先行し,数年~十数年後に下気道症状である膿性痰,咳が出現してくる.さらに,労作時呼吸困難が出現し,気管支拡張や肺の破壊・線維化が進行して慢性呼吸不全状態となり死に至る.
検査成績
一般検査所見としては,慢性の上下気道の感染症状の反映として,末梢血白血球数の増加,赤沈・CRPの上昇がみられる.すべての患者にみられるわけではないが,特異的な所見として,寒冷凝集素価の持続性の高値,IgG・IgA値の上昇,リウマトイド因子陽性などがみられる. 画像所見は特徴的であり,特にHRCT像は診断的価値が高い.胸部X線写真では,中下肺野に強い,両側びまん性の辺縁のボケた小粒状影を認め,これに種々の程度の気管支拡張像と過膨張所見が加わる(図7-3-11).CT(HRCT)では,①びまん性の小葉中心性粒状影,②分岐線状陰影,③気道壁の肥厚とさまざまな程度の拡張像がみられる.小粒状影は,分岐線状影に連続し,木の枝につぼみがついた状態(tree-in-bud appearance)となる(図7-3-12).この分岐線状陰影は,拡張して分泌物が貯留し,壁が肥厚した末梢気道病変を示している.
痰からは早期にはインフルエンザ菌Haemophilus influenzaeなどが検出されるが,進展すると緑膿菌への菌交代を生じる.呼吸機能上は,初~早期には病変を反映して,閉塞性換気障害が前景に立つが,進行すると拘束性障害が加わり,混合型の障害を呈する.
診断・鑑別診断
DPBの診断基準(表7-3-4)を示す.慢性副鼻腔炎に慢性下気道感染症を合併した例で,画像上前述のような特徴を示し,閉塞性障害を呈する例では臨床的にも診断は容易である.さらに寒冷凝集素価の高値,HLA-B54陽性などが診断を補佐することになる.通常,外科的肺生検による病理診断は必要とされないが,非定型例,関節リウマチ合併例,HTLV-1陽性例やほかのSBSとの鑑別困難例では生検が必要となることもある.
鑑別診断としては,ほかのSBS,COPD,気管支喘息,間質性肺炎などがあげられる.近年,前述したようにDPBが激減したことから,臨床医がDPBを経験することがまれとなり,COPDや喘息として加療されている例も少なからずみられ,注意を要する.
予後・治療
1980年代までは,きわめて予後不良の疾患であり,初診時からの5年生存率は42%,緑膿菌菌交代発現からの5年生存率は8%というきびしいものであった.しかしながら,1980年代以降,後述する工藤によるマクロライド療法の導入(Kudohら,1998)により,予後の著明な改善がみられ,早期に治療されれば,むしろ予後のきわめてよい疾患となった. 基本的治療としてはエリスロマイシン400~600 mg/日を6カ月~数年間用いる.クラリスロマイシン200 mg/日でも同様の効果がみられる.有効例では,2週間後くらいから,痰の減少を中心に自覚症状の改善がみられはじめる.近年,マクロライドのDPBに対する効果から,マクロライドの抗菌作用以外のさまざまな効果が新作用として研究され,COPDの急性増悪の予防効果や,抗炎症作用などに対して大きな注目が集まっている.[杉山幸比古]
■文献
Homma H, Yamanaka A, et al: Diffuse panbronchiolitis: A disease of the transitional zone of the lung. Chest, 83: 63-69, 1983.
Sugiyama Y, Kudoh S, et al: Analysis of HLA antigen in patients with diffuse panbronchiolitis. Am Rev Respir Dis, 141: 1459-1462, 1990.
Kono C, Yamaguchi T, et al: Historical changes in epidemiology of diffuse panbronchiolitis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis, 29: 19-25, 2012.
Kudoh S, Azuma A, et al: Improvement of survival in patient with diffuse panbronchiolitis treated with low-dose erythromycin. Am J Respir Crit Care Med, 157: 1829-1832, 1998.
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報