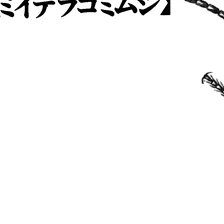ミイデラゴミムシ
Pheropsophus jessoensis
甲虫目ゴミムシ科の昆虫。頭部,胸部は黄色で黒色紋が,上翅は黒色で黄色紋がある。上翅は光沢がなく,隆起条を縦列する。体長16mm内外。北海道から奄美大島までの各地に分布し,水田や河原など湿った土地に多い。成虫は夜間,地上を歩いて昆虫をはじめ,各種の小動物を捕食する。とらえると肛門からプッという音とともに刺激臭のある液体を霧状に噴射するのでヘッピリムシ,ヘコギムシとも呼ばれ,英名もbombardier beetleという。肛門近くの袋にヒドロキノンと過酸化水素を蓄え,危険にさらさせると,この二つの物質が混ぜ合わさり,発生したガスの爆発音とともにベンゾキノンという化学物質を噴射する。6月ころ土中へ産卵。孵化(ふか)した幼虫の行動は活発で,ケラの卵塊にたどり着き,卵を食べて成育する。脱皮後は肥満体となり,胸脚は退化して小さくなる。本種はホソクビゴミムシ亜科に属するが,この亜科を科とする学者もいる。
執筆者:林 長閑
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ミイデラゴミムシ
みいでらごみむし / 三井寺芥虫
[学] Pheropsophus jessoensis
昆虫綱甲虫目ゴミムシ科に属する昆虫。日本各地、朝鮮半島、中国に分布。体長約15ミリメートル。頭胸部は細く、黄色に黒紋がある。上ばねは黒くて中央の両側に太い黄色の横帯があり、前後にも横帯があって後方へ広がっている。おもに平地の草むら、石や倒木の下などに隠れ、夜間活動してミミズや虫の死体を食べる。成虫で越冬し浅い土中に群集する。捕まえようとすると肛門(こうもん)から霧状のガスをプッと発射するのでヘッピリムシともいう。琉球(りゅうきゅう)諸島には近縁種がいる。
[中根猛彦]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ミイデラゴミムシ
Pheropsophus jessoensis
甲虫目クビボソゴミムシ科。敵にあったり,おどしたりすると,腹端から淡黄白色のガスを「ぶすっ」という音とともに体外に発射する虫で,ヘッピリムシともいう。体長 11~18mm。頭部と前胸背は皺が多く,大きい点刻を粗布する。上翅には浅く細い条溝があり,間室には中央に太い隆条がある。上翅の黄褐色紋が目立つ。北海道から奄美大島にまで分布し,湿った枯れ草の下などにみられる。ガスをまともに皮膚に受けると一種のやけどを起す。沖縄地方には別種のオオミイデラゴミムシ P.javanusがすむ。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ミイデラゴミムシ
学名:Pheropsophus jessoensis
種名 / ミイデラゴミムシ
解説 / 成虫は、夜行性で肉食です。敵におそわれると、ガスを発射します。成虫で越冬します。
目名科名 / コウチュウ目|ホソクビゴミムシ科
体の大きさ / 11~18mm
分布 / 北海道~九州、トカラ列島、奄美大島
幼虫の食べ物 / ケラなどの卵
出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報
Sponserd by