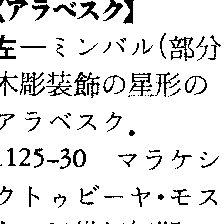翻訳|arabesque
精選版 日本国語大辞典 「アラベスク」の意味・読み・例文・類語
アラベスク
改訂新版 世界大百科事典 「アラベスク」の意味・わかりやすい解説
アラベスク
arabesque
フランス語で〈アラビア風〉の意,とくに装飾文様について多用される。優美な渦巻曲線が直線や放射状の星形文様とリズミカルに錯綜し,シンメトリカルで軽快な無限展開を繰り広げるが,幾何学文様の範疇に入るほど抽象化されたものではない。7世紀前半にアラビアに起こったイスラムは,教義上,人物・鳥獣などのモティーフの採用を禁じた。そのため,美術上の表現にはオリエント古来の幾何学的組紐文や蔓草文に,樹葉,花冠,果実などを図式化したモティーフをからみ合わせた精緻な平面装飾が一貫して用いられた。この装飾は建物内外の壁面,床石,じゅうたん,器物,写本装飾,ししゅう,アラビア文字の末端の装飾など,イスラム文化の造形的特質となった。アラベスクはさらに西欧中世の写本装飾に影響を与える一方で,ペルシア,インドを通じて中国,日本にまで及び,牡丹唐草文など種々の花模様へと変容してゆく。一方,ルネサンス時代にローマで古代遺跡が発掘されるに及び,ヘレニズム期,古代ローマ時代のグロテスク文様もまた,アラベスクの概念に含められた。古代遺跡の多くは,たとえばネロのドムス・アウレア(黄金の家)の場合のように地下に埋もれて洞窟(グロッタ)の観を呈していたので,その壁面装飾の文様をグロテスクと呼んだのである。しかしこのグロテスク文様は,一般に流麗な葉状の曲線文様の中に花冠,鳥獣,人体をからませた綺想風の文様で,アラベスク文様と類似しているところから,イタリア語でアラベスコとも呼ばれた。この古典古代の幻想的で華麗な文様はルネサンス期の美術にはむろんのこと,その発展様式ともいうべきバロック,ロココ時代の絵画,彫刻,工芸,庭園のデザインへと展開した。特にラファエロによるバチカンのロッジアのグロテスク装飾は,のちにラファエリスク(ラファエロ風)とも呼ばれた。一般にさまざまのモティーフを交えた古典系統の蔓草文様をアラベスクと総称し,イスラムの文様を主とするアラビア風文様は時にモレスクmauresque(moresque)と別称される。また,この用語は装飾的・幻想的な器楽曲の標題や舞踊のポーズにも用いられている。
執筆者:友部 直
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「アラベスク」の意味・わかりやすい解説
アラベスク
あらべすく
arabesque フランス語
原意は「アラビア風の」であるが、美術用語としては、イスラム美術に広範にみられる曲線的な装飾文様をいう。とくに、つる草のような優美な植物が絡み合った唐草模様をさすことが多いが、広義には、複雑に連続する幾何学図形、文様化されたアラビア文字をも含む。さらには、イスラム美術に限定せず、曲線の多い幻想的な装飾文様すべてをさしたり、人像や鳥獣を取り入れたグロテスク文様を含めることもある。
[篠塚二三男]
このことばは、他の芸術ジャンルにも取り入れられた。音楽では、一つの楽想を幻想的、装飾的に展開する作品の題名に用いられた。その初出は1839年出版のシューマンのピアノ小品『アラベスク・ハ長調』(作品18)である。ほかにドビュッシーのピアノ曲『二つのアラベスク』ホ長調・ト短調(1888)、ディーリアスのオーケストラ伴奏の合唱曲『アラベスク』(1911)などがある。バレエ用語としては、片足で立ち、片手を前に、他の手脚(てあし)を後ろに伸ばしたポーズをこの名でよぶ。
[関根敏子]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アラベスク」の意味・わかりやすい解説
アラベスク
arabesque
アラベスク
arabesque
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「アラベスク」の意味・わかりやすい解説
アラベスク(美術)【アラベスク】
→関連項目文様
アラベスク(舞踊)【アラベスク】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「アラベスク」の解説
アラベスク
arabesque
イスラーム文化から生まれた文様。植物の茎,葉を図案化して,唐草(からくさ)文様や幾何学文様に組み合わせ,さらにアラビア文字を植物に図案化して,菱,星,格子などを配した。モスクの壁面装飾,書物の飾りなどに用いられた。のちに動物も加えるようになり,ルネサンス以後ヨーロッパに広がる一方,アジアにも伝えられた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「アラベスク」の解説
アラベスク
arabesque
偶像崇拝が禁じられたイスラーム世界では,彫刻や絵画が発達しなかったかわりに,装飾が多用された。アラベスクはモスク(イスラーム礼拝堂)の壁画や書物の装丁に用いられ,のちにはアラビア文字や鳥獣・人物なども図案化されて,ルネサンス以後はヨーロッパでも流行した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
デジタル大辞泉プラス 「アラベスク」の解説
アラベスク〔漫画〕
アラベスク〔曲名〕
世界大百科事典(旧版)内のアラベスクの言及
【バレエ】より
…ジョバンニ・ダ・ボローニャ作の《メルクリウス》像によりC.ブラシスが創始したと伝えられる。アラベスクarabesque片足で立ち片足を後ろに上げ,片手または両手を前に伸ばすポーズ。人体でつくりうる最も長い線を示す。…
【バレエ】より
…ジョバンニ・ダ・ボローニャ作の《メルクリウス》像によりC.ブラシスが創始したと伝えられる。アラベスクarabesque片足で立ち片足を後ろに上げ,片手または両手を前に伸ばすポーズ。人体でつくりうる最も長い線を示す。…
【アッバース朝】より
…この古代ギリシアの学術の導入により,イスラム思想界では合理主義的なムータジラ派が盛んになり,一時は彼らの学説が公認教義となったほどである。美術面では,宗教的な理由から絵画や彫刻は発達せず,そのためにかえってアラベスクといわれる装飾模様が発達したが,この時代にはその祖型ともいうべきものができあがった。【森本 公誠】。…
※「アラベスク」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...