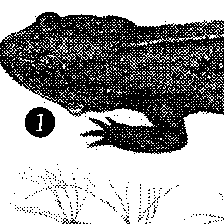イモリ (蠑螈/井守)
目次 民俗 有尾目イモリ科Salamandridaeの両生類 の総称 。イモリとヤモリ とは名前と姿が類似するためよく混同されるが,後者は指が吸盤状をした爬虫類 のトカゲ のなかまである。
約15属55種が北半球の温帯に広く分布 し,大半は全長10~15cmほどで水中 生活するものが多く,日本には2種が分布する。イモリ類は頭部 がやや扁平で幅広く,尾は発達して側扁し後半部はひれ状で,巧みに泳ぐ。四肢は陸上をゆっくり歩く程度に発達し,指は細いが前肢に4本,後肢に5本備わっている。皮膚は全体が細粒に覆われ耳腺が発達しており,フランス以東のヨーロッパに産するクシイモリ Triturus cristatus や,アメリカ合衆国カリフォルニア産のカリフォルニアイモリTaricha torosa には皮膚や筋肉などに毒性があることが知られている。
日本産のニホンイモリ Cynops pyrrhogaster をはじめイモリ類は繁殖期には興味ある性行動をとり,とくにヨーロッパ産には華やかな求愛行動 を見せるものがある。繁殖期の雄には美しい婚姻色が現れ,背中腺や尾の膜びれが発達する。雄は水底 で雌を認めると尾を曲げ雌の顔の前に向かって先端を細かく震わせる。雌は雄の求愛行動にこたえる場合は雄の体を吻(ふん)部で押し,雄は雌の前をゆっくり歩き始め,雌はその後に従う。やがて雄は尾をもち上げて総排出腔 から精包(精子塊)を落とし,雌はそれを排出腔を押しつけるようにして体内に取り入れる。雄の求愛ダンスは種によって多少異なるが,精包を放出して雌が取り込む過程は同じで,精子は雌の受精囊 に長い期間(翌シーズンころまで)生存する。卵は産卵 時に受精 し1個ずつ水草 などに産みつけられる。産卵数の多いものは200~350個ほどで,卵は1週間ほどでかえり,幼生は2~3ヵ月で変態する。子は1年から3~4年間陸上生活をして水に入り,2~3年目には性的に成熟する。
イモリ類のうち,南西諸島 ,東アジアに分布するイボイモリ 属Tylototriton と,イベリア半島 ,北アフリカ産のイベリアイボイモリ属Pleurodeles は原始的な種類で,後者は大きくて全長30cmに達する。サラマンドラ属Salamandra もやや大きく,ヨーロッパ中・南部産で,美しい斑紋 をもちfire salamanderの名で知られるマダラサラマンドラS.salamandra (全長18~24cm)や,アルプス地方の高地 などに分布するアルプスサラマンドラ S.atra (全長16cm)は,変態後は生涯水に入ることがない。卵胎生 で,雌は尾部を水に入れるだけで発生の進んだ幼生を生むが,誤って水に落ちるとおぼれてしまう。アルプスサラマンドラの卵のうち幼生になるのは2個のみで,他の40個ほどの卵は発育の栄養源となる。
イモリ類は発生や生理学の研究用として用いられ,例えば北アメリカ産ブチイモリNotophthalmus viridescens (英名red-spottednewt)(全長約10cm)は,ホルモン の研究に欠かせない実験動物とされる。松井 孝爾
民俗 日本では水とかげ の名もあり,また腹部がトカゲの白色と異なって紅色なので赤腹とも呼ばれる。井守の意味といわれるが,古くから男女が互いに思われようとする相手にこれの黒焼き を振りかけると効果ありということで一般に知られている。しかし,一方では中国の故事に〈やもり 〉に朱を与えて食わせ,これを粉にして女性に塗っておくと,男と交わった場合にはこの朱色が消え,交わらねば色はつねに消えずとあり,イモリの黒焼きの俗信はこの方式と混同したものという説もある。これはイモリとヤモリの名が近く形も似ているほか,その腹部の色が朱に近いからではないかと考えられる。千葉 徳爾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by
イモリ
広義には両生綱有尾目イモリ亜目、狭義にはそのうちのイモリ科に属する種の総称であるが、日本ではアカハラ イモリの通称としても用いられる。
イモリ科はヨーロッパ、北アフリカ、アジア、北アメリカ、および中央アメリカの一部に分布し、15属40種を含む。代表的な種としてはヨーロッパのクシイモリTriturus cristatus 、オビイモリ T. vulgaris 、サラマンドラSalamandra salamandra 、アジアのアカハライモリCynops pyrrhogaster 、イボイモリTylototriton andersoni 、アメリカのブチイモリNotophthalmus viridescens 、カリフォルニアイモリTaricha torosa などがある。体形は有尾類の典型的なもので、全長4~20センチメートル、頭は比較的小さく、細長い胴と尾がある。四肢は短小で、前肢に4本、後肢に5本の指がある。皮膚は一般に粗く、体表からフグ毒であるテトロドトキシン を分泌する種がある。
イモリ亜目には、イモリ科のほかにホライモリ科とアンヒューマ科が含まれるが、イモリ科に比して種数は少ない。上あご、下あごおよび口蓋(こうがい )に歯があり、肺があるなどの共通点があるが、ホライモリ科とアンヒューマ科では水中生活に適応して形態が特殊化している。
アカハライモリは本州、四国、九州および隣接の島々にすみ、全長10センチメートル内外で、背面は黒褐色、腹面は赤橙(せきとう)色の地に黒斑(こくはん)がある。雄は雌より小形で、繁殖期には総排出孔 の周囲が大きく膨らむ。また、雄の尾の側面は紫青色を呈する。琉球諸島(りゅうきゅうしょとう)には亜種シリケンイモリC. p. ensicauda が分布する。
[倉本 満]
イモリ科にはほぼ完全に地上性の種から水中性の種まであり、生息場所は多様である。わが国のイモリは低地から山地にかけ、主として溝、水田、沼などの止水にみられるほか、流れの緩い河川にも生息する。昆虫類、甲殻類、クモ類、ミミズ類などを食べる。
イモリ亜目はすべて体内受精であるが、交尾がないため、雌雄は複雑な求愛行動によって精包(精子塊)の授受を行う。雄には精包を形成するための分泌腺(せん)があり、そこから水底または地上に落とした精包を雌が総排出孔から取り込む様式が多いが、雄が雌に体を巻き付けて精包を移す種もある。精包は雌の貯精嚢(のう)に蓄えられ、卵は産卵直前に受精する。受精卵が輸卵管内で発育し、幼生となって産み出される種もあり、アルプスサラマンドラS. atra のように変態個体を産む種もある。
アカハライモリの産卵期は春から初夏までで、水底で雄は雌を認めると、その進路を阻むようにして雌の鼻先で尾を細かく振動させる。雌が反応すると雄は歩き始め、雌がそのあとに続く。やがて雄は水底に精包を放出し、雌がその上を通過するとき総排出孔からそれを取り込む。卵は1個ずつ水草の葉に包むようにして産み付けられる。孵化(ふか)した幼生は水中で生活し、変態して上陸するが、成熟するとふたたび水中生活を始める。
[倉本 満]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by
イモリTriturus pyrrhogaster
サンショウウオ目イモリ科。体長8~12cm。体表は粗雑で,背面は黒または暗褐色,腹面は赤あるいは黄橙色で普通不規則な黒色の斑紋がある。頭部は細長く,耳腺が発達する。尾は胴より長く,側扁し,雄では幅が広く末端で急にとがるが,雌では基部より次第に細まる。平地の池,小川,水田,高地の湿原や沼などいたるところに生息する。ほとんどを水中で過すが,冬は陸上で冬眠する。産卵期は4~7月。この時期になると雄の尾は灰紫色を帯びる。雄は求愛行動を行い,精子塊を排出する。精子塊は雌によって取込まれ,その体内で受精が行われる。産卵は池などの浅いところで行われ,卵は1個ずつ水草の葉などに包むようにして産みつけられる。産卵数は約 200個。北海道を除く日本各地に分布する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by
イモリ
有尾目イモリ科の両生類の総称。アカハラとも呼ばれるニホンイモリは,日本の代表的な種。全長8〜13cm,雄は一般に小さい。本州,四国,九州に分布。背面は黒紫色,腹面は赤色で黒色斑紋がある。平地や山地の川や池にすみ,ミミズ,昆虫,貝などを食べる。陸上の石の間,枯葉の下,または水底で冬眠。繁殖期に雄は青紫色の婚姻色を表し,雌の前で求愛する。雌は放出された精包を取り入れて体内受精。4〜7月ごろ水草に産卵。アカハラ
出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の イモリの言及
【黒焼き】より
…《日葡辞書》にCuroyaqi,Vno curoyaqiが見られることから室町末期には一般化していたと思われ,後者の〈鵜の黒焼〉はのどにささった魚の骨などをとるのに用いると説明されている。黒焼きといえばまずイモリのそれを思い出すが,これは古く中国で流布された女性の貞操監視法からの変化らしい。すなわち,[陶弘景](とうこうけい)などによると丹砂で養ったヤモリを陰干しにして粉にし,これを女性の臂(ひじ)などに塗ると赤いあざのようになり,いくら洗っても消えなくなる。…
※「イモリ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by