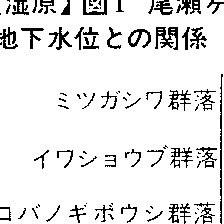翻訳|moor
精選版 日本国語大辞典 「湿原」の意味・読み・例文・類語
しつ‐げん【湿原】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「湿原」の意味・わかりやすい解説
湿原
しつげん
moor
過湿な条件を好む草本や蘚苔(せんたい)類あるいは低木に覆われ湿った土地。通常、潟や湖沼などが土砂で埋まって浅くなり、そこにミズゴケやアシなどが生育、繁茂することによって湿原ができるが、そうした地下水位の高い場所では年々枯死する植物の遺体が完全に分解せず、泥炭となって堆積(たいせき)していくため、湿原には泥炭を伴うものが多い。湿原は地下水位の高低により3種類に分けられる。地下水位が高く、水分過飽和な湿原を低層湿原といい、河川の氾濫(はんらん)原や沼沢地にできやすい。ここにはおもにアシやスゲ類が生育する。泥炭が集積して地下水位よりも高くなると、雨水のみで生活できるミズゴケやモウセンゴケ、ツルコケモモなどを主体とする湿原ができる。これを高層湿原といい、尾瀬ヶ原(群馬県)や釧路(くしろ)湿原(北海道)はその代表的なものである。両者の中間のヌマガヤやワタスゲの生育する湿原を中間湿原という。湿原は寒冷多雨の気候下でできやすく、北欧やシベリア、アラスカ、カナダなどに広く分布している。日本では北海道の海岸部や山岳地方に大規模なものがあるほか、東北日本の多雪山地にも広くみられ、谷地(やち)、田代(たしろ)などとよばれている。1980年代以降、多雪山地の湿原には、後氷期の積雪量の増加によって形成されたものが多数知られるようになった。
[小泉武栄]
植生
生態学では、沼沢地などといった多湿な環境のため木本植物が生育できず、草本植物が優占する群系をいい、湿生草原ともよぶ。湿地では低温や過湿のため植物の枯死体の分解が阻害されて泥炭が形成され、その上に湿原が発達する。泥炭の生態的条件によって低層湿原、中間湿原、高層湿原の別がある。また栄養塩類含有量から富栄養湿原、中栄養湿原、貧栄養湿原に分けられる。低層湿原は富栄養湿原である場合が多く、アシ、カサスゲなどが生育し、高層湿原は貧栄養湿原で、おもにミズゴケ類で特徴づけられる。
[奥田重俊]
『阪口豊著『泥炭地の地学――環境の変化を探る』(1974・東京大学出版会)』▽『鈴木良策著『湿原尾瀬――鈴木良策写真集』(1987・六興出版)』▽『『自然歳時記 新日本百景3 湖沼と湿原』(1987・集英社)』▽『本多勝一編『釧路湿原――日本環境の現在』(1993・朝日新聞社)』▽『森田敏隆写真『日本の大自然9 釧路湿原国立公園』(1993・毎日新聞社)』▽『鈴木静夫著『水辺の科学――湖・川・湿原から環境を考える』(1994・内田老鶴圃)』▽『阪口豊著『尾瀬ヶ原の自然史――景観の秘密をさぐる』(中公新書)』
改訂新版 世界大百科事典 「湿原」の意味・わかりやすい解説
湿原 (しつげん)
湿地に成立した草原のこと。欧米では湿原に対して細分された語が発達しており,日本の湿原という総称に対応する語はない。湿原は泥炭(ピートpeat)ができているかどうかで,沼沢湿原marsh,swampと泥炭湿原mireに大別される。
沼沢湿原は,湖沼の岸や河川の排水の悪い氾濫(はんらん)原などにみられ,栄養物質に富んだ水に涵養(かんよう)され,泥炭は集積しない。ヨシ原に代表されるが,オギはヨシよりも浅いところに,マコモ,ヒメガマは深いところに出現する傾向がみられ,沼沢植物の分布は水深と関係する。
泥炭湿原は,植物遺体の分解量が生産量を下回るためヨシ,スゲ類,ミズゴケ類などの植物遺体が集積し泥炭化するところに形成されるので,寒冷な亜寒帯・冷温帯に多い。低温でなくても貧栄養な水に涵養されれば植物遺体の分解が遅くなるので,熱帯にも泥炭湿原は出現するが,熱帯の泥炭は樹木の遺体が主体である。泥炭湿原の分布は広く,世界陸地面積の6%,900万km2を占める。栄養物質に富み酸性度も高くない水に涵養される鉱物質栄養性(富栄養性)湿原fenと,涵養水が雨水に限られ,栄養物質が少なく酸性の水に涵養される降水栄養性(貧栄養性)湿原bogとに大別され,中間のものを中栄養性湿原という。地下水位との関係でできた語で,よく用いられている低層湿原low moor,中間湿原middle moor,高層湿原high moorという呼び方は,それぞれ貧・中・富栄養性湿原の意味で使われている。
湿原の遷移
泥炭湿原のでき方には,湖沼の陸化による場合と,草原や森林の排水不良や湧水での沼沢化による場合とがあり,沼沢湿原,低層湿原,高層湿原へと進行するのが普通である。貧栄養な湖沼では,スゲ類が浮島となったり岸辺から開水面にマット状に張り出し,その上にミズゴケ類が発達して直接高層湿原化する場合がある。陸化型の場合は,湿原の層序の下層に湖成堆積物の層が出現するのでわかる。沼沢湿原において,ヨシなどの泥炭が集積すれば低層湿原に移行する。低層湿原もヨシ原に代表されるが,スゲ類が混じることが多い。さらに泥炭の集積が進み,ミズゴケ類が生育しはじめて高層化してくると中間湿原に発達する。この段階では,スゲ類に加えてヌマガヤ,ワタスゲ,オオイヌノハナヒゲなどの植物が多くなる。全域のミズゴケが生長しさらに高層化すると,ドーム状に中央がもり上がる。この段階では雨水の供給のみに依存する降水涵養型の典型的な高層湿原になる。尾瀬ヶ原はその最も代表的な例である。高層湿原がドーム状に中央がもり上がるのは,地下水面が深くやや乾燥し,かつ富栄養な水が流入する周縁部よりも中央部のミズゴケ類の生長がよくなるからと考えられている。
高層湿原には微地形が形成され,微地形と対応してさまざまの植物が生育している。微地形により地下水位が異なることが一因となってこの植物の分布が決められていることが知られている。ミズゴケ類でもり上がった小凸地hummock(ブルト)には,レンゲツツジ,ヒメシャクナゲ,ノリウツギなどの低木や,ヤマドリゼンマイ,ヌマガヤなどが生育する。小凹地hollow(シュレンケ)や湛水(たんすい)シュレンケpoolには,ミカヅキグサ,ヤチスギラン,ホロムイソウなどや,ハリミズゴケ,ウツクシミズゴケなどの半水生のミズゴケが生育する。池塘(ちとう)pond(ブレンケともいう。高層湿原にできる池)には,ヒツジグサ,オゼコウホネなどの浮葉植物,ミヤマホタルイなどの抽水植物,マット状に張り出したミツガシワが生育し,浮島がみられたりする。
アイルランドなどの極端に湿潤な海洋性気候下では,土壌は塩基が溶脱されて酸性となり,鉱物質基盤の上にミズゴケが直接生育できるため,ドームは形成されずに地形なりにミズゴケ類が平坦に広がったブランケット湿原blanket bogが発達する。日本の中部地方以北の多雪山地の冷涼な湿地に発達する山地貧養湿原とよばれる湿原はこの型で,ミズゴケ類,キンコウカ,イワイチョウなどが生育する。
シュレンケのミズゴケの生長がよくなりブルトに発達するとか,湛水シュレンケが浸食されて池塘ができるとか,池塘が埋まってシュレンケになるとかというように微地形は変化しても,水位や水質が変わらないかぎり高層湿原は長期に安定する。しかし排水がよくなり乾燥が進むと草原から森林へと移行するし,涵養水が富栄養化すると低層湿原に移行する。
執筆者:藤田 昇
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
最新 地学事典 「湿原」の解説
しつげん
湿原
mire ,fen ,bog
泥炭地(peatland)の上に湿性植物が群落を形成し生育している湿地のこと。日本では,北海道の低地~高地,本州では高地によく分布する。表流水や地下水・湧水によって涵養される湿原をfen,降水によって涵養される湿原をbogという。一般的に,bogはfenに比べてさらに貧栄養環境である。日本では低層湿原・中間湿原・高層湿原という用語がよく使われる。低層湿原はヨシ・スゲ類,高層湿原ではミズゴケ類などが優占するのが特徴で,中間湿原は両者の中間のもの。北海道の釧路湿原(低層湿原)や尾瀬ヶ原の湿原(高層湿原)などが有名。このような泥炭地とは別に,低緯度地域では,1年の内で数カ月程度冠水する場所で,嫌気的状態になり有機物の分解が進まないために形成される熱帯泥炭地もある。
執筆者:髙清水 康博・冨士田 裕子
参照項目:泥炭
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
百科事典マイペディア 「湿原」の意味・わかりやすい解説
湿原【しつげん】
→関連項目世界自然保護基金
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「湿原」の意味・わかりやすい解説
湿原
しつげん
moor; bog
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...