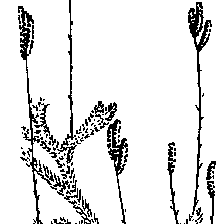ヒカゲノカズラ
Lycopodium clavatum L.var.nipponicum Nakai
山地の林下や路傍の日当りのよい場所にふつうに生えるヒカゲノカズラ科の多年生の常緑性草本。茎は主茎と側枝に分かれる。主茎は地表を長くはい,ところどころ分枝し,白色の根を出し,葉をややまばらにつける。側枝は数回,二叉(にさ)に分枝し,葉を密生する。直径は葉とともに5~10mm。葉は開出し,線形から広線形で,長さ4~6mm,幅0.5~1mm。胞子囊穂をつける枝は直立し,圧着した線形の葉をまばらにつけ,先で枝分れし,円柱状で長さ10~15cmの胞子囊穂を3~6個つける。胞子葉は広卵形,鋭先頭で先は糸状。胞子囊は葉の表側基部に1個つき,腎臓形。胞子は黄色。北海道から九州にみられ,北半球の温帯,暖帯に広く分布する。胞子を石松子(せきしようし)といい,薬用として散布剤,丸衣(がんい)などに利用する。
ヒカゲノカズラの仲間は特徴が単純なため,分類がきわめてむずかしい。この仲間はふつうヒカゲノカズラ属の中に入れられる。系統をよりはっきりさせるためにいくつかの属に分ける試みがなされているが,定説とはなっていない。ここでは近縁種よりも,姿・形のちがったものをとりあげる。マンネンスギL.obscurum L.は主茎が地中を長くはい,側枝である地上茎がよく分枝して樹木状になる。胞子囊穂が小枝端に1個つく。ヒモランL.sieboldii Miq.は着生茎がひも状で,まばらに分枝し,下垂,小さい葉が圧着する。ミズスギL.cernuum L.はやや大型で,茎が直立,枝分れし,匍匐(ほふく)枝を出す。葉は開出し,胞子囊穂は小枝から下向きにつく。トウゲシバL.serratum Thunb.は地上生で,茎が数本に枝分れして直立し,芽体をつける。葉の縁に鋸歯があり,はっきりした胞子囊穂をつくらない。
執筆者:加藤 雅啓
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ヒカゲノカズラ
ひかげのかずら / 日陰蔓
club-moss
running-pine
[学] Lycopodium clavatum L.
ヒカゲノカズラ科の常緑性シダ。径5ミリメートルの茎は長く地表をはい、針状の葉をつける。互生する側枝は直立し、さらに枝分れする。この枝の先に円柱状で長さ5センチメートル前後の胞子嚢穂(のうすい)を頂生する。北半球の温帯に普通にみられ、日本では北海道から九州にかけての丘陵地から深山にまで広く分布する。昔から親しまれた植物で、『古事記』にもその名が記され、『万葉集』巻19では「あしひきの 山下日影(ひかげ) かづらける 上にや更(さら)に、梅をしのはむ」と詠まれている(日影=ヒカゲノカズラ)。今日でも地方によっては新年や祝いの席に飾る風習がある。胞子は石松子(せきしょうし)といい、脂肪油が40~50%も含まれているため、防湿性がある。このため、かつては丸薬の衣としたり、ベビーパウダーに混入されていた。また、花火の閃光(せんこう)剤、鋳型の分型剤などにも利用されることがある。全草を煎用(せんよう)すれば利尿や通経の効があるという。近縁のアスヒカズラL. complanatumもヒカゲノカズラと同様に利用される。コスギランL. selagoも近縁種で、高山帯の岩間に生え、氷河期の生き残りとされる。メキシコでは駆虫剤に利用するが、近年、アルコール中毒の治療に有効とされるセラギンというアルカロイドが抽出された。料理のあしらいにスギのかわりに用いられるマンネンスギL. obscurumもこの仲間である。
[栗田子郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ヒカゲノカズラ(日陰の蔓)
ヒカゲノカズラ
Lycopodium clavatum; common club moss
ヒカゲノカズラ科の常緑性シダ植物。北半球の温帯から暖帯に広く分布し,山地の斜面や崖などの比較的に明るいところに生える。針金状の茎は長く地上をはい2~3mにもなり,側枝は叉状に数回分枝して斜上し,鱗片状の小さい葉を螺旋状に密生する。葉は鮮緑色で光沢があり,線形ないし広線形で硬く,中央に1本の葉脈がある。夏に,枝先に円柱形の胞子嚢穂を2~6本直立する。胞子嚢穂は黄緑色で広卵形。胞子は淡黄色四面体型で,表面に網状の模様があり,石松子 (せきしょうし) と呼ぶ。湿気を吸収しないので丸薬の衣や散布剤として使用する。また線香花火に混ぜたり,レンズの研磨にも用いられ,塗料 (特にエナメル) の伸びをよくするのにも使われる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「ヒカゲノカズラ」の意味・わかりやすい解説
ヒカゲノカズラ
ヒカゲノカズラ科の常緑シダ。沖縄を除く日本各地の崖,山腹などに多く生育し,日陰にはあまりはえない。茎は紐(ひも)状で長くのび,まばらに二叉(ふたまた)に分かれて地面をはう。葉は堅いとげ状で小さく,茎の周囲に密生。夏,2〜4叉に分枝する細い枝が立ち,頭に胞子嚢穂をつける。胞子は石松子(せきしょうし)といい,丸薬の衣などとする。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のヒカゲノカズラの言及
【鬘】より
…《万葉集》に〈梅の花咲きたる苑(にわ)の青柳は蘰(かずら)にすべくなりにけらずや〉とか〈あしびきの山下日蔭かづらける上にやさらに梅をしのばむ〉などとあるのがこの例である。ことに神事における〈ひかげのかずら〉や〈ゆうかずら〉は後世までもその形式が残り,大嘗祭(だいじようさい)には冠の巾子(こじ)から細いあげ巻の組ひもを結びたれ,これを〈ひかげの糸〉ともいい,木綿かずらのほうも,大和舞の舞人などが冠に紙の幣をつけることになごりをとどめた。 なお,かずらは髪飾のほか,頭髪の少ないのをおぎなう[かもじ](髢)や,毛髪で髷形(まげがた)をつくり頭にかぶって扮装する[鬘](かつら)の意にも用いる。…
【古生ヒカゲノカズラ】より
…初期のヒカゲノカズラの仲間で約3億7000万年前のデボン紀に産したシダ植物の化石群(目)Protolepidodendrales。ドレパノフィクスDrepanophycus,バラグワナチアBaragwanathia,[アステロキシロン]Asteroxylon,古生鱗木(りんぼく)Protolepidodendron(イラスト),コルポデキシロンColpodexylonなどを含む。…
【小葉植物】より
…[ヒカゲノカズラ]類Lycopsida(英名lycopods),石松(せきしよう)綱などともいう。シダ植物(無種子維管束植物)のうち,小葉性の葉をもった植物群で,現生にはヒカゲノカズラ属,イワヒバ属,ミズニラ属など5属があり,古生代に繁茂した鱗木(りんぼく)や蘆木(ろぼく)なども含まれる。…
※「ヒカゲノカズラ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by