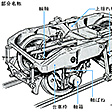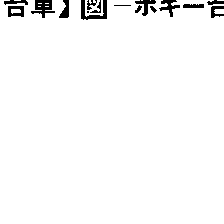翻訳|truck
精選版 日本国語大辞典 「台車」の意味・読み・例文・類語
だい‐しゃ【台車】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「台車」の意味・わかりやすい解説
台車
だいしゃ
truck
bogie
鉄道車両の車体から独立した、車輪・車軸などの走り装置を装備した構造物。通常一つの車体に対して二つの台車をもつ構成の車両が多い。台車が車体に対して自由に回転することで曲線を通過することができる。
台車の一般的な構造は以下のとおりである。足回りの最小単位として二対または三対の輪軸、軸受を収納した軸箱、台車の骨組をなす台車枠、軸箱と台車枠の間の軸ばね(一次サスペンション)、台車枠と車体の間の枕(まくら)ばね(二次サスペンション)、台車枠と車体の間に回転の自由度を与える心皿装置、車体と台車枠との間の左右方向の動きを許容する揺れ枕装置などである。車体は軸ばねと枕ばねの2段階のサスペンションで振動を抑制するのが一般的であるが、乗り心地をそれほど重視しない貨車では一方を省略することもある。また、振子列車など車体傾斜式列車の台車には、曲線通過時に乗客が感じる遠心力を緩和するための機構が取り付けられている。
[福田信毅]
分類
台車は構造によって種々の分類がされる。駆動装置が取り付けられた動軸を1本以上含む台車を動台車、動軸がない台車を従台車とよぶ。また、軸数によって、2軸台車、3軸台車とよぶこともある。2軸の動台車の軸配置をB、3軸の動台車の軸配置をCと表示することもある。4軸の機関車の軸配置でBo-Boと表示するのは2軸台車を2台もつ機関車で、二つの動軸は機械的結合がされていないことを示す。Co-Coの軸配置の機関車とは3軸の動台車を2台もつ機関車である。
なお、1990年ころから、二次サスペンションとして前後方向(台車枠が回転する方向)に変位ができる空気ばねを使い、枕梁を省略した台車(ボルスタレス台車とよぶ)が電車用台車に多く使われるようになった。これは1台車当り1トン程度の軽量化が図れるからである。
[福田信毅]
軸箱
車軸の軸受を収納するケースである軸箱は、輪軸とともにばね下質量となるので、軽量であることが望ましい。古い車両では、上下荷重は2列のころ軸受(ローラーベアリング)で支え、左右方向の荷重は玉軸受(ボールベアリング)で支えていたが、現在は2列の円錐ころ軸受(円錐ローラーベアリング)で上下・左右の荷重に対応するタイプが主流である。
軸箱と台車枠を結合する軸箱支持装置には、さまざまな構造のものがあり、それによって、台車の質量、軸箱の支持剛性が変わり、走行性能に大きく影響する。
以前は、台車枠から垂直に下げられた案内枠の中を、擦り板に沿って摺動(しゅうどう)させるペデスタル式の軸箱支持装置が多かったが、前後方向に隙間ができる、支持剛性を自由に選べないという欠点があった。1980年代なかばからは、軸箱をリンクや板バネで前後方向に拘束し、隙間をつくらない構造が採用されている(アルストームリンク式、ミンデン式)。そのほか、ゴムばねの剪断(せんだん)力で上下方向のばね定数を発生させ、圧縮力で前後方向の拘束を行うシェブロン式、円筒の中のゴムの圧縮で前後方向の軸箱の支持剛性を調節する筒型ゴム式などがある。
[福田信毅]
サスペンション
軸ばねには主としてコイルばねとゴムばねが使われている。枕ばねには、コイルばねと空気ばねが多く使用される。空気ばねには、車体重量が変わってもばねの長さが変化せず、しかもばね定数を小さくできるという利点がある。欠点は、コイルばねより高価なこと、圧縮空気の供給が必要なことであるが、現在では乗り心地のよい空気ばね台車が主流になっている。
[福田信毅]
改訂新版 世界大百科事典 「台車」の意味・わかりやすい解説
台車 (だいしゃ)
truck
鉄道車両の車体を支持して走行する装置。初期の鉄道車両には,車体にばねを介して輪軸を直接取り付けた固定軸車両が用いられた。しかし,2軸固定式の四輪車では曲線通過性能と走行性能の面から車体長に限界があるため,車両の大型化が必要となると,車体に対して回転の自由度をもたせた台車(ボギーbogie台車)を2組用いた車両(ボギー車)が生まれた。また車体長の短い2軸車でも走行安定性を向上させるため,輪軸と車体の間にはある程度の相対運動(前後,左右方向)が可能な構造が採られるようになってきている(これを1軸台車と呼ぶことがある)。
台車の構造
足まわりの最小単位として1本の車軸に2対の車輪を取り付けたものを輪軸と呼ぶが,ボギー台車は一般に,2対以上の輪軸,車軸用軸受を収納した軸箱,台車の骨組をなす台車枠,軸箱と台車枠との間で緩衝作用をする軸ばね,台車枠と車体との間で緩衝作用をする枕ばね,台車枠と車体の間に回転の自由度を与える心皿装置,台車枠と車体の間の左右方向の動きを許容する揺れ枕装置,ブレーキ装置などで構成される。軸ばねだけでは緩衝作用が不十分で,良好な乗りごこちが得られにくいので台車枠と車体の間にも枕ばねを入れているが,貨車や機関車の一部には軸ばねと枕ばねのうち一方を省略したものもある。
台車はその構造や用途によって種々分類され,さまざまの名称で呼ばれている。駆動装置が取り付けられている輪軸は動軸と呼ばれるが,この動軸を1本以上含む台車は動台車と呼ばれる。駆動装置のない軸は従軸と呼ばれ,従軸のみで構成されている台車は従台車という。動台車の中にカルダン式台車と呼ばれるものがあるが,これは電動機など駆動装置の一部を台車枠または車体に取り付け,自在継手やたわむことのできる軸を用いてばねの下にある輪軸へ駆動力を伝える方式のもので,電動機の一端を動軸上に乗せるつり掛け式台車に比べ,ばね下に加わる荷重が軽減されるため走行性能がよく,現在広く用いられている。駆動装置の軸が車軸に平行になっているものを平行カルダン式,車軸に直角になっているものを直角カルダン式と呼ぶ。
軸箱周辺の構造は台車の走行性能を決定する重要な因子となるので,この部分の構造にはさまざまの方式のものが考案されている。もっとも簡単なものは,台車枠から垂直に下げられた案内枠の中を,すり板を介して軸箱を摺動させるペデスタル式であるが,このほか,2本のリンクで軸箱を前後方向に拘束して上下動の案内とするアルストームリンク式,板ばねで軸箱を前後に拘束するミンデン式,ゴムばねで軸箱を前後方向にはさみ,ゴムのせん断で上下方向のばね作用を,圧縮で前後方向の拘束を行うシェブロン式などがある。軸ばねには主としてコイルばねとゴムばねが,枕ばねには主としてコイルばねと空気ばねが使用されている。
執筆者:福田 信毅
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「台車」の意味・わかりやすい解説
台車【だいしゃ】
→関連項目ボギー車
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「台車」の意味・わかりやすい解説
台車
だいしゃ
truck
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の台車の言及
【トラック】より
…貨物自動車ともいう。主として貨物の輸送を目的とする自動車。大型のものでは最大積載量が12tに達するものもみられ,これらのうちとくに長尺重量物の運搬には,自動車としての法規制がゆるやかなトレーラートラックが重用されている。 トラックも,基本的な構成は乗用車と大きく異なるものではない。エンジンは主として運行燃費の低減をはかるため,中型車以上ではディーゼルエンジンが採用され,その排気量は,大型車では優に1万ccを超え,2万ccにもせまるものもみられる。…
【鉱車】より
…鉱車と機関車,あるいは鉱車相互間の連結には,自動連結器も用いられるが,リンクチェーン・ピン方式が用いられることが多い。鉱石を入れる容器の代りに,平たんな荷台をとりつけたものは,台車と呼ばれて,坑木,ポンプなどの器材を運搬するのに用いられる。坑内運搬【西松 裕一】。…
※「台車」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...