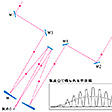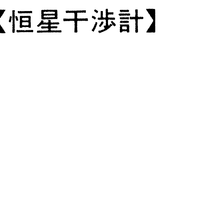日本大百科全書(ニッポニカ) 「恒星干渉計」の意味・わかりやすい解説
恒星干渉計
こうせいかんしょうけい
恒星の視直径(見かけの大きさ)、二重星の視角距離(見かけの距離を角度で表したもの)などを測定するための装置。1921年マイケルソンとピースFrancis Pease(1881―1938)が初めてウィルソン山天文台でベテルギウス(オリオン座α(アルファ)星)の視直径を測定した。これをマイケルソン式恒星干渉計という。遠方にある点光源から発した光を、ある一定の間隔だけ離した2枚の鏡で受けて焦点で重ねると、干渉縞(じま)が見える。この干渉縞の間隔は、鏡の間隔を大きくすると短くなる。実際に恒星は有限の視直径があるので、鏡の間隔を広げていくと、あるところで干渉縞が消える。このときの鏡の間隔の値から、恒星の視直径を求める。1990年代には地球大気のゆらぎによる位相の乱れを補正する補償光学技術を導入して安定した干渉縞の観測が可能となった。口径の大きな独立した望遠鏡を一つの干渉素子とする光赤外干渉計が稼働するようになり、鏡の間隔を数百メートル程度離した観測も可能になり、角視直径がミリ秒角(mas)を切る観測も行われている。多くの異なった間隔で得られた干渉縞を重ねて恒星の表面模様を求める観測も一般的になった。
恒星干渉計にはほかにロバート・ハンブリー・ブラウンRobert Hanbury Brown(1916―2002)の考案した天体強度干渉計がある。これは前者と違って光の強度のゆらぎについての干渉を測るものである。得られる干渉縞の明暗のコントラストと鏡の間隔の関係から恒星の視直径を出す。この方式では前者ほど機械的に安定な装置でなくてもよい。また大気のゆらぎによる干渉縞への影響も小さい。そのため長い鏡間隔の観測が可能であり、高角度分解能観測ができる。しかし、この干渉計の短所は、恒星干渉計のように2つのビームからの2次の相関ではなく、光の4次の相関のため感度が低く、雑音の問題で青い星しか観測ができないことである。位相が測定できないので観測目的が限られる。
[安藤裕康]
改訂新版 世界大百科事典 「恒星干渉計」の意味・わかりやすい解説
恒星干渉計 (こうせいかんしょうけい)
stellar interferometer
光の干渉を利用して微小な星の視直径を測定する器械。天体望遠鏡の空間分解能は地球大気の乱流のため1秒角程度に制限されるので,これよりも小さい恒星などの天体の大きさを直接測定することはできない。恒星干渉計は光の干渉を利用して恒星の大きさを測定する方法で,1868年にフランスのフィゾーA.H.L.Fizeauにより提案された。すなわち天体からの光を適当な間隔に置いた二つの鏡(図のM1およびM4)で受けた後重ね合わせると,光の波動性を証明したヤングの実験と同じ原理で,天体が大きさをもたない点光源であれば図のdに明りょうな干渉縞が観測される。しかし天体が大きさをもつとその異なる部分から出た光による干渉縞が異なる位相で重ね合わされるため,干渉縞は全体として見えにくくなる。このような干渉縞のコントラストの度合の解析から逆に天体の大きさを求めることができる。この方法の実際の応用は再び地球大気の乱流のため困難をきわめたが,1920年にマイケルソンA.A.MichelsonとピースF.G.Peaseはウィルソン山天文台において初めてこの方法で恒星視直径の実測に成功した。この観測では赤色超巨星ベテルギウスの視直径が0.047秒角と測定され,当時知られていたこの星までの距離を用いてこの星の半径が太陽半径の300倍にも達することが示された。その後ピースにより30年代にかけていくつかの赤色巨星の視直径の測定が行われたが,上記困難のため長い間それ以上の進展はなかった。70年代になって新しい技術的進歩をとり入れてこの方法の再生が試みられている。恒星視直径の測定には,このほか星からくる光を二つの凹面鏡で受け,光電管で増幅し各凹面鏡の出力強度の相関を測定する強度干渉法,スペックル干渉法,月による星食を用いる方法などがある。
執筆者:辻 隆
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「恒星干渉計」の意味・わかりやすい解説
恒星干渉計
こうせいかんしょうけい
stellar interferometer
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...