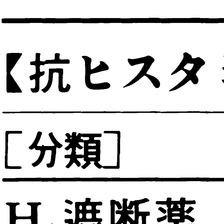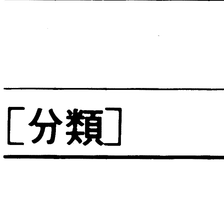改訂新版 世界大百科事典 「抗ヒスタミン薬」の意味・わかりやすい解説
抗ヒスタミン薬 (こうヒスタミンやく)
antihistaminics
抗ヒスタミン剤ともいう。生体内アミンの一つであるヒスタミンの作用に拮抗する薬物。ヒスタミンは,アレルギー性疾患や炎症の際に抗原抗体反応の結果として生体内貯蔵部位から遊離され,平滑筋の収縮(とくに気管支平滑筋が収縮すると喘息(ぜんそく)が生ずる)や血管透過性の亢進(水腫,蕁麻疹(じんましん),発疹,鼻炎などとなってあらわれる)などのアレルギー性症状の原因となっていると考えられる。アレルギー性症状のすべてがヒスタミンに起因すると考えるには疑問も多く,他の生体内物質の関与する可能性も高いが,上述の諸症状が抗ヒスタミン薬によってかなりよく緩和されることは事実である。抗ヒスタミン薬は,ヒスタミンが各組織に作用を及ぼす部位(ヒスタミン受容体とも呼ぶ)で拮抗するのであって,ヒスタミンの生成,遊離などには作用しない。1930年代からきわめて多くの抗ヒスタミン薬が開発され,上述のようなアレルギー性症状に対して用いられてきた。しかしヒスタミンには,これらの抗ヒスタミン薬によって拮抗されない作用のあることも知られており,長らく薬理学上の疑問となっていた。胃酸分泌の促進,心拍促進作用の一部,ある種の平滑筋の弛緩などである。70年代初頭にこれらの作用に拮抗する新しい化合物が見いだされ,従来の抗ヒスタミン薬で拮抗される作用をH1作用(ヒスタミンのH1受容体に対する作用)と呼び,新たに見いだされた化合物によって拮抗される作用をH2作用(ヒスタミンのH2受容体を介する作用)と呼ぶことになり一応の整理がついたが,細かい点ではまだ疑問も多い。これに伴い,抗ヒスタミン薬はH1遮断薬とH2遮断薬に大別されることになったが,単に抗ヒスタミン薬と呼ぶ場合には,従来の古典的抗ヒスタミン薬(すなわちH1遮断薬)のみを示す場合もあり,用語上の混乱が残っている。
歴史
H1遮断薬(古典的抗ヒスタミン薬)は,フランスのパスツール研究所のD.ボベらが抗アドレナリン薬の研究中,ヒスタミンと拮抗する化合物を見いだしたことを出発点として多数の化合物を合成試験し,抗ヒスタミン薬の原形というべき929Fに到達した(1937)。この化合物は毒性の強さから実用にはならなかったが,その後膨大な数の抗ヒスタミン薬が開発・使用され,現在でも相当数のものが使用されている。H2遮断薬は,フランスの製薬会社スミス・クライン・アンド・フレンチ社のブラックBlackらが約700種の化合物の中からブリママイドbrimamide,次いでメチアマイドmetiamideという化合物が従来の抗ヒスタミン薬で拮抗されないヒスタミンの作用に拮抗することを見いだし(1972),これがH1作用,H2作用という概念を生む端緒となった。これらは実用化には至らなかったが,次いで開発されたシメチジンは,ヒスタミンの胃酸分泌を抑制することから,胃潰瘍治療薬として実用化されるに至った。
化学構造
唯一の共通点はエチルアミンの構造(-CH2-CH2-N=)を有するということで,他の部分は多様である(表参照)。H1遮断薬にはヒスタミンの構造との類似点はエチルアミン構造以外ほとんどなく,H2遮断薬がむしろヒスタミンと類似の構造をもっている。
作用および適応症
H1遮断薬は,本来の作用を利用してアレルギー性疾患の対症療法に用いられる。(1)気管支喘息 効果はあまり明らかではない。(2)蕁麻疹 軟膏として用いることが多いが,皮下または静脈内注射や内服でも用いる。急性蕁麻疹にはとくによく効く。(3)皮膚炎,薬物疹 ウルシや毒虫のかぶれ,虫刺されなどではかゆみがとれる。薬物疹にも有効である。(4)花粉症,鼻炎 植物の花粉が抗原となる花粉症や,鼻炎に有効である。(5)感冒 いわゆる風邪にはアレルギー性症状を伴う場合が多いので,対症的に抗ヒスタミン薬を用いる。ほとんどの風邪薬に配合される。H1遮断薬は,抗ヒスタミン作用のほか,ほとんどすべてのものが局所麻酔作用を有する。また抗アセチルコリン作用や抗セロトニン作用を有するものもある。中枢作用としては抑制を示すものが多い。アミノアルキルエーテル類,フェノチアジン類,ピペラジン誘導体などには制吐作用,乗物酔いの予防効果があるので,制吐薬,乗物酔い予防薬としても用いられる。またプロメタジンなどパーキンソン症候群に対する治療効果が認められ,使用されているものもある。H2遮断薬は,目下胃潰瘍治療薬としての適用のみである。ヒスタミンの胃酸分泌促進作用に拮抗することを利用している。
副作用
H1遮断薬は一般的に眠け,倦怠,めまいなどの副作用を示す。消化器系には吐き気,下痢などを起こすこともある。H2遮断薬は,実用の歴史が浅く,副作用に関する情報は少ない。
→アレルギー
執筆者:重信 弘毅
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「抗ヒスタミン薬」の意味・わかりやすい解説
抗ヒスタミン薬
こうひすたみんやく
antihistaminics
ヒスタミンと特異的に拮抗(きっこう)する薬物。アレルギーの一つの原因としてヒスタミンがあり、このヒスタミンと拮抗することから抗アレルギー剤として用いられる。すなわち、急性じんま疹(しん)をはじめとしてアレルギー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎、感冒など上気道炎に伴う鼻汁、くしゃみ、咳嗽(がいそう)(咳(せき))の治療に用いられる。副作用として眠気をもつものが多く、その作用の大なるものは睡眠薬として用いられる。ジフェンヒドラミンが代表的な薬剤であり、これより作用が大きく副作用の少ないものが開発された。
アレルギーの原因としてはヒスタミンのみではなくセロトニンも関係することから、抗セロトニン作用のあるものや中枢神経に対する作用として静穏作用をもったもの、鎮吐作用、鎮咳作用や抗パーキンソン作用をもったものも開発され、抗ヒスタミン作用はその一部であるかのように考えられるようになった。またアレルギーを抑制する抗ヒスタミン薬が注射によりショックをおこした例もみられ、注射での応用はきわめて少なくなった。現在、かぜ薬の中に配合されて一般用医薬品として使用されているほか、眠気などの副作用の少ない薬剤がアレルギー性皮膚疾患やアレルギー性鼻炎の治療に用いられている。また乗り物酔いの薬としてもジメンヒドリナートがよく用いられる。
おもなものをあげると、塩酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、マレイン酸クロルフェニラミン、塩酸クレミゾール、塩酸トリプロリジン、塩酸イソチペンジル、塩酸プロメタジン、塩酸メトラジン、酒石酸アリメマジン、塩酸ジフェニルピラリン、塩酸イプロヘプチン、塩酸シクロヘプタジン(体重増加の目的でも使用される)、塩酸ホモクロルシクリジン、フマル酸クレマスチン、マレイン酸カルビノキサミン、マレイン酸ジメチンデン、ナパジシル酸メブヒドロリン、メタキシンなどがあり、抗アセチルコリン作用、抗ブラジキニン作用など抗ヒスタミン作用以外の作用もみられる。
[幸保文治]
百科事典マイペディア 「抗ヒスタミン薬」の意味・わかりやすい解説
抗ヒスタミン薬【こうヒスタミンやく】
→関連項目風邪薬|ジフェンヒドラミン|小児喘息|蕁麻疹|ヒスタミン
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
栄養・生化学辞典 「抗ヒスタミン薬」の解説
抗ヒスタミン薬
世界大百科事典(旧版)内の抗ヒスタミン薬の言及
【風邪薬】より
…症状の多様性に対応して次のような各種の薬物が配合される。
[抗ヒスタミン薬]
抗ヒスタミン剤ともいう。各種の炎症やアレルギー性症状が生体内貯蔵部位から遊離されたヒスタミンによって生ずるという考えから,抗ヒスタミン薬を配合する。…
【ヒスタミン】より
…その結果,発疹や吐き気,くしゃみ,痙攣(けいれん),下痢,呼吸困難などの症状を呈する。これらの症状は,ジフェンヒドラミンなどをはじめとする多くの抗ヒスタミン薬によって抑えられる。これらの薬剤は,ヒスタミンの作用に対して拮抗作用があることが知られている。…
※「抗ヒスタミン薬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...