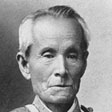精選版 日本国語大辞典 「東久世通禧」の意味・読み・例文・類語
ひがしくぜ‐みちとみ【東久世通禧】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「東久世通禧」の意味・わかりやすい解説
東久世通禧
ひがしくぜみちとみ
(1833―1912)
幕末・明治前期の公家(くげ)、政治家、外交官。天保(てんぽう)4年11月22日生まれ。竹亭などと号す。1842年(天保13)童形のまま東宮(とうぐう)出仕、以後もつねに側近として孝明(こうめい)天皇に近侍した。1863年(文久3)2月学習院出仕、国事参政となり、尊攘派(そんじょうは)公卿(くぎょう)として知られる。同年の八月十八日の政変により三条実美(さんじょうさねとみ)らと長州に逃れた(七卿落(しちきょうおち))。1865年(慶応1)長州藩から大宰府(だざいふ)に移り、1867年12月王政復古により帰洛(きらく)、新政府の参与(さんよ)に就任した。ついで明治政府の外国事務総督、神奈川府知事となり明治初年の外交を担当した。1869年(明治2)北海道開拓長官。1871年岩倉遣外使節に加わって欧米を巡視し翌年帰国。1882年元老院副議長、1890年貴族院副議長などを歴任した。著作に『竹亭回顧録維新前後』がある。明治45年1月4日没。
[佐々木克]
『霞会館華族資料調査委員会編『東久世通禧日記』上下・別巻(1992~1995・霞会館)』
新訂 政治家人名事典 明治~昭和 「東久世通禧」の解説
東久世 通禧
ヒガシクゼ ミチトミ
- 肩書
- 枢密院副議長,貴院副議長,侍従長
- 別名
- 幼名=保丸 字=熈卿 号=竹亭 古帆軒 通称=大籔 竹斎
- 生年月日
- 天保4年11月22日(1833年)
- 出生地
- 京都・丸太町
- 経歴
- 嘉永2年侍従、のち左近権少将。幕末、尊王攘夷を唱えた公家の一人。文久2年国事御用掛、3年国事参政となったが、同年8.18政変で三条実美ら6卿とともに長州兵に守られて西走(七卿落ち)、太宰府に移った。慶応3年王政復古で帰洛、参与となり、次いで外国事務総督、兵庫鎮台、横浜裁判所総督、外国官副知事などを歴任。明治4年侍従長となり岩倉具税の欧米巡遊に理事官として同行、5年帰国。のち、10年元老院議員、15年元老院副議長、21年枢密顧問官となり、23年貴院副議長、25年枢密院副議長を務めた。明治17年伯爵。著書に高瀬真卿編「竹亭回顧録―維新前後」。
- 受賞
- 勲一等
- 没年月日
- 明治45年1月4日
出典 日外アソシエーツ「新訂 政治家人名事典 明治~昭和」(2003年刊)新訂 政治家人名事典 明治~昭和について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「東久世通禧」の意味・わかりやすい解説
東久世通禧 (ひがしくぜみちとみ)
生没年:1833-1912(天保4-大正1)
幕末期の尊王攘夷派の公卿。号は竹亭,古帆軒。1863年(文久3),国事参政となったが,同年8月18日の政変で京都を追われ,七卿落の一人として長州へ下った。67年(慶応3)京都へもどって参与となり,68年(明治1)には外国事務取調掛,ついで外国事務総督となり,新政府の外交事務を統括した。69年には開拓長官として箱館に赴任し,71年侍従長となり,岩倉具視の欧米視察に同行。帰国後,元老院議官,同副議長,枢密顧問官,貴族院副議長,枢密院副議長を歴任した。
執筆者:小野 正雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「東久世通禧」の解説
東久世通禧 ひがしくぜ-みちとみ
天保(てんぽう)4年11月22日生まれ。東久世通峯(みちみね)の孫。文久3年(1863)京都から長州にのがれた七卿(しちきょう)のひとり。新政府で軍事参謀,兵庫・横浜裁判所総督,神奈川府知事,開拓長官などをつとめ,のち貴族院副議長,枢密院副議長。伯爵。明治45年1月4日死去。80歳。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東久世通禧」の意味・わかりやすい解説
東久世通禧
ひがしくぜみちとみ
[没]1912.1. 東京
幕末,明治期の公卿出身の政治家。「みちよし」とも読む。号は竹亭。文久3 (1863) 年の七卿落の一人。明治新政府参与,外国事務総督,のち貴族院,枢密院の副議長。伯爵。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の東久世通禧の言及
【開拓使】より
…版籍奉還後,ただちに開拓使が設置されたのは,日露雑居の地樺太をめぐってロシアとの関係が緊張し,北方の開拓が急務とされたからであり,開拓によって国富を増進できるのではないかという期待もあった。開拓長官は初め鍋島直正,次いで東久世通禧(みちとみ)だったが,1870年5月に黒田清隆が開拓次官になってからは,黒田が開拓使の実質的な中心となった。黒田は74年8月から開拓長官となり,鹿児島出身の官僚を多く集めたので,開拓使は薩摩閥の独占するところとなった。…
※「東久世通禧」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...