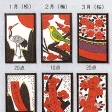精選版 日本国語大辞典 「花札」の意味・読み・例文・類語
はな‐ふだ【花札】
改訂新版 世界大百科事典 「花札」の意味・わかりやすい解説
花札 (はなふだ)
かるたの一種。古くは,〈花かるた〉〈花合(はなあわせ)〉〈武蔵野〉などと呼ばれた。通常48枚の札から成り,1月から12月までの12ヵ月にちなんだ12種類の花や草木がそれぞれ4枚ずつ描かれている。札にはおのおの点数が定められており,高い点数の札には,動物や器物などが描き添えてある。一般にゲームの便宜上,札の裏が黒いもの(黒裏)と,茶色のもの(赤裏)と2種類作られており,これらが一対として販売されることもある。おもな遊び方には〈八八(はちはち)〉〈馬鹿花(ばかつぱな)〉〈こいこい〉などがあり,地方的な特色も加わるとその種類はおびただしい数となるが,基本はだいたい下記のとおりである。通常3人で行うが,2人で行う場合もある。まず親をきめ,親から右回りに胴二(どうに),〈びき〉と呼ぶ。親になったものは,よく切りまぜた札を右回りに各人に7枚ずつわたるように2回に分けて裏向けに配り,また中央の場(ば)には6枚を表向けに2回に分けて配り,残った札は重ねたまま場の中央に伏せて置く。まず親から自分の手持ちの札を1枚出し,これと同種類(同じ月)の札が場にあれば合わせて取る。合う札がないときは,手札を1枚場に捨てる。そして,さらに場に重ねてある札を1枚めくって場に出し,これと同種類の札が場にあれば合わせて取る。合うものがなければ,そのまま場に出しておく。このようにして親から右回りに順次ゲームを進め,最も点数を多く取ったものを勝ちとする。そのほか遊びの種類によっては,出来役(できやく),手役などの得点も加算され,また配る札の枚数,点数,得点の計算方法もそれぞれ異なる。
花札の起源については諸説あるが,18世紀後半の寛政改革により賭博系統のかるた類が全面的に禁止されたため,その代用品として賭博系かるたの主流である〈天正かるた〉と,教育系かるたの流れをひく〈花鳥合せ〉とを折衷して創作されたとする説が有力である。天正かるたは,16世紀後半ポルトガル渡来のカルタを模して作られたもので,江戸時代に庶民に広まり,〈よみ〉〈めくり〉などと呼ばれて賭博に用いられたため,江戸幕府は寛政改革の以前にも,またそれ以後にも再三禁令を出したが,隠密裏に行われ生き続けた。一方,花鳥合せは,古来の貝覆(かいおおい)の流れをひく教育用の絵合せかるたの一種であり,初期のものは,同じ種類の花を2枚合わせるという単純なものであった。しかし,安永(1772-81)ころのものになると,札にそれぞれ点数が書かれていて,同種の花4枚を合わせる方式となり,その1枚には鳥獣などを描き添えて高い点数の札とするなど,賭博的な色彩をおびた。一組の枚数は200枚をこえる膨大なもので,上流階級の間でのみ遊ばれたものと思われる。この花鳥合せの絵柄の中には,松に鶴,梅に鶯,紅葉に鹿など,取合せや構図が今日の花札と同じものが幾つかある。天正かるたの構成は4種12枚,合計48枚であるが,これを12種4枚に組み変えただけで,枚数も同じ48枚とし,天正かるたの遊び方をそのまま引き継ぎ,絵柄を花鳥合せから採り入れて,優雅な花鳥風月を配した純日本的なものとするなど,巧みに偽装して花札が創作されたと考えられる。初期の花札には古歌が書き添えられているが,これも歌がるたのごとく見せかける偽装工作の一つであろう。このようにして誕生した花札も,結局は司直の目にとまるところとなり,他の賭博系かるた類とともに禁止された。当時の大坂年代記である《摂陽奇観》の文政2年(1819)の項に〈当春花合停止〉とあり,また,1831年(天保2)にも禁令が出されている。
明治に入り,新政府も引き続き花札を禁止したが,外国からトランプが輸入され自由に販売されるに及んで禁令も解かれ,花札の最盛期となり,一般庶民から上流階級に至るまで広く社交の具として使用された。初期の花札は金銀で彩色されていたため,光って見にくいうえ,絵柄もひと目で見わけ難かったので,〈八八〉の普及とともに絵柄をより図案化し,金銀彩のない花札が作られた。これが〈八八花〉つまり今日一般に使用されている花札で,このパターンが定着したのは明治20年代の後半と思われる。また,花札は日本各地でそれぞれ発展変化したため,地方札と呼ばれるその地方独特の絵柄の花札が作られた。越後花,山形花,金時花(四国)などのほか多くの種類があり,初期の花札の形態を残しているものが多かったが,現在ではその大半が消滅し,ほとんど全国的に〈八八花〉に統一された。
1902年骨牌税が施行されたが,これが今日のトランプ類税で,国内で販売される花札には税金が課せられることになっている。
→かるた
執筆者:村井 省三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「花札」の意味・わかりやすい解説
花札
はなふだ
花かるたともいい、欧米のトランプ、中国の麻雀牌(マージャンパイ)と並ぶ日本の代表的なかるた。さいころとともに賭(か)け事の用具としても使用されている。
[倉茂貞助]
歴史
天正(てんしょう)年間(1573~92)オランダの水夫によって長崎に伝えられた「うんすんかるた」からしだいに変化し、江戸末期のころつくられ普及したものである。花札ができるまでは、読みかるた、金吾(きんご)かるた、かぶかるた、めくり札などがあったが、ほかのかるたは廃れ、花札だけが今日なお広く親しまれている。花札という名称は、花の絵模様が描かれているからであろうが、本番と花番、本相撲と花相撲というように、花札の前に流行しためくり札を本札とし、それにかわる花札という意味をとる説もある。花札は48枚で、12か月に分け、絵模様によって札の月別と価値を決めている。花札はうんすんかるたやトランプと札の構成が違い、12種類の札がそれぞれ4枚ずつで、そのなかに不規則に上級の札が配列されているところに特色がある。
[倉茂貞助]
遊び方
「八八(はちはち)」「馬鹿花(ばかっぱな)」「一二三(ひふみ)」「四五六(しごろ)」「猪鹿蝶(いのしかちょう)」「三百けん」「六百けん」「こいこい」「おいちょかぶ」など30種を超える遊び方がある。なかでも「八八」が一般的でもっとも普及している。
[倉茂貞助]
八八
この遊びは普通3人で行う。合計264点の点数を3で割ると88点になるところからこの名称が出ている。勝負に参加する人数は6人以内で、まず親を決め、親が参加者に7枚ずつ配り、「場(ば)」(円陣の中央)に6枚の札をまく。残り札は重ねて伏せて置く。参加者は、配られた札のよしあしで勝負するか、一定の降り賃を払ってやめる(落ちる)かは自由。ただし親から順に3人が勝負をやめないときは、他の参加者は勝負を降りる。各回の勝負は3人または2人で争う。方法は、親から順に自分の持ち札1枚を場に出し、さらに場に伏せたまま重ねて置いてある残り札を1枚めくり、ともに場にある同じ絵模様の札とあわせてとる。あわせる札がないときは、札を出すだけである。これを、持ち札が全部なくなるまで繰り返したのち、各人がとった札の点数を計算し、3人の場合は88点を差し引いた残りが、2人の場合は2人の点数の差が勝ち点となる。これを12回行う。
八八には、とった点数のほかに、配られた札のなかにできる手役(てやく)、勝負でとった札のなかにできる出来役の2種類の役がある。手役は、三本、赤、短(たん)一、十(と)一、光(ぴか)一など12種類で、二つの手役が組み合わされているのをかさね手役といい31種類ある。出来役は、四光(しこう)、五光、雨入四光、赤短、青短、素(す)十六など15種類ある。勝負の途中で出来役ができたときは、ただちに勝負を打ち切ることができ、その場合は手役と出来役の点数を計算する。出来役ができても勝負を打ち切らず続ける場合、その後にほかの人に出来役ができて勝負を打ち切られると、前の出来役は自分の減点となる。手役と出来役の点数は、地方によって多少違うが、勝負を始める前に参加者の間で決めておけばよい。
[倉茂貞助]
おいちょかぶ
花札を使用する代表的な賭け事。花札ができる前は、「かぶかるた」という賭け事専用の札が使われていた。花札のうち雨と桐8枚を除いた40枚を使う。胴と客(親と子)に分かれ、胴は客の前に張り札として3ないし5枚の札を表を出して並べ、自分は伏せて1枚の札をとる。客は張り札を見て思い思いに金銭を賭ける。胴はさらに1枚ずつ、客が金銭を賭けているところは伏せて配り、金銭を賭けられてないところは表を出して配り、自分も伏せたまま1枚をとる。そこで胴と客とが勝負になる。2枚の札の月数の合計から10またはその倍数を差し引いて残りが9となるのを最高とする。ただ点数が6以下のときは、さらに1枚の札をもらうことができ、3枚の合計点で計算する。勝負の結果、胴が勝てば客の賭け金をとり、負ければ客の賭け金と同額をその客に支払う。おいちょかぶは点数の読み方が独特で、8をオイチョ、9をカブというところから「おいちょかぶ」の名称が出ている。
花札には「がんをつける」といって、いかさまの細工を施してある札がある。「そぐり札」「毛入りがん」「あつうす札」「ざらすべ札」「長札」「広札」「しみがん」などがあり、よほど注意して見なければわからないほど精巧にできている。
[倉茂貞助]
百科事典マイペディア 「花札」の意味・わかりやすい解説
花札【はなふだ】
→関連項目うんすんかるた|花合
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「花札」の意味・わかりやすい解説
花札
はなふだ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
占い用語集 「花札」の解説
花札
出典 占い学校 アカデメイア・カレッジ占い用語集について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...