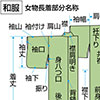関連語
精選版 日本国語大辞典 「衽」の意味・読み・例文・類語
普及版 字通 「衽」の読み・字形・画数・意味
衽
9画
[字訓] えり・すそ・おくみ
[説文解字]

[字形] 形声
声符は壬(じん)。壬にふくらむ意がある。〔説文〕八上に「衣の
 (えり)なり」とあり、衿は襟、衽はおくみをいう。左衽は東夷の俗。中国では死者の礼。〔儀礼、士喪礼〕「衽を奧に
(えり)なり」とあり、衿は襟、衽はおくみをいう。左衽は東夷の俗。中国では死者の礼。〔儀礼、士喪礼〕「衽を奧に (すす)む」、〔中庸、十〕「金革を衽(しとね)とす」のように、衽席の意にも用いる。仁の古い字形は、人の後ろに衽席をおく形で、安舒を原義とする字である。〔荘子、達生〕に「人の最も畏るる
(すす)む」、〔中庸、十〕「金革を衽(しとね)とす」のように、衽席の意にも用いる。仁の古い字形は、人の後ろに衽席をおく形で、安舒を原義とする字である。〔荘子、達生〕に「人の最も畏るる は、衽席の上、飮
は、衽席の上、飮 の
の なり」とみえる。
なり」とみえる。[訓義]
1. えり、すそ、おくみ。
2. も、はかま。
3. たもと、そで。
4. しとね、ねむしろ。
5. くさび代りのひも、両端を広くしたひも。
[古辞書の訓]
〔新
 字鏡〕衽 宇波加比(うはかひ) 〔和名抄〕袵 於保久比(おほくび) 〔字鏡〕衽 コロモノクビ・モノノヲ・ホヒ・モ・オホクビ・ヒモ・ウハカヒ
字鏡〕衽 宇波加比(うはかひ) 〔和名抄〕袵 於保久比(おほくび) 〔字鏡〕衽 コロモノクビ・モノノヲ・ホヒ・モ・オホクビ・ヒモ・ウハカヒ[語系]
衽・任・妊・恁nji
 mは同声。みなふくよかで安舒の意をもつ語である。
mは同声。みなふくよかで安舒の意をもつ語である。[熟語]
衽褐▶・衽左▶・衽裳▶・衽席▶・衽髪▶・衽服▶
[下接語]
臥衽・懐衽・衾衽・交衽・左衽・接衽・続衽・連衽・斂衽
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「衽」の意味・わかりやすい解説
衽
おくみ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「衽」の意味・わかりやすい解説
衽【おくみ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...