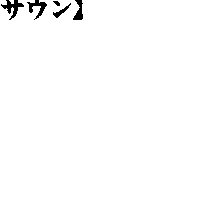精選版 日本国語大辞典 「サウン」の意味・読み・例文・類語
サウン
改訂新版 世界大百科事典 「サウン」の意味・わかりやすい解説
サウン
saung
ミャンマーの弓形ハープ。正しくはサウン・ガウsaung gaukという。〈ビルマの竪琴〉の名で知られる。舟形の胴と弓形の棹から成り,棹の先にボダイジュの葉の装飾がある。弦は絹またはナイロンの弦13~16本で繊細優美な音色をもつ。独奏または古典歌曲の伴奏に用いる。右手親指と人差指で弦をはじき,必要に応じて左手親指の爪で弦の端を押して音を変える。おもな調弦は5種類ほどあり,弦の端に結んである太い紐を棹に巻きつけて調弦する。敦煌,パガン,ボロブドゥールの仏教壁画をはじめ,高野山の《二十五菩薩来迎図》にも描かれている鳳首箜篌(ほうしゆくご)というハープがこの楽器の先祖で,古代インドに起源をもつと思われる。インド以東で現在なお演奏されている同種のハープは,ミャンマーのサウンのみである。
執筆者:大竹 知至
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サウン」の意味・わかりやすい解説
サウン
saung
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「サウン」の意味・わかりやすい解説
世界大百科事典(旧版)内のサウンの言及
【ミャンマー】より
…このときアユタヤの楽舞がビルマに伝えられ,しだいにビルマ風に変化して今日の様式が形成された。 代表的なものにサイン・ワインと呼ばれるにぎやかな野外で行われる合奏と,サウン(弓形ハープ)やパッタラー(竹琴)などによる静かな室内用音楽とがある。楽器はほかにドウンミン(箱形チター),タヨウ(3弦の胡弓),ミジャウン(鰐形チター),マダリン(マンドリンの変形楽器)や,オウジー(花杯形の太鼓)など多くの太鼓がある。…
※「サウン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...