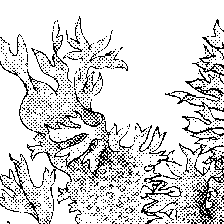トサカノリ
Meristotheca papulosa (Mont.) J.Ag.
ニワトリのとさかを思わせる紅色,肉質の美しい紅藻で,日本では関東地方以南の太平洋沿岸および九州西岸の低潮線下よりやや深いところの海底に生育する。体は厚みのある膜質で,不規則に叉(さ)状に分岐し全体は扇形となるが,側部より枝状突起を出し,また成熟すると半球状の囊果を縁辺に多数つけるので,体形は変化しやすい。大きさは10~30cmになる。海藻サラダなどの材料として市販されるトサカノリには紅色,緑色および無色の3種類があるが,いずれも同一種で,緑色のものは細胞内の紅色の色素フィコビリンが退色してクロロフィルの残っているもの,無色のものはクロロフィルも退色してしまったものである。台湾,ポリネシア,インド洋にも生育する。
執筆者:千原 光雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
トサカノリ
とさかのり / 鶏冠菜
[学] Meristotheca papulosa J. Agardh
紅藻植物、ミリン科の多年生海藻。柔らかい扁平(へんぺい)膜質の葉状体で、きれいな赤紅色を呈する。名の由来は、縁辺が不規則に裂開し、各頂部はとさか状の突出をもつことによる。古名では鳥坂苔をあてている。体の大きさ10~30センチメートル。房総半島以西の温海・暖海の外海、10メートル以浅の海底に周年生育する。とくに暖海域に多産し、古くから刺身のつまなどで食用とされていたが、ことに近年は海藻サラダなどとよばれて食品的利用が高まっている。
[新崎盛敏]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
トサカノリ(鶏冠菜)
トサカノリ
Meristotheca papulosa
紅藻類スギノリ目ミリン科の海藻。低潮線以下の岩上に生じる。藻体は膜質で平たく,不規則に叉状分岐し,しばしばのちに藻体の縁から副枝を生じたり,葉面からも突起を生じるので,いろいろな外形となる。全長 10~30cm,幅1~5cmばかりである。色は紅色で美しい。食用となる。分布は本州太平洋岸中南部より瀬戸内海,九州西岸を経て,台湾,ポリネシア,インド洋にまで及ぶ。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
トサカノリ
紅藻類トサカノリ科の海藻。本州中部以南の太平洋沿岸,瀬戸内海,九州地方に分布し,低潮線以下の岩上に生育する。高さ15〜30cm,体は扁平,肉質で不規則に叉状(さじょう)に分岐し,紅色で全体にニワトリのとさかを思わせる。サラダなど食用とする。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
トサカノリ
[Meristotheca papulosa].紅藻綱スギノリ目トサカノリ属の海藻.食用にする.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のトサカノリの言及
【海藻】より
…今日,食用にされるものは約100種にのぼる。日本の主な食用海藻としては緑藻類のアオサ,アオノリ,ヒトエグサ,ミル,イワヅタ,褐藻類のコンブ,ワカメ,アラメ,モズク,ヒジキ,ハバノリ,マツモ,紅藻類のアサクサノリ,スサビノリ,オゴノリ,トサカノリ,オキツノリ,キリンサイ,ウシケノリなどがある。
[分布]
海藻の水平分布には温度が関係し,寒海域では大型の褐藻とくにコンブ類が優占するが種数は多くない。…
※「トサカノリ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by