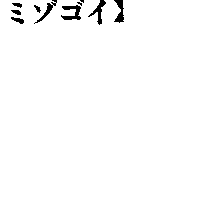ミゾゴイ (溝五位)
Japanese night heron
Gorsachius goisagi
コウノトリ目サギ科の鳥。全長約50cm。頭頸(とうけい)部は赤栗色,背以下の背面は暗赤褐色で細かい虫くい模様がある。下面は淡黄褐色だが,のどと腹には暗色縦斑がある。日本の準特産種で,本州,四国,九州,伊豆諸島で繁殖する。冬季には中国南部,台湾,フィリピンなどに渡るが,南日本で越冬するものもいるらしい。本州には4月ころ渡来し,暗い山林に単独かつがいですむ。群れはつくらない。日中は休んでいることが多く,夕方や日の出前に出て,林の中の渓流や溝で餌をあさる。食物はミミズ,サワガニ,昆虫類などで,小魚もとる。巣は,大きな木の横枝の上に小枝を集めてつくり,5~6月に繁殖する。卵は白色で,1腹3~4個を産む。抱卵,育雛(いくすう)は両親が交替でする。夜間や曇天の日にウォー,ウォーと聞こえる陰気な声で鳴く。別名をヤマイボという。近縁種にズグロミゾゴイG.melanolophusがあり,八重山列島に留鳥として生息している。
執筆者:森岡 弘之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ミゾゴイ
Gorsachius goisagi; Japanese night heron
ペリカン目サギ科。全長 49cm。頭上は黒褐色,頸,背,雨覆,尾は褐色,胸腹部は黄褐色で,前頸部から胸腹部には黒褐色の縦斑がある。脚は緑褐色。風切は黒褐色で,先端部は灰褐色。全体としては褐色の地味な鳥である。日本の本州,四国地方,九州地方にのみ繁殖分布し,中国南部,南西諸島,タイワン(台湾),フィリピンなどで越冬する。平地から山地の河川に近い森林などに生息し,樹上に単独あるいは小さなコロニーをつくって営巣する。繁殖期には日中にもよく活動し,湿地や沢でカエル,ザリガニ,小魚などをとっている。また,夜間には非常に低い声で「ぼーぼー」と鳴く。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ミゾゴイ
みぞごい / 溝五位
Japanese heron
[学] Gorsachius goisagi
鳥綱コウノトリ目サギ科の鳥。一名ヤマイボという。全長約50センチメートル。背面は赤褐色で、背や翼には暗色の細かい虫食い模様があり、下面は淡黄褐色で、のどと腹には黒褐色の縦斑(じゅうはん)がある。繁殖地は日本だけで、本州、四国、九州、伊豆諸島の山林で営巣し、冬はフィリピンや中国南部に渡るが、南日本で越冬するものもある。薄暗い林を好み、林の中の渓流や溝で昆虫類、ミミズ、サワガニなどをとって食べる。夜間ウォー、ウォーと陰気な声で鳴く。巣は樹上に小枝を集めてつくり、5、6月ごろ1腹3、4個の卵を産む。八重山(やえやま)列島からマレー諸島にかけて近縁種のズグロミゾゴイG. melanolophusが分布する。
[森岡弘之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ミゾゴイ
学名:Gorsachius goisagi
種名 / ミゾゴイ
目名科名 / サギ科
解説 / 森林にすみます。暗い林を好み川や沢を歩きながらサワガニをさがしたり、道ぞいの腐葉土でミミズをさがしたりします。主に日本で繁殖するサギです。
全長 / 49cm
食物 / サワガニ、ミミズなど
分布 / 本州、四国、九州で繁殖する夏鳥
環境 / 低山の林
鳴声 / ボォーゥ、ボォーゥ
絶滅危惧種 / ★
出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報
Sponserd by