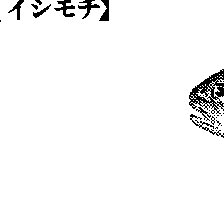イシモチ (石持)
Argyrosomus argentatus
スズキ目ニベ科の海産魚。頭骨内に炭酸カルシウムでできた大きな耳石(じせき)をもつためこの名がある。この耳石は体の平衡を保ったり,音を感じとる役目をしている。別名のシログチまたはグチは,本種がうきぶくろを用いてグーグーという大きな音を出すことに由来するが,これはとくに産卵時に顕著である。体は銀白色で,えらぶたに大きな黒斑があることが特徴であるが,ときにきわめて薄くなることもある。全長40cm余に達する。本州の東北南部以南,東シナ海からインド洋まで広く分布し,水深40~100mの砂泥底にすむ。多毛類,甲殻類,貝類などの底生動物を好んで食べる。成長は地域によって異なるが生後2年で体長20cmくらいになる。産卵期は5~8月で,5万~60万粒の卵を産む。底引網で漁獲され,おもにかまぼこの材料にされる。釣師が岸から釣る魚で〈イシモチ〉というのは,ほとんど近縁種のニベのことであり,イシモチはやや沖寄りにすむため岸からはほとんど釣れない。
執筆者:望月 賢二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
イシモチ
いしもち
硬骨魚綱スズキ目ニベ科の海水魚の1種シログチの別名。関東地方ではイシモチとよばれることが多く、また投げ釣りなどの対象種ニベをさす場合もある。名は、頭部(内耳)に大きな耳石(じせき)をもっていることに由来している。
関西ではグチまたはシログチという。秋が美味で、塩味を少し強くすると味がよい。中国料理では甘い酢煮にする。かまぼこの材料にもする。
[谷口順彦]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
イシモチ
ニベ科の魚。耳石が大きいためこの名がある。別名シログチ。地方名グチ,シラグチなど。全長40cm余に達する。北日本からインド洋まで広く分布し,近海の砂泥底にすむ。5〜8月に産卵。煮魚,塩焼によく,大量にとれるのでかまぼこの原料になる。ニベ科の魚の通性としてうきぶくろを振動させてグーグーと音を発する。釣人はニベを〈イシモチ〉と呼ぶことが多い。
→関連項目グチ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
イシモチ
[Argyrosomus argentatus].グチ,シログチともいう.スズキ目ニベ科の白身の海産魚で,体長40cmほどになる.食用魚.そのまま食べるほかカマボコなどの原料にする.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のイシモチの言及
【テンジクダイ(天竺鯛)】より
…和歌山県和歌浦でホタルジャコと呼ばれるが,別科の魚との混称である。高知県,長崎県のイシモチ,広島県のイシモチジャコは,大きな耳石(じせき)をもっていることに由来する。ニベ科の[イシモチ]とは別種。…
【ニベ(鮸)】より
…本州中部以南,東シナ海に分布する。愛知県三谷でコワイシモチ,鹿児島,長崎でヌベ,宇和島でハグチなどと呼ぶ。本科の他種とともにイシモチと呼ばれることも多いが,これは内耳にある耳石が大きいことによる。…
【ネンブツダイ(念仏鯛)】より
…そのため地方名も多く,キンギョ,ケイセイ,アカジャコ,ネブトなどがある。イシモチと呼ぶ地方もあるが,内耳に大きな耳石をもつためである。本種は本科の多くの種と同様マウスブリーダーである。…
※「イシモチ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by