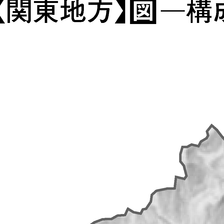精選版 日本国語大辞典 「関東地方」の意味・読み・例文・類語
かんとう‐ちほうクヮントウチハウ【関東地方】
- 東京都と神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の六県の地域の称。かつての関八州にあたり、大部分を関東平野が占める。関東。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「関東地方」の意味・わかりやすい解説
関東地方
かんとうちほう
本州のほぼ中央に位置し、東京都をはじめ、神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城の1都6県の地域をいう。関東の呼び名は、大化改新のころは鈴鹿(すずか)、不破(ふわ)、愛発(あらち)の三関(滋賀県と三重・岐阜・福井諸県との県境にあたる)から東のほうをさしていた。国土の開発が進むに伴い、平安末期からは、足柄(あしがら)・箱根両峠(東海道沿いの静岡・神奈川県境)と碓氷(うすい)峠(東山道(とうさんどう)沿いの長野・群馬県境)を連ねる線から東方および北方で、陸奥(むつ)(東北地方)より南を、関東(坂東(ばんどう))というようになり、現在に至っている。いま関東全域に首都東京の影響が及び、それに密着した動きは、東京への通勤・通学圏内の地域はもとより、より離れた地域にもみられる。なかでも東京都とそれに接する神奈川・千葉・埼玉の南関東3県は、人口・製造品出荷額がともに全国10位以内にあり、日本でも産業、文化のもっとも活発な地域をなしている。
全関東の中心で、しかも日本の中心でもある東京の前身の江戸は、100万以上もの人口が集まって世界有数の大都市に発展していた。徳川将軍家をはじめ参勤交代制によって江戸に屋敷を構えていた諸大名たちの生活物資の需要は膨大なものであった。食料(米・魚・酒・しょうゆ)、衣料(絹・綿・麻の織物)をはじめ、雑貨、道具類の製造については、関東は後進地域で、16世紀ごろには関東では入手しにくいものが少なくなく、関西(上方(かみがた))から入ってきた人々によって産地開発がなされていた。それらも17世紀になると、鹿島灘(かしまなだ)や東北南部海岸の魚や銚子(ちょうし)・野田(千葉県)のしょうゆのように、関東でもしだいにとれたり、つくられるようになった。米は食料で、また年貢用でもあったが、東北からの下り米が大量に上っていた。それらの江戸への輸送については、海岸沿いや利根(とね)川、江戸川をはじめ諸川の河岸(かし)、それに湖沼岸の諸地をたどって輸送ルートが開かれ、湊(みなと)や河岸の集落が発達していた。
1868年(慶応4)には江戸開城が行われ、ついで明治維新の新政の世となり、東京へ遷都されて日本の首都となった。そしてあらゆる中央官庁が集中し(霞(かすみ)が関・大手町地区)、外国公館も設けられ、東京は中央集権制による日本の政治・行政・外交の中心地となった。1930年(昭和5)ごろまでは東京は日本の政治・文化の中心地、大阪は商工業の中心地であったが、そのころから企業と政治との結び付きがより強められて、本社も東京に設けられることとなり、東京は日本産業の中枢管理機能の集中地ともなった。これに伴い人口の集中はいよいよ多くなり、東京通勤者の住宅地は隣接の南関東3県はもとより、近年は北関東諸県へも拡大されている。
東京はまた日本の学術文化とそれらの国際交流の中心でもある。なかでも日本学術会議や学会本部の多いことが東京の特色で、研究の向上に努めるとともに、外国学界との交流の窓口ともなっている。また、博物館、図書館、諸研究所、資料館、文書館なども多い。
横浜は開港後、日本最大の貿易港と東京の玄関口の役割を果たすこととなり、外国人の来住も急に増えていった。明治新政府は神奈川県知事に横浜税関長を兼ねさせ、大臣級の高官を配して港や市街の整備に努めた。やがて20世紀に入って工業が近代化してくると、東京下町の工場街が手狭となり、重化学工業も加わって、川崎や横浜東部に、海岸の埋立てによる臨海工業地帯が造成されて京浜工業地帯の中心となり、第二次世界大戦中にはより増強された。戦後は石油化学工業部門が加えられたが、1960年代の日本経済の高度成長期には手狭となった。その補充拡大地域が千葉県の湾岸にある京葉工業地域で、南は富津(ふっつ)市にまで及び、港(千葉港・木更津(きさらづ)港)もつくられ、石油色の濃い工業地帯となり、いま関東さらに日本の産業に果たす役割は大きい。
[浅香幸雄・中村和郎]
自然
日本最大の関東平野が広がっており、日本の8地方のうち、一つの地方としてのまとまりがもっともよい地形をなしている。まず南関東の中央に東京湾があり、その周りを関東平野が取り巻き、平野の外側のうち、南と東は海(相模(さがみ)湾、太平洋、鹿島灘(かしまなだ))で、西と北が山地となっている。西部の秩父(ちちぶ)、丹沢(たんざわ)の諸山地は広い意味の関東山地であり、その北部から北東方へかけては三国(みくに)山脈、帝釈(たいしゃく)山地の山並みが連なり、その南に中山性の足尾(あしお)山地がある。さらに北東部には阿武隈(あぶくま)高地の山丘が連なっているが、その南続きは八溝(やみぞ)山地で、最南端が筑波(つくば)山(876メートル)である。
これらの山地を地形的にみると、関東山地は甲武信(こぶし)ヶ岳(2475メートル)、雲取山(2017メートル)などの高山と、神流(かんな)川、荒川、多摩川などの源流をなす深い谷々とが隣り合って壮年期の地形をなしている。三国山脈も壮年期地形で、谷川岳(1978メートル)、三国山(1636メートル)、白砂山(2140メートル)などの峻峰(しゅんぽう)が連なっている。これらに対し、阿武隈高地は長い間の侵食によって低められ、山並みが波状をなして老年期地形となり、準平原化している地区や残丘地形もみられる。また南には、丘陵性の房総、三浦の両半島が突出している。
南西の東海地方との境をなす箱根山(典型的な三重式火山)は富士火山帯に属し、その南は伊豆半島から、大島、三宅(みやけ)島、八丈島などの伊豆諸島、さらに小笠原(おがさわら)諸島などの火山性の島々へと連なっている。また北方には那須火山帯(なすかざんたい)に属する火山群が連なり、榛名(はるな)山(1449メートル)、赤城(あかぎ)山(1828メートル)や、浅間(あさま)山(2568メートル)、四阿(あずまや)山(2354メートル)、白根山(日光白根、草津白根)の新しい火山、男体(なんたい)山(2486メートル)、それに東北地方との境に近い那須岳(1915メートル)などがある。これらの火山には火山性の湖があり、箱根の芦(あし)ノ湖、榛名の榛名湖は火口原湖、日光の中禅寺(ちゅうぜんじ)湖は溶岩堰止(せきとめ)湖である。
北部および西部の山地から流れ出る川には、中央部に利根(とね)川、荒川、多摩川、南部に相模川、酒匂(さかわ)川、北部に那珂(なか)川、久慈(くじ)川などがあり、それぞれ流域に平野をつくっている。これらの河川の中流から下流には、関東ローム層に覆われた台地や段丘地形が発達している。これは、関東地方が地質時代に、中央日本の諸地域とともに激しい隆起運動を受けたことを示すものである。また、低い沖積平野のなかでもより低いのは、東京湾から江戸川、鬼怒(きぬ)川、小貝(こかい)川の流域の南北方向に広がる一帯である。この中央部が東部の常陸(ひたち)・下総(しもうさ)の両台地面よりも低いのは、そこが構造性の陥没地帯にあたり、これを軸として東西両側とも隆起していることによるのであり、関東平野が構造盆地といわれるわけである。しかし、平野内の台地や段丘はさして高くはなく、諸河川のつくった沖積平野との間の交通を妨げることはほとんどない。湖沼は、東部の霞(かすみ)ヶ浦、北浦、涸(ひ)沼、南に手賀(てが)沼、印旛(いんば)沼がある。
気候は太平洋岸式気候区に属するが、北西部では三国山脈越しに日本海式気候の影響がみられる。平野部では、一般に気温・降水量の地域差は少ないが、南の臨海地域と北西の山沿い地域との間には大きな違いがみられる。南の房総・三浦両半島や、湘南(しょうなん)地方、伊豆諸島、小笠原(おがさわら)諸島では、気温の年較差・日較差がともに小さく、年中温和な気候である。また、伊豆諸島、小笠原諸島は、気候、植物が暖帯性・亜熱帯性で、きれいな海に囲まれている。北西部の山地から山麓(さんろく)にかけては、夏に雷雨が多く、冬はからっ風が吹く。また、京浜地方には市街地特有の都市気候がみられ、一般にやや高温で、高層ビルの間では強風(ビル風)が吹き、大気汚染度が大きく、環境保全が重要な問題となっている。
植生帯は、平野部は常緑広葉樹林帯、周辺(西部と北部)山地は夏緑広葉樹林帯、その山頂に近い高地は亜高山性植物帯に属している。平野部の常緑広葉樹林帯のうち、南部から東部へかけた海岸には暖地系植生がみられる。標高200~400メートルの山腹をみると、南部の房総・三浦両半島(清澄(きよすみ)山、大楠(おおぐす)山周辺)ではシイ林やタブノキ林(暖温帯林)がみられるが、北部、西部の関東周辺山地ではミズナラ林にクリ林(温帯林)が混在している。さらに700~1500メートルになると、南部の箱根や丹沢山地ではブナ、ミズナラ、ヒメシャラなどの高木を主とした夏緑広葉樹林が発達し、北部山地はブナ林、トチノキ林となっている。北部の三国山脈や帝釈山地では、オオシラビソ、トウヒ、コメツガなどの亜高山性の針葉樹林が発達し、尾瀬ヶ原は高層湿原として知られる。
[浅香幸雄・中村和郎]
産業
関東地方では巨大都市群に近接する立地条件のよさを利用して集約経営をし、野菜・果実・畜類飼育をあわせて生産額を高め、これらを中心作目とする都市型農家がみられる。農家数は第2種兼業、専業ともに、全体的には減少傾向にある。
水産業としては、沿岸・沖合両漁業における漁獲高は減少傾向にあり、遠洋漁業はやや伸びを示している。その拠点漁港として、銚子(ちょうし)、東京、三崎(三浦市)、那珂湊(なかみなと)(ひたちなか市)をはじめ、久里浜(くりはま)(横須賀市)、勝浦が知られる。水揚げ量のうち鮮魚としての出荷が高率であるのも、関東漁港の特色である。
関東の農林水産業における近年目だった動きとして観光化傾向がある。果物のもぎとり園、いも掘り園、観光花卉(かき)園、釣り堀などの経営者数・来客数はともに全国一であり、イチゴ狩り園、バーベキューガーデン、キノコ狩り、山菜狩りも多い。海、湖沼での遊漁も盛んで、釣り人口率は近畿、北陸とともに全国最高率である。また、農林漁家で民宿を経営するものも多い。こうして関東の農林水産業の観光化(第三次産業化)は、京浜巨大都市群住民の余暇―自由時間と所得の増加に伴い、より速く進められることであろう。
商業では、東京の都心・副都心には大規模で近代化した商店街が発達し、都の小売業販売額は全国の首位を占めている。これには都民相手のほかに関東全域から東京へ集まる買い物客への販売額も含まれている。また、卸売業販売額は小売業販売額の数倍にも上るが、これは都内はもとより、関東全域、さらに東日本一帯への売りさばきによるものである。これとは別に、近年は地方の中心都市に、東京の問屋やメーカーの販売店、サービスセンターが設けられ、また東京のデパートやスーパーマーケットの地方進出もみられ、地方の問屋や小売店にショックを与えている。そのほか、地方資本によるデパートやスーパーマーケットも発達してそれぞれ販売網を形成している。それらのなかには、東京のそれらと仕入れ、販売、宣伝などについて協定しているものも少なくない。なお、諸地方(県単位が主)には地方銀行が発達しているが、東京に本店のある都市銀行をはじめ、諸金融機関で地方都市へ支店を出しているものが多く、東京と関東諸地域との経済的な結び付きは、より深くかつ広範に強められている。
京浜工業地帯の工業出荷額はわが国四大工業地帯中第1位で、それに京葉工業地域や埼玉県、さらに茨城・栃木・群馬3県の近年の工業伸張の著しさは全国第一級である。工場数は東京は群を抜いて多いが、神奈川県では有力な大規模工場が目だち、1工場当り出荷額の多いことが特色であり、千葉・埼玉両県の新工場にも同じ傾向がみられる。また、京浜の工業は、機械、金属、化学、食料品、出版・印刷、さらに最新の先端技術産業などの諸分野にわたり、製品も素材や部品から完成品までがみられ、親工場・下請工場間の系列化もみられる。ここは技術革新の先駆地域で、工業関連の技術研究の高水準でも知られ、大規模で高度な研究者をもつ研究所の多いことも特色となっている。
京浜工業地帯の中心は、東京、川崎、横浜のほか、横須賀を加えた臨海地域で、川崎を中心に横浜、東京(江東区)には大製鉄工場があり、それに直接結ばれる造船、自動車、車両、重電気機械、また食料品、精油、それに石油化学コンビナートが2グループ建設されて、それぞれ特色ある施設・装置を備え、阪神工業地帯とともに全国をリードする新鋭工業地帯となっている。多くの埋立地に立地した大工場には、それぞれ専用の埠頭(ふとう)(工業港)が設けられ、航洋船が接岸して原料、製品の出し入れにあたっているのが特色であり、工業地帯は東京湾奥から東の千葉県の沿岸へと広がり、船橋、千葉、市原から木更津へ向かって拡大され、全国有数の大企業が進出して、京葉工業地域とよばれる。
近年は、これら東京湾岸に続く内陸地域、すなわち東京の北東部、川崎の北西部の多摩川低地、横浜の北郊・西郊の諸地域では、軽電機器をはじめ、ロボットによる各種の機器組立工場の建設が目だっている。そしてこれらは、さらにいくつもの幹線道路沿いに、湘南(しょうなん)(鎌倉の大船、藤沢、茅ヶ崎(ちがさき)、平塚、小田原)や神奈川県中央部(相模原(さがみはら)、大和(やまと)、厚木、伊勢原(いせはら)、秦野(はだの))、埼玉平野の諸都市(川越、川口、さいたま、熊谷(くまがや)、越谷(こしがや)、春日部(かすかべ)など)、千葉県北東部(松戸、柏(かしわ)など)、北関東の諸都市(高崎、前橋、太田、佐野、栃木、小山(おやま)、宇都宮、真岡(もおか)、土浦、水戸、ひたちなか)へも広がり、工場の増設が相次いでいる。また、茨城県南東部の鹿嶋(かしま)市と神栖(かみす)市にまたがって、鉄鋼と石油化学工業を中心とする鹿島臨海工業地域が形成されてきた。
関東地方には、明治時代におこった近代工業のほかに、歴史の古いもので近代化しているものもみられる。北部から西部にかけた山麓(さんろく)の桐生(きりゅう)、足利(あしかが)、伊勢崎(いせさき)、秩父(ちちぶ)、青梅(おうめ)、八王子などの諸機業は、江戸時代におこった伝統をもとに新しいくふうが加えられ、さらに化学繊維部門を取り入れて製品にも新生面を開き、中小企業者は団地へ集結して合理化に努めている。利根川下流地域の野田、銚子では歴史の古いしょうゆ醸造業が発達している。
これらの諸工業のエネルギー源としては、横須賀をはじめ横浜、川崎、東京、千葉などに出力100万キロワット以上の巨大な火力発電所が建設され、これが中心的動力となっている。そして早くから開発されていた水力電気はその補助として、関東地方はもとより、中部地方東部から東北地方南部にわたるいわゆる関東外圏に送られている。また茨城県東海村におこった原子力発電は、福島県の原子力発電所からの送電を補充して工業動力として使われている。
こうした国内第一の関東の工業、しかもその急激な発展は、核心の京浜工業地帯をはじめ諸地域に各種の公害をもたらしている。これらの諸公害に対し近年規制措置がより強化されている。このため京浜工業地帯の核心地域の川崎、横浜両市から北関東3県や山梨県などへ移転し、新しい無公害施設のもとで生産の増強を図る工場が増えている。また、工場が減った両市では環境問題は緩和されたが、市財政や市況の活性化を損することとなり、その対策が新しい課題となっている。
[浅香幸雄・中村和郎]
交通
明治維新後は、東京を中心とする幹線鉄道の建設が国策として進められ、明治中期には東海道、中央、高崎、東北、常磐(じょうばん)の諸線がほとんど開通し、首都東京と京阪神をはじめ、東日本諸地域との鉄道連絡が完了した。ついで明治後期には、私設鉄道(おもに軽便鉄道)の建設熱が盛んになり、京浜、京王、東武の諸線が開通した。大正時代に入っても、国鉄(現、JR)、私鉄(西武、東急など)の幹線・支線の新設や延長が相次ぎ、昭和初期にはほぼ現在の鉄道網が建設、整備された。また、昭和初期には東京に地下鉄が開通したが、第二次世界大戦後になって大規模な拡張が進められ、都区内相互間には東京地下鉄株式会社(通称・東京メトロ。旧帝都高速度交通営団)と東京都営による13路線に上る地下鉄網が形成されている。横浜でも市営地下鉄が複数の路線で運転され、新路線も検討が進められている。これらのJR、私鉄、地下鉄は、東京とその通勤・通学圏の神奈川、千葉、埼玉、茨城の関東4県間で相互乗り入れをし、利用圏がより拡大されている。また1964年(昭和39)には東海道新幹線が東京―新大阪間に開通して日本の鉄道交通に革命的超高速をもたらしたが、さらに1983年には東北、上越の両新幹線が、1992年(平成4)に山形新幹線、また時速270キロメートルの「のぞみ」が、東京―博多間を5時間04分で結ぶようになり、1997年には秋田新幹線と北陸新幹線(長野行新幹線ともいう)が開通し、地方と首都圏との移動時間の短縮化が進んでいる。
道路は、もっぱら国鉄依存であった貨物の長距離輸送が、大正初期以後には国道を併用して行われるようになって整備されるようになった。そしてまず、関東周辺山地を横切る諸街道の峠道の改良が始められ、昭和初期には国道筋の峠道は、ほとんど自動車交通が可能になった。第二次世界大戦中には、京浜間の交通を緩和するため第二京浜国道(現、国道1号)、産業道路、東京環状道路(国道16号)が新設された。そして、戦後は相次ぐ道路整備計画に基づいて、国道はもとより都道・県道の改良、舗装が促進され、新たに第三京浜道路、旧国道のバイパス道(現、国道20号・17号・18号・4号・6号の諸線)がつくられ、主要都道・県道の国道昇格がみられるなど、幹線道路の整備が急速に進められた。また、1964年には東京オリンピックの東京開催を機として首都高速道路の一部、ついで1969年には東名高速道路が通じた。のち中央、関越、上信越、東北、常磐、東関東、北関東、圏央、東京外環の各自動車道、首都高速湾岸線などの自動車道が相次いで建設され、関東の沿道の諸要地にインターチェンジが設けられている。これらの道路上には定期のバスやトラックがくまなく行き渡り、一般車の利用も多く、関東のそれらの交通量は全国最高である。1997年(平成9)12月には川崎―木更津間に東京湾横断自動車道路(延長約15キロメートル)の東京湾アクアラインが開通。なお、21世紀の高速交通体系の基幹路線としては、第2東名高速道路の建設が予定されている。
関東地方の主要港は、横浜、東京、千葉、川崎それに横須賀の諸港で、東京湾に集中している。横浜港からは、アジア、北アメリカ、ヨーロッパをはじめ、世界の主要港へ定期航路(貨物船)が通じ、日本の海の玄関口となっている。1980年代には同港の貿易額は、輸出で全国の約5分の1、輸入で約10分の1を占めていた。また千葉港の貿易額も全国上位で、輸入は原油がおもである。しかし、東京湾内の海運能力は飽和化を示し、出入口の浦賀水道は海難事故の危険性が高くなっている。そのため、東京湾外に新港を求める動きが目だち、鹿島工業整備特別地域の拠点として鹿島港が開港し、日立港も整備されている。
航空では、早く開港した東京国際空港(羽田空港)は、いまはおもに日本国内線用の空港とされ、国際便も一部利用している。ここの滑走路は短く、また数も少ないため、隣接の海面に埋め立て拡張工事が進められ、1997年7月より24時間稼働体制となり、1日の発着便数は大幅に増えた。また羽田空港から国際線を分離するために建設された新東京国際空港(現、成田国際空港)は1978年に開港し、日本の海外諸国に対する空の玄関口として、国際線定期便の離着陸が相次ぎ、貨物専用機も発着している。
[浅香幸雄・中村和郎]
開発
1960~1980年の20年間の関東の人口増加数は全国のそれの2分の1にも上り、ことに南関東の4都県での増加が著しかった。人口とともに工業、商業などの諸産業もまた関東、とくに南関東に集中しており、急激な都市化が進み、これに伴って住宅をはじめ交通・水、その他都市環境について問題がおこり、都市化のひずみが現れている。
こうした傾向は、第二次世界大戦後の混乱が収まりかけた1950年代早々から現れ始めたので、1956年(昭和31)に首都圏整備法が制定され、巨大都市の人口や産業の集中を抑制し、都市環境の整備が図られることとなった。それを具体化する第一次の首都圏整備計画では、東京を中心とする半径100キロメートル圏について、A既成市街地と、Bその周辺、Cその外側の周辺地域の3圏に分けて対策がたてられた。すなわち、A既成市街地については工場、大学などの新増設を抑制し、Bその周辺地域は近郊地帯としてグリーンベルトとする。Cさらにその外周地域は市街地開発地域として衛星都市をつくり、人口と産業の吸収を図ることとした。しかしこの計画は、その後の人口、産業の激増によって期待された効果をあげえず、ことにB地帯では開発も進み、乱開発状態を呈するようになった。そこで1966年には首都圏整備法を改正し、第二次首都圏基本計画が制定された。そこではとくにBの既成市街地周辺を改め都心から半径50キロメートル地域を近郊整備地帯とし、人口、産業の流入は認めるが乱開発は極力防止することとし、C地帯での衛星都市開発をより促進することとした。そしてB地区には近郊緑地保全区域も設定した。
その後も関東諸地域はそれぞれ急速に発展し、人口3500万に上る巨大都市ともいうべき状況となり、東京から放射状に出る幹線道路沿いはもとより、それらの中間地域でも無秩序な市街化がみられるようになり、改善整備に急を要するものが少なくない。東京をはじめ全関東のおもな問題点と、現在進められつつあるおもな対策事業をみる。
(1)住宅整備 東京都の人口は1980年まで減少傾向をたどっていたが、その後また増勢に転じている。都民の住宅数は世帯数を上回ってはいるが、質的には不十分で、全国の平均住宅水準以下のものが4分の3にも上っている。これに対し東京都では、マイタウン構想のもとに既成市街地や区部居住空間の再開発、再利用計画に取り組んできた。また都は、大規模開発として多摩、八王子両ニュータウンをはじめ、スプロール化を防ぎ、職と住とが調和した計画的な市街地づくりも各地で進めている。
(2)道路整備 関東では上記したように東京を中心とする放射状幹線自動車道をはじめ、それに並行する国道・県道は整備されているが、それら相互を結ぶ環状道路の整備が後れていた。1992年(平成4)東京外環自動車道が供用開始され、首都圏中央連絡自動車道の建設が進んでいる(一部開通)。
(3)鉄道整備 東海道・山陽新幹線に次いで、1983年には東北、上越両新幹線が開通し、1997年(平成9)には北陸新幹線も高崎経由で長野までが開通している。また、東京と隣接の南関東諸地域(都市化進行地域)間の鉄道の新設や延長工事が行われてきた。JRの通勤別線(大崎―大宮間・埼京線)をはじめ、新設、延長、増設の諸線は、ほとんどが延長運転や相互乗り入れ方式で利用効率を高め、都心との短絡化にくふうを凝らしているのも特色である。
近年の開発で注目されるものに、研究・文化施設の増強の著しさがあげられる。筑波研究学園都市(つくばけんきゅうがくえんとし)の建設は国営で、国際交流機能を大きく発揮し、1985年には国際科学技術博覧会(つくば'85)が開かれた。国立歴史民俗博物館(佐倉市)、昭和記念公園(東京)、子ども総合科学館(栃木)、さいたま水族館(埼玉)、テニスの森(東京)、湘南(しょうなん)国際村(神奈川)などの建設が相次いでいる。
さらに、ウォーターフロント開発が進められ、東京湾一帯の変貌が著しい。国際化、情報化の進展に対応して、横浜・東京・千葉では競って湾岸に多様な機能をもつ新都心を建設しつつある。横浜市はこれまで臨海部にあった旧国鉄ヤードや造船所などを移転させて、そこに日本一の高層ビルになった「横浜ランドマークタワー」や、「クイーンズスクエア横浜」などが開設されており、首都高速湾岸線が横浜ベイブリッジで横浜港をひとまたぎする。東京都は青海(あおみ)・有明・台場地区などに新都心を建設し、表玄関となるレインボーブリッジと、新交通システムによる東京臨海新交通(ゆりかもめ)が開通した(1995)。千葉県も幕張新都心に、東京都は13号埋立地や台場地区などに、臨海新都心開発を進め、日本最大の日本コンベンションセンター(幕張メッセ)がつくられた。開発の進んだ京浜・京葉地区と、まだ開発余力の大きい房総地区とを結ぶための東京湾横断道路も開通し、川崎―木更津(きさらづ)間の距離が大幅に短縮された。
[浅香幸雄・中村和郎]
人口
1960年(昭和35)の関東地方の人口は2300万であったが、その20年後の1980年には約3490万になった。この20年間に約1190万の増加をみたわけである。これら人口の全国比は、1960年には24.6%であったのが、1980年には29.8%となったのであるから、約5ポイントの増ということになる。しかも、その増加数1190万は同期間の全国増加数2354万の2分の1にあたる。この20年間の時代の性格(産業・経済・社会)の変遷を考えると、1960年は日本経済の高度成長が始まろうとしていた時期で、その後は高度成長とオイル・ショック、ついで低(安定)成長を経てきたのであった。その20年間に、面積からは全国の8.6%にすぎない関東に全日本の増加人口の2分の1が集中したことになる。人口が地域の産業・経済・社会活動の総和を表すものとすると、1960年以後の日本経済の高度成長の2分の1もが関東を舞台に進められたといえ、現代日本に果たしつつある関東の役割の大きさが知れる。人口の伸びは、それ以降も続いており、1990年(平成2)3854万人(全国比31.2%)、1995年3952万人(同31.5%)と、全国の人口の30%を超えた。2000年には4000万人を超え、2005年は4149万人となる。
また、1960年の人口を100%とすると、1980年のそれは関東全体では151.7%となるが、都県別にみると、埼玉・千葉・神奈川の南関東3県はともに200%を超えている。これに対し茨城・栃木・群馬の北関東3県と東京都は120%前後で、全国平均なみの増加率にとどまっていて、同じ関東でも相当な地域較差のあることが知られる。1990年に入っても、埼玉・千葉・神奈川の南関東3県は人口を伸ばしている。1991~1995年の5年間で、3~5%増、さらに茨城も3.9%増で、伸び率では、神奈川を抜いて第3位となった。一方、東京都の人口は1991~1995年の5年間で、1.7%の減と、東京と南関東諸県との数値の間にはいわゆる人口増加のドーナツ化現象がおきていた。しかし2000~2005年の増減率をみると、東京都の4.2%が最も高く、ドーナツ化現象に歯止めがかかっている。
[浅香幸雄・中村和郎]
歴史
縄文時代には、魚貝を得やすい東京湾岸をはじめ海岸地方に人々が集まり、また山地にも生活の基盤を置いていたので、関東地方は東北地方とともによく開けていた。しかし弥生(やよい)時代に入ると、水利をはじめ稲作条件が整っている近畿や西日本がまず開け、ついで東日本へと広がってきたので、台地の広い関東の水田開発は相当おくれてからなされたようである。そして、古代の国家勢力の進展に伴う、古墳文化や仏教文化も、近畿から関東へと伝えられてきた。大化改新のとき関東の諸地域に置かれていた国造(くにのみやつこ)は廃止され、新たに相模(さがみ)・上総(かずさ)(安房(あわ)は奈良時代に上総から分立)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)(以上東海道)、上野(こうずけ)・下野(しもつけ)・武蔵(むさし)(以上東山道。武蔵は奈良時代に東海道へ入る)の国々ができ、それぞれの国には国府が設けられ、行政を進めるために国司が置かれた。中世になると、源氏や北条氏などの関東武士が権力を握り、鎌倉は政治の中心地となった。また鎌倉五山を中心とする禅宗文化(鎌倉文化)は、いまに数々の貴重な文化を残している。しかし、これも大きくみると、近畿の文化には及ばないものであった。南北朝から室町・戦国に至る時代は、関東の進展が停滞した時代で、その庶民社会の進み方は近畿に比べて緩慢であり、足利学校(あしかががっこう)が建てられてはいるが、関東の儒学の研修や宗教活動は、近畿や北陸に比べると低調であったとされている。
江戸幕府ができて、関東の政治力の比重が大きくなり、江戸は急速に都市的発展を遂げ、江戸中期から後期にかけては、消費文化の華を咲かせた。また、江戸からやや離れた水戸をはじめ川越、小田原、佐倉、館林(たてばやし)、宇都宮、前橋など数十か所に城下町がつくられ、ともに藩内の行政・流通・文化の中心となってはいたが、関東のそれらは小藩、小城下町(陣屋町程度)にとどまっていた。したがって、江戸時代の都市らしいものは江戸ぐらいで、関東の地方文化はまだまだ低水準であった。当時、関東地方では、タバコ、ユウガオ(かんぴょう)、大麻、クワなどの商品作物が栽培され、製茶、絹織物、酒やしょうゆの醸造、木工業、水産加工業などの消費財製造業が各地に発達していたが、普及状況や技術水準は西日本のそれよりも低く、生産量も少なく、江戸市民向けの上質消費物資の多くは、廻船(かいせん)によっておもに近畿地方から移入された。元禄(げんろく)文化は上方(かみがた)(近畿)のものが優れ、文化・文政(ぶんかぶんせい)年間(1804~1830)になってようやく江戸文化が日本的に有力となった。
明治の遷都によって日本の首都となった東京(1868年江戸を東京と改称)は、横浜とともに順調な発展を続けてきた。しかし、これも政治を背景にした発展で、明治・大正時代には、横浜の貿易は全国を圧してはいたが、一般商業取引、工業生産はともに近畿の比重が関東よりも大きかった。1935年(昭和10)ごろから京浜の産業経済活動は阪神を上回るようになり、大学や出版をもとにした文化的活動も東京がより活発となり、各方面とも積極性に満ちた現代京浜の姿にかわってきた。
[浅香幸雄・中村和郎]
民俗
関東地方は日本列島の中央部に位置しているため、民俗的にも東西文化の接点である。刈上祭(かりあげまつり)は、気候と密接な関係があり、北部ほど早く南部は遅い。九州は霜月祭(しもつきまつり)、近畿、中国、四国は十月亥の子(いのこ)、東日本は十日夜(とおかんや)、北日本は9月の三度の九日(くんち)(9日、19日、29日)に行われている。亥の子も十日夜も、餅(もち)を搗(つ)いて作神様(さくがみさま)を祀(まつ)り子供が集団で土を打つ行事であるが、亥の子は静岡県から神奈川県、東京都を経て、千葉県から茨城県南部に伸びている。十日夜圏は群馬、長野、山梨各県から新潟、栃木、茨城の一部へ伸びている。埼玉県は十日夜圏であるが、亥の子の名称も混在している。関東地方に分布している行事で、2月と12月の8日に鬼や一つ目小僧がくるといって目籠(めかご)を竿頭(かんとう)高く掲げる「事八日(ことようか)」は、神奈川、東京、埼玉から群馬、栃木、茨城にかけて行われている。また、一つの石に男女の像を刻んだ双体道祖神や道祖神焼きは、群馬から長野、山梨、神奈川にかけて分布している。
関東地方は、日光、赤城(あかぎ)連山や筑波(つくば)山、秩父(ちちぶ)山地、丹沢(たんざわ)山地などの山々に囲まれているため、榛名(はるな)講、古峰(ふるみね)講、三峰(みつみね)講、武州御岳(みたけ)講、大山石尊(おおやませきそん)講などの著名な山岳信仰関係の講が多く、豊作祈願、雨乞(あまご)い、火伏せ、盗難除(よ)け、成人儀礼などさまざまの信仰を集め、近世中期以降観光や娯楽を兼ねた代参講が盛行した。また、利根(とね)川、那珂(なか)川、荒川、多摩川などの流域には由緒ある名社が多い。元荒川と多摩川に挟まれた関東ローム層の台地上には氷川神社(ひかわじんじゃ)(本社埼玉県さいたま市大宮区)が、利根(とね)川流域および江戸川流域には香取神社(かとりじんじゃ)(本社千葉県香取市)が、利根川から筑波山麓(さんろく)にかけては鹿島神社(かしまじんじゃ)(本社茨城県鹿嶋市)が分布している。武蔵野(むさしの)台地は古く出雲(いずも)系の一族によって開発され、利根川下流域はそれよりのちに大和(やまと)朝廷の東国進出の拠点となったものと考えられる。利根川流域や鹿島灘(なだ)に分布している大杉神社(本社茨城県稲敷市)は、舟運関係者に信仰され、近世中期の利根川水運の盛行とともに信仰圏を広げたものである。
土地のやせた山地と武蔵野の逃げ水などといわれる地下水面の低い関東平野は畑作優越地域であり、ムギ、サツマイモ、かんぴょう、こんにゃくなどの特産地となっている。養蚕は群馬、埼玉両県で全国繭(けん)産額の4分の1程度を産出し、茨城県もそれに次ぐ。蚕影(こかげ)様、絹笠(きぬがさ)様、オシラ様などいろいろの蚕神が信仰されているが、1月15日の小正月(こしょうがつ)や2月の初午(はつうま)に、ヤナギやコナラなどの枝に丸いものや繭型の繭玉団子をつけて繭の豊産を祈る行事は、関東地方一帯で行われている。稲作は畑作に比して低調であるが、台地や丘陵地帯の縁辺部の谷地田(やちた)では、田植をせず堆肥(たいひ)や灰などに種籾(たねもみ)を混ぜて直播(じかま)きする摘田(つみた)が行われていた。
民家の間取りは関東型とか西南日本型といわれる田の字型四間取りが多いが、東北地方に多い広間型もみられる。また、河川流域には奥の部屋や馬屋を突き出したツノヤも多く、洪水に備え高くかさ上げして土蔵を建てる水塚(みづか)もみられる。冬季のからっ風に備えた屋敷林は北関東地方の特徴である。一方、千葉県安房(あわ)地方には、母屋(おもや)と釜屋(かまや)などを別棟にする西南日本型の分棟型民家が多く、黒潮文化圏の影響が認められる。
関東地方の民俗には、葛西囃子(かさいばやし)、神田囃子のように江戸(東京)の民俗の影響の強いものもあり、東京からの距離や民俗文化伝播(でんぱ)の経路による差もみられる。稲荷(いなり)神の信仰も東京をはじめ関東各地に伝播しているが、東京、神奈川、埼玉の平野部では2月初午に祀(まつ)り、群馬、栃木などでは秋に祀る所が多い。
[内田賢作]
民話
首都東京をはじめとして、関東地方での民話の伝承状況は、早くから希薄であった。これは、江戸末期に青本や赤本(子供向き絵本)が盛行したことにも原因があったと思われる。都市部にあって語り手は早くから文字に追われていたのであろう。しかし、八丈島や房総半島の海村部、または奥武蔵(おくむさし)、秩父(ちちぶ)地方、奥利根(おくとね)などの山間部には、比較的遅くまで口語りの世界が残されていた。とりわけ関東北部の群馬、栃木の2県には、今日まで多くの話が伝えられてきた。なかでも群馬県利根郡、吾妻(あがつま)郡や栃木県芳賀(はが)郡などには、濃密な昔話の伝承が確認されて、関東にあって特徴ある伝承圏を形成している。利根郡は、福島県や新潟県に接し、越後瞽女(えちごごぜ)や飴(あめ)売り、桑摘みに通う出稼ぎ人などの通う道にもあたっている。それがために「熊の恩返し」「金の瓜(うり)」などの珍しい話もみいだされている。また吾妻郡は、俗に善光寺道とよばれる信州に通じる道筋にあたり、民話にもその影響が認められる。関東の山間地帯は、苧(お)(カラムシ)績(う)みや莚(むしろ)編み、木地挽(ひ)きなどの生業のなかに伝承の場が設けられた。実際、そうした夜なべ仕事の場が、古くから民話の揺籃(ようらん)であった。たとえば栃木県芳賀郡は葉タバコの生産地であり、昔話は葉タバコのしの夜仕事のなかで眠気を覚ますために語られていた。一方、都市部に近い神奈川、埼玉、茨城各県には、総じて「舌切り雀(すずめ)」「花咲爺(はなさかじじい)」「兎(うさぎ)と亀(かめ)の競走」「こぶ取り爺(じじい)」「かちかち山」「猿蟹(さるかに)合戦」「桃太郎」などの五大おとぎ話またはイソップ寓話(ぐうわ)の影響によって流布した話の浸透が著しい。足柄山の「金太郎」、上州館林(たてばやし)茂林寺(もりんじ)の「分福茶釜(ぶんぶくちゃがま)」、相模原(さがみはら)諏訪(すわ)神社の「蛇聟入(へびむこいり)」などのように、伝説化されて、その土地に定着した例もみられる。大都市を控え、諸職の出入りの多い土地がらを反映しているのが特色であるが、栃木県の「栗山(くりやま)話」、千葉県の「増間(ますま)話」、「印内の重右衛門話」、茨城県の「安寺持方(あてらもちかた)話」「額田(ぬかた)のたっつあい」などの愚か村話、笑い話はその典型的なものである。
[野村純一]
『藤本治義著『地方地質誌 関東地方』(1952・朝倉書店)』▽『大明堂編集部編『新日本地誌ゼミナール 関東地方』(1986・大明堂)』▽『日本地誌研究所編『日本地誌5~8巻 関東地方』(1981、1983・二宮書店)』▽『『図説日本文化地理大系 関東1~3』(1960~1963・小学館)』▽『『日本の地理3 関東編』(1961・岩波書店)』▽『鈴木重光ほか著『日本民俗誌大系8巻 関東』(1975・角川書店)』▽『宮田登、宮本袈裟雄編『山岳宗教史研究叢書8 日光山と関東の修験道』(1979・名著出版)』▽『野村純一著『日本の世間話』(1995・東京書籍)』▽『網野善彦ほか編『日本民俗文化大系 全14巻・別巻1』(1994・小学館)』

関東地方地勢図

関東地方位置図

八溝山

筑波山

浅間山

白根山(日光白根)

白根山(草津白根)

男体山

西山(八丈富士)

芦ノ湖

榛名湖

中禅寺湖

霞ヶ浦

涸沼

印旛沼

尾瀬(群馬県側)

利根川河口

国立歴史民俗博物館

東京湾横断道路(東京湾アクアライン)

東京国際空港(羽田空港)

横浜ベイブリッジ

レインボーブリッジ

ゆりかもめ

足利学校

氷川神社

香取神宮
改訂新版 世界大百科事典 「関東地方」の意味・わかりやすい解説
関東地方 (かんとうちほう)
本州の南東部,太平洋に面する地方。東京都をはじめ,隣接する神奈川,埼玉,千葉および北部を占める群馬,栃木,茨城の6県より構成される。明治以前,関八州(相模,武蔵,安房,上総,下総,常陸,上野,下野)といわれた地域とほぼ一致する。古くは三関(鈴鹿,不破,愛発(あらち))以西の関西に対して関東の呼称が使われ,その後足柄,碓氷の坂(峠)以東を指して坂東とも呼ばれた。西と北を山地に囲まれた日本最大の関東平野が約半分の面積を占め,南と東は海に面するという自然的単元としても,東京を中心とした文化的・経済的性格においてもまとまった特色を示している。伊豆諸島,小笠原諸島を含む面積は3万2425km2,人口約4260万(2010)で,人口密度は1218人/km2,全国平均の3.6倍に達する。
自然と生活
関東地方の北および西は,標高2000m級の三国山脈,関東山地をめぐらし,南西端近くに箱根山(1438m)があって中部地方と区画され,北東部から北西部にかけては那須岳,関東地方最高峰の白根山(2578m)を含む日光火山群,赤城山,榛名山,草津白根山,浅間山などの火山および北東部には阿武隈高地が東北地方から延びている。これらの山地に源を発する利根川,相模川,多摩川,荒川,那珂川,久慈川などの河川は関東平野を潤して,東京湾,相模湾,あるいは鹿島灘に注いでいる。丘陵の広い房総半島,三浦半島では太平洋側が高く,両半島を流れる河川の多くは,北または北西へ流れて東京湾,相模湾へ注ぐ。関東地方は大きく浅い盆地となり,その最も低い部分は,渡良瀬川が利根川本流に合流する古河(こが)市付近で,赤麻沼が洪水調整池となっていた。江戸川との分流点,関宿の堤防が切れると江戸が危いといわれ,河道の付替えなど治水工事は江戸時代から現代までくり返し施工されてきた。また東京都の東端部には地盤沈下のため海抜0m以下の部分も存在する。
武蔵野,相模原,下総台地などの台地が広く,畑地に利用されていることも関東地方の特色である。台地の表面は箱根山,浅間山,赤城山などの火山灰を被り,赤土の関東ローム層となって,冬は霜柱が立ち,春は風塵が舞いあがりやすい。水利が悪いために開発が遅れ,平地林として近年まで留まっていた所が広く,1960年代に建設が決定し,80年代初めになってほぼ輪郭の定まった筑波研究学園都市の土地もその一部であった。台地を刻む樹枝状の谷は谷地(やち)(湿地)であるが,古くから一毛作田として利用された。台地が削られたハケ(崖)には泉が湧き,飲料水が得られて集落が立地する。縄文時代には海進によって,さいたま市の旧大宮市,土浦市などの内陸にまで海湾が入り込み,崖の上縁に沿って貝塚が多く作られた。この海岸地帯は海の幸と狩猟,焼畑による山の幸を合わせ得ることができた。弥生時代の海退に伴って,低地に水田が作られた場合も,たとえば小櫃(おびつ)川下流の菅生(すごう)(木更津市)などのように台地縁に住居が営まれた。
関東地方の大部分は温和な太平洋式気候であるが,北部,西部は冬寒く,夏暑い内陸気候を示す。1月の平均気温は銚子が5.8℃で熊谷は3.1℃,8月はそれぞれ24.8℃と25.9℃で年較差は銚子が小さい。降水量は1692mmと1207mmで銚子が多い。降水は梅雨,秋霖を含む夏の半年に多く,冬は秩父おろし,赤城おろしと呼ぶ北西の空っ風が吹いて冷たい。雷雨は関東の山に発生し,通り道には雷に関連する神社がある。積雪は上越の分水界を越えて南にまで下がり,奥日光,草津,上越などはスキー場としても温泉場としてもにぎわう。台風の来襲は9月から10月が多く,第2次大戦後最大の被害は1947年9月のカスリン台風であった。近年は大河川の治水工事が進んだが,都市の過密化が中小河川の洪水被害を増大させている。
開発と社会の歩み
先史時代からの歴史をもつこの地域も畿内を中心とする古代政権が確立する過程でその辺境の性格を強めた。律令制のもとでは関東の北部は東山道,南部は東海道に分属し,国郡の制が定まり,国府,国分寺,総社などがおかれた。特にこの地域では北九州の防人(さきもり)や奥羽の平定に多くの農民が出征するという重い任務を担った。関東地方の丘陵,原野には馬牧が設けられて貢馬を育て,麻,絹が都へ送られた。7世紀には百済,高麗の帰化人が入植して,養蚕・機織,製紙,冶金などの技術を伝えて開拓を促進した。10世紀には平将門の乱,平忠常の乱が起こり,在地の有力者は農民を家子郎党とし,武蔵七党など多くの武士団が作られた。12世紀末には鎌倉に幕府が置かれ,関東地方は武家政治の中心となった。室町時代に幕府は京に移ったが,関東地方には鎌倉公方,古河公方などが置かれ,東国支配の拠点として重視された。既に15世紀に太田道灌によって基礎を築かれた江戸は,徳川家康による江戸幕府の開設によって,人口100万人の大城下町として発達し,その後背地としての関東地方は江戸地回り経済圏に組みこまれた。江戸時代には交通路も整備され,水利事業も進んだが,特に江戸の都市用水を供給する神田上水,玉川上水は,武蔵野の新田開発にも貢献し,明治に入ってからは東京水道に組み入れられ,1960年以後の利根川ダム,武蔵水路などの水系を完成する端緒として高く評価される。新田開発は,16世紀後半から始まり,17世紀には渡良瀬川の水を岡登(おかのぼり)用水として笠懸野(かさかけの)を灌漑し,また九十九里浜の椿海干拓などが進んだ。日本橋を基点とした五街道と河川交通,および大坂,奥州との海上交通が整備され,国内の往来,流通が活発になった。小田原,水戸,宇都宮,佐倉,古河,川越などの城下町は宿場,または港津としても繁栄した。関東平野周辺の青梅(おうめ),飯能,渋川,桐生などの谷口集落には市が立ち,繭,生糸,織物などの取引が行われた。機業は明治に入って機械化され,生糸は横浜港より輸出される代表的産物となった。
都市化する関東
1868年(明治1)東京が首都に定められ,日本の政治・経済・文化の中心となったことは関東の都市および農村に大きな影響をもたらした。東京および横浜などは関東大震災(1923)と第2次大戦の空襲(1945)の2回の大きな打撃を受けたが復興し,東京区部は800万人,横浜市は200万人をこえる夜間人口を集めている。都心から2時間以内の地域は通勤圏となり,衛星都市の発達が著しい。天然の良港横浜に加えて,東京,川崎,千葉などの人工港湾が作られ,東京湾北半の海岸は重化学工業をはじめ,出版,印刷,雑貨にいたるまであらゆる工業の集まった日本最大の京浜工業地帯および京葉工業地域,流通センター,都市施設によって占められている。自然の海岸は房総,三浦,伊豆,および常陸以北でないと見いだされない。内陸および鹿島臨海工業地域,日立を含む関東1都6県の工業出荷額は全国の32%(1995)に達している。
都市化,工業化にもかかわらず,関東の東部と北部はなお農業が盛んである。稲作,酪農,養豚,茶(狭山),苗木(安行)のほか多種類にわたる野菜の生産があり,ネギ,ハクサイ,キャベツなどの出荷量は全国比3割以上に達する。その基礎は畑の輪作と都市への出荷による高い生産性である。首都圏整備計画は関東の1都6県と山梨県を加え,首都の過密を押さえ,周辺の経済的発展と自然環境の保全を図りつつ計画されている。
執筆者:木内 信蔵
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「関東地方」の意味・わかりやすい解説
関東地方
かんとうちほう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「関東地方」の意味・わかりやすい解説
関東地方【かんとうちほう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...