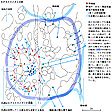改訂新版 世界大百科事典 「縄張り」の意味・わかりやすい解説
縄張り (なわばり)
本来,土地などに縄を張って境界を定め,自他を区別したり,特別の区域(結界)を明らかにすることで,古い民俗慣習に基づく。戦国時代以降,区画内での土地利用計画,建物の配置計画をもさすようになり,もっぱら築城に際して用いられた。建築用語としてはまた,設計図に基づいて建物の配置を定めるため縄を張ることをいい,縄打ち,経始ともよぶ。一方,縄張りは土地や地域を占有する表示ともなり,占有された区域そのものをさすようになった。博徒などが勢力圏を縄張りとよぶ例は,江戸時代初期からみられ,今日ではアウトローの世界だけでなく,一般社会や動物の生態におけるテリトリーに関しても用いられている。
城郭の縄張り
中・近世城郭の場合,縄張りは全体の平面計画,平面形態を指す。城郭研究において,現存する城跡の構造を確認して,その防御上の意味を解釈しつつ詳細に描いた図を縄張図と呼んでいる。縄張りを構成する要素は曲輪(くるわ),堀,土塁,石垣,櫓(やぐら)台,虎口(こぐち),道,武者隠しなどの付属施設からなり,それらの組合せによって,城それぞれの個性と良し悪しがきまる。主として近世城郭について,曲輪配置から連郭式,梯郭式,輪(円)郭式あるいは囲郭式などの縄張りの分類がなされているが,これらは他の構成要素や地形との関係によって評価が異なることがあるので注意を要する。戦国期までの山城(やまじろ)についてみると,縄張りの発達のおもな要素は空堀の使い方と虎口の形であり,虎口は馬出しの使用で頂点に達する。織豊期に石垣が本格的に採用されると縄張りの発達の仕方が変わり,櫓の配置,塁線の重なりと折れ(横矢掛り)および虎口の升形(ますがた)の使い方が決め手となる。
執筆者:村田 修三+西 和夫
勢力圏としての縄張り
縄張りの観念には,一定の土地と,その上において自己の独占的恣意的に支配しうる権利と,さらに自圏と他圏との内外を峻別する鋭い境界の意識の3者がふくまれている。博徒やてきやなどの縄張りは,こうした考え方がもっとも顕著にあらわれているものである。博徒では,一家すなわち総長の支配する地域圏は島,または火場所,費場所とよばれている。総長はその地域圏内の賭場支配権をにぎり,その貢租的利益の収取によりその生活をたてている。総長は身内の各親分にその賭場支配権を分与し,管理させる。総長配下の貸元親分は盆をあずかって,寺銭その他の貢租的な収納にあたる。各子分も,それぞれの段階に応じてその縄張りから利益の分与を得ているので,集団的に専有する縄張りは他の侵害を許さぬよう生命をかけても守る死守(シモリ)と称される。てきやの場合は,縄張りは庭場というが,その原理には変わりはない。
大都市の盛り場などでは,いくつもの集団が入り組んで縄張りを構成していることがある。また,どの集団も占有していない所属不明の場所や新開地などは,カケツケ場(駆付け場所),草生え場所などと称し,これをめぐっての競争もしばしば行われる。各集団はその縄張りの拡大をめざして互いに蚕食しあっており,縄張り争いは絶え間がない。また,勢力が均衡している場合には,相互の協定が行われる。縄張りは,日本のやくざ社会に限るものではなく,アメリカのマフィアなどの暴力組織にも見られる。さらに,集団主義の傾向が強い日本では,一般社会でもこの傾向が見られる。
執筆者:岩井 弘融
動物の縄張り
動物生態学用語としての〈なわばり〉とは同種または異種の他個体(またはグループ)に対し,単独または複数で防衛する地域,すなわちテリトリーterritoryである。なわばり現象は,古くギリシア時代から気づかれていたが,本格的な調査,研究が始まるのは,ハワードH.E.Howardが《鳥の生活におけるなわばり》(1920)を著してからで,以来,小鳥類については膨大な量の研究がなされてきた。しかし,多くの研究はなわばりの諸機能に関するものであって,なわばり自体がどのようなものなのかは,自明なものとされすぎてきたためか,実証的な研究はごく最近になるまでほとんどなされてこなかった。
なわばりの防衛
ホオジロという小鳥はおもに雄が1万m2ほどのなわばりを防衛するが,調査の結果,行動圏の中心部から外側に向かって,つがい相手以外の個体を入れない地域,一方的に侵入個体を追い出す地域,隣接個体と身体的闘争をする地域,一方的に逃げ戻る地域が,同心円状に存在することなどがわかった。これは,なわばりの境界が2隣接個体の行動圏の中心部から外側に向かいしだいに弱くなる,攻撃性強度のバランスによって決定していることをよく示している。
ホオジロがさえずった地点をすべて地図上にプロットしてみると,なわばり占有雄が侵入個体と身体的闘争をした地域とよく一致する。すなわち,さえずる範囲がなわばりの範囲である。鳴禽(めいきん)類(スズメ目の小鳥)ではこのように,さえずることによって,自分のなわばり範囲をつねに他個体に対して示し,立入り禁止のメッセージとして送信している。さえずりが立入禁止信号であることは,ハゴロモガラスの雄の舌下神経を切断してさえずれなくすると,回りからの侵入頻度が増すことや,シジュウカラのなわばり占有個体を人為的に除去し,代りにスピーカーからその個体のさえずりを流しておくと,流さなかったなわばりより新参者の定着がずっと遅れるとか,隣接個体のさえずりと,聞いたことのない個体のさえずりの両方をスピーカーから流すと,聞いたことのない個体のさえずりに,より強く反応を示す(ノドジロシトド)などの野外実験からも示されている。こうしたなわばりへの立入禁止信号は,哺乳類の場合には主としてにおいづけ(マーキングmarking)によってなされており,鳥や哺乳類など高等な動物ほど直接的闘争を避けている傾向がある。
食物を確保するためのなわばり
なわばりによって動物が守っているものはなんであろうか。まず第1には食物が考えられる。このことは,異なる種の体重となわばりの面積の間に正の相関関係があることとか,餌密度となわばり面積の間に負の相関関係があることなどから間接的に推測されてきた。一方,動物が守っている食物資源を直接的に測定して,必要な食物量であるかどうかを推定する試みも,ある種の単食性の魚や小鳥でなされている。アユは夏に遡上(そじよう)して1個体が1m2ほどの面積を防衛するが,そのなかに存在する藻の量を測定すると,およそ7~8尾を養える食物量を有する。しかし,氷河時代の水温から藻の生長速度を算定してみると,ちょうどアユ1尾分の必要量に見合っているので,アユのなわばりは氷河期の遺存習性であろうという。東アフリカの花みつ食性の鳥タイヨウチョウの1種は,なわばり面積に関係なくつねにその中に1600個の花を含むなわばりを守るという。これらのことから,なわばりが食物確保の役に立っていると予想される。
ところで,アユにしてもタイヨウチョウにしても,個体群密度や,自分のなわばり内の花数が変化すると,なわばり行動は現れたり消えたりする。アユでは密度が高い年には,なわばりを解消して群れアユになるが,これは侵入者が多すぎて追い払いきれず,なわばり防衛の経済性が低下してしまうからであるといわれている。また,タイヨウチョウの場合も,なわばり内の花数が少なすぎると,なわばりを防衛するのに要するエネルギーが,そこから得られるエネルギーを上回ってしまうし,花数が十分すぎると,守ることの意味があまりなくなる。タイヨウチョウの別の種の実験結果から試算すると,この鳥はなわばり内に60個から207個の花を有する場合に,なわばりを張ることが経済的に見合うことが予測され,野外での観察結果もほぼこれに合っていた。ブチハイエナは,食物の予想が可能で豊富なヌゴロンゴロ・クレーターでは群れテリトリーを守り,食物が季節的に変化するセレンゲティ草原では,固定した地域を防衛しないで広い地域をさまよい歩くという。こうした同種内の行動の差も,なわばりを守ることで費やすエネルギーと,得られる食物量の経済性のバランスから説明することができる。
繁殖のためのなわばり
なわばりを防衛する対象物として第2に考えられるのが交尾の相手である。ソウゲンライチョウではなん羽かの雄たちが草原の1ヵ所に集まって,そのおのおのが直径1~2mくらいの小さな踏み固められた裸地を防衛する。このなわばりにはもちろん食物は含まれておらず,雌がやってきて,このなかの1羽(中央にいる順位の高い雄)と交尾をした後,産卵,育雛(いくすう)のために別の場所へ去っていく。こうしたなわばりは,交尾のための場所を守るものである。交尾のためのなわばりも,それを張るか解消するかは防衛することの経済性にかかっている。例えば,雌のシオカラトンボが池へ到着する時間や場所が予測可能なところでは,雄はなわばりを張って雌を待つが,雌の到着が時間的にも空間的にも予測不能な場所では雄は池の上を広くさまよう。
一方の極にこうした交尾のためだけのなわばりがあり,他方の極にアユの場合のような食物のためだけのなわばりがあるが,多くの場合は,この両方の機能を併せもつことが多い。例えば,鳥類では現生種のおよそ87%は,ホオジロのようなきっちりしたなわばりを守り,そのなかで交尾,巣づくり,育雛(いくすう)などの全生活をまかなっている。
雄が防衛しているなわばりを雌が訪問して,そこでつがいになる動物では,その際,雌は雄のなわばりの質を評価しているのか,雄の質を直接的に評価して定着配偶するのかはほとんどわかっていない。なわばりが,動物の数が増えすぎないように動物社会のなかで自己調整の機能を果たしているという見方と,多くの高等動物の場合にはなわばりが機能する以前に,捕食とか食物不足とか巣場所の不足などの生態的条件によって個体数が抑えられていて,なわばりには個体群密度の自己調整機能はないという見方の両者ともに,実証的な証拠に今のところ欠けている。
執筆者:山岸 哲
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報