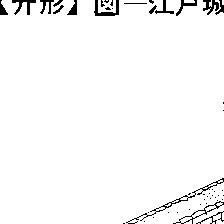ます‐がた【升形・枡形・斗形】
- 〘 名詞 〙
- ① 升のような四角の形。また、そのようなもの。
- [初出の実例]「アノ浄湯をくむ升形(マスガタ)の所を呼出しといふはな」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)四)
- ② 柱などの上にある方形または長方形の木。ます。とがた。
- [初出の実例]「或は九輪を下(おろ)され、ます形(ガタ)計あるもあり」(出典:太平記(14C後)二六)
- ③ 神輿(しんよ)の屋蓋(おくがい)の頂。また、宝珠形の下にある四角の露盤。
- ④ 防御のために城の入口に設ける四角形の空地。周りを門や櫓塀・石垣などで囲み、敵が直進できないようにつくる。
升形④〈東京都江戸城北の丸〉
- [初出の実例]「門前をも升形(マスカタ)といふ」(出典:甲陽軍鑑(17C初)品四二)
- ⑤ 昔の劇場の平土間で、升のように仕切った見物席。ます。
- [初出の実例]「勤め枡形(マスガタ)、切落し、中の間までもよいよいと」(出典:歌舞伎・伊勢平氏栄花暦(1782)三立(暫))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
升形
ますがた
[現在地名]金沢市安江町
文政六年(一八二三)安江木町のうち安江木木戸から同町上の木戸までを町域として成立した地子町(「又新斎日録」加賀藩史料)。両側町で北は鍛冶片原町に続く。肝煎は安左衛門(町奉行より出候町名)。町名は宮腰往来に通じる枡形の総構門が所在したことによる(金沢古蹟志)。
升形
ますがた
[現在地名]高知市升形・丸ノ内一―二丁目
郭中の本町の西詰と上町の本町筋との間にある広場で、もと本町の一部であったが、明治四年(一八七一)独立の町となった。当初の町づくりの際にここを広場にしたのは、緊急事態の際兵を集結させる場所が必要であり、その人数を概算するための「枡」になるものであった。本町の通りで毎年正月に行われる馭初式の際には騎馬武者たちの屯所にもなった。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
Sponserd by 
升(桝)形 (ますがた)
城郭への出入口である虎口(こぐち)の最も発達した形態で,方形空間を囲んで築かれた箱形の石垣でつくられる。升形を虎口の内側に設けるのを内升形といい,これが通常の形式で,外側に設ける外升形は数が少ない。升形に二つの門を開き,外に面した一の門を2本の角柱で妻破風造の屋根を支える高麗門(多門)形式とし,より重要で堅固に造られる内側の二の門は,渡り櫓に入母屋造の屋根を載せる櫓門形式で造られるのが通常である。そしてこの二つの門は,必ず直角に配される。この構造により,戦闘に際して侵入した敵の直進を妨げ,升形の周囲,櫓門からこれを攻撃することができる。また升形内に城兵を待機させて,敵の攻撃を避け,一気に出撃することができる。一方,門が二つあることにより,城兵が入門する際,二の門を閉じたまま一の門を開いて升形内に城兵を入れ,一の門を閉じたのち二の門を開いて郭内へ入れる方法がとられた。つまり升形内で不審者を点検し,隊列を整え,さらに二つの門を同時に開かぬことによって敵の侵入の危険を少なくしたものである。このほか,近世の宿場においても,出入口にあたる街道の部分を鉤(かぎ)の手に曲げ,場合によっては土塁や木戸門を築いて,通行を規制するために設けられた升形もあった。
→見附
執筆者:玉井 哲雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の升形の言及
【虎口】より
…城あるいはその各郭の出入口。小口とも書く。単なる出入りだけでなく,防御と攻撃(出撃)の機能を持たせるために種々のくふうと施設が加わって発達した。木戸や矢倉を設けるだけのものから,前面に堀を設けて橋や坂で入る橋虎口や堀虎口,両脇の土塁を食違いにして直進を妨げる食違い虎口などが中世城郭でよく用いられた。中世末期に堀の外に小さな台場を張り出した馬出(うまだし)と,塁で囲んだ方形の空間をはさみこんだ枡形(ますがた)が考案され,近世城郭で完成した。…
【城】より
…その動きは大名権力の強化に伴って進み,築城術を飛躍的に発展させる。石垣を使用することが多くなる西国に対して,土だけの東国(特に武田・後北条両氏)の城では空堀(特に横堀)と土塁の使い方がじょうずで,[虎口](こぐち)(郭の出入口)における馬出しと升形(ますがた)の発達を見た。 大名居城では,家臣団の集住とそれを経済的に支える城下町の建設という課題に直面し,肥大化した城郭を長大な外郭線で囲い込む総構えの手法が導入されるようになるが,従来の山城のままでは無理な場合が多いので,平山城ないし平城へ移らざるをえなくなる。…
※「升形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 
 升形④〈東京都江戸城北の丸〉
升形④〈東京都江戸城北の丸〉