関連語
精選版 日本国語大辞典 「釵子」の意味・読み・例文・類語
さい‐し【釵子】
- 〘 名詞 〙
- ① かんざしの一種。宝髻(ほうけい)と呼ぶ、宮廷婦人の正装とする髪上げの際に使用する。近世は、金銅で角一本、丸二本からなる。角は平額(ひらびたい)に、丸はその左右に挿し込むためとする。
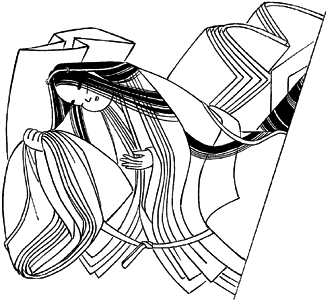 釵子①〈扇面法華経表紙〉
釵子①〈扇面法華経表紙〉- [初出の実例]「髪丈にあまり、装束鮮やかなる下仕へ、さいし、もとゆひして廿人いできて御前に参る」(出典:宇津保物語(970‐999頃)祭の使)
- 「御額あげさせ給へりける御さいしに、分け目の御髪(ぐし)のいささか寄りてしるく見えさせ給ふぞ、聞えんかたなき」(出典:枕草子(10C終)二七八)
- [その他の文献]〔中華古今注‐釵子〕
- ② 近世以来、女官が正装の時に頭髪の前につけた飾りの平額(ひらびたい)をいう。従来の釵子をかんざしと呼んだことに対して、これと区別するための呼称。
釵子の補助注記
( ①について ) 二つに分かれた脚をもつかんざしで、木、竹、銀、銅、金銅などでつくられる。日本には古墳時代に大陸から伝えられたが、類例は少ない。奈良時代には唐の影響で華麗なものがつくられ、中世に及んでいる。
さ‐し【釵子】
- 〘 名詞 〙 かんざし。
- [初出の実例]「あまたあらばさしはせずとも玉くしげあけん折々思ひ出にせよ」(出典:小式部内侍本伊勢物語(10C前)H)
- [その他の文献]〔中華古今注‐釵子〕
日本大百科全書(ニッポニカ) 「釵子」の意味・わかりやすい解説
普及版 字通 「釵子」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の釵子の言及
【髪飾】より
…古墳時代には花枝や木の芽を髪にさすことが流行,呪術的な目的ももっていた。この時代,大陸文化の影響と思われる銀製の釵子(さいし)(束髪ピンの類)もみられた。貴族階級では中国風の髪飾がもてはやされ,それは平安時代にも受けつがれ,頭に平打ちで鳳凰の飾りなどのせるようになった。…
【簪】より
…しかし江戸時代の簪は宗教的な意味は含まず,純粋に髪飾として独自の発達をとげたといえる。 奈良時代に隋・唐時代の二またに分かれた簪が日本に伝わり,これを釵子(さいし)と呼んだ。遺品では法隆寺献納宝物に,聖徳太子が用いたと伝えられる銀製雲形釵子がある。…
※「釵子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

