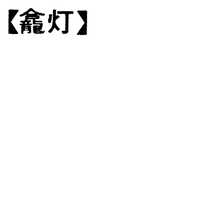関連語
精選版 日本国語大辞典 「龕灯」の意味・読み・例文・類語
改訂新版 世界大百科事典 「龕灯」の意味・わかりやすい解説
龕灯 (がんどう)
ろうそく用の携行灯火具。鼠灯台(ねずみとうだい)などとともに江戸時代に発明された。長さ30cm前後,直径12~13cm,竹箍(たけたが)あるいは鉄箍(かなたが)をはめて桶状に作り,底部外側に取っ手をつけ,内部には組み合わされた2個の鉄輪(かなわ)を装置して,どんなに振りまわしてもこれが自由に回転して,鉄輪に立てられたろうそくがつねに垂直の位置を保ち,火が消えないような機構をもっている。現在の懐中電灯のように,使用者のほうは見えないで,その思う方向のみを照射することができる。目明しなどが夜間の捜索に使用したが,赤穂浪士も吉良邸討入りのときにこれを持参したといい伝えられている。明治時代にはいってからもブリキ製のものなどが一部で使用されていた。
執筆者:宮本 馨太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「龕灯」の意味・わかりやすい解説
百科事典マイペディア 「龕灯」の意味・わかりやすい解説
龕灯【がんどう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...