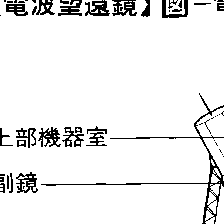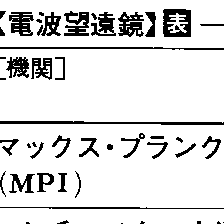精選版 日本国語大辞典 「電波望遠鏡」の意味・読み・例文・類語
日本大百科全書(ニッポニカ) 「電波望遠鏡」の意味・わかりやすい解説
電波望遠鏡
でんぱぼうえんきょう
radio telescope
宇宙からやってくる電波を集め、強め、分析して、宇宙におけるさまざまな自然現象を研究する道具として発達した装置が、電波望遠鏡である。可視光望遠鏡と同様に、大きな回転放物面(パラボラ)等の反射鏡を用いて宇宙からのかすかな電波を一点(焦点)に集め、受信機システムで分析するのが基本である。可視光望遠鏡の場合は、その焦点に拡大レンズを置いて目でのぞいたり写真乾板やCCDカメラを置いて写真に撮ったりするが、電波では波長が長いため、波長が短いミリ波・サブミリ波を除いては基本的に焦点面検出はできない。そのかわり、集めた電波を電磁波の波動のままアンテナや電磁ホーンで取り込み受信機に導いて、波のままで強め(増幅)、低周波の電波に周波数変換(ヘテロダイン変換)し、周波数分析(電波分光)や、偏波、強度の測定などを行うことができる。長波長の電波では、パラボラのかわりに長大な放物面柱を用いたり、広帯域アンテナを多数並べたダイポール・アレイなどによる集光も行われる。
電波望遠鏡の方式としては、大型の回転放物面をもつ単一パラボラ型電波望遠鏡と、多くの集光器(アンテナ)と受信機システムを互いに距離を置いて配し、ケーブルで全体をつなぎ合わせて一つの電波望遠鏡とする電波干渉計がある。遠い宇宙を観測する望遠鏡としては、まずは「集光器」である反射鏡の直径を大きくすることが、より大きな集光力とより高い分解能を実現するために重要である。だが観測する電波源の構造を細かく見分ける能力(分解能)は、反射鏡の直径に比例し観測する電波の波長に反比例するから、光に比べて波長が桁(けた)違いに(1000倍から1000万倍)長い電波では、反射鏡を相当に大きくしても分解能は悪く、ぼやけた電波天体の姿しかとらえられない。そこで空間分解能の不足を補うため、互いに遠く離して設置した複数のアンテナをケーブルでつなぎ、同時に観測して受信電波を合成する電波干渉計が発明された。電波観測は技術的に比較的容易な長波長から高度なエレクトロニクスを要する短波長へと進んだが、現在では地上で観測できる最低周波数である2~30メガヘルツ(波長15メートル~10メートル)から、赤外線との境界で大気を通して観測できる限界である1000ギガヘルツ(波長0.3ミリメートル)付近まで、電波の全帯域を覆って観測が行われている。なお電波の周波数と波長との間には、「周波数(メガヘルツ)×波長(メートル)≒300」という関係がある。
[海部宣男 2017年7月19日]
歴史
宇宙からの電波は、1931年、雷の電波を研究していたアメリカの電波技師カール・ジャンスキーが発見した。独自のパラボラ型電波望遠鏡をつくってジャンスキーの観測を受け継いだのがアメリカの若手電波工学者グロート・リーバーGrote Reber(1911―2002)で、天の川に沿って電波が放出されていることや、いくつかの孤立した電波源が存在することなどを明らかにした。太陽からの電波は、第二次世界大戦中、レーダーの研究をしていたイギリスのヘイJames Stanley Hey(1909―2000)が最初に発見したとされる。宇宙からの電波も太陽からの電波も、電波技術の向上がもたらした偶然の発見である。
第二次世界大戦の終了とともに、電波天文学は急速に発展した。早くも1946~1948年には、電波観測の空間分解能不足を克服する手段としての電波干渉計が、イギリスのマーチン・ライル、オーストラリアのジョン・ボルトンJohn Gatenby Bolton(1922―1993)らによって開発された。一方、回転放物面の主反射鏡は、観測しようとする電波の波長に比べて十分な滑らかさであればよい。電波天文学初期(1950~1960年代)には波長1メートルから10センチメートル程度の長波長での観測が主流だったから、このころ建設された大型電波望遠鏡はほとんどがパラボラ型やシリンダー型の反射面を軽量の金網によって構成したものだった。反射鏡は光学望遠鏡と同様、天球の動きを追って方向を変えるため、二つの回転軸をもつ架台の上に置いて駆動されねばならないが、軽量の主鏡であれば直径数十メートルの巨大な電波望遠鏡の建設も比較的容易だったのである。1960年代には、イギリス・ジョドレルバンクの76メートル鏡(1957)、オーストラリア・パークスの64メートル鏡(1961)、アメリカ・グリーンバンクの高精度43メートル鏡(1965)などが競って観測を開始し、水素原子の波長21センチ線、パルサー、クエーサー、宇宙背景放射などの大発見が相次いで、電波天文学の黄金時代が幕を開けた。
波長が短い電波への進出は技術的困難のために遅れたが、1980年ころからの半導体工学、精密工学、大型コンピュータなど第一線の技術の発展によって、電波としてもっとも波長が短いミリ波帯で、巨大で精密な単一パラボラ望遠鏡や干渉計の実現が急速に進んだ。これは、ミリ波帯で宇宙の低温の分子が放つ星間分子のスペクトル線が次々と発見され、星間分子雲(暗黒星雲)からの星の形成や銀河系の構造などが明らかになってきたことに大きく刺激されたものである。日本では東京天文台(当時)野辺山(のべやま)宇宙電波観測所の45メートルミリ波望遠鏡とミリ波干渉計、アメリカではカリフォルニア工科大学のミリ波干渉計、ヨーロッパではドイツのマックス・プランク電波天文学研究所の100メートル鏡、フランスにおかれた国際電波天文学研究所であるミリ波天文学研究所の30メートルミリ波鏡とミリ波干渉計などが建設され、その成果が競われた。また電波干渉計は、高速コンピュータの登場により、天体の電波画像を高分解能で描き出す電波写真儀(開口合成電波干渉計とよばれる)へと発展した。開口合成電波干渉計も短波長帯に進出し、チリで2013年から観測を開始した大型電波干渉計ALMA(アルマ)をはじめとする本格的なミリ波・サブミリ波開口合成干渉計が、銀河系内の惑星形成現場や遠方の銀河の進化の観測などに活躍している。
[海部宣男 2017年7月19日]
単一パラボラ型電波望遠鏡
単一パラボラ型電波望遠鏡は、技術と観測の発展とともに高精度化してきた歴史がある。口径数10メートルから100メートルの巨大な主反射鏡が有効に電波を集めるためには、回転放物面からのずれが観測する波長の10数分の1以下に抑えられなければならない。だが天体を追って駆動されるため重力変形が起き、また太陽光にさらされるなどのため熱変形が起きる。重力変形に対しては、野辺山45メートル鏡で用いられた回転放物面から新たな回転放物面に変形するように反射鏡支持構造を設計するホモロガス変形法が有効で、現在広く用いられている。また電波による鏡面精度の測定、主鏡骨組みの温度を均一に保つ断熱構造などが、最近の高精度の大型パラボラでは一般的である。主反射鏡で焦点に集められた電波は、焦点に置かれた電磁ホーンにより導波管へ取り込まれ、受信機に導かれる。受信の検出感度を決定するのは、初段に置かれた前置増幅器(プリアンプ)ないしはミクサ・プリアンプで、ヘリウムガスなどで極低温に冷やし、内部での雑音電波発生を極力抑えなければならない。センチメートル波では各種のHEMT(高電子移動度トランジスタ)増幅器やその発展であるMMIC(モノリシックマイクロ波集積回路)を冷却して用いる。短波長のミリ波・サブミリ波ではミクサ・プリアンプ方式が主流で、超伝導効果を用いた半導体周波数混合器(ミクサ)によって低周波への変換をまず行い(ヘテロダイン検波)、すぐに上記の低温増幅器で増幅する。
扱いやすい周波数帯域で充分に増幅された宇宙からの電波は、さらに分析装置へ送られる。受信電波を周波数ごとに細分し、その強度を同時に測定する電波分光器には、レーザーと音響光学効果を応用したAOS(音響光学型電波分光器)方式や、コンピュータによる高速相関を用いた自己相関型デジタル分光器方式があり、スペクトル線の検出、分析に用いられる。音響光学型は野辺山45メートル電波望遠鏡用に3万チャネルという巨大なものが開発されて広く活躍し、ミリ波天文学の発展とともに世界で広く用いられてきた。しかしデジタル技術の発展とともに、最近はデジタル自己相関型電波分光器が音響光学型にとってかわりつつある。そのほか電波の振動面の方向や偏りの程度を測る偏波計、電波強度の速い変化を測定する装置などが、目的に応じて使用される。
電波望遠鏡の制御と膨大なデータの処理のためには、高速で大容量のコンピュータが必要である。単一パラボラ型の電波望遠鏡は基本としては一時に空の一点からの電波しか受けられないので、電波天体の構造を調べるには次々と多くの点について観測を行い、蓄積したデータをコンピュータ内で解析して画像を合成する。このようにして合成された電波画像が、いわば光学望遠鏡の写真に相当する。しかし現在ミリ波帯では、10から数十のホーンと受信機を並べて組み込むマルチ・ビーム受信機や、天空を連続的に掃いて行きながら適時データを取り込んですばやく画像化する移動観測法も、盛んに用いられるようになった。さらにミリ波・サブミリ波では、ヘテロダイン検波方式と併せて可視光と同様に電波を光子のエネルギーとして受け取る直接検出方式も盛んになっている。熱検出素子である各種のボロメータなど超低温で働く各種の半導体検出器と、それを1000個以上並べた「サブミリ波カメラ」が、すでに実際の観測に用いられている。
[海部宣男 2017年7月19日]
電波干渉計
波長が長いことによる電波観測の分解能不足を補うため、1940年代から1960年代にかけて電波干渉計が発明・開発された。基本は、二つのアンテナ(パラボラ型反射鏡などの集光器)を互いに離して置き、同時に観測した天体の電波をそれぞれの位相を維持しながらケーブルで送り、一つにあわせて干渉させることである。このときの空間分解能は、二つのアンテナの間の距離を直径とする電波望遠鏡の分解能に相当する。ただし二つだけでは集光力・情報量ともに不足なので、多くのアンテナを配置して相互に結合し、一つの電波望遠鏡とする。この場合、各素子アンテナ間の距離(基線長)のすべてと、天球上の目的天体に対するすべての基線の角度だけの情報が得られることになる。さらに地球の自転による電波源の回転も考慮しつつすべてのアンテナ間の受信電波の相互相関をとり、最後に全データをフーリエ変換することによって、電波源の二次元強度分布、すなわち電波画像が得られる。最適な素子配置が得られる場合には、画像の画素数は基本的に(最大基線長÷素子アンテナの直径)2となる。システムは複雑になるが、この方式によって電波天体の微細な構造を直接描き出すことが可能になった。これを、開口合成干渉計という。アメリカのVLA(Very Large Array、超大型電波干渉計)は、直径25メートルのアンテナを27基、40キロメートルの範囲に配置した巨大な開口合成干渉計である。VLAの空間分解能は、光学望遠鏡のそれにほぼ匹敵する。さらに日米欧の共同で建設され2013年から活動を始めたチリ・アタカマ高地のALMA(アルマ、大型ミリ波サブミリ波電波干渉計)は、7~12メートルの高精度パラボラ66基を十数キロメートルの広範囲に移動・配置する高度な開口合成干渉計で、最高空間分解能は大型光学望遠鏡を大きくしのぐ0.01秒角を達成する。長波長の電波でも、国際共同で大陸規模の開口合成望遠鏡をつくるSKA計画が進行中で、すでにオーストラリアと南アフリカを中心にその第一フェーズの建設が始まっている。
電波干渉計の別の発展として、ケーブルのかわりに高精度の時計信号を媒介として、全地球上の大型電波望遠鏡で同時観測した電波を集め合成するのが、VLBI(超長基線電波干渉計)である。世界ではアメリカのVLBA(Very Long Baseline Array、超長基線電波干渉計)、ヨーロッパ諸国が展開するEVN(European VLBI Network、欧州VLBIネットワーク)、日本と韓国のKaVA(KVN and VERA Array、日韓合同VLBI観測網)、東アジア諸国を結ぶEAVN(East Asian VLBI Network、東アジアVLBIネットワーク)などが活動中で、それぞれ角度で1000分の1秒という高分解能を達成している。今後の方向としては、SKAがすでにそうであるように、開口合成電波干渉計とVLBIとの合体が進むことになる。
[海部宣男 2017年7月19日]
『海部宣男著『銀河から宇宙へ』(1972・新日本出版社)』▽『赤羽賢司・海部宣男・田原博人著『宇宙電波天文学』(1988/復刊・2012・共立出版)』▽『海部宣男著『電波望遠鏡をつくる』(1986・大月書店)』▽『海部宣男著『望遠鏡』岩波講座「物理の世界」(2005・岩波書店)』▽『中井直正他編『宇宙の観測2 電波天文学』シリーズ現代の天文学16(2009・日本評論社)』

グリーンバンク天文台43m電波望遠鏡

グリーンバンク天文台100m電波望遠鏡

野辺山宇宙電波観測所45m電波望遠鏡

野辺山宇宙電波観測所45m電波望遠鏡の…

野辺山宇宙電波観測所ミリ波干渉計

ALMA(アタカマ大型ミリ波サブミリ波…

ALMAの高精度パラボラアンテナ

アメリカ国立電波天文台超大型干渉電波望…

ロングベースライン天文台25mVLBA…
改訂新版 世界大百科事典 「電波望遠鏡」の意味・わかりやすい解説
電波望遠鏡 (でんぱぼうえんきょう)
radio telescope
天体からの電波を観測するためのアンテナ。宇宙は,超高温から超低温,また超高密度から真空に限りなく近い低密度まで,きわめて変化に富む物質の運動の場である。これらの運動に伴い,電波,赤外線,可視光,紫外線,X線,γ線にいたる,あらゆるエネルギーの電磁波の放射・吸収過程が繰り返されている。われわれが今日みる宇宙の姿は,これら電磁波の全波長域からの情報を用いて構築されたものであるが,とくに光(可視光)と電波の望遠鏡に負うところが大きい。それは,この二つの波長領域の電磁波においてのみ,地球大気をとおして地上から宇宙を直接観測できるからである。地上に設置される光と電波の観測装置は,各時代の最新の技術をとり入れつつ,ますます巨大かつ複雑なシステムへの道を歩んでいる。
電波で見える宇宙の姿は,光で見たそれとはまったく異なる世界である。電波は光に比べ電磁波としてのエネルギーは10⁻4~10⁻7と低く,その関連する現象も低エネルギーである。光ではまったく見ることのできない極低温の暗黒星雲が,電波では原子や分子のスペクトル線によって観測できる。また,超新星や銀河中心核爆発による可視光領域での放射はすぐにおとろえてしまうが,爆発によって生じた比較的低エネルギーの宇宙線は長期間にわたって拡散しつつ生き残り,電波を放つことによって観測されるのである。高温のプラズマ現象,すなわち主として星をその観測対象としてきた可視光の天文学に対して,低温で,広がった対象すなわち主として星間物質の観測を可能にした電波望遠鏡は,それまでの宇宙像を大きくぬりかえる役割を果たした。星間物質から星へ,また星から星間物質へという銀河系内における基本的な物質の運動が把握されたからであり,またもっと大きなスケールでは,銀河やクエーサーの活動性やガスと星の系としての銀河の大局的性質が研究できるようになったからである。
地球大気にあいた電波の窓は大略波長10mから1mmまでと広く,波長によって電波望遠鏡のしくみも,また対象とする天体,現象も大きく異なる。一般に長波長では超新星やクエーサーなどによる爆発現象,短波長では低温の星間物質や星の誕生の過程などがおもな観測対象である。
電波望遠鏡の歴史
1931年にK.ジャンスキーが初めて宇宙からの電波を発見したのは,水平回転が可能な大型のダイポールアンテナアレーを用いてである。これは雷からの電波の到来方向を知る目的で作ったもので,電波望遠鏡というよりは可動アンテナと呼ぶべきであろう。当時,電波技術は非常に新しい分野だったので,光のみを扱ってきた天文学者にとっては電波望遠鏡を作ることはおろか,この発見の意義を理解することすらむずかしかった。しかしアメリカの若い無線工学者リーバーGroat Reberはジャンスキーの発見を知って,自宅の庭に直径9.5mものパラボラアンテナを作った。これは世界最初の電波望遠鏡であった。木製ではあったが全天どこへでもむけられるこのアンテナは,基本的に今日の大型電波望遠鏡と同じである。
電波観測は技術的な制約のため長波長からスタートした。望遠鏡が観測対象の構造を詳しくみわける能力,すなわち分解能は,(観測波長/望遠鏡の口径)で決まる。当然,波長がきわめて長い電波での観測は,ぼやけた構造しか得ることができず,当初は電波天体の詳しい構造の研究どころか,その位置さえつかむことができなかった。そこで干渉の原理を応用した電波干渉計が,1940年代末にオーストラリアやイギリスで相次いで実用化され,互いに遠く離しておいた2台ないしそれ以上のアンテナをケーブルでつないで,天球上の電波天体の位置や構造が観測されるようになった。
50年代の電波干渉計の活躍と水素原子の21cm波の発見などの刺激をうけて,60年代には巨大な電波望遠鏡が世界各国で続々と建設された。57年に完成したマンチェスター大学ジョドレルバンク観測所の76mパラボラ鏡はその先駆である。60年代はいわば巨大パラボラ鏡の時代で,オーストラリア電波物理学研究所の64m鏡(パークス)やアメリカ国立電波天文台の43m鏡(グリーンバンク)など,今日も活躍している優れた装置により,電波天文学を光学天文学と並ぶ宇宙観測の基本的分野として確立した。一方で工学の進歩によるパラボラの高精度化が進み,受信機製作に欠かせないエレクトロニクス・半導体技術の発展とあいまって,観測波長は短波長へと進んだ。72年完成の西ドイツの100m鏡(マックス・プランク研究所)は,世界最大のパラボラ鏡であると同時に,精度の面でも一時代を画するものであった。
電波干渉計を発展させた開口合成電波干渉計は,ケンブリッジ大学のライルMartin Ryleらによって1960年代に実用化され,70年代にはその大規模なものが作られるようになった。これは大光学望遠鏡に匹敵する分解能でシャープな電波画像を得ることができる装置であり,イギリス(ケンブリッジ大学),オランダ(ウェスタボーク),また最近ではアメリカ国立電波天文台(ニューメキシコ)で大規模な装置が活動中である。また分解能では,さらにこれをはるかにしのいで,角度で1万分の1秒の構造もみわけることのできる超長基線干渉計(VLBI)が1960年代に実用化され,めざましく進歩しつつある。
現在は,こうした開口合成電波干渉計,超長基線干渉計とともに,波長1cm~1mmの短波長(ミリ波)での観測を目的とした,高精度のパラボラ鏡の建設が世界的に進みつつある。ミリ波での星間分子のスペクトルを中心とした,宇宙電波分光観測の発展を反映したものであり,国立天文台の45m電波望遠鏡およびミリ波干渉計(野辺山)は,そのトップをきる新鋭装置である。
電波望遠鏡の種類
電波望遠鏡は,単一パラボラ型と開口合成型(干渉計)とに大別される。単一パラボラ型は,大口径によって多くの電波を1点に集めるもので,機動性と感度,またさまざまな観測目的に即応できる万能性において優れている。開口合成型は,多くの小型アンテナを配置してケーブルでこれらを結び,同時に天体を追尾して各アンテナに入った天体からの電波を集め,これらを互いに干渉させて電波画像を合成するもので,分解能に優れ,画像を得られる利点がある。いわば,両者は互いに補い合う機能をもっている。超長基線干渉計はケーブルのかわりに高速磁気テープを用いることで,事実上地球上のあらゆる電波望遠鏡どうしをも結びつけて,開口合成型とすることができ,分解能ではさらに飛躍的に優れている。しかし,一般に分解能をあげるほど,集光面積が伴わないために感度は下がる。
電波望遠鏡の機能
どの種類の電波望遠鏡でも,(1)天体の追尾,(2)電波の集光,(3)高感度での増幅,(4)分光・検出,(5)データ解析の機能を必要としている。
天体の追尾は,単一パラボラ型ではとくに重要であり,目的の天体を十分な精度(分解能の数分の1以上)で常時追尾しなければならない。開口合成型では,天体追尾は電波の位相制御で行うので負担が軽い。集光は,電波を集める機能であるが,この際,電波の反射面に観測波長の10分の1以上の誤差があると,電波の光路差のためエネルギーが失われ,十分な集光ができない。長波長では電波を集めるパラボラ面は金網で十分であるが,ミリ波のような短波長での観測には,精密に仕上げられた反射パネルで鏡面を覆う必要がある。このため,大口径パラボラ鏡ほど,短波長の観測の実現が困難になる。開口合成法では,ケーブルなど電波を集めてくる通り道の電気長を高精度に保つことに相当し,やはり短波長・長アンテナ間隔になるほど技術的にむずかしい問題が生ずる。増幅は,こうして集めた電波を,可能な限りの低損失で強める機能である。長~中波長では冷却した電界効果トランジスター増幅器,パラメトリック増幅器,メーザー増幅器などが用いられるが,ミリ波では冷却ダイオードミキサーによる周波数変換を介さねばならない。現在,超伝導素子などの応用によるミリ波での受信器低損失化の研究が各国で競って進められている。
増幅した電波は,電波分光器などへ送られて周波数や偏波情報にわけ,最終的には電圧信号に変えられてコンピューターに入力される。電波スペクトルを得るための電波分光器の大容量化も,レーザー応用の音響光学型電波分光器,LSI技術を用いたディジタル分光器など,最近の発展が著しい。
大型コンピューターによるデータ解析・画像処理は,電波望遠鏡には欠かせない。視野をもたず,光軸方向にだけ感度をもつ単一パラボラ型の場合は,多くの観測点からのデータを蓄積して,最終的に画像に仕上げる過程が重要である。開口合成型の場合はさらに大量情報の高速処理を必要とする。
VLA
最新鋭かつ世界最大の開口合成電波干渉計は,アメリカ国立電波天文台のVLA(very large arrayの略)である。標高2000mの高地に,1辺21kmのレールをY字形に敷き,これに沿って直径25mのパラボラを27基配置している。アンテナの配置は,観測目的によってさまざまに変えることができる。観測波長は20cmから1cm,中央の観測室に集められた電波を処理して,分解能最高0″.1というシャープな電波写真をとることができる。1981年に完成し,現在クエーサーや銀河爆発現象の解明などに大きな威力を発揮している。
野辺山宇宙電波観測所
ミリ波では世界最大の装置をもつ新鋭観測所である。東京大学東京天文台(現,大学共同利用機関法人の自然科学研究機構国立天文台)が10年の準備,5年の建設期間をかけて長野県野辺山高原(標高1350m)に建設したもので,1982年に全国共同利用観測所としてスタートした。おもな装置は直径45mの高精度パラボラ鏡と,直径10mのパラボラ5基からなる開口合成鏡である。いずれの装置も,ミリ波で最高の感度と分解能を実現して星間物質や星の誕生,銀河の構造などを解明する目的のため,とくに高精度に作られた。
45m鏡はレーザー測定技術の応用による鏡面測定,相似的変形のみを許す構造設計,カーボンファイバーを用いた高精度反射パネルなどの技術開発をつみ重ねて,直径45mのパラボラ面全面にわたって0.2mm(自垂平均誤差)という高い鏡面精度を実現している。また電波望遠鏡としては初めてのナスミス光学系,大容量の音響光学型電波分光器などで観測効率を大幅にあげることに成功した。現在内外の研究者によって,星の誕生過程,銀河の構造などに関する新しい成果があげられつつある。
開口合成型の電波干渉計は東西560m,南北520mのレールに沿って10mパラボラ5基を配置するもので,ミリ波で最高の1″の分解能で電波写真をとる。超高速のディジタル分光器などを備え,45m鏡にやや遅れて観測を開始した。この両者の能力を組み合わせて,さらに活発な観測が期待されている。
→電波干渉計 →電波天文学
執筆者:海部 宣男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電波望遠鏡」の意味・わかりやすい解説
電波望遠鏡
でんぱぼうえんきょう
radio telescope
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「電波望遠鏡」の意味・わかりやすい解説
電波望遠鏡【でんぱぼうえんきょう】
→関連項目天体望遠鏡
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
知恵蔵 「電波望遠鏡」の解説
電波望遠鏡
(谷口義明 愛媛大学宇宙進化研究センターセンター長 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
イチロー
[1973~ ]プロ野球選手。愛知の生まれ。本名、鈴木一朗。平成3年(1991)オリックスに入団。平成6年(1994)、当時のプロ野球新記録となる1シーズン210安打を放ち首位打者となる。平成13年(...
お知らせ
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新