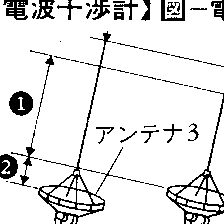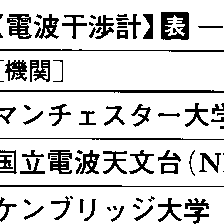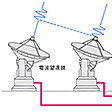精選版 日本国語大辞典 「電波干渉計」の意味・読み・例文・類語
でんぱ‐かんしょうけい‥カンセフケイ【電波干渉計】
- 〘 名詞 〙 二つまたはそれ以上のアンテナを配置し、受信した同一天体の電波を互いに干渉させることによって高い分解能力を得る電波望遠鏡。
改訂新版 世界大百科事典 「電波干渉計」の意味・わかりやすい解説
電波干渉計 (でんぱかんしょうけい)
radio interferometer
ある規則に従って配列した複数個のアンテナで天体の電波を受け,それぞれのアンテナ出力を互いに干渉させることによって,電波源の位置,形状を測定する電波望遠鏡の一種。
天体の電波観測に干渉計を用いる理由は,分解能(解像力)をよくするためである。電波は光に比べると波長が103~108倍長いので,単独のアンテナでは十分よい分解能を得ることはできない。アンテナの口径をD,波長をλとすると,分解能はλ/D(rad)である。したがって,例えば口径50mの大型アンテナを波長1cmで使うと,分解能は約40″である。得られる天体の電波像では,40″より細かい模様はぼけている。これに対し可視光では口径わずか10cmの望遠鏡で約1″の分解能が得られる。波長1cmで1″の分解能を得るには口径約2kmの超大型アンテナを必要とするが,これは現実的でない。単独の巨大アンテナを建設するかわりに2km四方に多数の小口径アンテナを配置し,それらのアンテナ出力をケーブルで1ヵ所に集め互いに干渉させることにより,口径2kmの巨大アンテナに匹敵する分解能を得ようとするのが電波干渉計の目的である。現在では,例えば北アメリカ大陸とオーストラリア大陸にあるアンテナを用いて,光学望遠鏡の分解能をはるかにしのぐ驚異的な分解能を得ることが可能である。
原理
電波干渉計の基本である二つのアンテナからなる系を考える。東西方向に距離D12だけ離した二つのアンテナ1および2に,子午面と角度θをなす天体から電波が入射する場合を考える。二つのアンテナまでの光路差はL sin θとなり,この差が波長の整数倍のとき二つのアンテナ出力は強め合い,反対に半波長の奇数倍ずれたときは二つの出力は打ち消し合う。天体の方向は時間とともに変わり,それにつれて光路差が変化するので,その結果二つのアンテナ出力の和は,山と谷とを繰り返す干渉縞を示す。干渉縞の山の時刻から天体の位置を決めるとき,何番目の山が真の天体の位置を表すか一義的に決定することができない。しかし,干渉縞の山と山との間隔は,2アンテナ間の距離によって変わるので,間隔の異なるいくつかのアンテナの組合せで干渉縞の山の時刻を測定することによって,天体の位置を一義的に決めることが可能となる。干渉縞の山と山との間隔は,アンテナ間の距離を広げるとそれに反比例して狭くなる。したがって,距離の遠く離れたアンテナの組合せによって天体の細かな構造を測り,反対に接近して置かれたアンテナの組合せによって大きなスケールの構造を測ることができる。干渉計の分解能は,もっとも遠く離れたアンテナ間の距離をLとするとλ/L(rad)程度である(λは波長)。
種類
もっとも簡単な電波干渉計は,二つのアンテナからなる2素子干渉計である。天体の位置を一義的に決定すること,また天体の構造を測ることができないので,干渉計としては不完全なものであるが,1950年ころの電波天文学初期の観測において,電波銀河や超新星など光学的天体との同定で活躍したという歴史的意義がある。オーソドックスな電波干渉計では,数十個から100個程度のアンテナをある規則に従って配列する。配列のしかたによって種々の名称がつけられている。等間隔に並べる格子型干渉計,そのうちT字型に配列するものをT字型干渉計,円周上に配列するものを円形干渉計という。少ない数のアンテナでできるだけ高い分解能を得ようとして,さまざまな形の変則的配列法も考えられている。なかでも,はやい時間変動を示さない天体に対しては,アンテナの設置位置を可動にして配列を変えたり,あるいは地球回転によってアンテナの配列方向が変わることを利用した開口合成型の電波干渉計(これを開口合成電波干渉計と呼んでいる)が広く用いられている。これによって,わずか数個のアンテナでも時間をかけて観測することによって,高い分解能をもつ二次元像を得ることが可能である。アンテナからの信号を互いに干渉させて天体の像を作るのに,以前は電気回路を組み合わせてハード的に行っていたが,現在では二つずつのアンテナの組合せで位相,振幅を測って記録し,コンピューターで最終的に像を合成するソフト的な処理法が広く行われている。異なる大陸にある二つ以上のアンテナによって天体の位置や大きさの上限値を1/1000″程度の精度で決める超長基線干渉計(VLBI)は,共通の原子時計を基準にしてそれぞれの地点で天体電波をサンプルし,のちに両地点の記録を処理することによって天体の位置などを正確に求めるものである。また,位置の知れている電波源を観測することによって,2点間の距離を精度よく決め,大陸移動を調べる試みが行われており,測地学や地震学への応用は今後重要性を増してくるであろう。
東京天文台(現,大学共同利用機関法人の自然科学研究機構国立天文台)野辺山宇宙電波観測所の開口合成型5素子干渉計は,東西560m,南北520mにレールを敷き,30ヵ所にアンテナ設置用のステーションを設けてある。アンテナは口径10mで鏡面精度約100μmを誇り,波長2.6mmの一酸化炭素線まで観測できるのが特徴である。合成される電波像の分解能は,波長2.6mmおよび13.6mmでそれぞれ1秒角,5秒角である。太陽観測用としては,東京天文台野辺山太陽電波観測所および名古屋大学空電研究所(現,太陽地球環境研究所)に波長1.8cm,3cm,8cmの干渉計がある。アメリカ国立天文台のVLA(very large arrayの略)は,現在世界でもっとも規模の大きい電波干渉計である。口径25mのアンテナ27基を1辺が約20kmのY字型レール上を移動させる開口合成型の電波干渉計で,0.1秒角の優れた分解能を誇っている。
電波天文学は電波干渉計の分解能の向上と歩調を合わせて発展してきたといっても過言ではない。電波源の位置を電波干渉計によって正確に決めることによって,超新星のなごりや特異な銀河などとの同定が行われ,天体を光と電波で研究することができるようになった。準星などの強い電波を放射する銀河は,光で見える銀河をはさんでその両側に二つ目構造をもつことがわかり,それが銀河中心核で起こる激しい爆発現象を解明する重要な手がかりとなっている。
→電波望遠鏡
執筆者:甲斐 敬造
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「電波干渉計」の意味・わかりやすい解説
電波干渉計
でんぱかんしょうけい
radio interferometer
電波望遠鏡の一種。小型の電波望遠鏡(アンテナ)を複数組み合わせて、単一のアンテナでは実現不可能な巨大な電波望遠鏡と等価な解像力を得る装置。基本となるのは、2台のアンテナを使った二素子電波干渉計である。光の干渉と同じ原理で、それぞれのアンテナで受信した天体からの電波を重ね合わせると、天体の方向により強め合ったり、弱め合ったりする。この結果、地球上の干渉計からは地球の自転による天体の方向の変化に伴い、規律正しい正弦波状の信号、つまり電波の干渉縞(じま)がでる。この干渉縞の振幅と位相には、天体の位置、明るさの分布についての情報が含まれている。
原理的には、わずか2台のアンテナでも、アンテナ間隔(基線長)と方向をいろいろ変えて観測し、蓄積された干渉縞のデータをフーリエ変換という数学的な処理を行うことにより、天体の二次元電波写真が得られる。これが、「開口合成法」の原理である。通常は、より効率的に電波写真を得るため、複数のアンテナを組み合わせ、しかも地球の自転による基線の変化を利用する。一般に望遠鏡の解像力は、波長に対する口径の比で決まる。したがって、口径10センチメートルの光学望遠鏡と同じ解像力を得るには、波長1センチメートルの電波では2キロメートルもの口径が必要となる。このため、電波天文学では古くから干渉計の技術が使われてきた。
国立天文台野辺山(のべやま)宇宙電波観測所にあるミリ波干渉計は、口径10メートルのアンテナ6台を組み合わせ、最大600メートルの電波望遠鏡に匹敵する解像力を有する。アメリカのニュー・メキシコ州にある超大型電波干渉計VLA(Very Large Array)は、口径25メートルのアンテナを27台組み合わせたもので、電波干渉計としては世界最大規模。電波干渉計の基線長を数千キロメートル以上に伸ばしたものが超長基線電波干渉計(VLBI)である。
[石黒正人]
百科事典マイペディア 「電波干渉計」の意味・わかりやすい解説
電波干渉計【でんぱかんしょうけい】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...