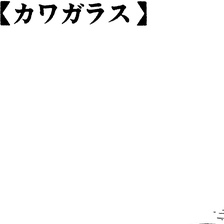カワガラス (河烏)
dipper
スズメ目カワガラス科Cinclidaeの鳥の総称,またはそのうちの1種を指す。この科の鳥は全長15~20cm,くびと尾が短く,ずんぐりした体つきをしているが,脚は長くて強い。羽色は濃褐色か,濃褐色と白色で,雌雄同色である。山地の谷川に単独かつがいですみ,スズメ目の中では水中に潜って食物をとることに適応した唯一の鳥である。ヨーロッパ,アジア,北アメリカ,南アメリカにそれぞれ1種ずつが分布する。
カワガラスCinclus pallasiは全長約20cm,全身が濃褐色をしていて,谷川にすんでいるところからその名がついた。一年中テリトリーをもって生活し,ビッ,ビッと鳴きながら,流れに沿って水面を低く直線的に早く飛ぶ。渓流の石の上を歩いて食物をとることもあるが,ほとんどの食物は水中からとる。水かきはないが,強い脚で流れの中の水底を歩き,石の間から水生昆虫の幼虫をとったり,水中に飛び込み,翼をはばたいて水に潜り,小魚をくちばしでくわえとる。秋につがいになり,春早くから雄はチー,チー,ジョイ,ジョイなどと複雑なさえずりをする。2~6月に,滝の裏側,流れの中や岸にある岩陰の棚,橋の下などにコケ類を使って大きな球形の巣をつくり,1腹4~5個の卵を産む。ヒマラヤ山地以東の東アジアに分布し,日本では北海道から九州まで留島として分布している。ヨーロッパにはムナジロカワガラスC.cinclus,アラスカからパナマにかけアメリカカワガラスC.mexicanus,南アメリカにはシロガシラカワガラスC.leucocephalusが分布する。
執筆者:齋藤 隆史
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
カワガラス
Cinclus pallasii; brown dipper
スズメ目カワガラス科。全長 21~23cm。全身暗褐色。和名とは違い,カラスの仲間ではない。尾は短めで姿がずんぐりしている。分布はカザフスタン,アフガニスタン北部からヒマラヤ地方を経てインドシナ半島北部,ユーラシア大陸東部,ロシア南東部まで及ぶ。平地から亜高山帯までの河川急流域にすみ,滝の陰,堰堤の水抜き口の奥など水が流れ落ちる裏側や,水しぶきのかかる川岸の物陰などにコケなどを用いて球形の巣をつくる。スズメ目では特異で,はばたいて潜水し,水底をはって進む。カワゲラ類,トビケラ類,カゲロウ類など水生昆虫の幼虫や亜成虫,魚卵,小魚などをとる。日本では北海道から屋久島まで全国に生息する。なおカワガラス科 Cinclidaeは 1属 5種からなり,ユーラシア大陸,日本,サハリン島,千島列島,南北アメリカ大陸に分布する。生態は本種に似て,山地の渓流に生息する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
カワガラス
かわがらす / 川烏
川鴉
dipper
広義には鳥綱スズメ目カワガラス科に属する鳥の総称で、狭義にはそのうちの1種をさす。同科Cinclidaeはユーラシア、南・北アメリカに4種が分布する。全長14~22センチメートル、全体に黒褐色であるが、頭の上と腹が白いものもある。いずれも渓流にすみ、滝の裏側や岩の間にコケを用いて営巣する。
種としてのカワガラスCinclus pallasiiはヒマラヤやアフガニスタン以東のアジアに分布しており、日本でも全国的に生息している。全身黒褐色で、全長22センチメートル。短い尾を振りながら、岩の上を跳んだり、水に潜り底を歩いたりして、川の中の昆虫などをとらえる。夏季は標高1500メートルほどの渓流にもいるが、冬季には下流へ下ることが多い。他種よりも早くからさえずり始め、繁殖開始も早く2、3月からであり、4~6個の白色の卵を産む。
[柳澤紀夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
カワガラス
学名:Cinclus pallasii
種名 / カワガラス
目名科名 / カワガラス科
解説 / 渓流で、水中をのぞいたり、潜水してトビケラやカワゲラの幼虫、魚などをとります。
全長 / 22cm
食物 / 水生昆虫、魚
分布 / 九州以北では留鳥
環境 / 山地の渓流
鳴声 / ビッ、ビッ
出典 小学館の図鑑NEO[新版]鳥小学館の図鑑NEO[新版]鳥について 情報
Sponserd by 
カワガラス
カワガラス科の鳥。翼長10cm。ミソサザイに似るがはるかに大きく,全身暗褐色。アジア東部に広く分布し,日本では全国の渓流や山地の湖にすむ。水面すれすれに低く飛び,水中を泳いで水生昆虫などを食べる。巣は滝の裏側や岩のくぼみにコケなどで作る。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by