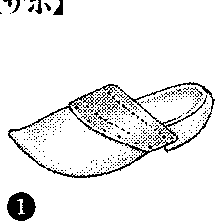関連語
精選版 日本国語大辞典 「サボ」の意味・読み・例文・類語
サボ
改訂新版 世界大百科事典 「サボ」の意味・わかりやすい解説
サボ
sabot
ブナ,クルミ,ハンノキ,トネリコなど耐水性のある堅い木材をくり抜いて作られた木靴。ローマ時代から知られており,オランダ,フランス,ベルギーなどの農民や工場労働者などに愛用されてきた。普通素足で履くが,内側にわらや布を敷くこともある。男女,子どもを問わず用いられ,大きさは異なるが,つま先部がとがって上方にやや反った形は共通する。また足の甲が接する履き口の部分だけに,革を打ちつけたものもある。堅牢であるところから,水気の多いところ,田畑などでは実用に適している。さらにサボの底に2本あるいは3本の支えの足をもっているものが,アフガニスタン,韓国などに見られる。これもまた,一材からのくり抜きで作られるが,下駄の一種とも考えられる。なお,フランス語のサボタージュは日本では怠業の意に用いられるが,本来労働争議の際,サボで工場の床を踏みならしたり,機械や製品を故意に打ちこわしたりしたことに由来。
執筆者:近藤 四郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「サボ」の意味・わかりやすい解説
百科事典マイペディア 「サボ」の意味・わかりやすい解説
サボ
→関連項目靴
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サボ」の意味・わかりやすい解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...