ケイトウ
けいとう / 鶏頭
[学] Celosia cristata L.
ヒユ科(APG分類:ヒユ科)の一年草。インド、熱帯アジア、アフリカ原産で、日本には古く中国から渡来し、『万葉集』にも詠まれている。現在は園芸用に花壇、切り花、鉢植えなどに広く栽培され、属名のセロシアの名で多くの園芸品種があり、春播(ま)き一年草として夏から秋までの観賞草花として親しまれている。
園芸種として一般によく栽培されるものに、トサカケイトウ、ウモウケイトウ、ヤリゲイトウがある。トサカケイトウは、花冠がニワトリのとさか状を呈し、球状のものや扇子状のものがある。草丈は20センチメートルくらいの矮性(わいせい)のものから、80センチメートルくらいの高性のものまで種類が多い。矮性種にコーラルガーデン、ジュエルボックス、中性種にファイアグロー、トレアドール、高性種にクルメケイトウなどの品種がある。ウモウケイトウ(フサゲイトウ)は、基部から多く分枝し、茎頂に羽毛状の花冠をつける花期の長い系統である。矮性種にフェザー、キューピー、中性種にアプリコットブランデー、高性種にフォレストファイア、ゴールデントライアンフなど多品種がある。ヤリゲイトウは、花穂がとさか状とならず、長くとがる種類である。
[金子勝巳 2021年1月21日]
5月上・中旬、気温が安定したころ、地表を均一にならし、薄く播種(はしゅ)し、軽く表面を沈圧する。移植は本葉3~5枚のころに10センチメートル間隔に仮植し、本葉10枚くらいで日当りと排水のよい所に定植する。トサカケイトウは20~30センチメートル、ウモウケイトウは40~50センチメートル間隔で植えるとよい。鉢づくりは、矮性種を選び5~6号鉢に3本くらい植え、水ぎれと肥料ぎれにならないよう管理する。幼苗時に苗腐(なえぐされ)病やネキリムシなどの被害が出やすい。苗腐病にはタチガレン散布、ネキリムシにはオルトラン粒剤で予防する。
[金子勝巳 2021年1月21日]
アジアの熱帯地方などが原産で、野菜から花卉(かき)に改良された。『万葉集』の「韓藍(からあい)」をケイトウとする見方に従えば、渡来は古い。江戸時代にはまだ食用の名残(なごり)があり、貝原益軒は『菜譜(さいふ)』(1704)で「若葉をゆでて、しょうゆにひたして食べると、ヒユよりうまいが、和(あ)え物としてはヒユに劣る」と述べる。別種のヒモゲイトウはアンデス原産で、種子が穀物となり、中国雲南省やヒマラヤ地方でも栽培されている。
[湯浅浩史 2021年1月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ケイトウ (鶏頭)
cockscomb
Celosia argentea L.var.cristata(L.)Kuntz.
文字通りニワトリの肉冠のような花序をつけるヒユ科の春まき一年草。古くに中国から渡来したらしく,《花壇綱目》(1681)や《大和本草》(1708)には鶏頭花(けいとうげ)と記されている。園芸種には二,三の系統があるが,いずれも茎は直立性で卵形,卵状披針形の葉を互生し,夏から秋にかけて茎の先端に紅色,桃色,黄色などの花序を形成し,それに多数の小花を密生する。小花は白色または帯紅色で,花被片は5枚,おしべ5本,めしべ1本。果実は球形もしくは卵形で,中に黒色で光沢のある種子ができる。花序の形や色彩に多くの変異があり,それらは次のような品種群にまとめられる。トサカケイトウは花序がトサカ状のもので,もっとも普通に栽培される。久留米ケイトウはその花序が塊状に発達したものである。羽毛ゲイトウ(別名フサゲイトウ)は花序が細かく分岐して紐状となり,炎のような形となる。フォレストファイヤー,フェザーなどの品種がある。ヤリゲイトウは細裂した花序が全体として尖卵形となる。その中で軸が短縮して,全体が球形となるものをとくに玉ゲイトウと呼んでいる。八千代,赤玉などの品種がある。
ケイトウは移植をきらうので,4月上旬に直まきとし,適宜間引きを重ねて8~9月に花穂を見るようにする。切花のためには久留米,八千代などの品種がよく,窒素肥料を元肥に多く使用すると生育が良い。鉢作りにはいずれの系統も矮性品種を使用し,小鉢から大鉢に鉢替えして育てる。切花栽培や花壇,鉢植えのためには施肥を十分に行って花穂を大きくみごとにつくるが,種子がとれにくいので,種とりのためには窒素肥料を少なくして,やせ気味に育てるのがよい。
執筆者:浅山 英一 ノゲイトウCelosia argentea L.は栽培のヤリゲイトウに似るが,花穂は淡紅色または白色で,柄が長い。花被はより大きく長さ1cmに達する。熱帯の荒地に広く分布し,日本では本州西部・四国・九州南部に帰化している。
執筆者:矢原 徹一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ケイトウ(鶏頭)【ケイトウ】
トサカケイトウとも。熱帯アジア原産のヒユ科の一年草。茎は太く直立し,1m内外になり,披針形の葉を互生。茎頂が帯化してニワトリのとさか状の花序になり,多数の細かい花をつける。花序は黄,白,桃,赤など色彩の変化に富む。花期は8〜11月で,花壇植,切花に向く。春まきで,栽培は容易。草たけが20〜30cmの矮性(わいせい)品種や,花序がとさか状にならずに房状や球状などになる系統もある。また,ケイトウの近似種で,日本の暖地に野生化しているインド原産のノゲイトウが栽培されており,〈セロシア〉などと呼ばれて切り花にされている。→ハゲイトウ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ケイトウ(鶏頭)
ケイトウ
Celosia cristata; cockscomb
ヒユ科の一年草。熱帯インドの原産。庭園で観賞用に植えられる。茎は赤く高さ約 90cmほどで質が木質化して硬く,縦に何本もの稜がある。葉は互生し長楕円形,鋭尖頭で基部も細まり柄がある。秋に,帯化して扁平に発達した花軸上に多数の小花をつける。その形がニワトリの鶏冠に似ているのでこの名がついた。花軸部は赤く,花は赤,黄,白など種々の色のものがある。花弁はなく萼片が5個,おしべも5本で,萼は花後も宿存する。果実は熟すると帽子のようにふたの取れる蓋果で,中に3~5個の黒い種子が入っている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「ケイトウ」の読み・字形・画数・意味
【 灯】けいとう
灯】けいとう
【 灯】けいとう
灯】けいとう
【 洞】けいとう
洞】けいとう
【 桃】けいとう
桃】けいとう
【 刀】けいとう
刀】けいとう
【軽 】けいとう
】けいとう
【頸 】けいとう
】けいとう
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 




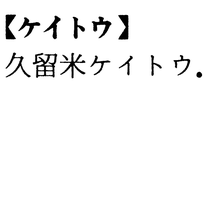
 灯】けいとう
灯】けいとう 」の
」の 灯】けいとう
灯】けいとう 」の
」の 洞】けいとう
洞】けいとう 」の
」の 桃】けいとう
桃】けいとう 」の
」の 刀】けいとう
刀】けいとう 」の
」の 】けいとう
】けいとう 】けいとう
】けいとう