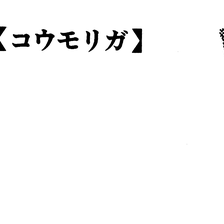コウモリガ (蝙蝠蛾)
swift moth
鱗翅目コウモリガ科Hepialidaeに属する昆虫の総称。中型から大型の原始的なガで,前・後翅の大きさや形が似ていて,翅脈数がほぼ12本ある。昔はこのような脈相の科を鱗翅目の中の同翅亜目としていたが,最近の分類では,この群の中で小腮鬚(しようさいしゆ)の発達していないコウモリガ科をコウモリガ亜目Exoporiaとして区別している。触角は非常に短く,口器はごく小さい。幼虫は草木の茎,樹木の幹や枝にトンネルを掘って食入し,食入口には糞を糸でつづるので,被害を受けた木を見分けることができる。日本には8種分布している。
コウモリガEndoclyta excrescensは開張5~11cmの大型種で,近縁のキマダラコウモリE.sinensisとともに全国に分布し,幼虫は各種の樹木にトンネルを掘る害虫。成虫は夏の終りころに出現し,夕暮時に雄は活発に飛び回り,雌を探して交尾する。雌はけし粒のような黒色の卵を草の中へばらばらと産み落とす。
執筆者:井上 寛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
コウモリガ
こうもりが / 蝙蝠蛾
ghost moth
昆虫綱鱗翅(りんし)目コウモリガ科の総称、またはそのなかの1種。夕暮れ時に活発に飛ぶようすがコウモリを連想させるところから名づけられた。この科は小さなグループで、日本には8種が知られている。前後翅の形がほぼ等しく、翅脈数も同じであるので、鱗翅目のなかでもっとも原始的な科の一つとされている。幼虫は、大形種では樹木の幹や枝にトンネルを掘って侵入し、小形種では草の茎の中に侵入する。成虫は夜間灯火に飛来することもあるが、夕暮れ時に飛び、交尾、産卵をする。
日本の代表的な種の一つであるコウモリガEndoclyta excrescensは、はねの開張45~110ミリメートル、前翅は赤褐色、不規則な帯状の紋があり、ところどころに黒点または黒斑(こくはん)がある。北海道から屋久(やく)島までと、中国やシベリア東部に分布する。夏の終わりごろに出現する。幼虫は果樹、林木、庭木など、多数の木に穴をあけて侵入、食害する害虫で、老熟までに2~3年かかり、穿入孔(せんにゅうこう)に繭をつくって坑道内で蛹化(ようか)する。多発すると被害が大きい。
[井上 寛]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
コウモリガ
Phassus excrescens
鱗翅目コウモリガ科。前翅長 30~50mm,体長もほぼ同長。夕方活発に飛ぶのでその名がある。全体暗褐色で,前翅には黄白色の斜帯がある。翅は細長く先端がとがり,後翅は前翅よりわずかに短い。触角は毛状で細く短い。成虫は夏季に出現する。幼虫はクサギ,キリなどの樹幹を穿孔して食害する。北海道,本州,四国,九州,アムールに分布する。なおコウモリガ科 Hepialidaeはガのなかでも原始的な科で,触角は小さく,前後翅の脈相が類似している。世界に約 300種が知られるが,大部分は南半球に産し,日本には8種が分布している。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
コウモリガ
学名:Endoclyta excrescens
種名 / コウモリガ
解説 / 触角は短く、単純な構造をしています。夕方活発に飛びます。幼虫は、木の幹にあなをあけて食べます。
目名科名 / チョウ目|コウモリガ科
体の大きさ / (前ばねの長さ)26~55mm
分布 / 北海道~九州
成虫出現期 / 8~9月
幼虫の食べ物 / キリ、クヌギなど
出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のコウモリガの言及
【ガ(蛾)】より
…
[分類と種類]
最近では,学問的に根拠のうすいチョウ類とガ類に大別する分類法は排除され,鱗翅目は次の2亜目に大別されている。すなわち前・後翅の脈相が似ていて,その数も10本かそれ以上ある原始的なグループ(コバネガ亜目,スイコバネガ亜目,コウモリガ亜目)と,後翅の脈相が異なり,8脈かそれ以下しかないグループ(単門亜目と二門亜目)である。コバネガ亜目には[コバネガ]科(日本産は9種,以下同じ)が,スイコバネガ亜目にはスイコバネガ科(4種),コウモリガ亜目には[コウモリガ]科(8種)が含まれる。…
※「コウモリガ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by