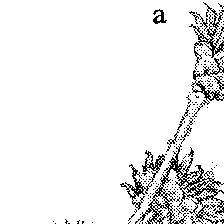フサザクラ
Euptelea polyandra Sieb.et Zucc.
湿った沢すじに多いフサザクラ科の落葉小高木。赤い花が房になって咲き,樹皮が桜に似るところからフサザクラの名がある。大きいものでは高さ8mほどになる。枝には短枝が発達する。葉は互生で卵円形,粗い鋸歯があり,先端は長く突出する。花は両性花で,葉の展開に先立って3~4月に咲く。花被はなく,おしべ,めしべとも多数で,おしべは房状について赤く目立つ。果実には翼があり,風散布する。日本特産で,本州,四国,九州に分布。材は挽物,艪(ろ),櫂(かい),建具等に用いられ,炭にも利用される。樹皮から鳥黐(とりもち)がとれる。
フサザクラ科はフサザクラ属Eupteleaだけからなり,2~3種がヒマラヤ,中国,日本に分布する。カツラ,ヤマグルマと同様,日本では普通にみられるものの,系統上,孤立した原始的な植物で,花被を欠き,離生あるいは半合着した心皮からなる原始的なめしべを有する特異な群で,スイセイジュとともに東アジアの植物相の原始性を代表している。
執筆者:植田 邦彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
フサザクラ
ふさざくら / 房桜
[学] Euptelea polyandra Sieb. et Zucc.
フサザクラ科(APG分類:フサザクラ科)の落葉高木。幹は直立し、高さ8メートルに達する。葉は長い葉柄があって互生し、扁円(へんえん)形または広卵形で幅約10センチメートル、先端は尾状にとがり、縁(へり)に不整の鋭い鋸歯(きょし)がある。早春、短枝の頂に両性花を束状につける。花柄は短く、花被(かひ)はない。雄しべは多数で花糸は短く、葯(やく)は線形で黒ずんだ紅色。雌しべは多数の離生心皮からなり、各子房に柄があり、全体として房状を呈し、名の由来となっている。果実も房状で、細い柄の先に扁平な翼がある。山地の川岸に生え、本州から九州に分布する。
フサザクラ科はヒマラヤ、中国、日本に1属2種しかなく、類縁の不明な特殊な植物である。
[古澤潔夫 2019年9月17日]
APG分類でもフサザクラ科とされる。
[編集部 2019年9月17日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
フサザクラ(総桜)
フサザクラ
Euptelea polyandra
フサザクラ科の落葉高木。東アジアに分布し,日本では北海道を除く各地の山地に普通に生える。幹は直立して分枝し,枝は赤褐色で,高さ 8mぐらいになる。葉は互生し扁円形で先が急にとがる。縁には不整の鋭い鋸歯があり,下面の葉脈に毛がある。3~5月に,葉に先立って短枝の上に花が集ってつく。両性花で花被はないが,多数あるおしべの葯 (やく) が赤褐色をしていて目立つ。果実は袋果で扁平な翼状をなす。樹皮からは鳥もちがとれる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
フサザクラ
タニグワとも。フサザクラ科の落葉高木。本州〜九州の山地にはえ,谷筋に多い。葉は広卵形で先は尾状にとがり,縁には大小不整の鋸歯(きょし)がある。3〜4月,葉の出る前,短枝の上に暗赤色の花を開く。花被はなく,おしべは赤く房状になり,めしべとともに多数。果実はゆがんだ倒卵形で翼があり,9〜10月,褐色に熟す。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by