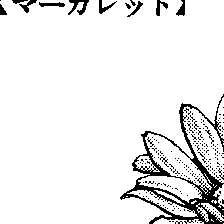マーガレット(その他表記)marguerite (margaret)
精選版 日本国語大辞典 「マーガレット」の意味・読み・例文・類語
マーガレット
- 〘 名詞 〙 ( [英語] marguerite )
- ① キク科の低木状多年草。カナリー島原産で観賞用に温室や庭園で栽培される。茎は高さ一メートルに達しよく分枝する。葉は互生し緑白色で羽状に深裂する。春から夏にかけ、枝端から長い花柄を出し、径五~八センチメートルの頭花を一個ずつ開く。周辺花は白色の舌状花で一列に並ぶ。中心花は黄色。和名きだちカミツレ。もくしゅんぎく。きだちカミルレ。《 季語・夏 》
- ② 明治一七~一八年(一八八四‐八五)ころから若い女性の間で行なわれた洋風の結髪。毛先を幅の広いリボンで飾ったもの。少しずつ型を変えながら流行を続け、昭和初期には髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンでとめて後ろに垂らすものになった。〔洋式婦人束髪法(1885)〕
 マーガレット②〈洋式婦人束髪法〉
マーガレット②〈洋式婦人束髪法〉
改訂新版 世界大百科事典 「マーガレット」の意味・わかりやすい解説
マーガレット
marguerite (margaret)
Paris daisy
Chrysanthemum frutescens L.
キク科の非耐寒性の半灌木状多年草。カナリア諸島の原産。日本では暖地で切花用として多く栽培されるが,鉢物,花壇にもよく利用されている。和名モクシュンギク。margueriteはギリシア語margaritēs(真珠)に由来し,その清純な白い花を真珠にたとえたものであろう。花の名としては国によってさす植物がちがい,英語のmargueriteはデージー(ヒナギク),ひいてはモクシュンギクをさし,フランス語ではデージーをさす。またドイツ語のMargeriteは,フランスギクをいう。Paris daisyの名は,この植物が初めフランスにおいて改良され園芸化されたことによる。原種は草丈1mぐらいでよく分枝して茂り,半灌木状となる。葉は幅が広いが,深い切れ込みがある。初夏のころに茎の上部で花茎を枝分れさせ,径3~4cmの一重咲きの白色頭状花を数多く咲かせる。栽培管理によって,最近は周年切花として利用される。改良品種が多く,径5~6cmの中輪種,四倍体の大輪品種,八重咲きや丁字咲品種のほか,近縁のシュンギクとの交配により改良された黄花種があり,これは葉の切れ込みが粗くシュンギクの葉に似ている。その他,桃色花品種などもある。ニュージーランドやアメリカでの改良が盛んで,鉢物むきに改良された矮性(わいせい)種なども育成されている。寒さに弱いため,暖地を除くと戸外での越冬は無理である。日当りと排水のよい土地を好み,暖地海岸の傾斜地でよく栽培される。繁殖はもっぱら挿木による。9月ごろ挿木を行い,発根後鉢上げをして1回摘芯をし,寒冷地では温室,フレームなどに入れて越冬させる。花壇には4月ごろ鉢から抜いて20~30cm間隔に定植をする。生育中の追肥に窒素分の多い肥料を施しすぎると,茎葉ばかり茂って花付きが悪くなる。
マーガレットを含むキク属Chrysanthemumは,地中海沿岸からヨーロッパに多く,いくつかの種が観賞,切花植物として利用されている。
フランスギクC.leucanthemum L.(英名oxeye daisy)は白花をつけ,マーガレットにしばしば混同されることもあるが,茎は木質化せず,単生するか,基部で分枝する草本で,耐寒性がある。初夏に出る花茎は高さ30~100cm,頭花は径3~6cmになる。ヨーロッパから中央アジアまで広く分布し,北アメリカなどには帰化している場合がある。秋に株分けによって繁殖する。
このフランスギクを基に交雑育成されたのがシャスタ・デージーC.burbankii Makino(英名Shasta daisy)で,アメリカの品種改良家L.バーバンクにより作出された。フランスギクと日本のハマギクあるいはコハマギクなどを交配して作出されたといわれる。草丈は60~80cm。強直な茎を叢生(そうせい)して直立させ,6月ころ,径5~6cmの純白色黄芯の頭状花を頂生する。葉は無毛で濃緑色,浅い鋸歯のある倒披針状長楕円形葉。ふつうは一重咲きであるが,二重咲き,八重咲き,丁字咲きなどの品種もあり,草丈30cmぐらいの矮性種もある。耐寒性のあるじょうぶな宿根草で,日当り,排水のよいところを好む。繁殖はおもに株分けにより,春または秋に行う。矮性種は春に種子をまいて栽培をすれば夏~秋に開花する。高性種は切花として多く利用されるが,庭や垣根沿いに群植しても美しい。
クリサンテマム・ムルティカウレC.multicaule Desf.は,最近になって,鉢物や花壇などに利用されるようになったキクの仲間の一・二年草で,茎はよく枝を分かち,高さ20~30cmになる。葉はやや多肉質で線形,長さ3~6cm,まばらに鋸歯があるか全縁である。茎の先端に,輝くような黄金で径3cmほどの頭花をつける。播種(はしゆ)は秋または春で,開花期は春から夏。原産地は北アフリカ。また花屋でノース・ポールと呼ばれるものは,クリサンテマム・パルドスムC.paludosum Poir.の園芸品種で,やはり近年栽培が多くなった。早春から初夏まで咲き,花色は白,原産地は北アフリカである。ハナワギクC.carinatum L.は一年草で,シュンギクによく似る。舌状花が紅褐色や黄と赤のものなどがあり,花弁の基部に輪状に斑(ふ)が入る。原産地はモロッコ。秋に種子をまくと翌年の5~7月に咲く。
執筆者:柳 宗民+堀田 満
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「マーガレット」の意味・わかりやすい解説
マーガレット
まーがれっと
marguerite
[学] Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.
Chrysanthemum frutescens L.
キク科(APG分類:キク科)の多年草。カナリア諸島原産。種名のfrutescensは低木状の意味で、茎の基部が木質化することによるが、和名のモクシュンギク(木春菊)も同様の理由による。全株無毛で、茎は高さ約1メートルで、よく分枝する。葉は互生し、灰緑色または鮮緑色の肉質で、2回羽状に深裂し、裂片は広線形で先はとがる。冬から春、茎上部の葉腋(ようえき)から花茎を出し、径約5センチメートルの頭状花を頂生する。頭花は一重咲きで、舌状花は白色、管状花は黄色が普通であるが、八重咲きの品種や、舌状花が淡黄色の品種もある。一般に広く栽培される白色花の品種は染色体数2n=27で、基本数n=9の三倍体で不稔(ふねん)であるが、近年2n=18の稔性の品種が導入されている。
切り花にするほか、鉢植えおよび花壇植えにする。栽培は排水のよい砂質壌土が適し、多少水分の多い所でよく育つ。寒さには弱く、冬は暖地以外ではフレームか温室で育てる。繁殖は挿芽により、5~6月に挿し、8~9月に定植し、冬季の切り花にするほか、挿芽活着後に鉢上げする。連作すると根腐(ねぐされ)病や萎凋(いちょう)病にかかりやすくなるので、連作は避ける。
[岡田正順 2022年4月19日]
文化史
マーガレットの名で扱われる花にはフランスギクや、古くはヒナギクも含まれ、混乱がみられる。カナリア諸島原産のマーガレット(パリス・マーガレット)は、16世紀中ごろ(別説によると17世紀末)にヨーロッパに伝わったとされ、それ以前のマーガレットはヒナギクの場合が多い。イギリスのヘンリー6世の妃のマーガレット・オブ・アンジューが紋章に使ったのもヒナギクである。一方、日本では現在もしばしばマーガレットと俗称されている耐寒性のあるフランスギクは、本来ヨーロッパに自生し、ヒナギクとともにヨーロッパでは中世以前はマーガレットとよばれた。マーガレットの名は、白い花を見立てたギリシア語の真珠マーガライトmargaritesに基づくとされるが、7月20日の聖マーガレットの日の近くに開花するからという異説もある。
[湯浅浩史 2022年4月19日]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マーガレット」の意味・わかりやすい解説
マーガレット[アンジュー]
Margaret of Anjou
[没]1482.8.25. ソミュール近郊
イングランド王ヘンリー6世の妃。アンジュー伯ルネ1世の娘。百年戦争中の英仏和約の一条件として 1445年結婚。夫が精神障害をきたしたので政治の実権を握り,サフォーク公,サマセット公に接近。これがヨーク派の反対を受け,バラ戦争が勃発。ランカスター派の指導者として活躍したが,61年敗れて夫とともにスコットランド,次いで大陸に亡命。 70年帰国して勝利し,夫を復位させたが,71年再び敗れてロンドン塔に幽閉された。 75年フランス王ルイ 11世が身のしろ金を支払ってくれたため解放され,フランスに帰ったのち,窮乏のうちに死んだ。
マーガレット
Chrysanthemum frutescens; marguerite
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「マーガレット」の意味・わかりやすい解説
マーガレット
→関連項目キク(菊)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル大辞泉プラス 「マーガレット」の解説
マーガレット
世界大百科事典(旧版)内のマーガレットの言及
【髪形】より
…一般の既婚者の間では銀杏返し(いちようがえし)が結われていたが,中・上流階級では束髪系統が一世を風靡した。束髪には西洋上げ巻,西洋下げ巻,イギリス巻,まかれいと(マーガレット)などがあり,たちまち全国にひろまった。このイギリス巻やマーガレットによって,初めて〈髪を編む〉という技法が日本に紹介され,鬢,髷,髱で構成された従来の髪形が変化していくことになった。…
【デージー】より
…【浅山 英一】
[伝承,象徴]
デージーは古く〈デイズ・アイday’s eye〉(〈太陽〉の意)と呼ばれ,その名は花の形が太陽に似ることに由来する。またマーガレットという別名(日本ではふつうモクシュンギクという別の花だけをマーガレットと呼ぶ)はつぼみと花冠の色が真珠(ラテン語でマルガリタmargarita)に似ることからきたが,ヘンリー6世の妃をはじめ同名をなのる女性は好んでこれを身に着けたという。中世には戦いで受けた傷の血止めに効果があるとされ,騎士は馬上武術試合の前にこれを襟に着けたという。…
※「マーガレット」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...