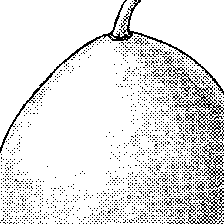ユウガオ
ゆうがお / 夕顔
[学] Lagenaria siceraria Standley var. hispida Hara
ウリ科(APG分類:ウリ科)の一年草。同じくウリ科のヒョウタンと近縁の種で、祖先種は西アフリカ原産。かんぴょう(干瓢)の原料植物として知られる。なお、ヒルガオ科のヨルガオを俗にユウガオとよぶことがあるが、本種とはまったくの別種であり、この俗称は正しくない。茎はつる性で枝分れして10メートル余に伸び、巻きひげで他物に絡まる。葉は心臓形でやや浅く裂け、茎葉全体に軟毛がある。雌雄異花。葉腋(ようえき)に1個ずつつき、深く5裂した白い花を夏の夕方から開き、翌朝にはしぼむ。花期後30日ほどで大形の果実が成長し、完熟するとヒョウタンのように果皮が堅くなる。果実の形によって丸形のマルユウガオと長形のナガユウガオに大別される。マルユウガオは果実は直径約30センチメートル、重さ10~30キログラムになる。発育しきって、果肉が堅くならないうちに収穫し、果軸を中心として外側から円周に沿って果肉を削り、幅3センチメートル、厚さ3ミリメートルほど、長さは2~3メートルの連続した帯状にする。これを天日に干してかんぴょうをつくる。ナガユウガオは長さ50~80センチメートル、太さ直径15センチメートルほどになる。これも輪切りにしてむいてかんぴょうとするが、かんぴょう用にはマルユウガオより品質が劣り、あんかけにして煮食されるが、やや苦味のあるものが多い。かんぴょうの主産地は栃木県南東部で、この地域ではもっぱらマルユウガオが栽培されている。
春に苗床に播種(はしゅ)し、数枚の葉をもった苗を畑に定植する。夏の夕方の開花時、結実をよくするため人工交雑を行う。またかんぴょうむきは深夜から行われて、日の出とともに干し、短い日数で早く干し上げることが良品質のかんぴょうをつくるこつとされる。
種子取り用に完熟期まで置いて、果肉が硬くなったユウガオは、炭入れ、火鉢、花器、玩具(がんぐ)の面など農村工芸の材料とされる。
[星川清親 2020年2月17日]
ユウガオは花に注目した名で、『枕草子(まくらのそうし)』は「いとをかしかりぬべき花」と述べ、『源氏物語』には「花の名は人めきて」と、短命の一夜花を薄幸の女性に重ねた「夕顔」の巻がある。明治以降はヒルガオ科のヨルガオがユウガオともよばれ、一部で混乱があるが、江戸時代までのユウガオはすべて本種である。日本では果実にくびれのないのをユウガオ、くびれるのをヒョウタンと区別するが、両者は容易に雑種ができ、世界的には形も連続し、苦味は顕性遺伝子に支配されるにすぎない。最古の農作物の一つで、現在もインド、東南アジア、台湾などでは広く生鮮野菜として流通している。かんぴょう(干瓢)は中国では3~4世紀にさかのぼり、『釈名(しゃくみょう)』に「瓠畜(こちく)」の名で、皮をむいて蓄え、冬に用いよと記述される。かんぴょうは現在の中国では北部に残るが少ない。日本では『延喜式(えんぎしき)』(927)に、大和(やまと)国の産物としてあがる。現代の主産地栃木県へは1712年(正徳2)、近江(おうみ)(滋賀県)水口(みなくち)藩主鳥居忠英(ただてる)が下野(しもつけ)(栃木県)壬生(みぶ)藩に移された際、奉行(ぶぎょう)の松本茂右衛門(もえもん)に命じて、配布・栽培させて広がった。
[湯浅浩史 2020年2月17日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ユウガオ (夕顔)
white flowered gourd
bottle gourd
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.var.clavata Ser.
ウリ科の一年草で,果実はかんぴょうの原料あるいは容器として利用される。花が夕方開き翌日午前中にしぼむので,アサガオ(朝顔),ヒルガオ(昼顔)に対してユウガオとつけられた。なお,ヒルガオ科のヨルガオもユウガオと呼ばれることがある。インドの原産で,かんぴょうの原料となるユウガオの系統は中国,日本で栽培され,ヒョウタンから苦みがなく果肉の軟らかいものが選択された。日本へは中国から渡来したと思われるが,その年代については明らかでない。茎はつる性でよく伸び,茎葉ともに軟毛がある。花は白色。雌雄同株で,果実は扁平なセイヨウナシ形,だるま形または長円筒形で,成熟果重は15~30kgにもなる。果皮色は白か青の単色,果肉は厚く白色。品種の分化はほとんどなく,従来果形により丸と長に分けられ,また果皮色で青か白に分類していた。現在はこれら在来種から純系分離で育成した,しもつけ白,しもつけ青の2品種が広く栽培されている。栽培は4月上旬~下旬に播種(はしゆ)し,親づるが4~5枚になったころ摘心し,子づる2~3本仕立てで孫づるに着果させる。ユウガオ栽培の主要目的は,果肉を帯状にはぎ乾燥させて作るかんぴょうの原料生産にある。かんぴょう用には開花後15~25日を経過した果実を収穫する。かんぴょう生産は栃木県が有名で,約80%以上の生産量を占める。未熟果は煮食,つけもの用とし,完熟果は内部を腐らせて除き,炭入れや花器など容器に加工する。またスイカつる割れ病予防のために,台木用としての種子需要も多い。
執筆者:金目 武男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ユウガオ(夕顔)【ユウガオ】
アフリカ〜熱帯アジア原産といわれるウリ科の一年草。ヒョウタンはこれの一変種。茎はつる性で巻きひげにより他物にからみつく。葉は互生有柄で丸みを帯びたハート形で浅く掌状に裂ける。花は雌雄同株で白色,夏の夕方から朝にかけて開く。果実は長い円筒形のものと大きく扁平のものとがあり,前者は若い果実を生食するほか花器などにし,後者はおもに干瓢(かんぴょう)にするほか,炭入れなどの器物に加工する。なお,ヨルガオのことをユウガオとも呼ぶ。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ユウガオ(夕顔)
ユウガオ
Legenaria siceraria var. hispida
ウリ科の一年生のつる植物。アフリカあるいはアジア熱帯の原産といわれ,植物分類学上はヒョウタン (瓢箪)と同一種とされる。暖地によく栽培され,全体が青緑色で軟毛がある。葉は柄があって互生し,円形で浅く掌状に裂ける。葉と向き合ってふたまたに分れた巻きひげがある。雌雄同株で,夏に葉腋に白花を生じる。雄花は長柄があり,雌花は短柄をもつ。液果は楕円形で 60~90cmの長さにもなり,白色の果肉は厚く,紐状にむいて干瓢 (かんぴょう) をつくる。特に大型でやや平たい球形の実をつける変種のフクベ L. siceraria var. depressaは栃木県下で多量に栽培されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ユウガオ
[Lagenaria siceraria].スミレ目ウリ科ユウガオ属の一年草.非常に若い果実を食用にし,完熟前のものからカンピョウを作る.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のユウガオの言及
【ウリ(瓜)】より
…巻きひげは托葉起源と考えられており,物にふれると刺激を受けてかなり急速に湾曲生長して巻きつく。花は一日花の虫媒花で,ほとんどのものは早朝に咲き午後には閉じるが,ユウガオ属やカラスウリ属のように夕方に開いて翌朝までに閉じるものもある。性表現型には雌雄両全株型から雌雄異株型まで分化がみられ,そのなかで雌雄異花同株型が最も一般的である。…
※「ユウガオ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by