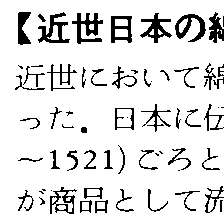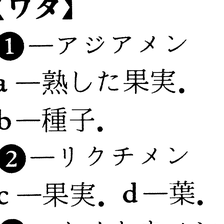改訂新版 世界大百科事典 「ワタ」の意味・わかりやすい解説
ワタ (棉/綿)
cotton plant
Gossypium
木質化するアオイ科ワタ属Gossypiumの多年草の総称であるが,栽培上は一年草として扱われるものが多い。繊維作物として広く栽培され,油料にも利用される。なお綿花とは,ワタの種子についた実綿(みわた)またはそれから生産された繊維をいう。根は直根が深く地中に入る。茎は1本立ちして側枝を出し,高さ1~1.5m,種によってはさらに高くなるものもある。葉はふつう3~5裂した掌状で,長い葉柄によって茎に互生する。花は側枝に咲き,ふつう黄色だが花底が赤いものや白花,赤花のものもある。花後球状で先端のややとがった蒴果(さくか)ができる。蒴の内部は3~5室に分かれ,それぞれ6~9個の種子が入っている。種子は卵形で,白色の長い綿毛lintと短い地毛fuzzにおおわれる。熟すと蒴が裂開し,綿毛が吹き出す。
種類
栽培ワタには起源の異なる数種類がある。リクチメン(陸地棉)G.hirsutum L.は世界のワタ作付面積の70%を占め,栽培上もっとも重要である。アジアメンとアメリカ野生棉との雑種起源と考えられ,新世界からポリネシア地域原産。綿毛は長さ13~33mm,比較的繊細で中~中細番手紡績用原料とされる。カイトウメン(海島棉)G.barbadense L.は南アメリカの原産で,その綿毛はワタの中で最も長く38~50mm,中には60mmに達するものもあり,100~140番手の細手の糸を紡ぐことができる。湿気の多い温暖な海洋性気候に適し,ブラジル,西インド諸島,アメリカ東海岸の一部に栽培される。エジプトメンもカイトウメンの一系統で,エジプトのナイル川流域とアメリカ西部で栽培される。アジアメンには二つの系統がある。G.herbaceum L.はシロバナワタとも呼ばれ,中近東からインドにかけて栽培される。日本の在来種はこの系統である。G.arboreum L.はキダチワタ(木立棉)とも呼ばれ,原産地のインドでは4~6mにもなるという。アジアメンは蒴果も小型で綿毛も9~23mmと短いが,強度が大きいので布団の中入れ綿として利用され,30番手以下の太糸の紡績用に用いられる。
栽培と利用の歴史
ワタの栽培と利用はきわめて古くから行われ,その起源の詳細は必ずしも明らかではない。インドでは古くからワタが栽培され,モヘンジョ・ダロの遺跡(現,パキスタン領)から前2500-前1500年の綿布が発見された。《リグ・ベーダ》(前1200-前1000)にもワタの記載があり,紀元前からインドでワタの利用があったことがわかる。インドのワタ製品はアラビア商人によってヨーロッパにもたらされた。インドに次いで古くワタが栽培されたのはアラビアで,ヨーロッパにワタの種子が伝えられたのは,アレクサンドロス大王の東征(前327)による。エジプトは現在ワタの主産地の一つであるが,前200年よりも以前にはワタを利用した証拠が発見されておらず,現在のエジプトメンは13~14世紀に栽培が始まったものとされる。南アメリカのワタはペルーで前1500年ころから利用されており,ブラジルでも古くから原住民によって利用されていた。中央アメリカでは前632年にワタが利用されていた記録がある。アメリカ合衆国のワタは,イギリスがパナマで栽培したインドのワタが,1740年ころにバージニア地方に伝わって栽培されるようになったものである。中国へは後漢の57-75年ころにインドから綿布がもたらされた。ワタの種子は10世紀に伝えられたが当初は観賞用で,本格的栽培は南宋の1125-62年ころに始まった。日本には古来ワタはなく,初めて記録にあらわれるのは孝謙天皇のときであるが,ここでのワタは国産ではなく,中国か朝鮮からの渡来品だったらしい。ワタが初めて日本で栽培されたのは,桓武天皇の延暦18年(799),三河国に漂着したインド人がもたらした種子による(《日本後紀》)。しかしこの種子は1年で絶えてしまい,その後もなん回か種子が渡来して栽培されたが数年で絶えている。経済的栽培が始まったのは別欄〈近世日本の綿作〉に見るように16世紀に入ってからである。江戸時代には国内の需要を満たしてなお余るほどで,日本もかつては世界的ワタ生産国の一つであった。
栽培と利用
ワタの生育には18℃以上の温度と十分な日照が必要で,また開花前の生長期に降水が十分あり,開花後収穫までは乾燥することが望ましい。塩分やアルカリには強いので,海岸や干拓地でも栽培できるが,酸性土壌には弱い。種子は表面が蠟物質におおわれているので,発芽をそろえるため,地毛を除き,水に浸したのち消毒してまく。収穫は裂開した蒴果から綿毛におおわれた種子を手で摘みとるが,多大の労力を必要とするため,アメリカなどでは薬剤を散布して落葉させて機械収穫を行うことが多い。
収穫後の種子から綿毛を分離し,綿糸,綿織物,ひも,綱などの紡織用,布団綿,脱脂綿などの製綿用の原料とする。綿毛を分離した種子は地毛除去機にかけられる。種子から分離した地毛はリンターlinterと呼ばれ,第1回目に分離したものは包帯,織物,詰物,クッションなどに使われる。ワタはまたセルロース原料としても重要で,この目的には第2回目に分離した地毛があてられ,綿火薬,レーヨン,セルロイドフィルムなどの製造に用いられる。繊維を除いた種子の綿実は重要な油料で,15~20%の綿実油を含む。食用油,マーガリン,セッケンの原料とする。油を絞ったかすも家畜の飼料および肥料として重要である。また若芽はアフリカや東南アジアで食用としても利用される。
執筆者:星川 清親
綿花の生産と消費
歴史的にみて綿花の生産が最も脚光を浴びるのは産業革命のときである。紡績機械の発明が綿製品の大量生産を可能にし,綿花に対する需要は飛躍的に伸びた。その後,世界の衣料材料の首位を占め,各国の農業作物や産業構造のみならず社会構造にも変化を与えた。イギリスの綿織物との競争に敗れたインドが,イギリスの植民地支配下に綿花生産基地となった例,アメリカの奴隷制度と結びついた南部諸州の綿花プランテーションなどはその代表的な例である。化学繊維が創出され,発達するにつれて,全繊維に占める綿の比重は低下したが,現在も繊維生産の首位を占め,その重要性に変化はない。
日本では,明治初期まで近畿地方を中心に綿の生産が行われていたが,開国後は急速に外国綿に淘汰された。世界の綿花生産は1980万t(1995,FAO資料による。以下同じ)で,中国(477万t),アメリカ(391万t),インド(238万t),パキスタン(184万t),ウズベキスタン(131万t),トルコ(76万t),ブラジル(52万t)がおもな生産国である。アメリカは第2次大戦後躍進したソ連,中国に生産では追いつかれたものの,輸出では依然として戦前からの最大の綿花供給国の地位を保っている。ほかに輸出の多い国はエジプト,パキスタン,トルコなどである。輸入は日本と中国が圧倒的に多く,この2国で世界全体の1/3を占める。これに韓国,ドイツ,イタリア,フランスなどが続く。
→綿織物業
執筆者:岡部 守
布団綿
綿が貴重品であった時代,布団などの寝具の詰物には,麻皮や苧屑(おくず)などが用いられた。昭和の初めまで苧屑類を〈わた〉と呼ぶ地方があったほどである。しかし江戸中期以降木綿綿が普及するにつれて,綿といえば木綿綿を指すようになった。化繊類の綿が著しく普及している現代では,ふたたび〈木綿の綿〉と特記する必要が生じている。
木綿の布団綿は,1枚300gを畳1枚くらいの大きさにのべたものを10枚1包(3kg)にして1本という。布団の種類によって異なるが,敷布団の場合は,詰物として木綿綿20~22枚くらいを縦横交互に重ねて入れる。綿は,つやのある乳白色で,弾力があり,夾雑物(きようざつぶつ)のないものがよい。品質表示は,白の特,1,2などの等級に分かれており,赤綿は最近ではほとんどみられない。最上とされる青梅(おうめ)綿は,丹前1着分350gを1包としている。ほかに,用途により,着物に入れる中入れ綿,どてら綿がある。木綿綿は吸湿性があるので,手まめに乾かすことが肝要である。長く使って堅くなったら打ち直して(1割くらい目減りする),新綿を補う。
近ごろは化繊との混綿がかなり出回っている。江戸時代から明治にかけては国産と中国綿が主であったが,近年はインド,パキスタン,ミャンマーなどの短毛筋(たんけすじ)綿から製綿されている。木綿綿の蠟質を脱脂したものが衛生綿である。
布団綿にはほかに次のようなものが用いられる。(1)パンヤ綿 繊維作物カポックなどの実綿の利用で,軽くふんわりしているのが特徴。繊維によりがなく短いため固まりやすく,ほこりも立ちやすいので,中袋に入れてから,まくらやクッションの詰物として用いるのがよい。パンヤのまくらは江戸時代のぜいたくの一つであった。(2)絹綿 真綿を指すこともあるが,繭の外側の毛羽に木綿綿を混ぜたもので,軽く暖かなのが特徴。高級布団や着物にする。丹前用(絹100%,80g)に作ってある吹止綿もある。(3)羊毛綿 最近使われ出したもので,羊毛を綿状にして布団に入れる。保温力と耐久性に優れているが,日本の風土に適するか否か,未知数である。(4)化学繊維綿 第2次世界大戦中のスフ綿に始まるが,戦後の化繊界の発達はすさまじく,天然繊維をしのぐほどの各種の綿が生産され,単独または混合して使われている。木綿と比べて軽く,吸湿性が少なく,打直しの必要がないが,かたよりやすい欠点があるので,キルティングしておくと水洗いもできる。なお羽毛やウレタンフォーム類も綿同様に用いられる。
執筆者:加藤 百合子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報