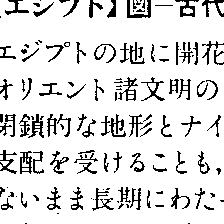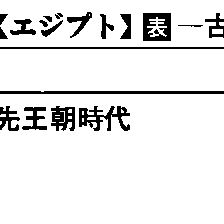改訂新版 世界大百科事典 「エジプト」の意味・わかりやすい解説
エジプト
Egypt
アフリカ大陸の北東隅,ナイル川第1急湍(たん)以北の約1200kmにわたる細長い流域地帯が本来のエジプトで,地形上幅8~25kmの河谷地帯(上エジプト)と河口のデルタ地帯(下エジプト)とからなる。古くよりガルビーヤ砂漠中のオアシス(シワSiwa,バフリーヤal-Baḥrīya,ファラーフィラal-Farāfira,ダーヒラal-Dākhila,ハーリジャ(カルガ)al-Khārija,Khargaの各オアシス),第1・第2急湍間の下ヌビア,紅海沿岸,シナイ半島を勢力圏とし,この地域は現在のエジプト・アラブ共和国にほぼ対応する。エジプトという名称は,古都メンフィスの別名フウト・カ・プタハḤut-ka-Ptaḥに由来するとみられるギリシア名アイギュプトスAigyptosの転訛である。古代エジプト人は自国のことをケメトKemet(〈赤い〉砂漠に対する〈黒い〉土の国の意),タ・ウイTa-wi(上エジプトと下エジプトの〈二つの国〉の意)などと呼んだ。ヘブライ語ではミツライムMiṣrayimと記され,現代アラビア語での名称ミスルMiṣrにつながる。
北アフリカの砂漠地帯を貫いて北流するナイル川がエジプトの生命線である。デルタ北西端のアレクサンドリアの年間降雨量204mm,カイロ30mm,ミニヤー以南の上エジプトはほとんど0に近いという,オリエントでは砂漠につぐ乾燥地帯にあり,ナイル川の浸食作用により形成された河谷および河口に,川が上流より運んできた肥沃な沖積土が堆積してつくりあげた土地(ナイル河谷約2万2000km2,デルタ約1万3000km2)だけが,人間の生存と農耕に不可欠な水を得て,人間生活の舞台となった。この状況は,灌漑地域の拡大による近年の生活空間の広がりにもかかわらず,基本的には変わっていない。毎年6月半ばより10月までの約4ヵ月間,ナイル川に流入する青ナイルとアトバラ川の水源であるエチオピア高原の季節的降雨を集めて増水した河水は,両岸の沖積原を覆う。この期間は主要作物である麦類の休閑期にあたるため,水路によって堤防で囲った耕地に増水を導き,約1ヵ月間冠水したままの状態に保つというエジプト独特の貯溜式灌漑が案出され,エジプトを古代世界最大の穀倉とした。まさにエジプトは〈ナイルの賜(たまもの)〉(ヘロドトス《歴史》2巻5節)であり,古代エジプト人は川を恵みの神ハピHapiとして崇拝した。灌漑機構の効率的な配置・運用のための集団労働の必要から政治社会の組織化が進んだ。
東西を砂漠で限られた閉鎖的な地形と,きわめて規則的な季節的増水をもたらすナイル川の恵みとにより,エジプト文明は他のオリエント文明に比べて相対的に孤立した自律的発展を示す。このため文明の性格は伝統主義的,保守的で,豊かな食糧と砂漠の鉱物資源(石材,金,銅など)のおかげで対外侵略に乗り出すことはまれであり,平和的な交易で満足した。王朝末期以来次々と他民族の征服を受けて政治的自立を失い,ギリシア文明,イスラム文明などの強い影響を被ったが,古代に確立した生活様式を根本的に変えることなく,民族的特性を現在もなお保持している。
歴史
先史時代
旧石器・中石器時代
エジプトのナイル流域の人類の痕跡はヨーロッパの第2間氷期までさかのぼる。前期および中期旧石器の文化は西ヨーロッパや北アフリカと共通である。当時は湿潤で,北アフリカには草原が広がり,各所に森林が繁茂し,野生動物の宝庫であった。前期旧石器はナイル河岸の30mおよび15m段丘,カイロ近郊アッバーシーヤ`Abbāsīya,ハーリジャ・オアシスなどで確認され,アブビル型やアシュール型の握斧(あくふ),剝片(はくへん)石器(30m段丘),中後期アシュール文化の石器(15m段丘)が発見されている。中期旧石器は9m段丘上にみられ,ルバロア型の剝片石器や三角形の小型尖頭器(ポイント)などを特徴とする。これらはアッバーシーヤ,ハーリジャのほかファイユーム湖辺でも発見されている。後期旧石器時代とともに北アフリカの乾燥化が始まり,エジプトは周辺地域と異なる文化を形成する。北アフリカのカプサ文化やレバントの後期旧石器文化の石刃(ブレード)石器文化に対するルバロア型の剝片石器文化(エピ・ルバロア型とよばれる)である。同時にファイユームのエピ・ルバロア文化,ハーリジャのルバロア・カルガ文化とこれに続くカルガ文化,上エジプトのセビル文化など各地に地方色ある文化が出現する。上エジプト,クーム・アンブーKūm Ambū(コム・オンボKom Ombo)近郊の3m段丘より発見されたセビル文化は3期に分かれ,中期以降細石器化の傾向が顕著である。エジプトの場合典型的な中石器文化はまだ確認されていないが,細石器的傾向を示すものとして前述のセビル文化後期,カルガ文化のほかパレスティナのナトゥフ文化と類似する下エジプトのヘルワン文化がある。
原始農耕文化
沖積世に入ると乾燥化はいっそう進んでサハラは砂漠となり,ナイル流域の自然条件はほぼ現在に近づく。西アジア起源の農耕が伝わり,デルタ西縁のメリムデ・バニー・サラーマMerimde Banī Salāma(メリムデ遺跡),ファイユーム(ファイユームA文化),中エジプトのターサTasa(ターサーTāsā)にエジプト最古の農耕遺跡がみられる。これらの遺跡の時代・性格など未解決の部分が多いが,今のところ前5000年ころに始まり,前5千年紀を通じて存続した新石器文化とされている。大麦,エンマ小麦を栽培し,ヤギ,羊,牛,豚を飼育するが,なお狩猟漁労採集にも依存し,集落の規模は小さい。穀物はフリント製石刃を木柄に取り付けた石鎌で刈り,地中に埋め込んだ編籠や地下貯蔵穴に蓄え,石棒と石皿で粉にした。弓矢・棍棒などでカモシカ,カバ,ワニを狩り,銛(もり)で魚を捕った。石器にはほかに局部磨製石斧があり,石鍬(いしぐわ)として用いられたと見られる。亜麻も栽培され織物とされた。土器は手づくねの黒地または赤地の粗製品が日常用いられたが,ターサでは朝顔形の口縁をもつ幾何学文の黒色刻文土器も作られた。住居は簡単な木組みに葦の壁や天井をめぐらせた程度で,楕円形や馬蹄形のプランをもつが,メリムデでは後に粘土張りの床・壁をもち,排水用の土器を床に埋め込んだ竪穴式住居も発達する。ファイユームには炉址も発見されている。埋葬には地方色が見られ,メリムデでは住居の近くまたは住居内に掘った浅い坑に右側を下にして顔を東に向けた横臥屈葬で,副葬品はほとんどないが,ターサでは墓地内に左下西面の横臥屈葬である。副葬品には,土器,石器のほかさまざまな装身具類(貝製・象牙製ビーズ,貝製の垂飾(すいしよく),駝鳥(だちよう)の卵殻の円盤)や日用品(象牙製の櫛,眼の周りに塗るクジャク石をすりつぶすための化粧板)がある。シナイ半島産のクジャク石や紅海産の貝など,既に交易も始まっていることが知られる。
先王朝時代
原始農耕文化はエジプト独自の文化の始まりであり,上エジプトではターサ文化に続いてバダーリ文化,アムラ(ナカダ第1)文化,ゲルゼ(ナカダ第2)文化と継起し王朝時代へ移行する。しかし下エジプトのメリムデ文化に続くオマリ文化,マアディ文化の内容は,ナイル水位の上昇によるデルタ内部の考古学的調査の困難さのためほとんど不明である。
バダーリ文化は遺跡の分布,文化の内容共に先行するターサ文化と重なる部分が多く,ターサ文化をバダーリ文化の一局面とみる説も強い。鍛造による銅製のビーズが出現し,金石併用期に入ったことを示す。土器には黒色刻文土器のほか,赤色磨研土器,黒色口縁土器が加わり,細かな条痕文を特徴とする。象牙製の櫛やスプーンの動物装飾,小型の人物土偶や象牙偶(特に女性像)は造形美術の萌芽を示す。土器をはじめ南方の強い影響が指摘されている。
アムラ文化はナカダを中心に上エジプト全域に広がり,人工灌漑の普及による農耕経済の確立を示唆するが,土器(白色交線文土器)の文様,動物形土器,動物装飾の櫛・化粧板(パレット)・ピン,各種の狩猟具(鏃,槍,銛,棍棒)などからみて依然として狩猟漁労も重要な生業である。銅の使用も拡大し,化粧具,銛,鏃,ピンなどが作られ,金のビーズも多量出土する。交易圏は拡大し,アジアから銀,鉛が輸入されている。
ゲルゼ文化と共に人口の増加,文化水準の著しい向上,社会分化の拡大と政治的統一の進行など王朝時代への発展が加速する。アムラ文化と同じく上エジプト中部から上エジプト全体を覆い,下ヌビアに及び,末期にはデルタのマアディ文化にも取って代わる。土器は特徴的な〈彩文土器〉や波状把手土器が出現し,手回しドリルの導入により精巧な石製容器が製作され,圧剝法によるフリント製石器(石刃,石鏃など)の技法も最高水準に達する。化粧板は動物形が盛行するが,後期には大型の楯形奉納用化粧板が出現,表面に浮彫が施された。集落,墓地の規模は拡大し,日乾煉瓦造りの住居や墓も現れ,後期には西デルタに周壁をもつ都市が成立する。西デルタを通じて注口土器や円筒印章などが伝えられ,西アジアとの交渉の活発化を示す。文字の使用も始まったと見られる。
王朝時代
時代区分
王国の統一による歴史時代の開始からアレクサンドロス大王のエジプト征服までは〈王朝時代〉とよばれ,前3世紀にマネトン(マネト)が著した《エジプト史》にもとづいて31の王朝に分けられている。この王朝区分は現代においても踏襲されているが,王権の強弱(同時に文明の水準の高低)に対応して,古王国・中王国・新王国の各時代,それらにはさまれた第1・第2中間期,および興隆期(初期王朝時代)と衰退期(末期王朝時代)の7期にまとめられている。
初期王朝時代
マネトンによればメネスという名のティニス出身の上エジプト王が下エジプトを征服して第1王朝を開き,新都メンフィスを建設したという。王国の最終的統一以前にも〈さそり〉王など下エジプトを征服した上エジプト王がいたことはゲルゼ文化末期の奉納用大型化粧板の浮彫などから知られており,ゲルゼ文化のデルタへの浸透はこの過程に対応すると考えられる(〈原王朝〉)。メネスが当時の王名のどれを指すのか論争があるが,下エジプト征服を刻む有名な化粧板の奉納者ナルメルNarmer王よりも,メンフィスの墓地サッカラに最初の王墓を建造した次のアハAha王と見るべきであろう。ティニスからメンフィスへの王都移転は,王国統一に協力した上エジプト有力首長の影響力からの離脱と下エジプトの確保とを目指しており,州知事を通じて州単位の灌漑水路網を整備し,レバノン杉の輸入など対外交易を独占しつつ王権の強化と中央集権化が進められた。王は天の神ホルス(隼(はやぶさ)の姿をとる)の化身とされ,王名はセレクserekhと呼ばれる隼を頂く王宮の枠内に記された。第2王朝末,王権強化に反対する勢力がペルイブセンPeribsen王を擁立,国内は一時乱れるが,カセケムイKhasekhemui王が再統一に成功,王の権威は最終的に確立する。
古王国時代
第3王朝とともに王を頂点とする中央集権国家は名実ともに完成,古代エジプト文明は最初の繁栄期を迎える。王は行政(司法を含む),祭祀の最高責任者であり,みずから行うべき機能を委任して代行させるものとして官僚・神官の任命権を握り,要職には王族をあてた。地方には40あまり(プトレマイオス王朝では42)の州(ノモスnomos)が置かれ,州知事が任命された。州は守護神を共同信仰する共同体あるいは部族国家を原型とすると思われるが,初期王朝時代に整備された貯溜式灌漑水路網の一単位に相当し,それぞれが公儀宗教に組み込まれた州の守護神をもつ。王は天の神ホルスの化身,第4王朝初頭では太陽神そのもの,第5王朝以降は太陽神ラーの子として統治し,死後は冥界の支配者オシリス神として永遠に支配するとされ,これにふさわしい墓所として壮大なピラミッドが造営された。このため古王国時代は〈ピラミッド時代〉とも呼ばれる。第3王朝のジェセル王がサッカラに造営した〈階段ピラミッド〉を最初とし,第4王朝の祖スネフルSnefru王のメイドゥーム,ダハシュールのピラミッドを経て,ギーザの三大ピラミッド(クフKhufu,カフラーKhafra,メンカウラーMenkaura3王のピラミッド)で頂点に達する。とくにクフ王の〈大ピラミッド〉の周囲に整然と配置された王妃の小ピラミッド,王族・高官のマスタバ墳は,高度に中央集権化された国家の身分秩序を忠実に反映している。
第5王朝にはいると太陽神ラーの信仰が有力となり,王はピラミッドと同時に太陽神殿をも造営し,国家祭祀の中心は王から太陽神に移る。このためピラミッドは小規模となり,建造技術も急速に低下する。王族の高官職独占は崩れ,官職世襲化の動きが強まる。この傾向は第6王朝になると州知事職を中心にいっそう加速し,州知事は土着化して自立性を強め,ペピ2世Pepi IIの在位94年という長い治世が終わると,王権は有名無実となる。しかし第5~6王朝の対外交渉は活発で,ヌビア,シナイ半島,ビュブロス,プント(現在のソマリアか)にしばしば交易遠征隊が派遣され,銅,香料,木材,象牙などが輸入された。第6王朝のウニWniやハルクウフHarkhufのヌビア遠征は名高い。
第1中間期
第7~8王朝は短命な王が相次いで交替,王朝の支配領域は首都メンフィス周辺に限られ,各地に州知事の世襲化した州侯が分立,一種の〈封建時代〉を現出する。この時代の初めメンフィスを中心に民衆による〈社会革命〉が行われたことが,《イプエルの訓戒》などの文学作品から読み取れる。しかしこの激しい混乱期は長続きはせず,ヘラクレオポリスを都とする第9・10王朝とテーベを都とする第11王朝との国土二分状態が約100年間続き,中エジプトをめぐって一進一退の和戦を繰り返す。社会の混乱は,古王国時代の神殿墳墓の破壊略奪など従来の権威に対する挑戦を引き出し,古王国時代に確立した秩序を至上とする価値観を揺るがして厭世観や来世への不信,王や神に対する非難などさまざまな思想の実験を行わせた(〈思想革命〉)。これらの実験は当時興隆した文学にその痕跡をとどめている。
中王国時代
南北2王朝の対立は,南が北を征服して統一を回復するというエジプト史の基本パターン通り第11王朝メンチュヘテプ2世Mentuhetep IIの国土再統一で終わる。以後テーベは約1000年にわたりエジプトの政治の中心となり,その守護神アメンも王朝神・国家神として神々の王の地位を保つことになる。第11王朝は中央集権国家体制の再建に急であったため,第1中間期に成長した世襲貴族の反発をかってクーデタで倒され,アメンエムハト1世を祖とする第12王朝が成立する。新しい王朝は地方有力貴族の多くを州知事に任命,貢租の一部の自由裁量処分や私兵の保持など支持勢力である世襲貴族の特権を尊重するが,州知事間の衝突や特定の州知事の勢力拡大を防ぐため,州の境界と灌漑水路の用水権を明確に定め,裁判官の任命権を確保,王権の経済的基盤を強化するためファイユームの干拓に着手し,首都をテーベからファイユーム盆地に近いイチ・タウイ(現在のラーフーン)に移すなど将来の中央集権化の実現へ向けて準備する。王に忠実な官僚を養成するため,第1中間期に形成された都市居住の工人層や王に直属する小土地保有民(いわゆる〈庶民〉)の子弟に対し教育を奨励し,文字を習得させた。アメンエムハト1世の方針は,王の暗殺にもかかわらずセンウセルト1世以下の諸王によって受け継がれ,第5代センウセルト3世Senusert IIIの〈行政改革〉の断行により完全な中央集権化に成功する。対外交易も活発で,ビュブロス,クレタ,プント,シナイ半島,ワーディー・ハンマーマートにしばしば通商のための遠征隊が派遣され,王権の経済基盤強化に貢献した。ヌビアに対しては軍事遠征が行われ,植民地化が試みられた。センウセルト3世は治世の前半ヌビアに親征して第2急湍地方までを領土とし,セムナ,ブヘンなどの要塞を築いて南の備えとした。〈行政改革〉によって完成した官僚機構は,古王国に比べて官僚の数がはるかに多く,機構も複雑化し,同一の任務に必ず複数の官僚が関係し,相互にチェックし合い,最終の判断は宰相を通じて王に一元化するしくみになっている。王権の基盤である工人層は,同業組合によって国家の統制を受けた。
第2中間期
第13王朝にはいると王権は再び衰えて王位は次々と交替する。しかし前半は官僚機構が有効に働いたため社会の混乱は少なかった。デルタ東部国境の防備が手薄となったのに乗じてヒクソスと呼ばれる異民族がアジアより侵入,デルタ東部を中心に定着し,傭兵として実力を蓄えたのち,前1650年ころクーデタにより新王朝を開く(第15王朝)。前2千年紀前半の西アジアはインド・ヨーロッパ語系諸民族の移動を契機とする民族大移動期にあたり,小アジアのヒッタイト,ユーフラテス上流のミタンニ,バビロニアのカッシートなどインド・ヨーロッパ語系民族を支配者とする国家が建国された。この余波がシリア・パレスティナを経てエジプトに達したもので,第15王朝を形成したヒクソスの主力民族については北西セム人(アモリ人)説とフルリ人説とが対立している。第15王朝はデルタから南パレスティナを直接支配するとともに上エジプト,ヌビアには宗主権を行使した。ヒクソスの支配はエジプト史の転換点といえる。アジアの一部を包含する国家の出現の結果エジプトはそれまでの交易中心の相対的孤立状態を脱し,政治・経済・文化ともにアジアと緊密な関係をもつにいたる。ヒクソス自体は独自の文化に乏しいが,馬と戦車,複合弓,青銅製の剣,小札鎧(こざねよろい)など各種の軍事技術・兵器をはじめ,新しい文化要素がさかんに流入した。ヒクソスの宗主権下にテーベに成立した第17王朝は,異民族支配からの解放を旗印に職業軍人層の養成,軍事国家体制の整備,国民意識の高揚に努力し,新王国時代の対外進出の道を準備する。
新王国時代--第18王朝
前1542年ころテーベ王朝のアアフメス1世Aahmes Iがヒクソスの王都アバリスを占領,ヒクソスを国外に駆逐し第18王朝を開く。王はヒクソスの最後の根拠地をたたくため南パレスティナに遠征,下ヌビアも回復する。トトメス1世Thotmes Iは当時シリア・パレスティナに進出を図っていたミタンニに対抗して一時的にユーフラテス河畔まで占領する。しかしハトシェプスト女王は平和交易政策に転じ,プントとの香料貿易を再開,国内ではディール・アルバフリーの葬祭殿をはじめ,旺盛な建築活動を行い,芸術の復興を鼓吹する。女王の死後単独の支配者となったトトメス3世はただちにアジア遠征を再開,17回に及ぶ出兵の末,北はユーフラテス河畔から南はナイル第4急湍に達するエジプト史上最大の領土を獲得,一時的な支配権の承認をこえた植民地としての支配体制を確立する。王は有能な将軍であると同時に行政官であり,臣属国の君侯の地位は保障して自治を認める代りに,長子を人質としてテーベの宮廷に集め,エジプト風の教育を施した。アジアの支配地を三つの属州に分割してそれぞれ総督を置き,要所に駐屯軍を常駐させ,臣属国に対する押さえとし,一方ヌビアは総督を置いて直轄支配地とした。王の巧みな支配体制は帝国の繁栄を保障し,当時の大国(ヒッタイト,バビロニア,アッシリア,キプロスなど)はこぞって友好関係を求めて朝貢した。交易圏はエーゲ諸島からアラビアに及び臣属国の貢租や戦利品を含めた膨大な富が王の宝庫に流入,カルナック神殿はじめ豪壮な建築にあてられた。トトメス4世Thotmes IVのミタンニとの同盟とミタンニ王女の後宮入りにより支配体制はいっそう固まり,アメンヘテプ3世(在位,前14世紀前半)の下で頂点に達する。当時のエジプトを軸とするオリエント世界の外交関係の史料が,楔形文字で記された〈アマルナ文書〉である。
しかしこの征服の加護者とされたテーベの守護神アメンもまた大量の富や土地の寄進を受けて経済力を蓄え,アメン神官団の政治や王位継承への介入が始まる。神官団の影響力を排除し,王権の一元支配の貫徹を目ざしたのがイクナートン(アメンヘテプ4世)の〈宗教改革〉である。しかし急激な改革に伴う内政の混乱とヒッタイトの進出によるアジア植民地の喪失は官僚と軍人の信頼を失わせ,改革は一代限りで終わり,ツタンカーメン王による伝統信仰の復興がなされる。アメン神官団の支持で将軍ホルエムハブHoremhabが即位,王権側の試みは挫折して軍人と神官の勝利に終わる。
→アマルナ時代
新王国時代--ラメセス時代
第19王朝の諸王は帝国の再建を試み,セティ1世はパレスティナの再征服に成功,シリアに軍を進めるが北シリアはヒッタイト側にとどまる。ラメセス2世は北シリアの回復を目ざして東デルタに新都ペル・ラメセスを建設,オロンテス河畔のカデシュでヒッタイト軍と決戦するが痛み分けに終わり(前1286ころ),のち前1260年ころヒッタイト王ハットゥシリ3世との間で平和条約を結んで,戦争状態の終結,政治亡命者の引渡し,相互軍事援助,国境の現状維持を確認し合い,ヒッタイト王女を後宮に迎えた。その際ヒッタイト王自身もエジプトを訪問している。両国が防御同盟を結んだのはアッシリアの進出と東地中海北部で新しい民族移動(〈海の民〉の移動)の動きが始まったためである。条約締結により対外情勢は一時的に安定,王の精力は国内での大建築活動に向けられた(カルナック神殿大列柱室,アブ・シンベル神殿など)。メルエンプタハMerenptah王はリビア人と連合して,西デルタに侵入してきた〈海の民〉(シチリア人,サルディニア人,アカイア人,リュキア人,テュルセニア人)を撃退,捕虜を傭兵としてエジプトに定住させた。ヘブライ人の〈出エジプト〉は王の晩年の事件かもしれない。〈海の民〉は第19王朝末期の混乱に乗じてヒッタイト王国を滅ぼし,第20王朝初頭水陸よりパレスティナ・東デルタに迫るが,ラメセス3世はこれを撃破,捕らえたフィリスティア(ペリシテ)人らを南パレスティナ海岸に定住させ国境の備えとした。対外的には危機を脱するが,国内では神殿への富の集中,神官職の世襲化,外人傭兵の増大,官僚の汚職など状況は悪化し,ラメセス3世を継いだ4世から11世までの同名の王の間に王権は急速に衰え,アジア植民地は失われ,経済力も低下した。傭兵と神官のみ勢力を増大,ついにアメン大司祭ヘリホルHerihorが王位を奪取する(前1070ころ)。
末期王朝時代
ヘリホルと同じころデルタのタニスで将軍スメンデスSmendesが即位,第21王朝を開く。以後政治の中心は完全にデルタに移り,テーベはアメンの聖都として宗教の中心地の色彩を強める。前950年ラメセス時代以降傭兵として定住していたリビア人の将軍シェションク(シシャク)Sheshonqがブバスティスに第22王朝を開き,エルサレムを占領するなど一時勢威をふるうが,のちサイスに第23~24王朝が並立,政治・文化ともに水準低下が著しく,第21~24王朝を〈第3中間期〉と呼ぶ学者もいる。前8世紀後半ナイル第4急湍地方のナパタに興ったエチオピア人の王がエジプトを征服(第25王朝),アメン信仰の復興など文化の再建に努めるが,前671年アッシリア王エサルハドンにタハルカTaharqa王が追われ,エジプトはアッシリア帝国の一部となる。しかし将軍プサンメティコス(プサメティコス)1世がイオニア人傭兵の援助でアッシリアから自立(第26王朝),文化の復興のため古王国時代の芸術・言語・文字を模倣した復古主義を推進した。王はイオニア人傭兵をデルタに植民させ,のちアアフメス(アマシス)2世Aahmes IIがメンフィスに都を移したが,ギリシア人商人のため植民市ナウクラティスの建設を許可,ギリシア交易の独占権を与え,経済の復興の一助とした。ネコ(ネカウ)2世は,アッシリア再興のため援軍を送るが,前605年カルケミシュの会戦で新バビロニア王ネブカドネザル2世の軍に大敗し,以後アジアへの野心を放棄する。オリエント世界を統一したアケメネス朝ペルシアのキュロス2世(大王)の子カンビュセス2世は前525年エジプトを征服(第27王朝),第28~30王朝の下で一時的に独立を回復するが,再びペルシア帝国に併合され(第31王朝),前332年アレクサンドロス大王に征服される。相次ぐ異民族支配の下でエジプト文明はますます神殿と神官の手で担われていくことになる。
王朝時代の社会と文化
社会
社会の中心は王,すなわちファラオ(旧約聖書ではパロ,エジプト語ペル・アア〈大きな家〉に由来)である。王は地上において創造神の役割を演じ,創造神が天地創造時に定めた宇宙秩序(エジプト語マアト)を維持し更新することが期待され,この意味で神と見なされた。マアト維持の機能は,人間社会に対する行政機能と,秩序を保証する神々との調和ある関係を保つための祭祀機能とからなり,王はそれぞれを官僚と神官に権限を委任して代行させた。理念上,官職と神官職との区別はなく,いずれに任命されるかはまったく王の意志次第とされた。古王国前半においては,ファラオの職務代行者はファラオの血統の濃い者こそふさわしいとして,要職は王族(とくに王子)に独占されている。後には文字を習得し,有能でさえあれば,家柄に関係なく高位に昇進できるとされた。国家の要職についた官僚(および神官)が〈大人(たいじん)〉(貴族)である。古代エジプトの社会層は〈大人〉と〈小人(しようじん)〉とに大別でき,下級官僚(〈書記〉)から〈大人〉への道は理念上平等である。現実には教育を受けうるのは貴族の子弟に事実上限られ,中王国時代王権が積極的な勧誘を行った場合を除き,農民や工人の子弟が〈大人〉になることは困難であった。
軍役は賦役の一部として課せられたため,軍人層の成立は,大規模な軍事遠征が恒常化する新王国時代以降である。しかしその社会的評価は低く,指揮官には文官優越の原則が堅持され,新王国後半からは外人傭兵が軍隊の主力となっていく。工人層(彫刻師,金細工師,金属細工師,宝石細工師,指物(さしもの)師,大工,左官,石工,陶工,履物作りなど)は,原料のほとんどが国家の統制品であり,独立自営は事実上不可能であったため,もっぱら国営の工房か神殿など公的機関の経営する工房で働いた。新王国時代の王墓造営工人の集落がテーベ西岸のディール・アルマディーナに発見されている。対外交易は国家に独占され,国内の物資流通も国家統制下にあるため,新王国末期にいたるまで商人層は存在しない。一般人民の大部分を占めるのは農民で,貢納と賦役の主要部分を受け持った。貢租は収穫直後,収穫の2~4割を納入,賦役は増水による農閑期に軍隊として組織され,灌漑水路の開削や浚渫(しゆんせつ),開拓,宮殿や墓陵の造営,採鉱・採石・交易のための遠征や軍事遠征に従事した。土地の所有権は王にあり,国有地もしくは神殿・官庁など公的機関の直営領を割り当てられて耕作した。新王国以降になると事実上の所有権をもち,土地を売却する農民も出現する。官職に付随する土地,功労者に下賜された土地など〈大人〉層の場合には早くから事実上の土地所有が見られた。奴隷の数は少なく,家内奴隷が主体で,生産の主要な担い手となることはなく,貢納賦役の忌避者,罪人,外人奴隷,奴隷の子などからなり,新王国では捕虜奴隷が急増する。商業の未発達のため債務奴隷の少ないのがエジプト奴隷制度の特色である。当時の生活の状況は墓壁に描かれた浮彫や絵画から具体的に知ることができる。
宗教
宗教は社会のあらゆる分野を支配している。多神教で,自然現象,天体,動物,石,樹木など人知を超えたあらゆるものに神性を認めて神格化し,部族,村落,都市,州ごとに守護神をもっている。狩猟民の信仰に由来する動物神が多く,歴史時代にはいって神の擬人化が進んでも,完全な人間の姿で表現される神はプタハ,ミン,オシリス,アメンなどごくわずかで,人体に動物の頭をもつ姿で表現される神が多い(山犬頭のアヌビス,隼頭のホルス,雄羊頭のクヌムKhnumなど)。これらの地方神のうちプタハ,ラー,アメンなどは,国家統一後王朝の守護神・国家神として最高神とされたが,州の守護神もまたそれぞれの州で天地の創造者として最高神とされ,王の主宰する公儀宗教に組み込まれて厚く尊崇された。これら諸神の並存する世界に秩序を与えるため,神々を家族に構成し,特殊な職業の守護神と見なし(プタハは工人,クヌムは陶工,トートは書記,アヌビスはミイラ作りなど),宇宙創造神話を軸とする神話の体系化(〈神学〉)を試みた。太陽神アトゥムを創造神とするヘリオポリス神学,4組の原初の男女神(のち月神トート)を創造神とするヘルモポリス神学,市神プタハの言葉による天地創造のメンフィス神学などが知られている。うちヘリオポリス神学がアトゥムに代わってラーを創造神とし,冥界の支配者オシリスとその子ホルスを神々の系譜に加えて優勢となり,創造神は太陽神ラーという観念が定着,新王国の国家神アメン・ラーのように,他の神々もラーとの習合により創造神の地位を正当化した。神殿は神の住居とされ,王侯貴族同様神官が召使いとして仕え,祭祀の基本は神像に対する身の回りの世話と飲食物の奉仕であった。
エジプト人は死後の再生復活を信じ,現世と同じ生活が来世も続くことを願った。古王国時代は王のみが死後オシリスとなって永生を得,臣民は来世も王に仕えて永生にあずかるとされたが,第1中間期の王権の衰退後は,必要な準備さえ整えれば誰でも永生復活が可能とされた。準備とはまず,(1)死者の住居である墓,(2)死後の生活に必要な品々の副葬,(3)飲食物の定期的な供与(供養)の確保であり,生前より心がけておかねばならず,死ぬと,(4)遺骸をミイラにして保存し,(5)魂を呼び戻し復活させるための葬儀を営んだ。生者と同じく死者も食物が不可欠とされたため,供養の準備に力が注がれ,供養用の土地指定,食物の副葬,模型の副葬,供物や供物に関係する場面の模型や壁画を現実化するための呪文の壁面装飾など工夫がこらされ,供物の壁画は来世で実現したい現世の生活の壁画へと主題を広げていく。
文学と学問
宗教文学には死者の永生復活を助ける呪文を集めた古王国の〈ピラミッド・テキスト〉,中王国の〈棺柩(かんきゆう)文(コフィン・テキスト)〉,新王国の〈死者の書〉,新王国王墓の壁に記された《冥界(案内)書》《アテン賛歌》など神々に対する賛歌があり,王に対する賛歌やラメセス2世の《カデシュ戦勝歌》もある。世俗文学ではまず教訓文学が出現,古王国のカゲムニやプタハヘテプ,中王国のドゥアケティ,新王国のアニの教訓や書記への勧めなどが書かれ,官僚としての人生の知恵を教えた。官吏たちの自伝的な墓碑銘もある。第1中間期から中王国にかけては世俗文学の興隆期で《雄弁な農夫の物語》《イプエルの訓戒》《ネフェルティの予言》《シヌヘの物語》《難破した水夫の物語》《生活に疲れた者の魂との対話》などに混乱に対する政治責任の追及,厭世観,新しい秩序の賛美などのさまざまな思想上の実験が反映されている。新王国の《二人兄弟の物語》《ウェンアメン航海記》は当時の開放的な空気を反映して,心情を率直に表現している。当時の日常生活を反映する恋歌や,牧人・農夫・漁師の歌もパピルスや墓壁の場面に記されて残っている。
学問は実用的な目的に奉仕するものとして発達した。灌漑農業に必要な増水・減水や播種・収穫の時期,ピラミッドの地取り,宗教祭儀の正しい日時の決定などのため天体観測がなされて天文学や暦学が生まれ,減水後の耕地の再測量,灌漑工事やピラミッド・神殿建築など土木工事のための数学(特に幾何学),ミイラ製作の必要から解剖や症状診断,薬理の知識を得て医学や薬学が発達した。ただし治療には投薬とともに呪術的処置も併用されている。これらの科学的知識はパピルスに記されて神殿の文庫に保管された。算術や幾何学の例題と解答を集めた〈リンド・パピルス〉,病気の症状と治療法を集成した〈エーベルス・パピルス〉,外科手術の診断と治療法の〈エドウィン・スミス・パピルス〉などがある。〈実学〉として発達したため知識の集積にとどまり,事実をつなぐ法則の発見にはいたっていない。
グレコ・ロマン時代
プトレマイオス朝
前323年のアレクサンドロス大王の病没後,部将の一人プトレマイオス1世はエジプト太守として赴任,部将間の後継者争いの末に前305年エジプト王位を宣言する。王はファラオの完全な後継者としてその宮廷儀礼を踏襲,支配民族であるギリシア人固有のポリスは,第26王朝以来のナウクラティス,アレクサンドロス大王の建設したアレクサンドリアにプトレマイスを加えたにとどめ,前代よりの行政機構をそのまま受け継ぎ,要職にギリシア人(およびマケドニア人)をあて,ギリシア的合理性をもって運用した。国土王有の原則はいっそう徹底し,神殿領,兵役義務の代償に軍人に与えられる軍事賦田地,高位高官に贈られる恩賜地のような下賜地といえども貢納の義務を負い,一方,王領の農民は借地人として登録され,作物の種類や播種量,播種・収穫の時期まで統制を受け,貢納賦役の義務は重く,小麦の収穫の1/3を納入した。経済活動にも国家統制の網がめぐらされ,油,塩,パピルス,織物,ビール,皮革などの生産・販売,天然炭酸ソーダ(ナトロン)坑,鉱山,採石場での採掘,狩猟,漁労,牧畜,銀行業務など直接間接に国家の独占事業とされ,毎年生産規定を発布,価格を公定し,高い関税を輸入品に課して国内での高価格を維持した。南シリア沿岸地方の領有により,南アラビア経由のインド商品(象牙,染料,黒檀(こくたん),木綿,絹など)およびアラビア商品(真珠,香料,珊瑚(さんご)など)の仲継貿易は国庫に大きな利潤をもたらし,首都アレクサンドリアは国際都市として栄え,豪奢な宮廷生活を支えた。こうしてプトレマイオス1世から同3世までの間に,中央集権的官僚機構,統制経済および東西交易による利潤の獲得と国力の充実により,プトレマイオス王朝はヘレニズム世界最強の国家に成長し,その領土は北はフェニキア沿岸,キプロス島,小アジア沿岸,キクラデス諸島からトラキア,黒海沿岸に及び,西はキレナイカに達した。土着エジプト人の支持を確保するために旧来の神々の信仰を認め,ファラオとして祭祀を主宰,神殿を建立したが,ギリシア人とエジプト人との融合を宗教上で積極的に推進するため,メンフィスで崇拝された聖牛ハピHapiの姿をもったオシリス神にギリシアの神ハデス(プルトン)の属性を加えた新しい予言と治癒の神セラピスを創設して国家神とし,オシリスの妻イシスとその子ハルポクラテスHarpokratēs(ホルスの一形態)と共に三柱神とした。君主崇拝も採用され,プトレマイオス2世以降王は生前より神として国家祭儀を受け,死後は救済神として祀られた。2世はまた実姉アルシノエ2世を王妃とし,エジプト王家に伝統的な姉弟(兄妹)婚を導入した。
しかしシリアのセレウコス朝にアンティオコス3世が即位すると,東西交易の拠点フェニキア沿岸の占拠を狙って進軍,プトレマイオス4世はエジプト人を初めて徴兵してこれを撃退する(前217,ラフィアの戦)が,5世の在位中(前204-前180)にキプロス以外の全海外領土を喪失,ローマに援助を求めたため以後ローマの東方干渉が始まる。ラフィアの戦の勝利によるエジプト人の民族的自覚と海外領土喪失による農民への重税は,農地放棄や農民一揆を頻発させ,神官階級の特権を増大させ,国家財政はいっそう窮迫した。王位継承をめぐる王室内の対立はローマの干渉をいっそう露骨にし,ローマの将軍アントニウスと結んだクレオパトラ(7世)は,オクタウィアヌス(後のアウグストゥス)に敗れて(アクティウムの海戦),エジプトはローマの属州となる。
→プトレマイオス王国
ローマのエジプト支配
オクタウィアヌスはエジプトの戦略的・財政的重要性を認識し,騎士階級出身者を総督に任命する皇帝直属の属州としたのみならず,ファラオの後継者としてプトレマイオス王朝の統治原理を継承し,皇帝の金庫,ローマ市民の穀倉として最大限に利用し尽くすこととした。ローマ人が官僚・軍人として渡来し,ギリシア人,マケドニア人は第2位に転落,エジプト人の被征服者としての地位はいっそう固定した。既にプトレマイオス朝後半より土地私有の傾向が増大していたが,皇帝はこれを承認,その代償として土地私有者を強制的に国家官僚に任命した。村や町は自治体としての機能を認められ,評議会が組織されたが,徴税義務が課せられ,義務の増大以外の何ものでもなかった。ローマ帝国の窮乏化とともにエジプトに対する財政的負担はますます増大,国有地農民の逃亡が相次ぎ,荒廃した国有地は私有地に強制的に割り当てられ,大土地所有を促進した。この傾向は東・西ローマ帝国分裂(395)後も変わらず,穀物納付先が東ローマ(ビザンティン)帝国の首都コンスタンティノープルに代わっただけで,大土地所有はさらに進行,地方の大領主は独自の徴税機構をもち,自己の船と船員を用いてアレクサンドリアまで運んだ。重税にあえぐ農民は後年イスラム軍を解放者として歓迎することになる。
五賢帝時代までのローマ皇帝はファラオと同じく伝統的な神々の神殿を建立,祭祀を主宰する姿を壁面に刻ませ,カルトゥーシュ(王名枠)にヒエログリフで名前を記した。ラテン語はギリシア語とともに公用語とされたが,ローマ文化は浸透せず,アレクサンドリアを中心にギリシア文化とエジプト文化の混交が進み,エジプト固有の文化は神殿と神官の手に集中していく。1世紀よりキリスト教が普及し,2世紀にはアレクサンドリアに司教が置かれ,問答教示法による教校も開設され,エジプトは新興キリスト教の一大中心地として大迫害をくぐりぬけ,教義をめぐる論争では中心的役割を演じた。4世紀には修道院運動もアントニウスにより始められた。4世紀末テオドシウス帝によるキリスト教国教化はエジプトから古来の神々を根絶し,エジプト人の国民的自覚はコプト教会に受け継がれていった。
執筆者:屋形 禎亮
イスラム時代
ビザンティン帝国をヤルムークの戦(636)に破り,シリアを征服したアラブ・イスラム軍は,次いでアムル・ブン・アルアースの指揮の下にエジプトへ侵攻し,641年にはビザンティン帝国のバビロン城を陥れて,翌年ここにフスタートFusṭāṭの町を建設した。この事件は,エジプト史ではファトフ(開くこと,征服)とよばれ,以後,エジプトのイスラム化,アラブ化が始まる。フスタートは,クーファやバスラとならぶ軍営都市(ミスル)の一つであったが,すでにコーランにモーセとヨセフの伝説の土地として描かれたエジプト全体もまたミスルMiṣrと呼ばれており,こののちエジプトとその首都を共にミスルと呼ぶことが一般化した。征服時エジプト住民の大多数を占めていた単性論派のコプト教徒は,ギリシア正教会のビザンティン帝国よりむしろムスリムの支配を歓迎し,ジンミー(被護民)として徴税をはじめとする帝国行政の諸分野に活躍した。アラブ化政策(705)によって公文書がコプト語からアラビア語に改められてからも,彼らは行政に重要な役割を演じて官僚の名家を次々に輩出したが,イスラムへの改宗もしだいに進み,14世紀ころまでにはコプト教徒の数は全人口の10分の1程度に減少していたという。
アラブによって〈牝牛の乳〉とたたえられたエジプトの富は,ウマイヤ朝(661-750)やアッバース朝(750-1258)政府の重要な財源であったが,バグダードから自立してトゥールーン朝(868-905)を興したイブン・トゥールーンは,豊かな租税収入を用いて各地に土木工事を起こすとともに,ローダ島にナイロメーターを建設して〈エジプトのための統治〉の実績をあげた。トゥールーン朝の滅亡後,エジプトは一時アッバース朝の支配に服したものの,30年後には再びイフシード朝(935-969)の下に自立した。この王朝はエジプト・シリアに加えてメッカ・メディナをも領有し,以後オスマン帝国の征服にいたるまでエジプトの諸王朝による両聖都の支配が続くことになる。
北アフリカに建国したファーティマ朝(909-1171)は,969年,エジプトを征服してフスタートの北に新都カイロを造営した。紅海経由の東西貿易を独占した政府は,その富を用いてトルコ人マムルークと黒人奴隷兵からなる強大な軍団を編成し,また多くの宣伝者(ダーリー)を各地に派遣して活発な宣教活動を続けたが,1065年に始まる〈7年の飢饉〉はエジプトを繁栄から衰退の極へと陥れた。この危機に登場したのが軍人出身の宰相バドル・アルジャマーリーBadr al-Jamālī(?-1094)で,彼はアルメニア軍団の武力を背景に諸改革を実行し,エジプトに秩序の回復と経済的な復興をもたらした。このシーア派王朝の下でコプト教徒とユダヤ教徒の待遇は改善され,特に前半期にはユダヤ教徒のイブン・キッリスIbn Killis(930-991)をはじめとしてジンミーで宰相(ワジール)の職を得た者は,ユダヤ教徒出身者が2名,コプト教徒出身者が5名に達した。カイロで発見されたゲニザ文書によれば,この時代の商業活動はムスリムとコプト教徒やユダヤ教徒との協業によって行われ,各街区(ハーラ)でもこれらの信徒は混住しているのが一般的であった。街区ごとに宗派別の住み分けが行われるようになるのは,キリスト教徒十字軍のエジプト侵攻とスンナ派復活の影響が現れる12世紀半ば以降のことである。
ファーティマ朝の宰相となって実権を掌握したサラーフ・アッディーン(サラディン)はアイユーブ朝(1169-1250)を創始し,国家の宗旨をシーア派からスンナ派に変更するとともに,それまでセルジューク朝やザンギー朝で実施されていたイクター制をエジプトに導入し,これを軍隊編制と農村支配のための基本制度に定めた。ナイル川流域のエジプトは政府による統治が容易であったから,水利機構の管理・維持は比較的よく行われ,その結果,農業生産は安定し,商品作物であるサトウキビも下エジプトから上エジプトへとしだいに拡大していった。しかし対十字軍戦争の遂行には莫大な戦費が必要であり,政府はその財源を得るためにアデンを攻略して,東西貿易の利益の独占を図ったのである。第7代スルタン,サーリフ(在位1240-49)は強力なマムルーク軍団を編制して君主権の強化を図ったが,やがてこれらのマムルークはクーデタを起こしてマムルーク朝(1250-1517)を樹立した。アイン・ジャールートの戦(1260)でモンゴル軍のエジプト侵入を阻止した第5代スルタン,バイバルス(在位1260-77)は,シリアに残存する十字軍勢力と戦う一方,アッバース家のカリフをカイロに擁立(1261)して,イスラム世界におけるマムルーク朝の威信を高めた。アミールやマムルーク騎士にはアイユーブ朝時代と同様にイクターが与えられ,その支配の下で稲やサトウキビの栽培はさらに発展し,カーリミー商人や奴隷商人が,インド洋・地中海貿易で活躍する基礎が固められていった。カイロは東方のバグダードに代わってイスラム文化の中心地となり,オスマン帝国時代の一時期を除いて,現代にまで続くイスラム世界内部でのカイロの優位が確立した。これに伴ってイスラム史におけるエジプトの独自な地位を評価しようとする動きが強まり,ファラオの時代をも視野に入れたエジプト年代記が執筆されるようになった。また,キンディーKindī(897-961)に始まるエジプトの美点(ファダーイル)と地誌(ヒタト)の記述は,マクリージーにより〈エジプト誌〉として集大成された。エジプトに古くから伝わるグノーシス思想はズー・アンヌーンによってイスラム神秘主義の体系化に援用されたが,この時代になるとイスラム神秘主義はさらに土着的な展開を遂げ,タンターのアフマディー教団は聖者アフマド・アルバダウィーの生誕祭をコプト暦によって祝ったという。
1517年,カイロに入城したオスマン帝国のセリム1世は,14世紀半ば以降,ペストの流行とマムルーク軍閥の抗争によって弱体化していたマムルーク朝の支配に終止符を打った。エジプトはオスマン帝国の一属州とされ,その統治はオスマン軍の行動を積極的に支援したマムルーク出身のアミール,ハーイル・ベイKhā'ir Bay(?-1522)にゆだねられた。征服後,マムルーク朝時代のイクターは一度国家に没収され,検地の後,改めてオスマン朝の財務官であるエミーンemīnに分与された。この土地をムカーターmuqāṭa‘といい,ムカーター内の土地で徴税の実務を担当したのは旧来通りのマムルークたちであった。これらのマムルークは,17世紀以降,オスマン帝国の支配がゆるむにつれて勢力を伸長し,やがて徴税請負人(ムルタジム)として独立の権限を振るうようになってゆく。オスマン帝国とマムルーク軍人の二重支配を受けて多くの農民が逃散の手段に訴えたから,農村の疲弊はさらに進行した。またイスラム文化の中心がイスタンブールへ移ったことにより,カイロをはじめとする諸都市では見るべき著作活動は行われなくなった。商工業者や農民は種々の神秘主義教団(タリーカ)に組織されていたが,これらの教団にも新しい宗教運動を起こすだけのエネルギーはもはや残されていなかったのである。
執筆者:佐藤 次高
近代
18世紀のエジプトは,オスマン帝国の支配のもとに実質的にはマムルークの将領たちが実権を握って党争を続けており,他方国際商業と結びついた農工業の商品生産が展開しつつあったが,1798-1801年のナポレオン軍の侵略・占領は,オスマン帝国とマムルーク軍を粉砕してこの構造の変容の道を開いた。フランス軍撤退後の混乱期には,カイロのウラマーや商人の一部が大衆を武装させて一種のコミューンを形づくり,1805年には,これに接近してきたオスマン帝国軍のアルバニア人傭兵隊長ムハンマド・アリーを総督(ワーリー)に擁立して,帝国政府にこれを認めさせた(ムハンマド・アリー朝の成立)。
ムハンマド・アリー(在位1805-48)は,権力を握ると,カイロの市民勢力を分裂させてこれを武装解除し,他方残存するマムルーク勢力を虐殺して,国の再編成に乗り出した。一方では農民の徴兵による洋式の新軍をつくり,オスマン帝国のもとめに応じて1811-18年アラビア半島のワッハーブ派王国を征服,25年ギリシアに出兵して独立軍を撃破した。他方,全土の国有を宣言して灌漑工事によって農地を開発,商品作物の作付強制と専売制,貿易独占を行い,機械制の軽工業を興し,軍人官吏養成の洋式学校を創設してフランス,イタリアに留学生を送った。これらの施策でエジプトにおける支配権を固めたムハンマド・アリーは自己の帝国を築く野心をもち,1820年にはスーダンを征服,やがてオスマン帝国と対立,31-33年,39-40年の2次にわたってシリアに遠征,イスタンブールに迫った。強力な中東国家の成立を恐れたイギリスは,列強を誘って軍事干渉でこれをはばみ,40年のロンドン4国条約でムハンマド・アリー一族の地位世襲を認める代りに,その支配権をエジプトに限ることとした(以後ムハンマド・アリー朝は,その称号をクーリー,ヘディーウ,スルタン,マリクと変えながらも1953年まで存続する)。
この条約によって,治外法権,関税自主権の欠如を含む1838年のイギリス・オスマン通商条約がエジプトにも適用されて,エジプトは産業革命を経た英仏を中心とする世界市場に従属的に組み込まれてゆくこととなり,貿易独占体制ひいては自立的な工業機械化の道はついえた。その後エジプトは,60年代に,アメリカの南北戦争を契機として綿作と綿花貿易を飛躍的に拡大させ,良質の綿花の単作供給市場として特化してゆくこととなる。こうした経済的社会的変化に対応して,土地法・商法その他の法制の洋式化も進行したが,思想の面ではタフターウィーやアリー・ムバーラクのように自立的な近代化を志向する人びとも現れた。
第3代のサイード・パシャ(在位1854-63)が認可してイスマーイール・パシャ(在位1863-79)のもとにフランス人レセップスが69年に開いたスエズ運河は,エジプトの戦略的地位の重要性を飛躍的に高め,かえって災いを招くことになった。イスマーイール・パシャの外債依存の欧化政策は,76年国家を破産させ,イギリス,フランス,ドイツ,オーストリアの財政管理が始まったが,これに対してアラービー運動とよばれる民族革命が起こった。発端は81年の青年将校の反乱であったが,アフマド・アラービー大佐を指導者とするワタン(祖国)党勢力は,立憲制の確立,議会の開設による外国支配の排除,総督の権限の制限を求め,ヨーロッパ支配に反発する名望家層やギリシア人高利貸に苦しむ農民大衆も立ち上がって,82年アフマド・アラービーを陸軍大臣とするワタン党政府が成立した。英仏をはじめとする列強は,この運動の民族革命的性格を危険視し介入を繰り返したが,インドに至るスエズ・ルートの確保を欲するイギリスは単独でこれに軍事干渉を行い,ついにはエジプト全土を占領,民族革命を挫折させた。以後エジプトはイギリスの軍事支配下に入ることになる。
1914年にいたるイギリス占領下に,エジプトは経済的には繁栄した。1898年のアスワン・ダム建設に代表される大規模な灌漑事業,旧ヘディーウ領地の払下げなどによって広大な農地が開発され,綿花やサトウキビを栽培する豪農大地主が成長した。ムハンマド・アブドゥフらのイスラムの内部改革運動はこうした社会変化を背景としたものである。他方,社会資本が充実した都市には,洋式教育を受けた知的中間層が成長して,ムスタファー・カーミルを代表とする民族主義運動が展開した。1906年のイギリス軍人とエジプト農民の間のトラブルに発したデンシワーイ事件には,大きな民族的高揚が興ったが,占領当局はこれを抑え,14年第1次世界大戦が始まると,イギリスはエジプトの保護国化を宣言した。
大戦中エジプト全土の労働力と資源の大規模な強制徴発が行われて中東の戦線に投入されたが,それはかえって19年の革命を爆発させる条件をつくりだした。サード・ザグルールを指導者として完全独立をめざすこの革命には,ムスリムもコプトも,都市も農村も,男も女もこぞって立ち上がり,デモ,スト,ボイコットなど多様な闘争を行った。22年イギリスは,ムハンマド・アリー朝のヘディーウ,フアード1世(在位1917-36)を王(マリク)と認めて形式的独立を与えたが,軍隊の駐留は続けスエズ運河とスーダンの諸特権を維持した。以後イギリス勢力と宮廷とサード・ザグルールを指導者とするワフド党の三つどもえの権力構造が,エジプト政治を支配することになる。経済面ではミスル銀行を中心とするコンツェルンのような民族資本も成長し,都市化現象が進み,ターハー・フサインらの自由主義的知識人が活躍し,労働,農民,社会主義,女性解放の諸運動が展開する。また,パレスティナ問題を媒介としてアラブの意識が初めてエジプト人の心をとらえはじめた時期でもあった。
都市化の進展は大衆の伝統的な生活秩序を崩壊させていったが,それは1930年代の世界恐慌による生活苦とあいまって,人びとに伝統的価値の崩壊の危機感をかもし,イスラムやアラブの覚醒をシンボルとする民族革命運動を激化させた。1929年から第2次世界大戦中にかけて100万以上もの人びとを組織したムスリム同胞団や,39年にナーセルら青年将校の結成した自由将校団は,大戦後に大きな役割を演じることとなる。大衆運動の高揚を背景に,1936年ワフド党のナッハース・パシャ内閣はイギリスとの同盟条約によってエジプトの地位を改善したが,スエズ運河地帯の駐兵は続き,スーダンの地位も変わらなかった。第2次世界大戦が始まるとイギリスは武力の威嚇でエジプトを連合国側に参戦させ,それは結果的に第1次世界大戦のとき以上の重い負担をエジプト人に強いた。大戦後大衆的な民族革命運動はいよいよ激化したが,48-49年のパレスティナ戦争におけるエジプトの敗北は,決定的にその後の革命への道を開いたといえる。そして,52年7月,自由将校団はクーデタを起こし,同26日ファールーク国王を追放し,53年6月共和国の成立を宣言した(エジプト革命)。これによってオスマン帝国以来の異民族支配を断ち切り,アラービー運動の掲げた〈エジプト人のエジプト〉というスローガンがようやく達成されることになった。
執筆者:三木 亘
エジプト・アラブ共和国
基本情報
正式名称=エジプト・アラブ共和国Jumhūrīya Misr al-`Arabīya/Arab Republic of Egypt
面積=100万2000km2
人口(2010)=7873万人
首都=カイロCairo(日本との時差=-7時間)
主要言語=アラビア語
通貨=エジプト・ポンドEgyptian Pound
自然,風土
アフリカ大陸の北東端を占める共和国。北は地中海,西はリビア,南はスーダン,東は紅海に面し,1982年には,イスラエルとの平和条約に基づき1967年の第3次中東戦争以来占領されていたシナイ半島が返還された。
国土は,ナイル河谷とナイル・デルタ,ガルビーヤGharbīya砂漠(総面積の67%),シャルキーヤSharqīya砂漠(同21%),シナイ半島(同6%)の四つに区分される。総面積は日本の2.7倍であるが,その97%は砂漠で占められる。居住面積は,全土の5.5%(約5万5000km2)にすぎず,それも,地中海沿岸,ナイル・デルタとナイル河谷に集中し,居住面積当りの人口密度は760人/km2(1980)を超える。とくに首都カイロには,680万人(1992)と全人口の10%以上が集まる。
気候は,地中海性気候の北部沿岸部を除き,大部分は砂漠気候に属する。雨は冬季に,ナイル・デルタ,中エジプト,シナイ半島や紅海沿岸の高地に少量降るが,ナイル川に沿って内陸に向かうほど,平均雨量は減少する。気温は,夏は内陸に向かうほど高く,ナイル川上流の上エジプトでは40℃を超すこともある。冬は逆に海岸部の方が内陸部より温暖である。
住民の大多数は,アラブ系エジプト人で,ハム語系の民族であった古代エジプト人と,アラブをはじめスーダン,ヌビアなどとの混血によって歴史的に形成された。アラビア語を公用語とするが,日常会話では,標準語のj音をg音で発音するなど,標準アラビア語とはかなり異なる発音がみられるエジプト方言が広く用いられる。住民の約90%はスンナ派イスラム教徒で,このほかコプト教徒が1割程度を占めるといわれる。
エジプトの風土は,先に述べた自然条件に大きくかかわり,何千年にも及ぶ自然と人間の歴史を反映している。エジプトとは,ひとことでいえばビクトリア湖とエチオピア高原の降雨を二大水源とする,白・青両ナイルの合流が砂漠のただ中に流れ込み,生命を与えられている国である。ゆえにエジプトは常にナイル河谷に目を注ぎ,そのグリーン・ゾーンは地中海を天にして屹立する〈一本(ひともと)の草木だ〉とか〈ナツメヤシの樹〉にたとえられる一方,砂漠は不毛の地として視野からはずされた。エジプトは〈広さ〉ではなく〈長さ〉だといわれるが,この言葉もまたこの国の本質をつかんでいる。ナイル川は国土を南北に貫き,道路も鉄道も幹線はナイル川に沿って走り,物資も労働人口としての人間も南北に移動し,東西の動きは微々たるものである。ナイル川が地中海を目指して北に流れるのに対し,ほとんど年間を通じて北から南へ吹きこむ風があり,この北風が,古来特に動力機のない時代に,ナイル川による南北の往復を可能にし,文明を担う影の力ともなってきた点は見のがせない。
ナイル川は砂漠に囲まれた国土に農耕を可能にしたが,それはいっさいを天水によらず年1回全エジプトを蘇生させる氾濫という自然のドラマに依拠するものであった。往時ナイル川は氾濫時に奔馬のごとくエジプトを縦に駈け抜け,その後に来る渇水時には,人びとはナイル川の水の一滴ずつを赤児をあやすようにいつくしんだという。ここでエジプトの灌漑農業に注目してみる。太古においてエジプトは病原菌の蔓延する手のつけられない大湿原だったが,ナイル河谷の住人は,果敢に働きかけ豊饒の地とした。まさに〈ナイルにその本来の役割を果たさせたのは,ほかならぬナイル河谷の住人だった〉(現代エジプトの地理学者ガマール・ヒムダーンの言葉)。だが1条の水脈に一国の生命が全的にゆだねられているという事実は,さまざまな事態を潜在させていた。まず,上(かみ)と下(しも)の農耕民同士の間で,特に渇水期に水争いが生じ,血が流されるため裁定者の存在が不可欠であった。また自然の猛威をほしいままにするナイル川を御して生産に結びつけるためには,治水という一大事業が必要であった。堤の築造,用水堀の開削,貯水工事から成る治水事業には大規模な労働人口を動員しうる権力者を不可欠とした。つまりエジプトの生態系は,ナイル川,農民,支配者(裁定者)の3者によって構成されるべき必然性をもっていたといえる。
そこでナイル川と農民との関係をまず見ると,そこには文字通り生命の存続を約束してくれる水と肥沃な沖積土(タミー)とをもたらしてくれる風土への限りない謝恩の念が培われていた。
〈エジプト人は砂漠の中にあって,常に反砂漠的であった〉(ガマール・ヒムダーン)と言われるように,彼らは砂漠には背を向けたが,背で感得している砂漠の不毛に対する意識は,ナイル川の恩寵への謝恩の念を日々鮮烈にしたであろう。この抑え難いまでの謝恩の念は,毎年訪れる洪水という自然のドラマを目撃することによって,人間の力を超えたものの存在へと,いよいよ強く結びついていった。このようにして汎宗教的な精神風土が生まれ,キリスト教やイスラムのように後に外から来た宗教を受け入れる地盤が用意されるにいたった。この汎宗教的な精神風土の存在は,エジプト人の精神傾向の一つと目される,不可視なものへの信仰ghaybūbīyaとか宿命論的傾向,さらには,不可視なものを見る力を付与されている聖者への崇拝に基づく土着宗教への志向を考えるうえで見落とすことができない。
他方農民と支配者との関係はどうであったか。風土が求めた公正な水の配分と治水とをつかさどる者は,現実には歴史が証言するように,抑圧者となって出現し,農民を収奪してやまなかった。エジプトの地勢も支配者が抑圧を強化させるのを助けた。まず周囲が砂漠であり,農民は死と同義の砂漠に逃れるよりは,生の可能性の残されたナイル川の岸辺にしがみついたため,抑圧者の射程内に置かれた。また国土が平たんであることも支配を徹底させるに好都合であった。また一国の生命線が1条の河筋によっているため,水脈を握ることによって支配を徹底しえた。〈おれ(支配者)に土地と労役をよこせ。おれは水をやるから〉ということわざはこのことを表現している。
農民にとって支配者は忌まわしい必要悪でしかなかった。かくしてナイル河谷につなぎとめられ,そこにとどまるほかに道のない農民は,支配者に対し,〈どうにか耐えられる範囲での休戦〉という処世訓により,事を構えずひたすら耐えたが,それは〈屈従による延命〉といわれるものでもあった。屈辱に甘んじ,卑屈になり,今日が昨日と同じであればそれでよしとする生き方は,無気力な保守性を培っていった。このような身の処し方は,長い間に病んだ精神傾向を育て,ついにはエジプト社会をもむしばむものとなり,不幸にもエジプト民衆相互の関係を損なうまでになった。このようにして生まれた性向は,エジプト人自らがエジプト的性格として,論議や著作の対象として取り上げるものとなっており,古くは,15世紀の歴史家マクリージーが,小心,臆病,讒言癖,権力への走狗などとその性向を指摘している。これらの病んだ性向は,エジプト社会に深く巣くっており,さまざまな社会現象の影にひそむものとなっているのである。
執筆者:奴田原 睦明
政治
1952年の共和政革命(エジプト革命)によって,エジプトは植民地を脱し,独立を達成することができた反面,エジプト国民はその後長期にわたって,軍部主導的な体制を押し付けられることになった。エジプト社会には人口の50~60%を占める下層大衆と,中産階級以上の人びととの間に容易に越えがたい厚い壁があり,社会の〈底辺〉からの経済的近代化と政治参加の実現を阻んでいる。革命政権もまたその厚い壁を突き破ることはできず,〈中産階級革命〉の域内にとどまっている。このような意味で,エジプト政治の展開過程は発展途上国の典型的事例を成している。
ナーセル時代(1954-70),サーダート時代(1970-81)を通して革命政権が採り続けた国内政治の体制は,〈単一政党制〉である。自由将校団のメンバーを中核とし,少数の影響力のある軍将校とテクノクラートがそれに加わって指導部が形成され,ここに排他的に政策決定権が集中する。1962-64年のアラブ社会主義連合(ASU)最高執行委員会の構成は,委員18名中自由将校団出身9名,その他の軍将校出身3名,民間人6名(うち博士号所有者5名)であった。そしてASUの下部組織は,指導部の決定を中央から地方大衆レベルにまで浸透させる役割を担った。ただしその動員力は当時のソ連,中国のような社会主義国と比べれば,はるかに及ばなかった。
このような動員体制下では当然大統領の権限は強大なものとなり,複数政党間の選挙を介した政権獲得競争は認められない。国民議会はASUの党員だけで構成され,ムスリム同胞団などのイスラム主義的運動,旧ワフド党,共産党などの政治参加は阻まれた。さらに警察を使った恐怖政治によって,反政府勢力は地下活動を余儀なくされたのである。こうした閉塞状況に対する旧政体分子,労働者,学生らの不満は,67年の第3次中東戦争大敗北の後,民主化要求として一挙に噴き出し,これに対しナーセルは68年,〈3月30日宣言〉によって一部自由化の方針を打ち出した。にもかかわらず政策決定が密室的に,指導部内の利害関係,権力闘争によってなされる過程に変りはなく,このことは73年戦争前後からサーダート政権が推し進めた政治・経済両面の〈自由化〉政策についても当てはまることである。
76年以降ASUの役割は大幅に縮小され,代わって限定的〈複数政党制〉が制度化された。これは民主化のレベル・アップにより民衆の経済的不満を牽制し,反政府勢力を体制内に取り込もうとする措置である。78年には国民議会で圧倒的多数を占める国民民主党(NDP)を成立させて,ASUに代わるサーダート政権の支持母体を築いた。ただしサーダート時代に入り恐怖政治的要素が少なくなった点には注目すべきである。
このように政治体制に連続性が見られる一方,焦眉の急である経済発展のモデルは,ナーセル期のソ連型社会主義からサーダート期の欧米型自由主義の方向へと大きく転換した。
次に対外関係の構造についてみると,革命前の長い異民族による支配の経験は,エジプト人に〈大国依存〉の行動様式を植え付けたといえよう。1954年イギリス軍撤退協定が成立すると,この特性は55年以降,軍事経済援助を介した東側陣営,特にソ連への接近となって表れた。54-69年に東側諸国が約束した長期経済援助総額は17億3400万米ドル相当に上り,そのうち40%がアスワン・ハイ・ダム建設などの開発プロジェクトに関して履行された。ソ連の軍事援助は経済援助を5倍も上回る規模で行われ,特に1967年戦争敗北以降の軍再建に向けられた。
他方1955年バンドン会議出席後,ナーセルは,非同盟・積極的中立を唱えて新興独立諸国をリードし,また56年スエズ運河国有化,スエズ戦争(第2次中東戦争)を経て,58年シリアとの国家統合を行って〈アラブ連合共和国〉を樹立し,パン・アラブ主義外交を積極的に展開した(アラブ民族主義)。さらに61年シリアとの合邦が崩壊すると,イエメン内戦に軍事介入した。アラブ諸国間の政策調整は,64年第1回アラブ首脳会議開催以後,ナーセルの指導下で試行錯誤が続けられた。しかしこうした第三世界,アラブ地域レベルでの主導権追求は反欧米的立場に立つという点で,ソ連の中東戦略の許容範囲にあったと考えられる。
70年代に入ると,サーダート政権の下で従来の対ソ依存からアメリカを中心とする西側陣営へ乗り換える対外政策の大きな転換が起こった。これは指導部内におけるアリー・サブリーら親ソ派の失脚とサイイド・マレイら親米派の台頭によってもたらされたものである。その兆しは72年ソ連軍事顧問団追放に表れ,73年第4次中東戦争後の対米国交回復,アメリカ主導型シナイ撤兵交渉参加によって定着した。それと並行して第三世界,アラブ地域レベルへの関与はしだいに弱まってゆき,75年第2次シナイ撤兵協定成立に対するシリア,ヨルダン,イラク,PLOの反対に,早くもアラブ諸国間の亀裂が見え始めた。77年サーダートのイスラエル訪問,78年キャンプ・デービッド合意成立,79年二国間平和条約成立と進んだ対イスラエル単独和平の実現は,西側諸国にとって,アラブの大国が中東の安定勢力になることを意味した。しかしアラブ陣営は一斉に国交断絶の挙に出て,エジプトを孤立化させた。
サーダートは,81年10月にイスラム過激派に暗殺されるが,同政権末期の国内反政府運動の高まりは,下層中産階級を中心とする経済的不満と指導部の腐敗に対する怒りが,恐怖政治緩和によって増幅された結果もたらされたものである。ムバーラクMubārak政権は1982年4月シナイ完全返還後,イスラエルとの和平を維持しつつサーダート外交の修正を進めた。アラブ・レベルでは中東和平やイラン・イラク戦争調停を通してリビア,シリアを除くアラブ穏健派連合を念頭に置いた外交イニシアチブを発揮し,89年5月カサブランカでのアラブ首脳会議でアラブ連盟への正式復帰を果たした。
域外大国との関係を見ると,1981年サーダートはソ連大使を国外追放したが,84年にムバーラク政権は対ソ外交関係を正常化した。アメリカとの同盟関係は引き続き緊密に維持され,米主導の中東和平の仲介などを行ってアメリカの中東政策遂行に助力した。その見返りとしてエジプト政府は軍事援助に加え,米政府開発援助(1987-90年)において最多のイスラエル(12.3%)に次ぐ援助(10.1%)を受け取った。これはエジプトが同時期受け取ったODAの68%にのぼった。
内政においてムバーラク政権は1984年と87年の国民議会選挙を比較的自由に実施した結果,ムスリム同胞団,新ワフド党などの野党勢力の伸長が見られた(1987年総選挙では458全議席中95議席)。しかし1989年の諮問議会,翌90年の国民議会の両選挙では主要野党が選挙の実施方法をめぐり政府と対立,選挙をボイコットする事態に発展し,選挙結果は1984年以前のNDP独占へ逆戻りした。
執筆者:富田 広士
経済,産業
1952年革命以降のエジプト経済は政策基調からみて三つの期間に分けてとらえることができる。第1期は1952-60年にかけての〈経済のエジプト化〉が推進された期間である。その前半は主として経済の外国支配および外国資本からの離脱をめざし,後半はナーセル政権下で56年のスエズ運河国有化,57年の英仏系の銀行・企業約50社の国有化などのエジプト化が行われた。第2期は1961-70年の〈経済の社会主義化〉の時期で,特に前半ですべての銀行・保険会社の国有化,主要企業(資本金1万エジプト・ポンド以上)の国有化と労働者の経営参加,企業利潤の25%労働者還元,個人所得制限(5000エジプト・ポンド以下に)など厳しい社会主義化政策が実施された。しかし後半は67年の第3次中東戦争の敗北を主要因とする経済危機を招き,厳しい縮小均衡政策が採られた。そして第3期は1970-81年にかけてナーセルからサーダートへの政権引継ぎを契機に展開された〈経済の自由化〉の時期であり,前半では,親ソ政策から親米路線への劇的な政策転換が行われ,74年以降,為替および貿易の自由化,積極的な外資導入政策を含む一連の門戸開放政策(インフィターフ)が実施され,かつての厳しい統制経済を大幅に緩和した。
こうしたドラスティックな政策転換は,たび重なる戦争で疲弊した経済を,西側先進国の技術と資本,アラブ資本とエジプトの労働力を結合させ,有機的で効率の高い経済活動を促進させることを目的としたものであった。
ナーセル政権下でのエジプト経済は,1955-60年のGDP(国内総生産)成長率が5.3%で,61-65年に6.1%と高率を示すが,第3次中東戦争を含む65-70年にかけては2.9%と著しく低迷した。しかし,サーダート政権下の10年間(1971-80)をみると,前半の5ヵ年間が5.5%と低いものの,後半は約8.5%と高度成長を示している。
この高度成長を支えたのは,(1)石油輸出収入,(2)海外労働者送金,(3)長期海外資本流入,(4)スエズ運河収入などの外貨収入であり,ナーセル時代における外貨獲得源(綿花収入,観光収入,運河収入)と比べて,量的・質的な変化をみせている。だが,石油収入および労働者送金はいずれも石油高価格政策の下で生じた外部経済(外成的要因)の影響をうけたものであり,エジプトが将来も持続的経済成長を図るには,工業および農業の国内生産の拡大に依存する経済への転換が必要であることを示している。
エジプトの農業部門は,全世帯数の約50%,労働人口の約40%を占め,経済活動の中心をなしている。だがGDPに占める同部門の成長率とシェアは停滞しており,1955-65年で年率3.5%,66-78年が約2%前後と成長率は低く,シェアも1955/56年の34%から78年には25%と低下している。こうした農業不振の要因としては,第1に人口増加と生活水準向上に追いつかない生産の停滞,農業自給率の低下,輸出農作物の減少などがあげられる。第2には政府の農産物の低価格買入政策と農業部門の過少投資,農地の減少などが指摘されている。かつてエジプトは綿花モノカルチャー経済であり,農産物の輸出国であったが,1974年以降食糧の純輸入国となっており,また食糧輸入の増大と生活必需7品目(小麦,砂糖など)への補助金増加が赤字財政の主因となっている。
一方エジプトの工業部門は,1930年代より綿工業を中心に発展をみせていたが,ナーセル政権下で伝統的な繊維・食品加工などの軽工業が軽視され,57年以降,化学・電機・金属などの重工業分野に投資が集中した。しかし,イスラエルとの戦時体制が続き,外貨不足による原料の入手,部品・設備の更新が容易でなく,しかも,60年以後社会主義化の導入に伴う国営企業部門の過剰雇用と中央集権的非効率経営に災いされて,十分な発展を遂げていない。70年以降工業部門の多様化と民間部門の活性化が図られ,化学肥料・機械製品・金属工業の分野でかなりの伸びを示し,GDPに占める工業部門のシェアも1956年の18%に比べ78年には24%へと拡大し,民間部門の寄与率も1970年の25%から80年には31%へと若干増加をみせた。
ムバーラク政権は基本的には前政権の開放経済政策を引き継ぎ,前政権下で顕在化した経済構造の歪みの是正を目指した。特に国内経済の不均衡と国際収支の慢性的赤字の改善を当面の重要課題としたが,85年以降の石油不況による原油価格の下落によって,経済改革の推進は大きな困難に直面している。さらに,石油収入,出稼労働者送金,スエズ運河収入,観光収入の四大外貨収入は1983/84年度の78億ドルから1986/87年度には48億ドルへと急減し,この外貨収入の減少は経常赤字を拡大させ,対外債務(1986年6月末の対外債務残高338億ドルと推定)の著しい累積となった。こうした状況下で政府は87年5月IMFから3億3000万ドルのスタンドバイ・クレジットの合意を取り付け,複数為替レートの統一,補助金制度の廃止,財政赤字の縮小等の経済改革プログラムを実施する予定であったが,結局そのコンディショナリティを十分達成することができず,1億6000万ドル分が未実行となった。1987年以降補助金の削減,為替切下げ,さらに政府投資が抑制されたが,その結果経済成長を鈍化(1981-91年で年平均2.8%)させ,物価の上昇をもたらした。
エジプトが経済改革に挫折しかかったとき,湾岸戦争が勃発した。この戦争において西側陣営への協調姿勢を示したエジプトは戦争への貢献の報酬として先進国や湾岸産油国から多額の贈与および債務削減が認められた。91年5月にはIMFがスタンドバイ・クレジット(37億ドル)を承認,パリ・クラブ(ヨーロッパ債権諸国会議)との間で公的債務の50%削減が合意された(元本60億ドルと延滞金25億ドル)。さらに93年9月にIMFとのEFF(拡大信用供与措置=4億SDR)が締結され,第2次債務削減が実施された。
このようにエジプト経済は当面の外貨制約から解放されたものの,これとして対外的要因に振りまわされたもので,いつ抜本的な経済改革に取り組むことができるのか注目されている。
執筆者:中邑 豊朗
エジプトの歴史は抑圧と搾取の歴史であったといっても過言でない。近代を迎えるや西欧列強に蚕食され,大英帝国はエジプトを〈綿の田荘〉とした。国内にあっては不在地主が横行し,飽食した都市と貧血症にあえぐ農村とに二分された。灌漑による農業は支配者の周囲に膨大な官僚機構を生み出し,農民の負担はいっそう過酷なものとなった。その結果,当然ながらエジプト社会にはお上(かみ)(政府)への不信と怨念が潜伏し,人々の間には身内同士で互助しあおうという社会的傾向ができ上がってしまっている。民衆の〈お上嫌い〉は公共物を見ると破損せずにはおかぬような敵愾心などの形をさえとる。政府への不信感は代々民衆の血の中に受け継がれ,徴税と徴兵は常に強い反発と擾乱を呼び起こした。なかでも徴兵は血税の謂(いい)であり,農民各自の最後の堡塁である家を盛り立てるという悲願を挫折させるものであったから,徴兵逃れに誰もが腐心し,コネ,賄賂などの社会の病理があまねく露呈し,結局弱者が最後に〈つけ〉を払わされた。
社会が病んでいる場合,必死に保身をはかろうとする民衆の行為も不健康なものとなることを免れない。例えばエジプトにはファフラーウィヤという言葉があるが,これは状況を擬態によってやり過ごす,場当り的対処の仕方で,ちょうどカメレオンが保護色によって身を守るのと同じやり方である。〈世の中がいい加減なのだから,その場をなんとかごまかせればよい〉というわけである。
民衆は各自の家の中では厳しい倫理観を貫こうとするが,対社会的にはまるで人格などもたぬ者のように振る舞うことが多々ある。またエジプト社会では言葉が浮薄きわまりないものとなる傾向がみられる。例えば会議が終わると同時にそこで討議されたことのすべてが雲散霧消するというぐあいである。
エジプトの社会現象としてよくヌクタnuktaが挙げられる。これは社会正義が保証されておらず,抑圧が過酷をきわめる社会において,民衆がうっぷんのはけ口として,特に政治権力を風刺する地口のごときものであるが,ヌクタが作者不明であって,決して自らの身を危険にさらさない巧妙さはきわめてエジプト的であるといえよう。
エジプト人の行動パターンには特異なものが少なくないが,風土と関連があると思われる一例を挙げてみる。それは〈待つ〉という基本的姿勢である。エジプトは地理的には北にヨーロッパ,南にアフリカ,東にアジアを配し,自らは中央に置かれ常に往還に位置したため,いやおうなく仲介者の役を果たしつつ生き延びなければならなかった。そのため自らは待機し,他者の動向を見守り,なんらかの自分に有利な兆しを見てはじめて介入するという姿勢を地理的に学んだという指摘がある。またナイル川の洪水の訪れ方,すなわち〈遅れるかもしれぬが,履行されぬということはない〉ということから,確信をもって事態の好転を待つことをエジプト人は体得しており,そこには時間を確定することはさして重要でなく,要は事が成就することだという考え方が特徴的に見られる。これは蓋然性に対する弾力のある対応にも通じ,彼らはことを事前にきっちりと練り上げてしまうことを好まず,〈見てみよう〉とか〈状況にあわせて〉とよく言い,柔軟な対応の妙を見せるのである。
現在エジプトは農村社会においてさえ大きな変貌を遂げつつあるが,その一端を文盲撲滅運動が担っている。ナーセル革命による教育の機会均等はようやくその実をあげ始め,外界の価値観が閉鎖された社会に持ち込まれ,農村は教育の普及をてことして着実に変わりつつある。この場合にも,農民は抽象的観念では動かないが,教育を受けることが給料生活者への道を開き,よって相続において土地を細分しないですむという農民の論理によって浸透していく。外界からの情報は大きな影響力をもってきている。しかし農民は新聞を役人のイメージと結びつけて嫌い,読めるようになろうと努力しないが,ラジオは農作業をしながら喜々として耳を傾け,この二つのメディアの間には我々に想像できないような差異があるという。農村の変革には農民の感性と彼らの論理による納得のしかたで,さらにそれに応じた時間の絶対量が必要とされるだろうが,それらの農民の対応のしかたも,風土にその遠因をもつものが少なくないのである。
エジプトの文化については,この項の〈歴史〉でも言及したが,そのほか,〈エジプト美術〉〈エジプト音楽〉〈アラブ文学〉などの項目も参照されたい。
執筆者:奴田原 睦明
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報