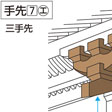関連語
精選版 日本国語大辞典 「手先」の意味・読み・例文・類語
て‐さき【手先】
- 〘 名詞 〙
- ① 手のさき。指のさき。
- [初出の実例]「袖の長き物を着て、手さきをも見すべからず」(出典:風姿花伝(1400‐02頃)二)
- 「割合に手先の器用ばかりで総身の筋肉が働かない」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉七)
- ② 先頭の兵。先鋒。
- [初出の実例]「五百余騎、東西より相近(ちかづい)て、手崎(サキ)をまくりて中を破らんとするに」(出典:太平記(14C後)二六)
- ③ 手下として追いつかわれるもの。
- [初出の実例]「名を松田肇と呼び〈略〉常に川岸の手先となりて奔走する」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉下)
- ④ おかっぴき。めあかし。探偵。
- [初出の実例]「盗賊火附改組之者に而、近頃手先と唱、目明同様之ものを専ら召仕」(出典:法曹後鑑‐享和元年(1801)五月(古事類苑・法律四九))
- ⑤ 雁股(かりまた)、兜(かぶと)の吹返し、空穂(うつぼ)などの武具類の先端をいう。
- [初出の実例]「浄妙房が甲(かぶと)の手さきに手をおいて」(出典:平家物語(13C前)四)
- ⑥ 建築の用語。
- ⑦ 帯の先端部の折り出しの部分。
- [初出の実例]「帯の手先(テサキ)、はりさしのかたはしにも彼もんを付る也」(出典:仮名草子・都風俗鑑(1681)三)
た‐な‐さき【手先】
世界大百科事典(旧版)内の手先の言及
【建築組物】より
…柱上に肘木をおくだけのものを舟肘木,斗一つの上に肘木をおくものを大斗(だいと)肘木,その上に斗を三つおくものを三斗(みつど)組という。壁から直角に前方へ出たものを手先(てさき)の組物といい,三斗組で前方に肘木を出し,先に斗をのせたものを出三斗(でみつど),その先の斗の上に1組の斗と肘木をのせたものを出組(でぐみ)という。出組よりもう1手出れば二手先(ふたてさき),以下,三手先,四手先となる(図3)。…
【目明し】より
…江戸時代に諸役人の手先になって,私的に犯罪の探査,犯罪者の逮捕を助けたもの。岡引(おかつぴき),御用聞,小者,手先ともいう。…
※「手先」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...