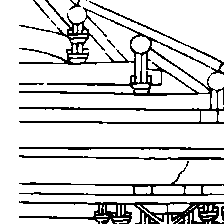関連語
精選版 日本国語大辞典 「斗栱」の意味・読み・例文・類語
と‐きょう【斗栱・枓栱】
改訂新版 世界大百科事典 「斗栱」の意味・わかりやすい解説
斗栱 (ときょう)
中国の木造建築で柱の上に置かれて軒などの上部構造を支える部材。組物。日本や朝鮮半島にも伝えられ,寺院や宮殿建築に常用された。斗(ます)と肘木(ひじき)(栱)からなる。始源は斗と束(つか),肘木と双斗などの簡単な形式であったが,時代とともに複雑化し,尾垂木(おだるき)を組み入れ,前後上下に何層にも組み重ねる形式が出現した。構造と装飾の両面を兼ねた造形上の特色であり,その形式は建築の時代・様式を顕著に反映した指標でもある。
→建築組物
執筆者:田中 淡
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「斗栱」の意味・わかりやすい解説
斗栱
ときょう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「斗栱」の解説
斗栱
ときょう
「くみもの」ともいう。斗 (ます) と呼ぶ桝形の部材と,肘木 (ひじき) (栱)と呼ぶ舟形の腕木を一組とし,軒・天井などを支えるために用いられる。一組を手先と呼び,たとえば三組を使って三段に持ち送ると三手先という。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「斗栱」の意味・わかりやすい解説
斗栱
ときょう
→組物
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...