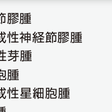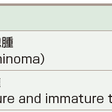内科学 第10版 「脳腫瘍総論」の解説
脳腫瘍総論(脳腫瘍・脊髄腫瘍)
脳腫瘍(brain tumor)とは,頭蓋内に発生する新生物である.脳,くも膜,硬膜など頭蓋内の組織から発生するものを原発性脳腫瘍,他臓器の悪性腫瘍が頭蓋内に転移したものを転移性脳腫瘍とよぶ.
分類
中枢神経系には神経上皮組織以外に中胚葉,外胚葉組織が存在するため,原発性脳腫瘍の分類も中枢神経系の組織発生を基準に行われる.脳腫瘍の標準的な分類法であるWHO分類2000年版では,脳腫瘍を神経上皮,末梢神経,髄膜由来の腫瘍,リンパ腫および造血細胞由来の腫瘍,胚細胞系腫瘍,トルコ鞍近傍腫瘍,転移性腫瘍の7つに大分類,さらにそれらを115種類の腫瘍に細分類した.ただし,このWHO分類では,従来脳腫瘍に分類されていた下垂体腺腫,類皮腫,類表皮腫,脊索腫などが除外されているが,本項では従来どおりこれらも脳腫瘍として取り扱うことにする.
原発性脳腫瘍は神経膠細胞や神経細胞など神経組織を構成する細胞由来の腫瘍(WHO分類では神経上皮由来の腫瘍に大分類)と,それ以外の腫瘍に大別することができる.前者には,いわゆるグリオーマ(神経膠腫)とよばれる星細胞腫,退形成性星細胞腫,膠芽腫,乏突起神経膠腫,上衣腫などの一群の腫瘍のほか,神経細胞由来のガングリオサイトーマ,胎児性腫瘍の髄芽腫などが含まれる.後者すなわち神経組織以外を発生母地とする腫瘍には,髄膜腫,神経鞘腫,下垂体腺腫,血管芽腫,悪性リンパ腫,頭蓋咽頭腫,胚細胞系腫瘍などが含まれる. 転移性脳腫瘍では,他臓器に発生するあらゆる悪性腫瘍がその原発巣になり得るが,肺癌,乳癌,消化器癌,泌尿器癌の頻度が高い.
統計学的事項
原発性脳腫瘍の発生頻度は,人口10万人あたり8~10人程度とされている.転移性脳腫瘍に関しては,原発性に比べその発生頻度は低いとされてきたが,近年増加の傾向にある.
1)脳腫瘍別の発生頻度(表15-14-1):
脳腫瘍全国集計調査報告(第12巻,2009年)によると,髄膜腫:26.4%,神経膠腫:24.5%(星細胞腫,退形成性星細胞腫,膠芽腫,乏突起神経膠腫,上衣腫などをまとめたもの),下垂体腺腫18.1%,神経鞘腫:10.7%,頭蓋咽頭腫:3.5%,悪性リンパ腫:3.1%,胚細胞系腫瘍:2.8%の順である.近年,髄芽腫が減少し,悪性リンパ腫が増加している.
2)脳腫瘍の好発年齢:
あらゆる腫瘍があらゆる年齢の患者に発生しうるが,その発生頻度をみると小児と成人との間に大きな差がある.小児期に多い腫瘍としては,星細胞腫,髄芽腫,頭蓋咽頭腫,胚細胞系腫瘍,上衣腫があげられる.一方,成人に多い腫瘍は,神経膠腫,髄膜腫,下垂体腺腫,神経鞘腫,悪性リンパ腫,転移性脳腫瘍などである.
3)脳腫瘍の好発部位:
神経膠腫,髄膜腫,転移性脳腫瘍など,成人に好発する腫瘍は一般にテント上に多く,一方,小児では髄芽腫や小脳星細胞腫などテント下腫瘍が多い.したがって,前述のWHO分類にあるように病理組織学的に細かく分類される脳腫瘍も,臨床的には腫瘍の好発部位を念頭におき,その局在から鑑別診断を行うことが重要になってくる.たとえば大脳半球の脳実質外腫瘍であれば髄膜腫を,脳実質内腫瘍であれば星細胞,退形成性星細胞腫,膠芽腫,転移性脳腫瘍,悪性リンパ腫などを考える必要がある.またトルコ鞍内あるいは傍鞍部腫瘍としては,下垂体腺腫,頭蓋咽頭腫,胚細胞系腫瘍,髄膜腫,視神経膠腫などを鑑別しなくてはならない.脳室系には脈絡叢乳頭腫,上衣腫などが,頭蓋底部には骨由来の脊索腫や軟骨腫,さらに副鼻腔,鼻咽頭由来の癌腫が発生する.後頭蓋窩には脳実質外腫瘍として神経鞘腫,髄膜腫,類表皮腫が,また脳実質内腫瘍としては髄芽腫,星細胞腫,血管芽腫が発生する.
病因
近年の分子生物学の進歩により,脳腫瘍の発生や悪性変化に癌遺伝子や癌抑制遺伝子の発現異常が関与していることが判明した.また,神経線維腫症やvon Hippel-Lindau病などの神経皮膚症候群に伴う脳腫瘍の発生についても,遺伝子異常の関与が明らかになった.しかし,これらの脳腫瘍に伴うさまざまな遺伝子異常を引き起こす真の病因は依然として不明である.脳腫瘍を惹起する外的要因としては,外傷,放射線,化学物質,ウイルスなどが想定されているが,放射線治療後に二次的発生する髄膜腫,肉腫,グリオーマ以外には明確な因果関係は証明されていない.
臨床症状
頭蓋内圧亢進症状と腫瘍の発生部位に対応する局所脳症状とに分類されるが,これらの臨床症状は数週間から数年間にわたり徐々に進行・増悪することが一般的である.組織学的に悪性度の高いものでは,症状は急速に進行するが,特に腫瘍内出血を伴った場合には,脳血管障害を思わせるような急性増悪もありうる.
1)頭蓋内圧亢進症状:
腫瘍自体あるいはそれに伴う脳浮腫によって頭蓋内容が増加するために起こるが,後頭蓋窩に発生する腫瘍ではしばしば水頭症を併発するので,これが頭蓋内圧亢進の原因になる.患者は頭痛を訴え,嘔吐し,眼底にはうっ血乳頭を認める.病態が進行して脳ヘルニアを起こせば,意識障害も起こる.
2)局所脳症状:
a)てんかん発作:一般に脳腫瘍患者の30%程度が,てんかん発作をきたすとされている.特に成人で初発するてんかん発作に関しては,脳腫瘍の存在を強く疑う必要がある.てんかん発作はテント上腫瘍に圧倒的に多く,前頭葉,側頭葉,頭頂葉の腫瘍に高頻度にみられる.
b)前頭葉障害:腫瘍が前頭葉後半に発生すると反対側の片麻痺,腱反射亢進をみるが,優位側半球の場合には運動性失語をみることもある.両側の前頭葉に障害が及ぶと,無関心,認知症,尿失禁などの抑制障害をみる.
c)側頭葉障害:腫瘍が優位側半球側頭葉の後方に発生すると,感覚性失語をきたす.また,視放線が障害されると同名性上四分盲をみる.
d)頭頂葉障害:腫瘍が中心溝に近いと対側の感覚障害をきたす.頭頂葉連合野の障害では失行・失認を認めるが,優位側半球角回付近の病変ではGerstmann症候群をみる.
e)後頭葉障害:病変と反対側の同名性半盲をきたす.視野欠損は左右同等で,黄斑回避を伴う.
f)トルコ鞍,傍鞍部腫瘍(表15-14-2):視神経,視交叉の圧迫により視力・視野障害をきたす.下垂体腺腫が鞍上部に伸展して視交叉を下方より圧迫すると,初期の段階では両耳側上四分盲,そして最終的には左右対称の両耳側半盲を呈することになる.一方,頭蓋咽頭腫など下垂体腺腫以外の傍鞍部腫瘍では,視野障害はしばしば左右非対称になる.胚細胞系腫瘍や頭蓋咽頭腫などにより視床下部・下垂体系が障害されると,副腎皮質の機能低下症,小人症,尿崩症などが起こる.髄膜腫が海綿静脈洞に発生あるいは浸潤すると,眼球運動障害,顔面知覚障害(三叉神経第一枝領域)が生じる.ホルモン産生下垂体腺腫では,プロラクチン,成長ホルモン,副腎皮質刺激ホルモンなどの異常分泌に伴うさまざまな臨床症状をみる.
g)松果体部腫瘍:中脳水道狭窄あるいは閉塞による水頭症,上方注視麻痺(Parinaud徴候)やArgyll Robertson瞳孔をきたす.
h)小脳橋角部腫瘍:顔面,蝸牛,前庭神経のいずれもが障害されうるが,聴神経鞘腫では聴力低下が初発症状のことが多い.腫瘍が大きくなり,橋や中小脳脚さらに小脳半球へ圧迫が加わると,Bruns 眼振や小脳症状を伴ってくる.
i)脳幹部腫瘍:運動・感覚の神経線維,第3~12脳神経の神経核とその髄内線維が錯綜するため,中脳・橋・延髄と病変の部位によりさまざまな神経症状を呈することになる.橋神経膠腫では,顔面神経麻痺や外転神経麻痺をしばしば伴うが,これに交差性の片麻痺が加わりMillard-Gubler症候群を呈することもある.脳幹部神経膠腫が発育し脳幹が腫大すると,最終的には第4脳室が閉塞され水頭症が発生する.しかし,このような水頭症は次に述べる第4脳室腫瘍とは対照的に,病期のかなり進行した段階ではじめてみられるのがふつうである.
j)第四脳室腫瘍:上衣腫と髄芽腫が代表的なものであるが,ともに腫瘍により第4脳室は容易に占拠・閉塞されるため,かなり早い時期から水頭症を併発する.したがって,ほとんどの患者は頭蓋内圧亢進症状で発症することになるが,髄芽腫では腫瘍が小脳虫部より発生するため,しばしば体幹失調をみる.一方,上衣腫の多くは第4脳室底から発生するが,外転神経麻痺や顔面神経麻痺を呈することは比較的まれである.
k)頭蓋底腫瘍:前頭蓋底腫瘍では嗅覚障害や視力視野障害を,中頭蓋窩の腫瘍では三叉神経障害や眼球運動障害を認める.腫瘍が後頭蓋窩に伸展すれば,顔面神経,内耳神経,さらに下部脳幹神経や舌下神経までが障害されることになる.鼻咽頭腫瘍が頭蓋底に広汎に浸潤すると,錐体路兆候なしに一側の脳神経が多発性に障害されるGarcin症候群を呈する.
診断
1)脳腫瘍と腫瘍マーカー:
ホルモン産生下垂体腺腫におけるプロラクチン,成長ホルモン,副腎皮質刺激ホルモンはその典型であるが,胚細胞系腫瘍におけるヒト絨毛ゴナドトロピン(hCG)とα-フェトプロテイン(AFP)が腫瘍マーカーとして重要である(表15-14-3).絨毛癌では血中hCGが,卵黄囊腫瘍では血中AFPが上昇するが,これらは髄液中にも高濃度で検出される.
2)脳腫瘍の画像診断:
MRI(magnetic resonance imaging)とCTによって行われる.特にMRIの有用性に疑問の余地はなく,腫瘍の局在や周辺の解剖構造の偏位・変形について詳細な情報を提供するばかりでなく,その病理診断に関しても,術前にかなり正確に予測できるようになった.動脈や静脈の描出には,MR angiography(MRA)やMR venography(MRV)が用いられる.さらに最近ではMR spectroscopy(MRS)を利用して,腫瘍再発と放射線壊死の鑑別や腫瘍の悪性度を評価する試みもなされている.また,functional MRIを用いて運動野や言語野を同定することにより,これらの領域の近傍に発生する腫瘍の手術がより安全に行えるようになった.
治療
手術,放射線治療,化学療法,免疫療法などがある.髄膜腫,下垂体腺腫,神経鞘腫などでは,手術によって腫瘍が全摘出されれば完治を期待することができる.脳実質に浸潤性に発育する神経膠腫などでも,腫瘍の90%以上が切除された場合と部分摘出に終わった場合とでは,その予後に差のあることが知られており,やはり外科的治療の役割は大きいものと考えられている.また,MRIの出現により脳腫瘍の術前診断の精度はかなり高いものになったが,腫瘍の病理診断を確定するために生検を含めた外科的処置が必要になることも少なくない.従来の放射線治療は手術後の補助療法として行われることが多く,退形成性星細胞腫,膠芽腫,髄芽腫,胚細胞系腫瘍などでは一定の治療効果のあることが実証されてきた.一方で,これまでの経験の蓄積から発達期の脳に対する放射線の悪影響が明らかとなり,現在では3歳以下の症例に対する放射線治療は極力避けるべきと考えられている.また,最近では腫瘍の直径が3 cm以下ということを条件に,ガンマナイフやLINACを用いた放射線外科治療(radiosurgery)がさかんに行われるようになった.転移性脳腫瘍などがそのよい適応と考えられているが,髄膜腫や神経鞘腫などの良性腫瘍に対しても放射線外科治療が施行されており,腫瘍発育を抑制するなどの治療効果が確認されている.化学療法には,ニトロソウレア系薬物(カルムスチン,ロムスチン,ニムスチンなど),ビンクリスチンなどのアルカロイド系,シスプラチンやカルボプラチン,プロカルバジン,ブレオマイシンなどの薬剤が使用される.手術・放射線治療と組み合わせて行う多剤併用療法が一般的であるが,小児例では化学療法を併用することにより,放射線治療の開始時期をできるだけ遅らせる,あるいは照射線量を可能なかぎり減少させるなどの試みがなされている.[新井 一]
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報