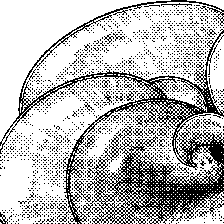ウミウチワ (海団扇)
Padina arborescens Holm.
団扇を思わせる形状のアミジグサ科の褐藻で,タイドプール中によく群生する。体の大きさは10~20cmになり,黄色を呈する。縁辺の細胞がいっせいに分裂しながら生長するので,体には同心円状の生長線が見られる。体には表と裏があり,生殖器官は裏側にできる。藻体には外見上区別のつかない雌雄の単相の配偶体と複相の胞子体とがあり,配偶体には生卵器と造精器,胞子体には四分胞子囊がつくられる。受精卵は発芽すると複相の胞子体になり,ここに減数分裂によってつくられた四分胞子が発芽すると単相の配偶体となる。暖流海域に分布する。同属の似た種類にコナウミウチワ,アカバウミウチワ,ウスユキウチワ,オキナウチワなどがあり,いずれも暖流海域に分布する。
執筆者:千原 光雄
ウミウチワ (海団扇)
sea-fan
Anthogorgia bocki
花虫綱トゲヤギ科の腔腸動物(刺胞動物)。紀伊半島以南のやや深い海底に分布し,枝が一平面に広がって扇状の群体をつくる。不規則に分岐した枝は交差して癒着し,網状になり,大きなものでは高さが1mにもなる。骨軸は黒い角質で,表面には細かい縦線が走る。ポリプは直径1mmくらいで枝の全面に不規則に分布するが,とくに枝の末端では密集する。共肉は比較的厚い。通常外皮下には多毛類のシリス科の1種が共生している。しばしば海岸に打ち上げられたり,漁網にかかったりする。
執筆者:今島 実
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ウミウチワ
Anthogorgia bocki; sea-fan
刺胞動物門花虫綱八放サンゴ亜綱ヤギ目トゲヤギ科。一平面内に扇状に広がった群体をつくり,大きなものでは高さが 1mにもなる。枝は不規則に分岐し,それぞれが互いに癒合して網状になる。黒い角質の骨軸をもつ。共肉は比較的厚く,枝の全面に直径 1mmほどの多数の個虫がある。紀伊半島以南,西太平洋の水深 200m内外にすみ,黒い骨軸が岸に打ち上げられることがある。(→サンゴ,刺胞動物,花虫類,無脊椎動物)
ウミウチワ(海団扇)
ウミウチワ
Padina arborescens
褐藻類アミジグサ目アミジグサ科の海藻。藻体は葉状,革質で厚く,扇形,同心円状に筋が入っている。古くなると縦に裂ける。低潮線に近いタイドプールに群生する。この藻の表面には種々の藻が着生する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ウミウチワ(海産動物)
うみうちわ / 石帆
海団扇
sea fan
[学] Anthogorgia bocki
腔腸(こうちょう)動物門花虫綱八放サンゴ亜綱ヤギ目全軸亜目トゲヤギ科に属する海産動物。群体は扇状に広がり、枝は不規則に分岐し、互いに癒着して網状となり、大きなものでは高さ1メートルにも及ぶ。共肉は橙(だいだい)色。小笠原(おがさわら)諸島および紀伊半島以南の太平洋岸の深所に産し、漁網に絡まってあがってくる。骨軸は角質で黒褐色、中に骨片を膠着(こうちゃく)させず角質の石灰化もほとんどみられない。ポリプは枝の全面に不規則に分布し、径、高さとも1ミリメートルぐらいで、共肉中に退縮しない。共肉下には多毛類のシリスの1種がトンネルをつくって多数共生している。
[内田紘臣]
ウミウチワ(海藻)
うみうちわ
peacock's tail
[学] Padina arborescens Holmes
褐藻植物、アミジグサ科の海藻。黄褐色で、粗い手触りの膜状葉体をもつ。団扇(うちわ)形で、葉面に同心円状の層紋があり、径20~30センチメートル内外の大きさになる。老成体は縁から裂けて、数枚の裂片となる。日本沿岸各地の外海に広く分布する多年生藻。同属には、小形で体表面に淡く石灰質が沈着するオキナウチワなどがある。また、属は違うが、同形の小形で、同心円層紋がはっきりみられるシマオウギなどがある。ウミウチワの仲間はどちらかというと暖海性で、サンゴ礁内の潮だまり(タイドプール)などに群生するが、適応性は広く、温海、寒海の地域にも分布する。
[新崎盛敏]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ウミウチワ
花虫綱トゲヤギ科の腔腸(こうちょう)動物。群体は扇状に一平面に広がり,高さが1mにもなる。枝は不規則に分かれ,互いに癒合(ゆごう)して網状。枝の全面に直径1mmほどのポリプが群生する。紀伊半島以南のやや深い海底の岩などに着生する。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by