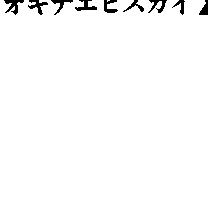オキナエビスガイ
おきなえびすがい / 翁戎貝
Beyrich's slit shell
emperor shell
millionaire shell
[学] Mikadotrochus beyrichi
軟体動物門腹足綱オキナエビスガイ科の巻き貝。相模(さがみ)湾、房総半島沿岸、伊豆七島、遠州灘(なだ)の水深50~250メートルの岩礁底にすむ。殻高、殻径とも110ミリメートルに達するものもあるが、普通は80~90ミリメートルである。形は整った円錐(えんすい)形で、各層がいくぶん膨らんでいる。螺層(らそう)は11階、顆粒(かりゅう)状の強い螺肋(らろく)がある。殻口の外唇に細くて深い切れ込みがあり、上方の螺層では切れ込み帯となっている。殻表は橙黄(とうこう)色の火炎状の模様があり美しい。軸唇は厚く、ねじれていて、臍孔(へそあな)は開かない。殻底は弱く膨らみ、顆粒状の螺肋がある。殻口内には強い真珠光沢があり、蓋(ふた)は丸く殻口に比べて小さい。この貝は、1875年(明治8)東京大学の医学の教師をしていたドイツ人ヒルゲンドルフが江の島の土産物(みやげもの)屋で購入して自国に持ち帰り、1877年に新種として学術誌に発表した。しかし、日本ではそれより以前1843年(天保14)武蔵石寿(むさしせきじゅ)(1766―1860)が著した『目八譜(もくはちふ)』にすでに、エビスガイの老大成したものという意味でオキナエビスの名で図示(厳密にはベニオキナエビスガイにあたる)されている。このほうが早いが、和文和名のみで学術的な記載方法にあわないため認められなかった。ヒルゲンドルフの発表後、各国からこの珍しい貝の入手希望があり、とくに大英博物館から東京大学に、標本を買いたいから採集してほしいとの申し込みがあった。神奈川県三崎の東京大学臨海実験所の青木熊吉(1864―1940)はこのために採集し、教授の飯島魁(いいじまいさお)、箕作佳吉(みつくりかきち)に持参したところ、その報酬に金40円をもらった。彼が漏らした「長者になった」という感想から、チョウジャガイ(長者貝)の別名がつけられたと伝えられている。
[奥谷喬司]
オキナエビスガイ類は、古生代シルル紀に現れ、石炭紀に栄えたが、その後衰退し、現在は日本からフィリピン近海にかけて7種、ニュー・カレドニア近海に1種、アフリカ近海に1種、カリブ海からブラジル沖にかけて8種、合計17種が分布している。これらの種の軟体部をみると、まだ原始的な左右相称の形態をとどめていて、えらや心耳などが1対ある(高度に分化した巻き貝ではおもに左側のえらと心耳が退化して、右のものしか残っていない)。このためにオキナエビスガイ類は「生きた化石」の一つとして著名である。
日本産には本種のほか、コシダカオキナエビスガイM. schmaltzi(房総半島、伊豆諸島、および紀伊半島から九州西岸まで)、ベニオキナエビスガイM. hirasei(紀伊半島から沖縄まで)、テラマチオキナエビスガイPerotrochus teramachii(四国沖から東シナ海、さらに南シナ海からスル海まで)、アケボノオキナエビスガイP. diluculum(伊豆七島)、リュウグウオキナエビスガイEntemnotrochus rumphii(四国沖から台湾、さらにインドネシアまで)の5種があり、いずれも美しい希種のため収集家にもてはやされる。
[奥谷喬司]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
オキナエビスガイ (翁戎貝)
Mikadotrochus beyrichi
古生代から中生代に栄えた貝類の生残りで,〈生きている化石〉と称される学術上貴重なオキナエビスガイ科の巻貝。殻の高さと太さともに11cmの円錐形,巻きは11階。殻口は外側に細く深い切れ込みがあるのがこの類の特徴であり,上方の巻きではそれをふさいだ切れ込み帯となっている。ふたはまるくて褐色。内面は強い真珠光沢がある。軟体は巻いているが,えらや心耳などいろいろな器官が左右1対あるのは,多くの巻貝が左側の器官のみになっているのに対して原始的なことを示す特徴であり,学術的に貴重な理由である。銚子沖から相模湾,伊豆諸島,志摩大王崎沖に分布し,水深50~200mの岩れき底にすむ。
1844年(弘化1)に武蔵石寿(むさしせきじゆ)が《目八譜(もくはちふ)》に図説し,エビスガイの老大成したものとしてオキナエビスの名を与えたのが最初で,75年に東京医学校(現,東京大学医学部)の動植物学の教師であったヒルゲンドルフF.M.Hilgendorf(1839-1904)が江の島のみやげ物屋で発見し,ドイツへ帰国後77年に学界へ発表した。この原始的な珍しい種が日本に産することで有名となり,イギリスの大英博物館から東京大学へ1個100ドルで購入したいと採集方依頼があった。そこで三崎臨海実験所の採集人青木熊吉が生きた貝を採集,箕作佳吉(みつくりかきち)教授に届けたところ,ほうびに金40円をもらった。あまりに大金なので熊吉は長者になったような気がするといったので,この貝をチョウジャガイともいうようになった。
日本産はこの種のほか5種あり,ベニオキナエビスガイM.hiraseiはこの種に似て紅色でやや低い円錐形で,銚子沖から沖縄,フィリピンに分布する。木村蒹葭堂(けんかどう)が1775年(安永4)に《奇貝図譜》を著して,これに図説している。これは世界でこの類の発見の最初の記録である。リュウグウオキナエビスガイEntemnotrochus rumphiは最大の種で,殻の太さは19cmに達し,東シナ海からインドネシアに分布する。このほかテラマチオキナエビスガイ,コシタカオキナエビスガイ,アケボノオキナエビスガイがある。millionaire shellは日本製英語であるが今は英名となっている。
この類は古生代シルル紀に現れて中生代ジュラ紀に栄えたが,新生代に入ると衰え,現生種は約20種にすぎない。
執筆者:波部 忠重
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「オキナエビスガイ」の意味・わかりやすい解説
オキナエビスガイ
チョウジャガイとも。オキナエビスガイ科の巻貝。高さ・幅とも10cm。殻は円錐形でだいだい色。殻口の外側に細長い切れ込みがある。原始的な構造で軟体は巻いているが,鰓(えら)や心臓等は1対。左右相称の体制をとどめる。古生代・中生代に栄えた類で,現在は15種。伊豆半島,相模湾,千葉県,志摩大王崎沖の水深50〜200mの岩礫(がんれき)底にすむ。ヒルゲンドルフが1875年に江の島で発見した。近縁のベニオキナエビスガイは本種に似るが,やや低い円錐形。紅色で,殻表の凹凸が細かく,銚子沖〜沖縄,フィリピンに産する。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のオキナエビスガイの言及
【貝】より
…深根輔仁の《本草和名》(918ころ)に始まり,江戸時代に入って多くなった。大江流芳の《貝尽(かいつくし)浦の錦》(1749)や松岡玄達の《怡顔斉介品(いがんさいかいひん)》(1758)などが出,また木村蒹葭堂(けんかどう)の《奇貝図譜》(1775)はベニオキナエビスガイはじめ多くの深海産の貝を図説したものである。〈生きている化石〉オキナエビスガイが西インド諸島で発見されて学会を驚かせたのが1855年であるから,それより80年も前のことである。…
※「オキナエビスガイ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by