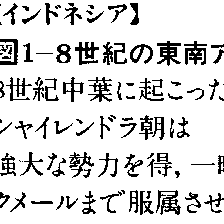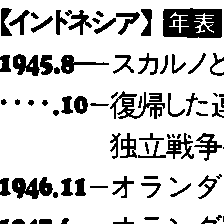目次 自然 住民,宗教,基層文化 社会 歴史 ヒンドゥー・ジャワ王国の興亡 イスラム化と植民地化 インドネシア民族主義 インドネシア共和国 政治,外交 政治 外交 経済 教育,文化 文学 美術 音楽,舞踊 スマトラ ジャワ,バリ,マドゥラ カリマンタン スラウェシ その他の地域 基本情報 正式名称 =インドネシア共和国Republic of Indonesia 面積 =191万0931km2 人口 (2010)=2億3764万人 首都 =ジャカルタJakarta(日本との時差=-2時間) 主要言語 =インドネシア語,ジャワ語,スンダ語 通貨 =ルピアRupiah
東南アジアの大国。赤道をはさんでその南北に広がる島嶼(とうしよ)国家である。国名は〈島嶼のインド〉の意で,その文化的影響を大きく受けた〈大陸のインド〉に対する意識から名付けられた。
自然 インドネシアは赤道を中心に広がるマレー諸島の大部分を占める世界最大の群島であり,同時に地質的には世界で最も複雑な構造を示す地域でもある。すなわちここは古い時代の比較的安定した二つの地塊(東部のサフール海棚と西部のスンダ海棚)の間にはさまれた地盤のきわめて不安定な地域で,スンダ海棚はアジア大陸の延長部分であり,その上にカリマンタン(ボルネオ)島が現れている。これに対しサフール海棚はニューギニアとともにオーストラリア大陸と連接し,浅いアラフラ海を形成する。そしてこの二つの海棚間に第三紀の強い造山運動によってスンダ山系を生じ,スマトラ島から東へ連なる大小スンダ列島を生じた。これは遠くヒマラヤ造山帯に連なる山系で,激しい火山活動を伴い,世界的な火山地帯となっている。火山の数は130にも及ぶが,今なお活動を続けるものは78,その中ではスマトラ島のクリンチ,ジャワ島のメラピ,ブロモ,スメル,バリ島のアグンなどが名高い。スンバワ島のタンボラ,スンダ海峡中のクラカタウ 火山のように世界的な大爆発の歴史を示したものもある。また群島東部には環太平洋火山帯が通り,スラウェシ(セレベス)島,モルッカ諸島方面に多くの火山がそびえる。したがってインドネシアは全体として地震が多い。これらの火山活動は,一方では肥沃な火山性土壌を形成して生活に好条件を与える。スマトラ西岸やジャワの稠密な人口集中もこれと無関係ではない。火山地域から外れたボルネオの希薄な人口とは対照的である。
気候的には赤道直下の雨林気候とその南北に広がるモンスーン気候 の二つに区分されるが,一般に常時高温で,全地域が年平均25~27℃の範囲内にある。雨量はモンスーン気候の地域では雨季と乾季により著しい差があり,西部ジャワの山地では雨季に4000mmに達する所もあるが,スンダ列島の東部に向かうほど乾季が長く,雨量は少なくなる。また乾・雨両季の中間に赤道前線の接近の程度により干害を受けることもある。しかし全体的には熱帯多雨の特質が明らかで,密林に覆われる所が多い。〈赤道にかけられたエメラルドの首飾〉という形容句は群島の常緑景観をよく示したものといえよう。高い火山地形が多いため,標高による気温の変化も著しく,イリアン・ジャヤ の4000~5000m級の高山では氷河や万年雪が見られ,ジャワでも3000mの高さになれば冷涼で高山植物も見られる。ブロモ火山の標高2200m付近では年平均気温は16℃,700mのバンドン高原では22℃となる。これらは近代において低地の暑熱を避けての高原休養都市の発達や,気温の垂直差を利用しての各種農作物の栽培に有利な条件ともなった。
こうした植物分布の豊かさはインドネシアの自然の一大特色で,それはこの地域本来のものにアジア系,オーストラリア系のものが混在することによっていっそう著しくなる。被子植物だけでも2万5000種あり,ヤシの種類も1000以上にのぼる。花の多様性,ことに蘭の種類の多いことも特色といえよう。森林の5分の1はまだ原生林のままで,イリアン・ジャヤ,ボルネオの森林率は80%にも及ぶが,ジャワでは23%ほどに低下している。しかし高山地域を除けば,焼畑農業の行われた所では原生林が失われてアラン・アラン草(イネ科の多年草チガヤ)の茂る草原に変わったり,さらにそこに第二次林が茂った所が多い。
動物分布は地理的位置によってアジア,オーストラリア両系のものを含む。西部の島々ではアジア系のものと同じく,象や虎もいるが,マカッサル海峡とロンボク海峡をつなぐいわゆるウォーレス線を境に東部ではオーストラリア系のものが著しくなり,有袋類などがみられる。さらにスラウェシ東岸とティモール島東端とを結ぶウェーバー線によっても若干の動物(鹿の類)の分布の境界線が設定されている。そのほかインドネシアは各種の特殊動物の存在でも知られ,オランウータン,バンテン(野生の牛),野生の小型の馬,コモドオオトカゲ などは有名で,保護区が設けられている。貴重な鳥類も多い。別技 篤彦
住民,宗教,基層文化 インドネシアの住民は200とも350ともいわれる民族集団に分かれ,互いに言語,社会構造,生活様式を異にしている。インドネシア共和国は各民族集団別の人口統計作成を意識的に避けているので,正確な数字は得られないが,ジャワ島中・東部を本拠とするジャワ族 (約6000万。1982推計。以下同),同島西部のスンダ族 (2000万弱)のごとき巨大な集団から,イリアン・ジャヤに見いだされるような数百人規模の諸集団まで,それぞれの規模はきわめて多様である。なお数百万人規模に達する著名な民族集団としては,スマトラ島北端のアチェ族 ,中北部のバタク族 ,西部のミナンカバウ族 ,東岸一帯のマレー人 ,マドゥラ島およびジャワ島東端部のマドゥラ族 ,バリ 島のバリ族,スラウェシ島南部のブギス族 などがある。またおもに17世紀以降大量に来住しインドネシア全域の都市部に住む華人(中国)系住民は300万~400万人と数えられる(1971推計)。華人系,インド系などの後来者を除くインドネシアの諸民族集団は,東端部のイリアン・ジャヤ,ハルマヘラ島北部のパプア諸語 系集団を例外として,言語的にはすべてアウストロネシア語族のインドネシア語派 に属する。彼らは元来中国西南部に居住し,前2500-前1500年ころ南下して現在のインドネシアの地に広がったと考えられる。インドネシア語派の諸言語は,またマレーシアとフィリピンの全域,タイ南部(マレー人),ベトナムやカンボジアの一部(チャム系諸集団),台湾山地,さらに遠くマダガスカル島全域にまで分布し,これらの住民はすべて言語系統を一にし,基層文化上の類似を示す。その後インドネシアの地には,新たな他民族の大規模な来住や侵入,定着は見られなかった。17世紀以降この地をしだいに植民地化していったオランダ人も,ラテン・アメリカのスペイン人のごとく大規模な通婚により民族構成を変化させることはしなかった。オランダ植民地時代以降に来住した華人やインド人,アラブも今日まで周縁的で弱い少数派集団の地位にとどまっている。したがってインドネシアの民族構成は表層において著しく多様でありながら,基層においては同質的である。
インドネシア全域の政治的統一は,19世紀から20世紀初頭にかけてオランダの手により初めて実現されたのであり,それ以前は上記の200~350の諸民族集団ごとに,ほぼ独立した社会生活が営まれていた。その多くは身分制と首長制を伴う社会であったが,ジャワ族,バリ族,アチェ族のように王権観念と王国組織を高度に発達させた例を除く他の多くの社会は,親族的・村落的結合を基盤にした小規模なものであり,王は存在したとしても現実的統治力の弱い象徴的存在であった。生業の面では,スマトラ島南東部のクブ族,カリマンタン山地部のプナン族など若干の移動的採集狩猟民を除き,ほぼすべての民族集団が農業を主としてきた。その伝統的類型は大きく3種に区分できる。第1は,ジャワ族,スンダ族,マドゥラ族,バリ族,ミナンカバウ族,ロンボク島のササク族など,灌漑水稲耕作を行うもの,第2は,他の大半の民族集団の例であって,陸稲などの焼畑耕作を行うもの,第3は,東ヌサ・トンガラ州,マルク州,イリアン・ジャヤ州など東端地域に見られる類型で,焼畑とならんでサゴヤシ,バナナなどに大きく依存する。現在では灌漑水稲耕作が上記第1類型の諸集団以外にも急速に広まっている。一方,東南アジア各地,インド,中国などと結ぶ海洋交易も古くから盛んであり,こうした商業活動の伝統も農業と並んで重要である。
インドネシア住民の宗教生活の基層には,土地,家屋,泉,樹木,岩,山,海などあらゆる場に存在する諸精霊,秀でた人物や物体に宿る超越的力,神格化した死者霊などへの信仰が見いだされる。歴史史料が現れ始める5~8世紀ころのスマトラ,ジャワでは,すでにインドから渡来したヒンドゥー教,仏教が受容されていた。とくに8~14世紀にはジャワ島中・東部の諸王国において,いわゆるヒンドゥー・ジャワ文化が頂点をきわめた。13世紀末にスマトラ北西端に伝わったイスラムは,その後海洋交易路を通じてインドネシアの各地域に広まり,16世紀にはジャワ人もほとんどがイスラム化する。ただバリ島にはイスラム化の波が及ばず,バリ化されたヒンドゥー的信仰と文化が今日まで保たれている。海洋交易路から外れた周辺地域や大島嶼内奥部の住民もまたイスラム化の波を受けることなく伝統的な固有信仰を保っていたが,ここでは19~20世紀にヨーロッパ人宣教師が活動し,キリスト教化した地域も多い。スマトラのバタク族,スラウェシ北端のミナハサ族などがプロテスタント の中心であり,また東ヌサ・トンガラ州のティモール島,フロレス島などではカトリックの力が強い。
今日一般にインドネシア国民の90%がイスラム教徒だといわれる。だが多くの場合その信仰はアラブ的厳格さと隔たった自由で混交的なものである。この傾向はとくにジャワ族に強く,土着的・ヒンドゥー的要素を含めたジャワ的伝統をコーランの教えに優越させる立場が多数を占める。一方,スンダ族,アチェ族,ミナンカバウ族,ブギス族などの間では,国内の多数派であるジャワ族との対抗関係もあって,よりコーランに忠実で厳格な信仰を守ろうとする傾向が強い。インドネシア人の宗教生活は,土着的基層の上にまずインド的宗教が接木され,さらにイスラム,キリスト教が接木されたものであり,日常の民俗的次元では諸宗教の違いを超えた大きな共通性が見られる。関本 照夫
社会 近年の目ざましい工業化,都市化の進展にもかかわらず,インドネシア人口の3分の2(1995)は,依然として農村社会に生活している。世界有数の島嶼国家であるインドネシアでは,農村社会のありさまも地域によって多様であるが,一方その基層にはある程度の共通性も認められる。例えば農村内の社会階層制度に関していえば,村の先住民の子孫が通常社会的に高い地位を享受している。冠婚葬祭,農作業,災厄などにおけるゴトン・ロヨン (相互扶助)活動は,村人の生活において重要な機能を果たす。また女性の社会的地位も一般に高い。このような特徴は,オランダ植民地支配の進展や貨幣経済の浸透に伴い,ジャワ農村社会などにおいて特に19世紀以降一部変容したが,概してインドネシアの農村社会に今でも広く見ることができる。
村内の土地利用や人間関係を律する上において,国の法律とは異なるアダット (慣習法)の影響が依然として認められることも,インドネシアの農村社会に共通の現象である。しかしアダットの内容自体はインドネシアの諸地域によってさまざまであり,村人たちはテレビ,ラジオなどを通じて都市文化の影響を受けつつも,一方でいまだにその地方固有のアダットの中で生活しているといってよい。アダットがいかに多様であるかは,基本的な人間関係を律する親族構造に如実に表れている。同じスマトラという一つの島をとっても,ガヨ族,ニアス族,バタク族は父系制の社会で,出自および財産相続も父方を通して行われる。しかし中央スマトラのミナンカバウ族やスメンド族は母系制の社会であり,東スマトラ沿岸のマレー人は双系制の社会である。ちなみに他の主要なインドネシア諸種族のうち,バリ族は父系制,ジャワ族,スンダ族は双系制,中部カリマンタンのダヤク族の一部は父方・母方のいずれを通じても出自をたどれる選系制の社会である。
農村に対比される都市の発展は,1945年の独立以降とくに顕著である。オランダ植民地時代以前では,古くはパレンバンやジャワ島北岸の港市のような商業都市が栄え,内陸部ではマタラム・イスラム王国のスラカルタやジョクジャカルタ のような宮廷都市が発達した。オランダ植民地支配の完成期である19世紀になると,バタビア(現,ジャカルタ),バンドン,スラバヤのような大都市が拡大,発達し,さらに行政・教育あるいは商業中心地としての地方都市も発展するにいたった。しかし商業作物栽培,プランテーション 経営を中心とする重商主義的従属主義の植民地政策のもとでは,都市の発展にもおのずと限界があった。インドネシア独立後の都市の発達は著しく,人口100万以上の都市は,ジャカルタ(916万。1996。以下同),スラバヤ(270万),バンドン(237万),メダン(191万),パレンバン(135万),スマラン(135万),ウジュン・パンダン (109万)の7都市がある。
都市はあらゆる意味で多様なインドネシア社会の縮図である。都市住民の大多数は地方からの流入者で,さらに中国人,インド人,アラブなども,インドネシア国籍取得者・非取得者の別なく都市に多く居住している。都市居住民の生活には,インドネシア語の日常的使用,核家族結合の優位,消費文化の浸透といった相似通った生活様式がみられる。貧富の格差も農村に比べると激しい。
都市居住がもたらす生活様式の一様化への傾向にもかかわらず,都市居住者はおのおのの出身地域のアダットと無縁の生活を送っているわけではない。例えばジャカルタ在住のミナンカバウ族,バタク族,メナド族などは,出身地域,ときには出身村別の同郷組織をつくっており,同郷人としての親睦を深めるとともに,冠婚葬祭に伴うアダット儀礼の都市での遂行,相互扶助,インフォーマルな婚姻の規制,出身村との関係の緊密化をはかっている。出身地別のある程度の職業分化や都市内居住地域の分化も見られる。このような傾向は地方出身者だけでなく,ジャカルタのバタウィ族のように都市そのものを出身地とする人々の間にも見られる。都市化の進行は,インドネシア社会の多様性を必ずしも払拭するものではない。
オランダ植民地時代,インドネシア社会の多様性に対する行政側の対応は,多様性を分割統治のための道具として利用する一方,他方では多様性の一元化を目指すものでもあった。アダットからまず刑法に関するものが分離され,オランダ司法機関の管轄下に置かれた。他の法領域の一元化をはかる前提として,アダットの体系的編纂も企てられたが,オランダ法学者の反対もあり果たされなかった。近年の同様の趣旨の試みとしては,スハルト政権下における婚姻法の制定や,村落行政機構の一元化への動きがあげられる。けだし国是〈多様性の中の統一〉は,インドネシアの社会が直面する現実と理想を象徴している。加藤 剛
歴史 赤道を中心として,東西約5100km,南北約1900kmに及ぶ広大な境域に点在する大小約1万3700の島々からなるインドネシアは,世界最大の群島国家である。インドネシアは面積で東南アジア全体の約43%,人口で東南アジア総人口の約40%を占めているから,東南アジアの超大国でもある。この国家が現在のような形で成立するに至る過程はきわめて複雑であるが,その歴史は次の四つの時期に大別することができる。第1期はヒンドゥー・ジャワ王国が興亡を繰り返す15世紀末ころまでの時期,第2期はイスラム王国が成立する16世紀からオランダによる植民地支配が今日のインドネシア全域に及ぶ19世紀末までの時期,第3期はインドネシア民族主義運動が開始され独立宣言が発せられる20世紀前半までの時期,第4期はインドネシアが独立国家として成立してから今日に至るまでの時期である。以下に各時期の歴史の主要な流れを概観してみよう。
ヒンドゥー・ジャワ王国の興亡 インドネシア語で祖国のことをタナ・アイルという。タナは土を意味しアイルは水を意味するから,字義通りには祖国とは〈土と水〉のことである。これはインドネシアが海(水)の世界と野(土)の世界という二つの世界から構成されていることを示していると考えることができる。海の世界とはスマトラ島のマラッカ海峡沿岸やジャワ海沿岸に代表される地域で,ここは海上交通によって古くから互いに往来が行われていただけでなく,海上交易によってインドネシア以外の地域とも結びついていた。ここは水路と海路で結ばれてきた世界である。これに対して野の世界はジャワ島内陸部の平地に代表される地域で,ここは古くから稲作農耕民が定着してきた人口支持力の高い世界である。インドネシアの歴史はこのうち海の世界を窓口として外来の文物,文化,制度を受け入れ,それが野の世界に根づいて開花するという形で進展してきたということができる。
現在の住民の祖先は,前2500年ころから前1500年ころにかけて中国雲南地方からインドシナ半島を数次にかけて南下し,この地に渡来したといわれている。後1世紀ころからインド文化の影響を受け,ヒンドゥー教,サンスクリット文化,ヒンドゥー的統治制度がもたらされ,後には仏教も伝来した。そしてこの時期以降さまざまな王国が興亡を繰り返した。4世紀末ころのクタイ(東カリマンタン)の碑文,5世紀半ばころのタルマ国(西ジャワ)碑文などの発見により,これらの場所に王国が存在したことが想定されている。その後7世紀半ばにパレンバン付近を王都として成立したスリウィジャヤ 王国はマラッカ海峡を押さえ中国,インドとも交流し盛衰の波を繰り返しながら14世紀まで存在した。スリウィジャヤは仏教国で,仏教布教の一中心地を形成していた。また8世紀以降ジャワ島中部には仏教国シャイレンドラ とヒンドゥー王国マタラム が興り,ボロブドゥール 石仏寺院やプランバナン 寺院群など多くの石造の宗教建築が建立された。その後王国の興亡の中心はジャワ島中部からジャワ島東部へ移行するとともに,王国の性格もヒンドゥー的性格とジャワ古来の諸要素が混交する傾向が強まっていった。東部ジャワでは10世紀初めにクディリ朝 が興り,13世紀初めまで存続した。その後マラン平原にシンガサリ 王国が興ってマドゥラ島やバリ島にまで勢力を伸ばした。この王国の末期に元軍のジャワ侵攻が行われたが,これを撃退しモジョケルトを王都として1293年に成立したマジャパイト 王国は,その後2世紀半にわたって威勢を誇った。ことに14世紀半ば第4代王ハヤム・ウルク と宰相ガジャ・マダ の時に全盛期を迎え,インドネシア各地に勢力圏を広げた。マジャパイト王国 の時代は,一方でジャワ商人,マレー商人が中国・インド商人と混じって活発な貿易活動を行った時代であり,また,中東部ジャワの平地部で稲作を基礎とする農業社会が発展した時代でもあったから,この王国は先の海の世界と野の世界を包括する大帝国であった。また,この時代までに,ジャワ古来の稲作文化とヒンドゥー・仏教文化が混交してヒンドゥー・ジャワ文化と呼ばれる今日のインドネシア文化の基層が成立し,王宮(クラトン )を宇宙の中心とする王国理念が成立し,影絵劇(ワヤン )に代表される独自の伝統芸能が確立した。
イスラム化と植民地化 インドネシアのイスラム化は13世紀ころから始まるとされるが,15世紀半ばころからはジャワ北岸の交易都市の有力者の中にしだいにイスラム教を信奉する者が現れ,マジャパイトと対立するようになった。こうしてしだいに盛時の威勢を失いつつあったマジャパイト王国は1520年ころにはまったく滅び去った。ジャワ北岸から始まったデマック,ジャパラ,ジャパン,パジャンなどのイスラム王国は徐々にジャワ内陸へ向かって浸透してソロ平原を押さえ,1582年にはセナパティ がマタラム・イスラム 王国を建てて王都をソロ(スラカルタ)付近においた。これがジャワにおける本格的なイスラム時代の始まりである。
イスラム王国の成立に踵を接するようにして,16世紀以降,モルッカ諸島の香料を求めてこの地域にやってきたポルトガル,スペイン,オランダ,イギリスの諸国はインドネシア海域で激しい勢力争いを演じた。この中で勝利を収めたのはオランダである。オランダは1596年にジャワ海に現れ,1602年には交戦能力を備えた貿易独占会社であるオランダ東インド会社を成立させ,19年にはバタビア(ジャカルタ)をインドネシア海域における貿易活動の根拠地と定め,その後相次いでモルッカ海の要衝の地を攻略して要塞を築いていく一方,この海域の制海権を握った。こうしてオランダは香料貿易を独占することとなったが,それは,航路と港湾を制する〈海域支配〉を実現していくことを意味した。
1628年と29年にマタラム王スルタン・アグン はバタビアのオランダ軍を攻撃したが敗退し,逆にそれ以降オランダの支配権はジャワ内陸へ向かって拡大していった。1749年,オランダはマタラム王国の後継者争いに介入し,これをソロ(スラカルタ )とジョクジャカルタ に分裂させた。この両国は19世紀初めまでにそれぞれがさらに2王家に分裂して,マタラムの領地は削減されその統一的な力は失われた。99年にオランダ東インド会社は経理乱脈の果てに倒産し,19世紀に入るとともに植民地経営は直接オランダ政府の手にゆだねられた。19世紀の前半はナポレオン戦争の影響で一時親フランス派のダーンデルス が総督に,次いでイギリス人ラッフルズ が植民地の支配者となった。東南アジア地域の英蘭の勢力分野はその後1824年の英蘭協約 により確定され,オランダはマレー半島を放棄する一方,スマトラ全域の支配権を掌握した。オランダは30年以降ファン・デン・ボス 総督のもとで〈強制栽培制度 〉を施行し,ジャワの土地と農民支配を本格的に開始した。圧制の典型として後世に伝えられるこの制度のもとで,農民は小説《マックス・ハーフェラール 》(ムルタトゥーリ作。1860)中に描かれるような責め苦にあえいだが,オランダ本国はことにコーヒー栽培を通じて莫大な富を獲得した。またこの制度を通じてジャワでは熱帯商品農産物の生産が本格的に行われるようになり,70年には〈土地二法〉(〈農業法〉)が制定されて土地の全面的調達が保障されるとともに,オランダ産業資本が農園企業に向けて大量に投下されるようになった。
19世紀のインドネシアは強制栽培制度に集約されるオランダの収奪体制がジャワにおいて完成する時期であるとともに,先の英蘭協約によって保障された支配圏に実効支配を樹立するためにジャワ以外の諸地域において一連の征服戦争が行われた時期であった。パドリ戦争 ,バリ戦争 ,アチェ戦争 などがそれであり,オランダは20世紀初頭までに今日のインドネシアの全域を平定してオランダ領東インド という一大植民地を出現させた。このことは先の〈海域支配〉の完成の後に陸地の全域を支配下におく〈領域支配〉が実現したことを意味した。これは支配下の領土と領民(面積と人口)がある特定の数量で明示されることを条件とする支配であり,今日のインドネシアが領域国家として成立するための外縁が設定されたことを意味していた。このオランダ領東インドという領域の内部では,バタビアを中心とする軍事・行政・産業・交通・通信・教育などのネットワークが樹立され,人種差別に基づく植民地的二重性に貫かれた〈秩序と安寧〉が維持されることになった。
インドネシア民族主義 20世紀に入るとオランダは〈白人の責務〉(イギリスの作家キップリング)という観念のオランダ的表現である〈倫理政策 〉とよばれる植民地政策を採用した。このなかで,農園と官庁における原住民下層書記官・官吏層の創出はとくに重視され,このためオランダ語の教育と法学・医学をはじめとする専門教育が必要とされた。とりわけ教育の対象とされたのはジャワの貴族階層(プリヤイ )の子弟であった。彼らは植民地官僚制の担い手であるとともに,著名なイスラム学者ヒュルフローニェ の思想にみられるような,19世紀末までに達成した軍事制圧の基礎の上にオランダ語と西欧文化の流入を通じて本国と植民地民衆の強固な精神的一体化をめざすパクス・ネーエルランディカ (パクス・ブリタニカ に拮抗する〈オランダの平和〉と〈オランダ的秩序と安寧〉)を実現するための,原住民側の相手方として役割づけられたのである。
しかしそれとは逆にこの倫理政策を通じて住民の間にはオランダ領東インドという領土をインドネシアという一体的な領域としてとらえなおし,オランダ領東インドを支配している植民地的秩序を解体してこの同じ境域に新しい独立国家を樹立しようとする自覚がめばえ始めた。この独立国家はインドネシアとして想定され,この境域内の住民はインドネシア民族であると想定された。また独立国家を担う政体の正統性は従来の王国のように王や王統に基づくのではなく,〈人民の意思〉に基づくべきものであると想定された。さらにマジャパイトに象徴されるかつての王国の栄光やディポネゴロ 戦争,アチェ戦争 などの武力抵抗の歴史が想起された。これらはすべてインドネシアという未来の共同体を創出するための営為であり,それがインドネシア民族主義であった。しかしその歩みは苦難にみちていた。
1908年には最初の民族的な組織としてブディ・ウトモ がバタビア医学校の生徒を中心に結成された。11年以来ジャワ各地で組織され12年ソロでイスラム同盟 として結束したイスラム商人を中心とする民族組織は,チョクロアミノト の指導下に10年代を通じて同盟員200万人に達したといわれ,イスラムをシンボルとする民族的団結と農園労働の待遇改善を要求して植民地政府に深刻な脅威を与えた。一方,オランダ人社会主義者スネーフリート のもとに,14年以来東インド社会民主主義同盟として組織されていた左派人士は,イスラム同盟内で支持者を拡大して20年にインドネシア共産党 を結成し,以後20年代を通じてイスラム同盟をしのぐ最大の反政庁勢力となった。26年末から27年にかけてその共産党指導下で西スマトラ,西・東部ジャワの民衆は蜂起した。これは全国的規模をもち植民地全体の解放をめざす民族蜂起であった。政庁はかねてからセマウン ,タン・マラカ ,ムソ らの共産党指導者を逮捕・追放していたが,蜂起とともにさらに弾圧を加え2000名に及ぶ共産党と人民同盟(共産党傘下の大衆組織)の指導者を,西イリアンの湿地帯タナ・メラに政治犯抑留キャンプを設置して追放した。こうして共産党が壊滅した後に民族運動の表舞台に登場するのは,オランダから帰国した留学生を中心とする知的エリート層である。彼らは27年にスカルノ を党首とするインドネシア国民党 を結成し〈ムルデカ(独立)〉の合言葉に象徴される民族主義を鼓吹した。民族主義精神の高揚は翌28年10月に〈青年の誓い〉が採択されて,インドネシアというただ一つの祖国・民族・言語が高らかに宣言されたことにもよく示されていた。しかし国民党も29年末には指導者が逮捕され,31年には解散を余儀なくされた。30年代に入ると植民地政府の民族主義に対する対応はいっそう強圧的になり,国民党の後身であるパルティンド と民族教育協会をはじめとする独立を主張する非協力政党の活動は,指導者の相次ぐ逮捕や集会制限・禁止などの措置によって次々と封じ込まれていった。民族主義は全体として協調主義に移行していき,39年にはタムリン らの指導下でこれらの諸組織の合同体としてガピ (インドネシア政治連合)が結成された。とはいえ,民族主義のエネルギーは分散され,強力な反植民地運動が組織されることはなかった。
そのようななかで時代は突如として日本軍政に入っていった。42年蘭印(オランダ領東インド)軍を降伏させた日本軍は3年半にわたって軍政をしき,〈大東亜戦争〉完遂のために,短期間のうちに大量の各種資源,農産物などの戦争用物資と戦時労働力の調達を図る一方,兵補・義勇軍のような軍事組織,隣組・警防団のような民間組織を通じて軍事技術と闘争精神の注入を図った。また,軍政下で組織されたプートラ(民族総力結集運動。1943年3月より開始),ジャワ奉公会 (プートラに代わって1944年3月に組織)のような大衆運動,イスラム教徒の組織化(マシュミ,ミヤイなど)は,官製のものであったが,民族独立の希求を広く社会の全般にわたって高めていくことになった。さらに戦況の変化と独立希求の高まりにより,45年3月には独立準備調査会が設置された。こうして日本が降伏した2日後の45年8月17日,スカルノが独立宣言を読み上げ,独立インドネシアの誕生が告げられたのである。
インドネシア共和国 1945年以降のインドネシア政治史は,45-49年の独立戦争期,50-59年の憲政期,59-65年のナサコム体制期,66年以降の〈新体制〉期の4期に分けることができる。
独立戦争期は,再植民地化をもくろむオランダに対してインドネシアが武力抗争を展開した時期である。この間,軍政期に成立の基礎をおくインドネシア国軍はスディルマン 将軍のもと,45年11月のスラバヤの戦をはじめとして各地で不屈のゲリラ戦を展開した。国際世論もインドネシアを支持し,49年12月のハーグ協定 によりインドネシアは名実ともに独立を獲得した。
50年に政党政治に基礎をおく50年憲法が発布され,以後58年末まで各種政党内閣が国政を担当した。55年には最初の総選挙が実施され,国民党,マシュミ党 ,ナフダトゥル・ウラマ 党,共産党の4政党が主要な政党として国民の支持を集めた。またこの年,中国,インドをはじめとする史上初のアジア・アフリカ会議 が29ヵ国出席のもとにバンドンで開かれ,自由独立・平等互恵の〈バンドン精神〉(バンドン会議)が新興諸国間で広く承認された。
しかし50年代において政党政治は不安定であり,経済建設をはじめとする課題を解決しえないことが露呈されていった。その中でスカルノ 大統領は軍と共産党の支持のもとに59年,〈1945年憲法〉への復帰を宣言して独裁権を強め,これ以後大統領内閣が組織された。スカルノ は民族主義と宗教と共産主義を打って一丸とする挙国体制(ナサコム)のもとに,反マレーシア闘争(1963以後),国連脱退(1965年1月)など一連の反帝闘争を強化する一方,中国への接近を強めて北京-プノンペン-ジャカルタ枢軸といわれる外交路線を敷いた。60年代に入ると〈ナサコム〉という標語にもかかわらず,インドネシアの政治動向を決定する勢力はスカルノと国軍(ことに陸軍)と最大最強の大衆組織である共産党の三つである,という様相はますます強まった。とくにスカルノの健康がうんぬんされるにつれ,それ以降の権力掌握をめぐる軍と共産党の対立,イスラム系をはじめとする諸政党と共産党の対立は緊張の度を強めた。一方,たび重なる政治闘争は膨大な対外債務,全般的な生産の停滞,急激なインフレーション の進行をもたらして国内経済を疲弊の極に追いやっていた。
政治勢力間の対決は65年9月ついに爆発した。九月三〇日事件 を契機にこの事件の背後にあるとされた共産党勢力はスハルト 少将を先頭とする陸軍により徹底的に鎮圧された。スハルトは67年にスカルノ退陣を迫る軍内強硬派,学生行動戦線(カミ)らに推されて大統領代行となり,翌68年3月には正式に第2代共和国大統領に就任した。スハルト政権は〈開発〉を国家目標とする〈新体制(オルデ・バル)〉を掲げ,外国援助・外資導入をてことする経済開発政策と西側諸国との関係を修復する外交政策を推進した。スハルトを中核とする軍勢力は71年以降,98年1月まですべての総選挙に圧勝してきた。土屋 健治 編集部
政治,外交 政治 インドネシア共和国は,強力な大統領と軍部と中央集権的な官僚制に支えられた権威主義官僚制国家ということができる。しかし,1990年代に入って,市場経済化,情報のグローバル化の進展の中で,民主化の流れが必然のものとなり,権威主義体制に揺らぎが生じはじめているのも事実である。
インドネシア共和国の国章であるガルーダ(神鷲)の絵模様は国是を象徴している。鷲の翼,尾翼,胸,足の羽根の数は,独立した1945年8月17日の数字に合わせてそれぞれ19,45,8,17枚描かれている。胸の中の五つのシンボルは国是であるパンチャ・シラ (建国五原則)を表している。唯一絶対神への信仰(星),公平で文化的な人道主義(鎖),インドネシアの統一(榕樹),協議と代議制を通じ英知に導かれた民主主義(野牛),全人民に対しての社会正義(稲と綿)。鷲のつかむリボンには〈ビンネカ・トゥンガル・イカ(多様性の中の一体)〉という標語が書かれている。政治は,時の統治者による解釈に違いがあるにせよ,基本的には1945年に定められたパンチャシラと憲法(1945年憲法)によって営まれている。
憲法上インドネシア共和国の最高の国権機関は国民協議会(MPR)である。MPRは憲法,国策大綱を制定し,大統領・副大統領を任命する。このMPRは国会議員500名と,選挙によらない大統領任命議員500名とからなる。原則として5年に1回行われる総選挙は国会議員,州議会議員および県議会議員を選出する。国会議員500名のうち,1997年の選挙では425名が選挙で選出され,残り75名が大統領に任命された国軍出身者であった。この大統領任命議員は以前は140名にも達したが,漸次削減されてきている。現在,立法府である国会に立候補できるのは,法で定められた3会派だけである。つまり,ずっと与党でありつづけているゴルカル (職能グループ,公務員主体の組織),イスラム系の開発統一党(PPP),民族主義派とキリスト教との統一党であるインドネシア民主党 (PDI)の3会派である。任命議員の多いこと,政党の制限などから民主主義的でないとの批判も根強くある。現スハルト 大統領は1968年に就任,72,78,83,88,93年と過去6回のMPRで大統領に選出され,98年には無投票で7選,任期30年をこえる長期政権になる。
こうしたスハルト長期政権に対しては過去さまざまな批判があったが,政権を覆すような大きな動きとはなっていない。人々の声を国政に反映させることのできる政治的回路の未成熟と,それを成立させない権威主義体制による抑圧とが指摘されている。しかし96年,インドネシア民主党のメガワティ総裁(スカルノ前大統領の娘)の権力的解任と民主党本部襲撃事件は,民主派を勢いづかせ,各地で未曾有の暴動事件を生み出し,スハルト長期政権に暗雲を立ちこめさせている。
国軍(陸・海・空・警察の4軍)は二重機能論に基づき,いまだに国民の政治・経済・社会生活に深く関与し,高級官僚(閣僚,地方政府など)にも就任している。しばらくはインドネシア政治にとっての国軍の役割を無視することはできないだろう。司法機関には普通裁判所,宗教裁判所,軍事裁判所,国家行政裁判所,そしてそれに対応する検察庁がある。裁判においても政治への従属を嘆く声が聞かれる。またマスメディアをはじめとした言論統制も厳しく行われ,政府に批判的な記事を書くと出版許可証が取り消されることもしばしばある。このようにインドネシア政治は民主主義とは相容れない状況が濃厚にあるが,環境運動,人権運動などに関わるNGOも成長しつつあり,また経済のグローバル化も進展しつつあり,21世紀には大きな変動期に入っていくものと思われる。
外交 インドネシアはこれまで一貫して〈自主的で積極的な外交〉および〈非同盟外交〉をスローガンに外交を展開してきた。しかし,スカルノの時代と,現スハルトの時代では外交姿勢が非常に異なっている。スカルノは自ら非同盟外交を成功させ(1955年のバンドン会議,61年に成立した非同盟諸国会議への参加など),その勢いで反西側の容共外交を展開した。スハルトは自主的・積極的・非同盟外交を継承したとはいえ,反共外交に転じたのである。経済開発を優先し,西側の債権国会議(IGGI,現在はCGI)に依拠し,世銀・IMF体制化で巨額の援助を取り込み,外資を積極的に取り入れることによって開発の成果を生み出すことに専心した。また一方で,地域の大国を意識し東南アジア諸国連合 (ASEAN)の強化をめざし,事務局をジャカルタに置く,ベトナムやビルマ(現,ミャンマー)の加盟に積極的に動くなど,地域的なヘゲモニー確保にも顕著な働きをしてきた。アメリカ,日本とはとりわけ緊密な政治経済関係を取り結び,アメリカからは武器を購入し,軍事教育訓練も受けている。非同盟外交も健在で,1992年には自ら議長としてジャカルタで非同盟諸国会議を開催している。また,94年にはアジア太平洋経済協力会議(APEC)をボゴールで実現させ,地域の大国としての存在をアピールした。しかしながら,東ティモールの武力併合と最近までも頻発する住民虐殺・抑圧の事実は,いまだに国際社会から反発を招いており,インドネシア外交の最大の弱点となっている。強権的な,また腐敗した政権に対しては国内外で反発の声が高く,インドネシア外交も21世紀にはやはり転換期を迎えることになるだろう。村井 吉敬
経済 人口2億人,面積日本の5倍のインドネシアは,石油,天然ガス,ニッケル,銅,木材などに恵まれた潜在的な経済大国といえる。スハルト政権は1960年代末から,外国資本に依存しつつ強力な開発政策によってインドネシア経済のパイの拡大,工業化に向けての産業構造変革を図ってきた。紆余曲折はあるものの,経済は順調に拡大し,工業化もかなり進展してきた。しかし97年,タイの通貨危機はインドネシアにも及び,膨大な対外債務,非効率的な大規模開発プロジェクト,スハルト・ファミリーの経済のあらゆる部門への参与などが問題化し,IMFによる監視下のもと経済再編を迫られている。
独立後のインドネシア経済は,主要産業部門である石油など鉱業部門,およびプランテーション部門をオランダ,アメリカなど外資に抑えられた植民地経済構造の状況におかれていた。スカルノは〈反新植民地主義・反帝国主義(NEKOLIM)〉の標語のもと,国有化・外資接収の政策を実施した。しかしながら強引な社会主義的経済政策はことごとく失敗し,インドネシア経済は,スカルノ失脚の原因になった1965年の九月三〇日事件当時には破局的状態にあった。スハルト新体制は経済建直しのため,欧米帰りの経済テクノクラートを閣僚に迎え,IMF・世界銀行,アメリカ,日本を中心にした西側陣営の援助,資本を積極的に取り入れ経済再建に乗り出した。具体的には,67年に発足したインドネシア援助国会議(IGGI,1992年からインドネシア援助協議グループCGIと名称を代えた)からの公的援助,および同年より発効した外国投資法にのっとり,外資企業の投資を積極的に受け入れることによる経済の活性化,開発の推進である。1968年から第1次五ヵ年開発計画を実施し,当初は基礎物資の確保,食糧増産を目標にしたが,しだいに石油,ガスに依存しない製造工業の強化,産業の高度化をめざす計画へと姿を変え,25年後の1993年には工業国へのテイク・オフをめざしたが,それにはまだ時間を要すると思われる。
たしかに経済のパイは大きく拡大し,1965年当時100ドル内外だった1人当たりGNPは95年には980ドルにまでなった。東南アジアではシンガポール,ブルネイ,マレーシア,タイ,フィリピンに次ぐ位置にある。産業構造も大きく変化し,国内総生産に占める製造工業の割合は1970年8.9%,80年13.6%,90年20.5%,96年24.6%と大きく拡大した。輸出品目を見るとよりドラスティックな変化が見てとれる。1976年,全輸出額85億ドルのうち原油・LNG・石油製品が70.2%を占め,これに木材,天然ゴム,コーヒーを加えると87.4%にもなっていた。工業製品輸出比は数%しかなかった。96年には全輸出額498億ドル,原油・LNG・石油製品の比率は23.5%にまで低下し,工業製品輸出比率が64.5%に達している。すでに工業国といえるような水準である。主要工業製品は繊維製品,木材加工品(主に合板),電子電機製品,皮革製品(靴など),鉄鋼・機械などである。
このような経済活動の拡大と産業構造の変化は,巨額の外国援助(特に世界銀行と日本)による経済インフラストラクチャー(ダム,道路,港湾など)の建設と民間外国資本の投下によるところが大きい。国内的には政府による開発投資,民間企業による投資の拡大もあった。特に,大統領やそのファミリー,政府高官と結びついた華人財閥の成長と投資を見逃すことはできない。しかしながら,外資依存体質,華人偏重体質はインドネシア経済の姿を歪め,社会的な不満を招いている。対外公的債務は95年までに1071億ドル(長期公的債務654億ドル,長期民間債務201億ドルなど)に達し,輸出総額に占める債務返済額・利子支払額の比率は42.4%にも達し,かなり危険な水準になっている。
70年代以降,外国資本に支えられつつ,強力な開発政策によって,インドネシア経済は大きく拡大し,工業化を達成してきた。近年は,航空機生産,国産自動車生産も手がけてきているが,解決されるべき問題も多々ある。所得の階層間格差,地域格差は以前よりも広がり,大量失業の問題も解決されていない。また米の自給を一時は達成したものの,米価の低価格維持により農民の米離れ傾向を招き,近年,再び輸入国に転じた。ジャワ島の過剰人口を解決するために行われている国策移住政策(トランスミグラシ)は,移住地の住民とのトラブルを起こし,また森林の乱開発にもつながっている。市場経済化の進展は商業作物の重視を促し,アブラヤシ農園などの大規模開発につながり,それが森林火災の原因にもなっている。多くのインドネシア住民にとって,真に望まれているのは住民本位の環境との調和を図った経済づくりであろう。村井 吉敬
教育,文化 現代の教育制度は,6・3・3制の上に5年制の大学と種々の短大があり,小学校と中学校の計9年間は義務教育化されている。1960年代後半以降,〈開発の時代〉の進展に伴って,教育政策が重視され,また教育への関心が社会全般に高まってきた。これを小学校の学校数,教員数,生徒数で示すと,1960年にそれぞれ,3万7673校,23万0633人,895万5098人であったのが,92年にはそれぞれ14万8257校,127万6217人,2959万8790人と著増している。また初等教育の就学率も,1950年の39%,61年の59%から77年には81%,94年には94%と増加してきている。こうして1995年には識字率(15歳以上)も83.8%に上昇し,教育水準は徐々に向上してきている。とはいえ,大学への進学率はまだ10%(1992)である。
1960年代後半からは,カセットラジオ,テープレコーダー,テレビを中心とする視聴覚消費財および,新聞・雑誌などの出版市場が一気に拡大し,ジャカルタを中心とする新しいファッション,歌謡曲,芸術活動,小説と詩などが全国の各地に浸透した。しかしこの結果,各地方の伝統的文化がただちに衰退するのではなく,逆に新しい表現の様式をえて,より全国的に受容されていくという傾向を示した。この意味で現在の文化は,地方とセンターの,また伝統と現代の諸要素が相互に作用し合う状況にある。土屋 健治
文学 ここにインドネシア文学 と呼ぶのは,独立インドネシアが憲法で国語と定めているインドネシア語による文学である。
インドネシアには,ジャワ語をはじめとして200を超す地方語(種族語)があるといわれる。それらの言語による文学は,地方語文学またはヌサンタラ文学と呼んで,インドネシア文学とは区別している。最も古く最も豊かな文学遺産をもつ地方語文学といえば,10世紀にさかのぼる歴史を誇るジャワ語文学である。なおヌサンタラ文学という名称には,インドネシア文学とマレーシア文学をまとめて指す用法もある。
インドネシア語 の前身は,古くからこの島嶼世界において共通語としての役割を果たし,オランダ領時代には準公用語として用いられたマレー語であった。今日のインドネシア語は,この共通語としてのマレー語が,20世紀初頭に始まるオランダ領植民地下の民族的覚醒の中で,〈わが祖国インドネシア〉の言語,〈インドネシア語〉と呼ばれ,〈インドネシア民族〉の自己表現を担う言語として発展してきたものにほかならない。そのようなインドネシア語による文学としてのインドネシア文学の開始も,この若きインドネシア民族の民族的自覚の歴史の中に求められることになる。具体的にはG.フランシスの《現地妻ダシマ》(1896),F.D.J.パンゲマナンの《野盗チョナット物語》(1900)など,世間の語り草となった事件を当時の植民地社会の共通語であったごく通俗的なマレー語で描いた,19世紀末から20世紀初頭にかけての小説をいわばその誕生前夜の文学としながら,インドネシア文学は1920年代に成立したと考えられる。アブドゥル・ムイスAbdul Muisの《サラー・アスハン(西洋かぶれ)》(1928)はこの期の代表的作品である。この小説の中で,民族主義者でもあった作者は,主人公と欧亜混血女性コリーとの結婚をテーマにして,村を捨て去りながら結局オランダ人社会にも入れられず破滅する西洋かぶれの青年官吏の悲劇を描いている。この作品は,健全な良書を供給することを任務とした政府機関バライ・プスタカ (図書局)から出版されたが,同局はコリーの描き方に手直しを求めて出版したという。
本格的な文学運動が始まったのは,新しいインドネシア統一文化の創造を目指す文学雑誌《プジャンガ・バル (新詩人)》(1933-42)の創刊によってであった。同誌を舞台に,主宰者の一人アリシャバナ が西欧合理精神の旗手として,土着伝統派との間に闘わせた論争は,文化論争の名で有名である。彼の《ラヤル・トゥルクンバン(帆を上げて)》(1936),アルミン・パネの《桎梏(しつこく)》(1940),アミル・ハムザの詩集《孤独の歌》(1935)などが,この《プジャンガ・バル》の代表的作品である。バライ・プスタカは,主人公の医師とその妻と愛人の三角関係を描いた《桎梏》を,不道徳な読み物であるという理由で出版を拒否し,同作品は《プジャンガ・バル》に発表された。
1942年からの日本軍政,続く45-49年の独立戦争という激動する時代の中から,〈45年世代〉と呼ばれる作家たちが生まれた。20年代作家,《プジャンガ・バル》作家が理想主義的,啓蒙主義的な作品を書いたのに対し,彼らは普遍的人間主義を基調に苛烈な現実の中に生きる民衆の姿を簡潔な文体で描いた。この時代の代表的作品には,インドネシア最大の作家と称されるプラムディア・アナンタ・トゥル の《ゲリラの家族》(1950),《ブロラ物語》(1952),主として短編を書いたイドルス の《地下の記録》(1948),インドネシア革命の渦中で苦悩する知識人を描いたモフタル・ルビス の《果てしなき道》(1952),そして国民的詩人ハイリル・アンワル の詩集《埃の中の轟き》(1949)などがある。1950年代後半から60年代前半にかけての〈ポスト45年世代〉とでもいうべき時代には,〈民衆のための芸術〉〈芸術のための芸術〉を巡って両派の対立が激しく,短編小説を多く生み出したにすぎない。
スカルノ体制下の政治イデオロギー優先の時代が65年の九月三〇日事件により突如幕を閉じた後,現代文学では新旧両世代のさまざまな傾向の作家の活躍が見られる。前述のプラムディア・アナンタ・トゥル,モフタル・ルビス,アリシャバナら長老が長編小説の発表によって健在ぶりを示す一方,イワン・シマトパン,女流のディニ,バリ島出身のプトゥ・ウィジャヤ,最も新しい世代のユディスティラ,詩人で演劇界のリーダーのレンドラ,評論のグナワン・モハマッド,アイップ・ロシディ,スバギオ・サストロワルドヨらが活躍している。現代人の疎外をテーマにしたもの,不条理主義的手法を取り入れたものなどが新しい流れである。回想録,伝記,大衆小説も多く出版されている。佐々木 信子
美術 インドネシアは多島国家であるが,歴史的に美術を考える上では,ジャワ島が中心となり,さらにスマトラ島とバリ島が従として取り上げられてきた。美術史上の時代区分は大きく2期に分けられ,いわゆる〈中部ジャワ期〉(8~10世紀)と〈東部ジャワ期〉(10~15世紀)とである。前者は仏教美術が主体で,きわめてインド的な性格が濃い。それに対し,後者はヒンドゥー教の美術が主で,インドネシア独自の土着的な性格が顕著となる。この両時代を一般に〈古代インドネシア美術〉と称し,それ以降の美術はあまり注目されない。それは16世紀以降,イスラムが浸透したため,造形活動が弱まり,古代インドネシアの伝統美術がまったく衰退したからである。
インドネシアの美術は,一般にチャンディ と称する遺構に伴って残存している。チャンディとは祖先の霊をまつる霊廟にあたるが,火山岩の切石を積み上げて建てた寺院建築である。この寺院に安置された石彫の神々(ヒンドゥー教)や仏像が,古代インドネシア美術のほとんどをなしている。その他,青銅製の品々も出土しているが,それらのほとんどは青銅像をはじめとし,祭儀用の器具・容器などである。先の石造の彫像は遺跡の内部に,あるいはジャカルタ国立博物館を中心に見ることができる。さらに青銅製の品々も,同じ博物館もしくはジョクジャカルタのソノブドヨ国立博物館に展示されている。
先述のように,インドネシアの美術はおもにヒンドゥー教と仏教に奉仕したもので,そのためそれら両宗教の発祥地であるインドから,美術も多くの恩恵をえている。とくにこのインド的な性格の濃い時代は,8世紀より10世紀ころまで続いた。この時代の美術(中部ジャワ期)の中心はジャワ島中部にあり,この地域には8~9世紀にかけてシャイレンドラ王国が栄え,大乗仏教(密教)のチャンディ建築が多く建てられた。これらの遺構はジョクジャカルタ北方にあり,ボロブドゥール 遺構群やプランバナン 遺構群は,当時の仏教美術を知る上での重要な遺跡となっている。当時の美術のインド的な性格は,例えば,彫刻における一貫して穏やかな丸味のある肉付けをもった表現に見られる。また仏教の図像は,北東インドのパーラ朝との関係が従来推定されてきたが,最近ではむしろ,西インドのデカン高原の石窟寺院(エローラなど)にその類似性が認められてきている。一方,同時期のヒンドゥー教の彫像としては,チャンディ・バノン出土の三主神(シバ,ビシュヌ,ブラフマー)像の傑作(ジャカルタ国立博物館)が代表的で,これらのヒンドゥー教彫像はおもに南インド美術からの影響を感じさせる。当時のヒンドゥー遺跡としては,ディエン高地 の遺跡があげられ,さらにマタラム王国の霊廟寺院,チャンディ・ロロジョングランは,インドネシアのヒンドゥー教建築として第一の聖殿である。
シャイレンドラ王国を中心とする中部ジャワの美術時代は,政治の中心が10世紀以降,ジャワ島東部へ移るとともに幕を閉じる。そして15世紀まで,東部ジャワに栄えたクディリ朝,シンガサリ王国,マジャパイト王国のもとで,美術は再び花を開くことになる。この東部ジャワの時代の美術(東部ジャワ期)も,チャンディ建築に伴って見られ,宗教はヒンドゥー教と仏教が共存し,さらに両者の混合(時輪教)がなされた。遺跡はスラバヤの南西一帯,ブランタス川の流域に散在し,チャンディ・パナタラン (14世紀建立)は,この時代の代表的な遺構として注目される。石造彫刻は,以前の作品とはまったくその作風を一新し,もはやインド美術の模倣から脱して,ジャワ独自の土着的な性格の強い作風へと変わる。その作風は形式的になり,とくに浮彫は影絵人形を思わせるような平面的なつくりとなる(例えば,チャンディ・スラワナ の基壇浮彫)。またこの基壇を飾る浮彫には,古代インドの叙事詩《マハーバーラタ》の翻案,《アルジュナ・ウィワハ》(1030)や《バラタユッダ》(1157)の物語文学が表されるようになる。したがって東部ジャワ美術は作風が土着的で,文学的色調がきわめて濃い点が特徴といえる。
16世紀以降のジャワ島では,イスラムの浸透によって,これまでのインド伝来の宗教に奉仕した美術の時代は終わる。しかし,バリ島はそのイスラムの浸透から免れえたために,今日までヒンドゥー教が現存し,美術もヒンドゥー的色彩にみちている。また,スマトラ島の美術は,従来スリウィジャヤ王国 の美術として,その王国に関係づけて論じられてきている。ムアラ・タクスの遺跡がその代表で,中部ジャワの美術と同様,インド的な性格の濃い仏像やヒンドゥー教の神像が発見されている。イスラム美術としては,建物の入口の門などに見られる石彫の装飾意匠が注目される。例えば,ジャワ島東部のバジャネガラにあるセンダンドゥウール寺 の入口の石彫浮彫(16世紀)や,マドゥラ島にあるアイル・マタのラツ・イブの墳墓(17世紀)などがあげられる。東部ジャワ期美術の伝統を踏襲し,緻密に刻みこんだ装飾美術である。伊東 照司
音楽,舞踊 この国の地理的条件および幾種類もの外来文化の影響の複雑な混交が芸能の上にも反映され,インドネシアの音楽,舞踊は多様性に富んでいる。その中から一般的特徴をあげると,(1)音楽と舞踊が政治や宗教儀礼の重要な機能をもち,そこから発展した芸能が多い。(2)歴史,社会慣習,思想などの伝達手段の一つとして,宗教的,哲学的な語り物があり,それが舞踊や他の芸術と結びついて,仮面舞踊劇,舞踊劇,影絵芝居,人形劇などの総合芸術を生み出している。(3)2,4拍子が基本的リズムであるが,複数の声や楽器が複雑にからみ合って一種のポリリズム効果を生み出す。この独得のリズム感覚と,集団で音楽を作り上げる傾向が,アジアの他の地域にくらべて合奏音楽をより盛んにしている。その代表的な形態がガムラン である。(4)ジャワとバリを中心とした地域の音楽は5音音階圏に入る。その種々の5音音階の中でペロッグ音階は日本の沖縄音階と,スレンドロ音階は律・民謡音階と,マドゥンダ音階は都節音階とよく似ており,なんらかのつながりを推察させる。しかし,スマトラなど西アジア音楽文化の影響の強い地域の音楽は,7音音階的旋法が優勢で,5音音階圏から外れているといえる。次に地域別にその特徴を見ることにする。
スマトラ 一般に13世紀以降の西アジア音楽文化の影響が顕著で,器楽より声楽の方が優位にあるといえる。マレー語の韻文による年代記ヒカヤットや散文詩パントゥンが,サルアン(笛)やルバーブ(弦楽器)の伴奏で舞踊を伴って歌い語られる。詩の朗唱はイスラム社会において,大きな精神的影響,ときには政治的な影響をももつ。楽器には,東南アジアに共通な竹製の打楽器やゴング類のほかは,ルバナ(片面枠型太鼓),スルナイ,ガンブス(ウード)などがあげられる。ルバナとスルナイを核とする合奏によって伴奏される男性の踊りは,闘技から発達したものといわれるが,恍惚状態にいたる激しいもので,民俗芸能の重要なジャンルをなし,スマトラ以外の地域にも多く見られる。内陸部に住むバタク族はカチャピやタタカナン(音高の異なる複数の太鼓からなる楽器)を用いる。
ジャワ,バリ,マドゥラ 14世紀を頂点とするヒンドゥー・ジャワ文化の伝統を受け継ぐこの地域は,バリ以外ほとんどイスラム化されたにもかかわらず,音楽的にはその影響がほとんどない。ヒンドゥー教の儀礼においては音楽,舞踊の果たす役割は大きく,10世紀以降の文献には宗教的な芸能として,仮面舞踊劇トペン,舞踊劇ガンブ,影絵芝居ワヤン・クリ(ワヤン )などの記述が見られる。金属製の旋律打楽器を中心とする大編成の器楽合奏ガムランが,この地域では最も特徴的である。この種のガムランは音の大きなゴング類や太鼓類を中心とする楽器群(戦闘や宗教儀礼用)と,グンデル,ガンバンなどやわらかい音色の鍵盤楽器群(祖霊供養儀礼用)とを結びつけて,17,18世紀の頃,ジャワとバリの王宮でそれぞれ完成されたものである。声楽に関してはジャワ語の定型詩を一定の朗吟旋律にのせて歌うことが盛んである。この歌の節回しはきわめて洗練されたもので,さまざまな様式で歌われる。
俗にスンダと呼ばれる西部ジャワでは声楽が盛んで,カチャピとスリン,またはカチャピとルバーブの伴奏による独唱トゥンバンが多く見られる。一方,中部ジャワでは,女性独唱と男性斉唱が加わりガムランが器楽と声楽の大合奏として特異な様式に発展した。ガムランは誕生日,結婚式,祝日,記念日などに演奏され,舞踊や他の芸能と結びついて総合芸術を生み出している。なかでもワヤン・クリは重要である。
イスラム化を拒絶したバリはヒンドゥー・ジャワ文化の伝統を直接受け継ぎ,音楽と舞踊は宗教儀礼のなかで重要な一部を担い続けている。とくにその種類は豊かで,高い芸術性を示している。
カリマンタン 内陸部のダヤク族の間では,サペ(撥弦楽器)と,その伴奏によるアニミスティックな色合いをもった男踊りと女踊りが知られている。さらに他の島々とも共通な竹の打楽器と,クレディ(笙の一種)が見られる。歌はあまり重要ではないといわれる。海岸部の部族間では,ゴングと太鼓と竹の打楽器による踊りが知られている。北部ではクリンタン合奏,南部ではジャワのガムランに似た合奏が行われる。
スラウェシ 英雄伝説や年代記などの弾き語り歌や,宗教的内容の歌が重要である。伴奏楽器にはルンバン(長大な竹の竪笛)とケセケセ(二弦の擦弦楽器)が用いられる。南スラウェシのケセケセの伴奏による弾き語りシンリリ,中部スラウェシのトラジャ族のルンバンの伴奏によって歌われるママラカはよく知られている。ルンバンは歌の伴奏のほか,自然の物音や動物の鳴き声などを吹きまねる。パカレナは女性の群舞であるが,ゴングと太鼓と竹の打楽器とわら製のチャルメラの伴奏で踊られ,スラウェシの踊りのなかで最も伝統的で洗練されている。
その他の地域 モルッカ諸島はキリスト教会音楽の影響により古来のものはあまり残っていないが,南東部にはタン・ラインまたはカパタと呼ばれる歴史や慣習を伝承していくための歌がある。また多声部の合唱が知られている。田村 史子