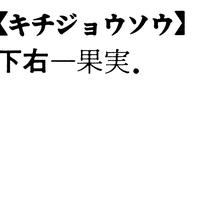キチジョウソウ (吉祥草)
Reineckea carnea Kunth.
日本と中国大陸に分布する1属1種のユリ科の多年草。スズラン属やオモト属に近縁であると考えられており,両者をつなぐ性質をもつ系統学的には興味深い植物である。根茎は長くはい,よく分岐する。根生葉は根茎の末端に叢生(そうせい)し,線形。花茎は秋から冬にかけて伸長し,葉がなく,高さ20cm内外で,斜上する葉にかくれたように咲く。和名はこの植物はめったに花をつけず,花をつけたときには吉事があるという言い伝えに由来すると言われる。このような言い伝えが生まれた理由の一つは,花が秋遅くに咲き,葉にかくれて目だちにくいことによるものであろう。花と花茎は淡紫色で花には両性花と雄花の分化がある。縁起のよい和名のためか,しばしば栽培される。繁殖力もあり,冬緑性なので縁石にそって植え込んだりするのによい。漢方では咳止めと止血の効ありとして薬用とする。
執筆者:矢原 徹一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
キチジョウソウ
きちじょうそう / 吉祥草
[学] Reineckea carnea (Andr.) Kunth
ユリ科(APG分類:キジカクシ科)の常緑多年草。茎は長く地上をはい、その先端の1、2か所の部位より葉を束生する。葉は濃緑色で広線形、長さ10~40センチメートル、幅0.5~2センチメートル、3~5本の平行脈がある。葉間から出る花茎は高さ10~15センチメートル、上部に穂状に花をつける。8、9月に淡紫色で径約1センチメートルの花を開く。花被片(かひへん)は6枚あり、上部は反曲するが、下部は筒状に合着する。両性花と雄花とがある。果実は肉質、球形で紅紫色に熟す。関東地方以西の本州、四国、九州および中国に分布する。
この草はまれにしか開花しないが、もしこれを植えている家に吉事があると花が開くという言い伝えから名づけられたという。
[河野昭一 2019年3月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
キチジョウソウ(吉祥草)
キチジョウソウ
Reineckia carnea
ユリ科の常緑多年草。関東以西から九州,中国に分布する。樹下の陰地に自生するが,庭園にもよく栽培される。茎は地面をはい,ところどころの節からひげ根を生じ,長さ 30cm,幅1~2cmの葉を根もとから叢生する。晩秋,葉の間から短い花穂を突き出し,小さな包葉と花柄とをもつ淡紫色の小花を総状につける。花は6枚の花被片があり,なかほどまで癒合して筒状になる。果実は円形の液果で,紅紫色になり,花茎についたまま越年する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「キチジョウソウ」の意味・わかりやすい解説
キチジョウソウ
関東〜九州,中国の樹林内にはえるユリ科の常緑多年草。葉は長さ10〜40cmの広線形で両端がとがり,長く地表をはった茎に数個つく。秋,高さ10cm内外の花茎を葉の間から出し,径1cmほどの淡紅紫色の花を密につける。花被片は6枚で,上部は外曲し,下部は花筒をつくる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のキチジョウソウの言及
【フッキソウ】より
…山地のやや湿った樹林下に小群をつくるツゲ科の常緑低木(イラスト)。北海道から九州まで分布し,中国にも産す。茎は横走する地下茎から斜上し,緑色で高さ20~30cmとなる。葉は倒卵状へら形で,上縁に粗い牙歯がある。質は厚く,表は深緑色で光沢がある。葉の寿命は通常2年で,当年葉~2年葉が階をなし,毎年伸長した茎の上部に群がって互生する。花期は3~5月。長さ2~5cmの穂状花序が頂生し,花をつけると仮軸分枝する。…
※「キチジョウソウ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by