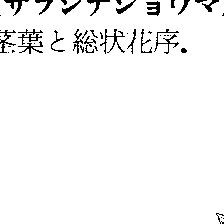サラシナショウマ
さらしなしょうま / 晒菜升麻
[学] Cimicifuga simplex Wormsk.
キンポウゲ科(APG分類:キンポウゲ科)の多年草。地下茎は太く横にはう。茎は高さ0.4~1.5メートル。根出葉は大形で3回3出複葉、小葉は卵形で鋭い鋸歯(きょし)があり、先端は急にとがる。8~10月、長さ約30センチメートルの細長い総状花序をつけ、白色で径約1センチメートルの花を開く。花弁、萼片(がくへん)は早い時期に落ち、白色の多数の雄しべが残る。温帯から亜寒帯の草原や林縁に生え、北海道から九州、および朝鮮半島、中国、東シベリア、カムチャツカ、樺太(からふと)(サハリン)に分布する。名は、若葉をゆでて水にさらして食べることによる。根を干したものを漢方では薬とする。サラシナショウマ属は北半球に約20種分布し、日本にはこのほかにイヌショウマ、ウスバミツバショウマの2種がある。いずれも果実は袋果で、鱗片(りんぺん)のある種子がある。
[門田裕一 2020年3月18日]
外面は黒褐色、内部は白色の根茎を漢方では升麻(しょうま)と称して、解熱、解毒、強壮剤として、麻疹(ましん)の初期、口舌の潰瘍(かいよう)、歯肉炎、脱肛(だっこう)などの治療に用いる。中国ではオオミツバショウマC. heracleifolia Komarov、フブキショウマC. dahurica (Turcz.) Maxim.の根茎も同様に用いる。
[長沢元夫 2020年3月18日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
サラシナショウマ (晒菜升麻)
bugbane
Cimicifuga simplex Wormsk.
山地の草原や林縁,まばらな落葉樹林のなかなどに生えるキンポウゲ科の大型の多年草。高さ1.5mに達する。よく発達した根茎があり,少数の根生葉をつける。根生葉と下部の茎葉は大型で,ふつう3回3出複葉,小葉は卵形で先がとがり,鋸歯がある。夏から秋にかけて,総状花序に多数の白色の花を密につける。萼片は4~5枚,長さ4~5cmで,早く落ちる。花弁は2~3枚で,萼片よりやや短く,先が2裂する。おしべは多数,白色で,萼片より長い。めしべは4~8本で,白色。果実は袋果で柄があり,数個の鱗片のある種子を入れる。シベリア東部,中国,朝鮮,日本の主として温帯・亜寒帯に分布し,小型のものは高山帯にもみられる。中国ではサラシナショウマ属Cimicifuga(英名bugbane)の数種の根茎が升麻と呼ばれ,薬用にされる。日本では主としてこのサラシナショウマが用いられる。解熱・解毒・消炎の効果がある。また若葉をゆで,水にさらして食用にすることがある。和名はこれに由来する。
執筆者:田村 道夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
サラシナショウマ(晒菜升麻)
サラシナショウマ
Cimicifuga simplex
キンポウゲ科の多年草で,アジア東部の冷温帯に広く分布する。日本全土の山地の樹下や草原に生える。高さ 1mにも達する。葉は3出を2,3回繰返す大型の複葉で,長い柄をもって互生する。葉柄のつけ根は膜質になって幅が広がり,茎を抱いている。7~8月,茎頂に長さ 20cmもの花穂を出し,多数の白色小花を密につける。個々の花には短柄があり,花弁は白い線形で早く散るが,多数あるおしべが白い糸状に残って瓶洗いのブラシのようにみえる。果実は袋果である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「サラシナショウマ」の意味・わかりやすい解説
サラシナショウマ
北海道〜九州,東アジア山中の草地にはえるキンポウゲ科の多年草。葉は大型で2〜3回3出複葉。夏〜秋,枝先に長さ20〜30cmの花穂を出し,小さな白色花を密につける。花には長さ5〜10mmの柄があり,多数の白いおしべが目だつ。後,小柄のある2〜7個の果実を結ぶ。近縁のイヌショウマは花に柄がなく,果実は1〜2個,小柄がない。オオバショウマは後者に似ているが,小葉の先がとがる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by