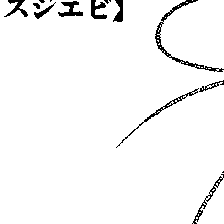スジエビ (筋蝦)
Palaemon paucidens
湖沼や流れの緩やかな河川にすむ甲殻綱テナガエビ科のエビであるが,テナガエビほど第2胸脚が長くない。体長約6cm。つくだ煮として食用にするほか,釣餌,魚類の天然餌料として重要である。無色透明で,頭胸甲に3~4本,腹部に7本の黒褐色の筋がある。胸脚の関節部は橙黄色。額角は頭胸甲より多少短く,ほとんど水平で,上縁に5~7本,下縁に2~4本のとげがある。千島,サハリン,日本全国,韓国に分布する。近縁のスジエビモドキP.serrifer,イソスジエビP.pacificus,アシナガスジエビP.ortmanniなどはすべて沿岸から浅海の岩礁にすむ。スジエビモドキは縞模様がスジエビに似ているが,額角上縁のとげが9~13本である。イソスジエビの縞模様は複雑である。アシナガスジエビの額角は頭胸甲長の2倍に達し,半前部が上方に曲がっている。いずれも食用や釣餌にされる。
執筆者:武田 正倫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
スジエビ
Palaemon paucidens
軟甲綱十脚目テナガエビ科。体長 5.5cm。額角は長く,上縁に 3~8歯,下縁に 1~5歯がある。淡褐色半透明で,頭胸甲の側面に濃色の複雑な縞模様があり,また腹部には七つの帯状紋がある。胸脚の各関節部は橙黄色。夏に 2回産卵する。卵数は 200~400個。分布は広く,ロシアのサハリン島から沖縄県の西表島までのおもに湖沼,河川にすむが,ときに汽水域でも見られる。海産の近縁種に比べて飼育が容易であるため,各種の生理学実験の好材料となっている。一般に川エビと呼ばれ,から揚げや佃煮にして食用にされるが,釣りのまき餌としても利用価値が高い。(→甲殻類,十脚類,節足動物,軟甲類)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
スジエビ
すじえび / 筋蝦
lake prawn
[学] Palaemon paucidens
節足動物門甲殻綱十脚(じっきゃく)目テナガエビ科の淡水エビ。体長5センチメートルほど。河川、湖沼などの流れがほとんどない所の砂泥底を好む。樺太(からふと)(サハリン)から九州、朝鮮半島に分布する。額角(がっかく)は頭胸甲よりわずかに短く、ほとんど水平で、上縁に3~8歯、下縁に1~5歯がある。第1、第2胸脚ははさみをもち、第2胸脚が長い。透明感のある淡褐色で、頭胸甲に3、4本、腹部に7本の濃褐色の線がある。産卵期は夏で、200~400個の卵を産む。幼生は11回の脱皮をするまで浮遊生活をする。寿命は3年。コサンエビやシラサエビなど地方名が多く、佃煮(つくだに)にされるほか、釣りの撒餌(まきえ)に利用される。
[武田正倫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by