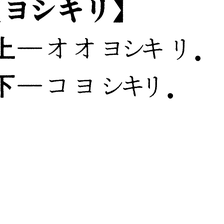ヨシキリ (葭切)
reed warbler
スズメ目ヒタキ科ウグイス亜科ヨシキリ属Acrocephalusの鳥の総称。約15種が含まれる。全長13~19cm。いずれも全体に褐色系のじみな羽色をしている。ヨーロッパ,アジア,アフリカ,オーストラリアに広く分布し,ヨシ原などの高茎草原にすむ。ヨシなどの茎を飛び移りながら,長い脚で茎に横どまりして昆虫やクモをとって食べる。草むらの中を潜行していることが多いので,さえずる雄以外は見ることが少ない。雄は草の茎の先のほうにとまって大きな声でさえずる。このグループの鳥は,外観はよく似ているが,さえずりは種によってかなりはっきりと違っている。日本で繁殖するヨシキリ類の中では,オオヨシキリA.arundinaceusはギョギョシ,ギョギョシ,ケケケケケ……とさえずり,コヨシキリA.bistrigicepsは,同様な節回しだが,もっと複雑で金属的な高い声でさえずる。オオヨシキリは,そのさえずりからギョウギョウシ(行々子)の別名をもつ。オオヨシキリは夜中にもしばしばさえずる。
巣は茎の間に枯葉を使ってつくり,深いわん形をしている。1腹の卵数は3~6個。巣づくりと抱卵は雌だけが行い,育雛(いくすう)は雌雄ともに行う。オオヨシキリの中には,一夫二妻で繁殖するものもいる。この類の巣は,カッコウにしばしば托卵される。北方で繁殖するものは,秋冬季温暖な地方に渡って越冬する。日本で繁殖する前記の2種は,夏鳥として5,6月に渡来し,9,10月に渡去する。台湾,東南アジア,フィリピンなどで越冬する。
執筆者:樋口 広芳
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ヨシキリ
よしきり / 葭切
葦切
reed warbler
鳥綱スズメ目ヒタキ科ウグイス亜科ヨシキリ属に含まれる鳥の総称。この属Acrocephalusの仲間には約25種があるが、それらは、和名からも、英名(葦原(あしはら)のムシクイの意)からもわかるように、おもに葦原などにすむ。ユーラシア、アフリカ、オーストラリアに分布し、渡りをするものが多い。日本には、夏鳥としてオオヨシキリとコヨシキリが分布する。一般に「ヨシキリ」または「ギョウギョウシ(行々子)」とよばれるのは、かならず葦原にすむオオヨシキリであるが、葦原周辺部の草原にもすむコヨシキリも混同されていることが多い。
[竹下信雄]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ヨシキリ
Acrocephalus; reed warblers
スズメ目ヨシキリ科ヨシキリ属の鳥の総称。43種からなり,オーストラリアムシクイ A. australis を除いてすべてアフリカ,ユーラシア大陸に分布するが,6種はすでに絶滅している。どの種も背面は黄褐色,緑褐色,灰褐色など一様な羽色をしていて,下面は黄褐色か黄白色で,全体に地味である。乾燥した草地,荒れ地,あるいは水辺のアシ原などに生息する。日本には夏鳥(→渡り鳥)としてオオヨシキリとコヨシキリが分布している。このほかにハシブトオオヨシキリ A. aedon など数種が迷鳥として記録されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ヨシキリ
ヒタキ科の鳥の一群の総称。日本にはオオヨシキリ(翼長8.5cm),コヨシキリ(翼長5.5cm)の2種が夏鳥として渡来。両種とも背面は淡褐色で腹面は黄白色,オオヨシキリはおもに水辺のヨシ原など,コヨシキリは低地から山地の草原にすみ,椀形の巣を作る。いずれも東アジアで繁殖し,冬は南方へ渡る。本州中部以南に多いのはオオヨシキリで,繁殖期にはヨシなどに止まってギョッ,ギョッとさえずるためギョウギョウシ(行々子)の名がある。カッコウによく托卵される。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のヨシキリの言及
【吉原雀】より
…長唄の曲をもとに作られたもので,《新吉原雀》ともいわれる。吉原雀はヨシキリの異名とされる。【浅川 玉兎】。…
※「ヨシキリ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by