コショウ (胡椒)
pepper
Piper nigrum L.
東インド原産のコショウ科の常緑つる植物。その実は最も古くから著名なスパイスの一つで,香辛味のほか防腐効果,食欲増進の効果などがある。古代ローマ時代のヨーロッパでは,シナモンとともに最も珍重され,コショウの粒は同量の銀と等価といわれた。コショウ貿易の利益の独占をめぐって,15世紀からのいわゆる大航海時代には,ヨーロッパ列強の東方進出,植民地争奪戦争などの事件が相次ぎ,世界史をゆり動かす原動力にもなったといわれる。
茎は7~8mに伸び,木質化する。節の部分はふくれており,下位の節から気根を出して他物にからみつく。葉は長さ10~15cmの卵形で革質,節に互生する。葉と対となる位置に約10cmの花穂がつき,雌雄異花あるいは同花で多数の小花が群がって咲き芳香がある。3~6mmほどの丸い果実が,長さ15~17cmに伸びた柄に房になってみのり,緑色から赤色になりさらに黒ずんで熟する。まだ青い未熟の果実を,房ごと収穫する。2日間日干しすると,しわがよって黒くなる。足で踏んで柄を除き,粒だけにしたものが黒コショウblack pepperである。完熟果を収穫するか,流水に漬けるかした後,乾かしてから摩擦によって果皮と果肉を除去し,灰白色の種子だけにしたものが白コショウwhite pepperである。コショウの成分はチャビシンで,1~3%含まれる。ピペリンも辛味成分になっているが,精製すると辛味を失う。香気成分は精油で,2%内外含まれる。繁殖はふつう挿木,ときには実生による。支柱にからませて仕立てる。2~3年目から収穫を始め,手入れがよいと25~30年も収穫が続けられる。赤道をはさんで南・北緯20°以内の地域でよく生育する。主産地はインドで,世界の1/3を生産し,スリランカ,インドネシア,タイ,マレー半島,西インド諸島,ブラジルなどでも生産される。
近縁種には,果実を長い穂のまま乾燥させて用いるナガコショウがあり,その一つのインドナガコショウP.longum L.はヒハツともいわれ,インド原産で栽培もされる。またジャワナガコショウP.retrofractum Vahl.もナガコショウの1種である。
執筆者:星川 清親
日本の利用史
コショウが日本にもたらされたのはかなり古いことで,天平勝宝8年(756)の《種々薬帳》(《東大寺献物帳》)に名が見えるように,はじめは薬種とされていた。しかし,獣肉や魚の料理に用いられたこともあったようで,後三条天皇はしばしばサバの頭にコショウをぬって焼いて食べたと,《古事談》は記している。いまでもトウガラシをコショウと呼ぶ地方があるが,トウガラシは渡来当初はコショウの一種と考えられていたらしい。《多聞院日記》文禄2年(1593)2月18日条には,〈コセウノタネ,尊識房ヨリ来。茄子タネフヱル時分ニ植トアル間今日植了。……惣ノ皮アカキ袋也。其内ニタネ数多在之。赤皮ノカラサ消肝了。コセウノ味ニテモ無之〉というくだりがある。もちろん,このコショウは赤トウガラシであるが,コショウの味ではないというのがおもしろい。元禄(1688-1704)ごろには薬屋で売られる一方,粉ザンショウなどといっしょにコショウの粉を売り歩く行商人があったことは,西鶴の作品などに見える。近松門左衛門の《大経師昔暦》に〈本妻の悋気(りんき)と饂飩に胡椒はお定り〉とあるように,江戸前期うどんにはコショウがつき物であった。後期になってそれが廃れたようで,大田南畝は〈近頃まで市の温飩に胡椒の粉をつゝみておこせしが,今はなし〉と《奴師労之(やつこだこ)》に書いている。
執筆者:鈴木 晋一
コショウ交易
コショウは古代から近世までの東西交易における主要商品であり,西ヨーロッパ,中国で珍重された。ペッパーpepperはサンスクリット語のpippali(ナガコショウ)が転訛した語とされるが,インド産のものが中央アジアの通商路を経由して中国にもたらされたため,〈胡〉の〈さんしょう(椒)〉とよびならわされた。ギリシア・ローマ時代には南インドのマラバル産コショウがインド洋の貿易風(ヒッパロスの風)を利用して輸出された。中世に入るともっぱらアラビア商人が独占的に扱った。15世紀末に新航路が開拓されると,ポルトガル,スペインなどは香料の獲得に力を入れ,マラッカ,キャンベイはその中継・集積港として栄え,また南インドのアラビア海沿岸の小海洋王国はコショウの輸出や関税収入を財源としていた。17世紀にはイギリス東インド会社がアジア貿易を一手に握り,コショウはアイ(藍),キャラコとともにインドからの主要な輸出商品となった。
→香辛料
執筆者:重松 伸司
コショウ科Piperaceae
熱帯を中心に8属300種ほどある科で,つる性あるいは草本状の低木になる。葉は互生,全縁で,花は花被をなくし多数が穂状に集まる。雌雄異花になったものも多い。子房には胚珠が1個,種子には胚乳がある。精油やアルカロイドを含み,キンマやヒハツのように薬用にされる種も多い。日本には,つる性常緑草本のフウトウカズラP.kadzura(Chois.)Ohwiが関東地方以南の暖地に分布している。またサダソウ属Peperomiaのいくつかの種はペペロミアの名称で観葉植物として多く栽培されている。
執筆者:堀田 満
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
コショウ
こしょう / 胡椒
pepper
[学] Piper nigrum L.
コショウ科(APG分類:コショウ科)の常緑藤本(とうほん)(つる植物)。インド南部のトラバンコール地方原産で、香辛料として古くから栽培されている。つるは木質化し、膨れた節があり、7~8メートル伸び、下位の節から気根を出して他物に絡みつく。葉は節に互生し、卵形、革質で長さ10~20センチメートル。葉と対(つい)のところに約10センチメートルの花穂がつき、多数の白色小花が群がって開く。花は単性または両性。果実は5ミリメートルほどの球形で、15~17センチメートルに伸びた果穂に房になってつき、初め緑色でのちに赤く熟し、完熟すると黒ずんだ色に変わる。
果実は成熟度(緑、赤、黒)によって成分や利用目的が異なり、グリーンペパー、黒こしょう、白こしょうとに分けられる。グリーンペパーは緑色の果実を摘み取り、缶詰や瓶詰にして利用する。黒く熟す直前の果実を房ごと収穫し、これを熱湯に浸(つ)けてから莚(むしろ)に広げ、足で踏むか手でもんで柄を除き、日干しあるいは火力乾燥したものが黒こしょうである。果穂の大部分が赤く熟したときに摘み取り、堆積(たいせき)するか、柄を除いてから数日間流水に浸けるかして果皮を除き、灰褐色の種子だけにして水洗、乾燥したものが白こしょうである。機械を使って黒こしょうの果皮を除いて白こしょうをつくることもある。
コショウの刺激性成分はチャビシンで1~3%含まれ、香気成分は胡椒油という揮発性の精油で2%内外含まれ、辛味の成分はピペリンというアルカロイドで5~13%含まれている。これらの成分の4分の3は果皮に含まれるので、香りと辛味は黒こしょうが強く、白こしょうは上品な香りと柔らかい辛味をもっている。
繁殖は普通は挿木による。苗を本畑に植え、支柱に絡ませて育てる。2、3年目から収穫ができ、一年中収穫できるが、収穫後に乾燥させるため、真夏の雨のない季節が適期である。赤道を挟んで南・北緯20度の地域でよく生育する。主産地はかつてはインドであったが、2000年以降、ベトナムでの生産量が増え、世界の3分の1を生産する。インド、ブラジル、インドネシア、マレーシア、スリランカなども産地である。
こしょうは、ヨーロッパでは紀元前400年ころから知られた香辛料の一つで、176年、アレクサンドリアでのこしょうの取引にローマ帝国が関税をかけたという記録がある。古代ローマ帝国の時代、産地インドから、海路と陸路を2年がかりでヨーロッパに運ばれ、こしょう粒の末端価格は同じ目方の銀と同じ価格であったといわれる。いかにこしょうが貴重品であったかがうかがわれる。15世紀ころからのヨーロッパの東方進出、植民地争奪戦争の一つの原因は、こしょう貿易の利益の独占にあったといわれ、こしょうは世界史を揺り動かす原動力にもなった。
[星川清親 2018年7月20日]
こしょうは、香辛味のほかに防腐効果もあるので、利用価値は非常に高い。「塩・こしょう」といわれるように、世界中の家庭の台所の常備品になっている。さまざまな料理に広く用いられるが、とくにソーセージの製造に不可欠とされる。粉にひいてあるものと、粒のままのもの(ホール)が市販されている。使用するつど粒をひいて用いたほうが、香りも優れ辛味の効きもよい。ピクルスや煮込み料理には粒のまま用いることもある。料理の種類や好みによって、黒こしょうと白こしょうを使い分けるとよい。グリーンペパーはステーキのソースやワイルドライス(アメリカマコモの果実)料理に入れる。近縁のインドナガコショウR. longum L.はロングペパーとよばれ、香りが強く甘味もあり、インドカレーの香辛料とする。薬用としては辛味性健胃薬として用いる。駆風、強精の効もあるという。
[星川清親 2018年7月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
コショウ
いうまでもなく、世界中で使われている「スパイスの王様」。
薬用の歴史も古く、インドの伝統医術アーユルヴェーダでは、コショウは体の老廃物や脂肪を燃焼させ、血管を浄化する薬。また、ギリシャのヒポクラテスは、「コショウとはちみつと酢を混ぜたものは婦人病によく効く」と述べています。
コショウにはおもに抗菌、食欲増進、消化促進、健胃、駆風(くふう)(腸管内にたまったガスの排除)、発汗促進、利尿、鎮痛といった作用があります。
具体的症状としては、食欲不振、消化不良、胃弱、吐(は)き気(け)、腹部膨満、歯痛などに有効。
○外用としての使い方
コショウの粉と米粒を練り合わせたもので下腹部を湿布すると、排尿をうながすのに役立ちます。
ただし、刺激が強いので十分に注意する必要があります。
〈色によって異なる風味の使いわけがポイント〉
○食品としての使い方
コショウには、完熟前の実を発酵させたあと、乾燥した黒コショウ、完熟した実の皮をむき、乾燥した白コショウ、完熟前の実を凍結乾燥、もしくは塩水に漬けたグリーンペッパーがあります。
ちなみに、赤いピンクペッパーは西洋ナナカマドの実で別種の植物です。
このうち、もっとも風味が強い黒コショウは、下ごしらえやストレートな辛みがほしいときに好適。風味のやわらかな白コショウは、料理の仕上げに用いるといいでしょう。
グリーンペッパーは、さらに風味がマイルド。ピンクペッパーもほとんど辛みはなく、ともに料理の彩りに使われます。
出典 小学館食の医学館について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「コショウ」の読み・字形・画数・意味
【姑 】こしよう(しやう)
】こしよう(しやう)
【孤 】こしよう
】こしよう
【胡 】こしよう
】こしよう
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 
コショウ(胡椒)【コショウ】
ペッパーとも。インド原産といわれるコショウ科の常緑性つる植物で,古くから熱帯アジア各地に栽培。茎は木質で,節ごとに出る根で他物にからまり,高さ8mにも達する。葉は革質で濃緑色。雌雄異花だが,時に両性花を生ずる。果実に強い香気と辛味があるので古くから香辛料として貴重視され,中世の西洋では通貨の役を果たしたという。完熟前に果実をとり,その熟度の高いものを発酵,流水にさらし外皮をとって白コショウとし,未熟のものを乾燥し黒コショウとする。白コショウが高級とされるが辛味は黒が強い。ソース,ケチャップなど西洋料理に広く愛用。
→関連項目健胃薬|香辛料|嗜好作物
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
コショウ(胡椒)
コショウ
Piper nigrum; pepper
コショウ科の常緑多年生つる植物で,南インド原産。高温多湿の熱帯雨林によく育ち,インドネシアなど東南アジアやブラジルで広く栽培されている。茎は長さ 5m以上,直径1~2cmに達し,節ごとに根を出して他物にからみついて伸びる。雌雄異株で,通常は3~4月と8~9月に垂れ下がった穂状花序を生じ,多数の白色の小花をつける。果実は直径 5mmぐらいの球形で赤く熟し,強い香気と辛みがあって,古くから香辛料に用いられている。成熟前の果実を皮ごとに用いたものが黒胡椒で,また完熟した果実の果皮や果肉を取除いて種子だけから製したものが白胡椒である。いずれも粉末にして料理の香辛料やソーセージ製造用など用途は広い。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
コショウ
[Piper nigrum].コショウ目コショウ科の植物の種子を乾燥したもので,スパイスとして広く用いられる.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のコショウの言及
【香辛料】より
…ただし,薑蒜類としながら蒜(ひる),大蒜(おおひる)などと呼ばれたニンニクやネギは除かれ,これらは別に葷菜(くんさい)類としてまとめられている。その薑蒜類には,辛夷(こぶし),蘭 (あららぎ)などいまでは使わぬものや,クルミのようなものも交じっているが,あとはショウガ,サンショウ,ワサビ,からし,タデ,橘皮(たちばなのかわ)といったものが並び,これらにトウガラシとコショウを加えると,おおむね近代以前の日本の香辛料は尽くせることになる。もう一つ〈こにし〉という珍しい名があるが,これは胡荽(こすい),胡
(あららぎ)などいまでは使わぬものや,クルミのようなものも交じっているが,あとはショウガ,サンショウ,ワサビ,からし,タデ,橘皮(たちばなのかわ)といったものが並び,これらにトウガラシとコショウを加えると,おおむね近代以前の日本の香辛料は尽くせることになる。もう一つ〈こにし〉という珍しい名があるが,これは胡荽(こすい),胡 と書き,コエンドロの古名である。…
と書き,コエンドロの古名である。…
【香料】より
…現代以前の香料は,小アジア,アラビア,東アフリカからインド,スリランカそして東南アジア,中国の西南部にかけての熱帯アジアに産した各種の植物性と若干の動物性の天然香料からなる。そしてそれらは,後に述べるように焚香(ふんこう)料,香辛料,化粧料の三つに大別される。これらの香料は,人類の歴史にあって古くより東西の文化圏に需要され伝播された。したがって主要香料の原産地の究明とその需要・伝播の解明はとりもなおさず東西の文化交渉の歴史を明らかにする手だての一つであろう。…
【中国料理】より
…中華料理とも称される。中国語では料理は〈菜〉と表し,〈菜単〉とはメニューを指す。中国各地方の料理,さらに宗教に由来する〈素菜〉(精進料理),〈清真菜〉(イスラム教徒の料理)などをふくめて中国料理という。
【特色】
中国料理は世界に類のない長い歴史と普遍性をもった料理である。一般的にどの国の誰が食べてもうまい料理として,フランス料理とともにあげられる。それぞれブルボン朝,明・清王朝などの宮廷料理から発達しており,洗練されつくした国際性の高い料理といわれる。…
【トウガラシ(唐辛子)】より
…第1は1542年(天文11)ポルトガル人が伝えたとするもの(佐藤信淵など),第2は1605年(慶長10)とする説(橘南谿(たちばななんけい)など),第3は秀吉の朝鮮出兵,つまり文禄・慶長の役(1592‐98)の際,種子を持ち帰ったとするもの(貝原益軒など)であるが,どうやら第3説が正しいようである。トウガラシの語が見られるのは《毛吹草》(1638)あたりからであるが,《多聞院日記》文禄2年(1593)2月18日条には,明らかにトウガラシである物がコショウとして記載されている。それは,コショウの種と称する物をもらったというのだが,その種はナスの種のように小さく平らで,赤い袋の中にたくさん入っており,その袋の皮の辛さには肝をつぶしたというのである。…
【肉食】より
… ところで,日本人の多くが肉食を避け,あるいは嫌ってきたことは,香辛料の使い方に大きな影響を与えた。たとえば,コショウは奈良時代以来輸入されていたが,室町時代以後うどんの薬味とされたくらいで,いっこうに用途がひろがらず,トウガラシが伝来するとまもなくその薬味の座をあけ渡してしまった。また,どういう使い方をされたのか不明だが,[コエンドロ](コリアンダー)が天皇の食膳に供されるために栽培されていたことが《延喜式》に見えるが,その後はまったく使われた形跡がない。…
※「コショウ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 

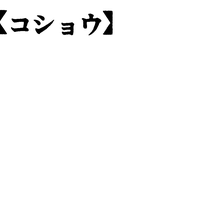




 】こしよう(しやう)
】こしよう(しやう) 舍に與ふ
舍に與ふ  (すなは)ち嫁して留
(すなは)ち嫁して留 すること
すること (なか)れ 善く新姑
(なか)れ 善く新姑 に事(つか)へ 時時、我が故(もと)の夫子を念(おも)へ
に事(つか)へ 時時、我が故(もと)の夫子を念(おも)へ 】こしよう
】こしよう 】こしよう
】こしよう