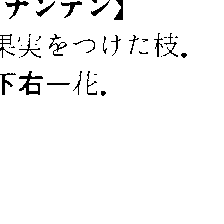ナンテン
なんてん / 南天
[学] Nandina domestica Thunb.
メギ科(APG分類:メギ科)の常緑低木。茎は叢生(そうせい)する。葉は大形の数回羽状複葉、小葉は披針(ひしん)形で全縁。6月ころ、茎の先に大形の円錐(えんすい)花序をつくり、多数の白色花を開く。萼片(がくへん)、花弁とも3枚ずつ輪生し、萼片は多数、花弁は6枚で光沢がある。雄しべは6本、葯(やく)は縦に裂ける。雌しべは1本、子房は1室で2、3個の胚珠(はいしゅ)がある。果実は球形、赤くてよく目だつ。果実の白い品種をシロミナンテンという。中国では野生するものが知られるが、日本産のものは野生か栽培の逸出したものかはっきりしない。ナンテンは、メギ科のなかでは、花被片(かひへん)の諸性質、胚珠や、花粉の形態、染色体数などにおいて特異で、ナンテン科として別科にする見解もある。ただしメギ科を特徴づける雌しべの構造、また分子系統の解析においては、メギ科に含まれる。
[寺林 進 2019年9月17日]
ナンテンは鎌倉時代から記録され、藤原定家(ていか)は1230年(寛喜2)、中宮権大夫(ちゅうぐうごんのだいぶ)が前栽(せんざい)に植える、と『明月記』に書き留めた。金閣寺の夕佳亭(せっかてい)には、ナンテンの床柱が使われたとの伝承がある。いけ花では最古の花道書『仙伝抄(せんでんしょう)』にすでに取り上げられている。元禄(げんろく)(1688~1704)のころには普及し、園芸品種が作出され始め、『草木錦葉集(そうもくきんようしゅう)』(1829)には斑入(ふい)りを中心に41の品種が載る。明治年間には120品種に増えたが、その後衰退し、現在は40品種ほどが維持されている。
ナンテンは難転に通じるとして、縁起植物に扱われ、盗人、火災、魔除(まよ)けに植えられた。京都鞍馬寺(くらまでら)の祭事、竹伐会式(たけきりえしき)や火祭りにはナンテンの小枝を身につける。ナンテンは果実にドメステチンメチルエステル、樹皮にナンジニン、ドメステンベルベリンなどの成分を含む。防虫、防腐の効果があり、葉を食物の掻敷(かいしき)に使い、古くは米櫃(こめびつ)や鎧櫃(よろいびつ)などに入れた。なお、「ナンテンの床柱」といわれているものは、普通イイギリなどの別種の材である。
[湯浅浩史 2019年9月17日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ナンテン (南天)
nandin
sacred bamboo
Nandina domestica Thunb.
生垣,庭木として日本人にはなじみ深い,赤い果実が特徴的なメギ科の常緑低木。高さ1~3m,株は叢生(そうせい)する。茎はあまり太くならない。葉は,数回羽状複葉で互生し,小葉は長さ3~7cm,春の芽ぶき時や秋~冬にかけて,紅くなる傾向がある。初夏,茎の先端に大型の円錐花序をつける。花は白色で,多数の鱗片状の萼片,6枚の花弁,6本のおしべ,1本のめしべからなる。葯は他のメギ科植物と異なって,縦裂開する。子房は1室で2~3個の胚珠がある。果実は秋~冬にかけて赤く熟し,美しい。果実が白っぽいものをシロミナンテンとして品種で区別している。中国中央部,日本(中部以西)に野生しているのが知られているが,自生のものか栽培品の逸出したものかはっきりしない。果実を日本では南天実(なんてんじつ),中国では天竺子(てんじくし)と称し,アルカロイド,ドメスティンdomestineを含み,民間では喘息,百日咳などの鎮咳薬として用いられる。樹皮や根皮も,胃病,脱肛,眼病に効きめがある。ナンテンは〈難転〉に通ずるということで,縁起木として好んで栽培される。シロミナンテン,キンシナンテン,フジナンテンなど,葉や果実の色の変化により多くの品種が区別されている。
ナンテンはメギ科では,花被の形態,胚珠の形態,葯の裂け方,染色体数,その他いくつかの点で特異で,別科ナンテン科とする見解もある。
執筆者:寺林 進+新田 あや
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ナンテン(南天)
ナンテン
Nandina domestica
メギ科の常緑低木。インドおよび中国の原産。日本では栽培されたものが広がり中部以南の山野に自生する。高さ 2mぐらいでほとんど分枝せず,葉は茎先に集ってつく。大型で3回羽状複葉となり,小葉は披針形ないし細めの楕円形で長さ3~7cmある。6月頃,茎頂に円錐花序を直立し,白色6弁の星形の小花を多数つける。晩秋に球形の果実が赤く熟し,紅葉も美しいので観賞用として庭木,鉢植にされる。園芸品としては実の白いシロナンテン,淡紫色のフジナンテンなどがあり,ほかに小葉が密生し切り花によいササバナンテンなどもあるが,種としては1属1種で,ときにはメギ科から独立してナンテン科とされることもある。果実を干して鎮咳剤として用いる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ナンテン(南天)【ナンテン】
中国と日本中部以西に分布するメギ科の常緑低木。日本のものは自生かどうかはっきりしない。庭木,切花,鉢植にされる。茎は群出し,高さ2m内外に直立する。葉は3回羽状複葉で,小葉は狭卵〜披針形。6月,枝の先に円錐花序をつけ,径6〜7mmの白色花を多数開く。秋〜冬,球形の液果が鮮赤色に熟して美しい。果実が白色のシロミナンテンや,淡紫色のフジナンテン,葉変り品のキンシナンテンなど園芸品種が多い。果実はドメスティンなどのアルカロイドを含み,鎮咳などに用いられる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by