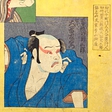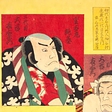日本大百科全書(ニッポニカ) 「大谷友右衛門」の意味・わかりやすい解説
大谷友右衛門
おおたにともえもん
歌舞伎(かぶき)俳優。現在8世まである。
初世(1744―1781)大坂生まれ、屋号山科屋(やましなや)。大坂の敵役(かたきやく)大谷広八の弟子の大谷友三郎が1766年(明和3)に改名。のち江戸に下り、あいきょうのある敵役として人気者となり、大坂下りの平敵(ひらがたき)・友右衛門のイメージを定着させた。
2世(1769―1830)これより屋号は明石屋(あかしや)となる。大坂の敵役谷村虎蔵が江戸に下って1795年(寛政7)襲名。化政(かせい)期(1804~1830)の敵役で、三都で活躍した。
4世(1791―1861)大坂の狂言作者出来島(できしま)専助の子。2世の門弟で、師の没後江戸に下り、1832年(天保3)襲名。同じ時期に京都で襲名した3世(1783―1839、2世の門弟)と一時期2人の友右衛門がいた。4世は風采(ふうさい)があがらず、立敵(たてがたき)には適さなかったが、平敵に長じ、幕末の異能俳優として活躍した。とくに『天下茶屋(てんがぢゃや)』の元右衛門役にくふうを凝らし、「友右衛門の元右衛門か元右衛門の友右衛門か」といわれ、単なる端役にすぎなかった元右衛門の役を格上げして今日まで伝えた。
6世(1886―1943)本名青木八重太郎。中村鷺助の子、5世中村歌右衛門の弟子。1920年(大正9)襲名。立役(たちやく)。
7世(1920―2012)6世の養子。女方。4世中村雀右衛門(じゃくえもん)の前名。
8世(1949― )7世の長男。本名青木知幸。1964年(昭和39)襲名。立役、女方(おんながた)を勤める。
[古井戸秀夫]
改訂新版 世界大百科事典 「大谷友右衛門」の意味・わかりやすい解説
大谷友右衛門 (おおたにともえもん)
歌舞伎俳優。1766年(明和3)に,敵役大谷広八の門弟大谷友三郎が友右衛門と改名したのにはじまる。8世までのうち,4世,6世が有名。(1)4世(1791-1861・寛政3-文久1) 大坂の狂言作者出来嶋専助の子。幼名福蔵。2世友右衛門に入門,大谷福蔵と名のる。のち大谷万作となり,1832年(天保3)11月江戸河原崎座に下り友右衛門を襲名。35年8月江戸中村座での《天下茶屋(敵討天下茶屋聚)》の安達元右衛門が大好評で,〈元右衛門が友右衛門か,友右衛門が元右衛門か〉と言われるほどのできばえだった。(2)6世(1886-1943・明治19-昭和18) 本名青木八重太郎。東京浅草猿若町に生まれる。中村鷺助の子。1893年5世中村芝翫(しかん)(後の5世歌右衛門)に入門。同年9月浅草吾妻座で中村翫兵衛を名のり初舞台。98年から子供芝居で活躍,中村おもちゃと改名。その後中村駒助,中村東蔵を経て,1920年4月市村座で,師の許しを得て友右衛門を襲名。名脇役として重んじられたが,鳥取の大地震で罹災死した。(3)7世は4世中村雀右衛門の前名。8世はその長男である。
執筆者:落合 清彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
新撰 芸能人物事典 明治~平成 「大谷友右衛門」の解説
大谷 友右衛門(6代目)
オオタニ トモエモン
- 職業
- 歌舞伎俳優
- 生年月日
- 明治19年
- 出身地
- 東京
- 経歴
- 5代目中村歌右衛門の弟子であったが、師の許しを得て、大正9年6代目友右衛門を襲名。芸熱心で知られ、名脇役と称された。
- 没年月日
- 昭和18年 9月11日 (1943年)
- 家族
- 養子=中村 雀右衛門(4代目)(人間国宝)
出典 日外アソシエーツ「新撰 芸能人物事典 明治~平成」(2010年刊)新撰 芸能人物事典 明治~平成について 情報
20世紀日本人名事典 「大谷友右衛門」の解説
大谷 友右衛門(6代目)
オオタニ トモエモン
明治〜昭和期の歌舞伎俳優
- 生年
- 明治19(1886)年
- 没年
- 昭和18(1943)年9月11日
- 出身地
- 東京
- 経歴
- 5代目中村歌右衛門の弟子であったが、師の許しを得て、大正9年6代目友右衛門を襲名。芸熱心で知られ、名脇役と称された。
出典 日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)20世紀日本人名事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「大谷友右衛門」の解説
大谷友右衛門(6代) おおたに-ともえもん
明治19年6月1日生まれ。中村鷺助(さぎすけ)の子。5代中村歌右衛門の門弟となり,明治26年東京浅草吾妻座で初舞台をふむ。中村駒助,5代中村東蔵をへて大正9年市村座で6代を襲名。芸熱心で,名脇役,とくに老役(ふけやく)として活躍した。昭和18年9月10日巡業中,鳥取地方におきた地震にあい死去。58歳。東京出身。本名は青木八重太郎。屋号は明石屋。
大谷友右衛門(3代) おおたに-ともえもん
寛政5年生まれ。中山舎柳の門弟となり,大坂の芝居にでる。文化9年江戸森田座で演じたのち,14年都座で2代嵐三八とあらためる。文政11年大坂にもどり,2代大谷友右衛門の門人となり嵐舎丸と改名。天保(てんぽう)2年京都で3代を襲名。敵役として活躍した。天保10年11月7日死去。47歳。京都出身。初名は中山門三。屋号は明石屋。
大谷友右衛門(5代) おおたに-ともえもん
天保(てんぽう)4年生まれ。4代大谷友右衛門の次男。天保9年江戸河原崎座で子役として初舞台。のち立役(たちやく)となり,京都,大坂に出演した。慶応元年5代を襲名。同年江戸にもどり人気役者として活躍。大谷紫道をへて明治3年5代大谷広次を襲名。明治6年2月1日死去。41歳。江戸出身。初名は大谷友松。屋号は明石屋。
大谷友右衛門(2代) おおたに-ともえもん
明和6年生まれ。谷村楯八の門にまなび,天明5年大坂角丸芝居の「曾我物語」の近江(おうみ)小藤太をつとめて初舞台をふむ。寛政2年江戸にいき中村座で活躍し,7年桐座で2代を襲名。敵役の名優として知られた。文政13年閏(うるう)3月24日死去。62歳。初名は谷村虎蔵。俳名は此友,金轡。屋号は明石屋。
大谷友右衛門(初代) おおたに-ともえもん
延享元年生まれ。大谷広八の門にはいり,大坂浜芝居の出羽(でわ)座,亀谷座で修業する。明和2年京都で「二代鑑」の鬼ケ岳を演じて好評をえる。のち江戸にいき,市村座で実悪の上手として活躍した。天明元年8月16日死去。38歳。初名は竹田友三郎。前名は大谷友三郎。俳名は此友。屋号は山科屋。
大谷友右衛門(4代) おおたに-ともえもん
寛政3年生まれ。2代大谷友右衛門に弟子入りし,大坂浜芝居で評判をえる。天保(てんぽう)2年江戸河原崎座で4代を襲名。6年「天下茶屋」の安達元右衛門で好評を得,以後敵役の名優として活躍した。万延2年1月6日死去。71歳。大坂出身。初名は大谷福蔵。前名は大谷万作。屋号は明石屋。
大谷友右衛門(8代) おおたに-ともえもん
昭和24年2月23日生まれ。4代中村雀右衛門の長男。昭和34年2代大谷広太郎を名のって初舞台,39年8代を襲名。はじめ女方から出発したが,その後立役(たちやく)も演じる。52,54年国立劇場奨励賞,平成11年松竹会長賞。東京出身。本名は青木知幸。屋号は明石屋。
世界大百科事典(旧版)内の大谷友右衛門の言及
【敵討天下茶屋聚】より
…江戸での初演は1816年(文化13)閏8月の桐座。のち35年(天保6)中村座で上演のとき,4世大谷友右衛門が元右衛門の役に工夫を加えた。浮田の家中早瀬玄蕃は,東間三郎右衛門に殺される。…
【中村雀右衛門】より
…(4)4世(1920(大正9)‐ )本名青木清治。6世大谷友右衛門の子。大谷広太郎,7世大谷友右衛門から64年雀右衛門を襲名。…
※「大谷友右衛門」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...