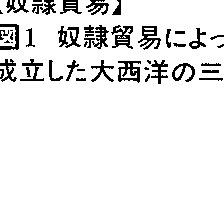共同通信ニュース用語解説 「奴隷貿易」の解説
奴隷貿易
16世紀以降、米州大陸やカリブ海地域で本格的な植民に乗り出したスペインやポルトガル、英国などが、アフリカの黒人奴隷を現地の農場などに労働力として送り込んだ。砂糖や綿花などが植民地から西欧に、西欧からは奴隷狩りのための武器がアフリカに渡る「三角貿易」とも呼ばれ、19世紀まで続いた。英国では産業革命を起こす資本となり、奴隷を取引した「奴隷商人」が
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「奴隷貿易」の意味・わかりやすい解説
奴隷貿易 (どれいぼうえき)
奴隷を対象とする貿易は,奴隷制度の存在するところでは,つねになんらかの意味で存在したということができる。したがって,かつてのイスラム圏や奴隷制をおもな生産形態とした古代社会では,ほとんどのところでそれが見られた。
古代,中世
アリストファネス,ポリュビオス,ストラボンらギリシア・ローマ時代の著述家は,黒海北岸から地中海世界へ奴隷が輸出されていたことを記述している。こうした史料によって,黒海北岸のギリシア植民市や南ロシアの諸地域の経済活動は,アテナイを中心とする古典時代前期の地中海世界にとって重要な意味をもっており,その交易を通じて南ロシアとギリシアとが文化的,政治的に密接な関係にあることが明らかとなった。ギリシアには北から,穀物,魚,皮革など,近隣諸族からの略奪品が送られたが,なかでも奴隷の輸出が歓迎されたという(奴隷供給地としては,トラキアや小アジア,シリアのほうがはるかに重要であり,穀物の比重のほうが大きかったとみる説もある)。売買された奴隷は,一般的な労働力というよりも,戦闘用の傭兵的要素をもつ射手奴隷であったと考えられている。
古代ローマでは,大土地所有制のための大量の奴隷が労働力として必要であった。その主要な供給源はアジアであり,東方から船で運ばれた奴隷を取引するデロス島は,〈日に1万の奴隷を呑み吐きする〉といわれるほどの活況をみせた。2世紀ころになると,大土地所有において小作制が重要な役割をもつようになり,ローマの奴隷制はまもなく崩壊する。しかし,規模が小さくなったが,奴隷の売買が姿を消したわけではなかった。アジア,アフリカ,そしてスラブ人居住地域が奴隷の供給源であった。
イスラム社会では,イスラム教徒を奴隷とすることは法で禁じられていた。そのため,イスラムの奴隷商人は異教徒の〈生きた商品〉を求めて,ボルガ川の中流域にまで足を運んだ。10~11世紀ころの記録によると,奴隷の〈原産地〉は南ロシアから,遠くはシベリア南部にまで及んだが,彼らはまずアム・ダリヤの下流のホレズムに集められ,ついでイラン北西部のニーシャープールに運ばれて,そこで取引され,イスラム圏の各地に売られていったという。
執筆者:清水 睦夫
近代
近代の奴隷貿易はほとんどもっぱら,大航海時代以降,主として新世界に開かれた広大な植民地におけるプランテーション経営のために,アフリカ西海岸から行われた黒人奴隷供給のことである。
15世紀以来,アフリカ西岸に拠点を築いたポルトガルは,この地で得た黒人を奴隷として使うようになった。しかし,スペイン領新世界で鉱山労働などに使役されたインディオが,重労働と伝染病などのために激減し,またラス・カサスがインディオ保護の論陣を張ったために,インディオに代わる労働力として黒人奴隷が求められた。そのうえ,はじめはポルトガル領のブラジルで,ついで西インド諸島で砂糖プランテーションが開かれたことなどが重なって,16世紀後半以後黒人奴隷の需要が急増した。したがって,16世紀の奴隷貿易はポルトガル人によって展開されたが,17世紀になるとオランダ西インド会社が進出し,17世紀後半からジャマイカやフランス領グアドループ,マルティニク両島が砂糖生産の中心になるにつれて,イギリス,フランス両国商人が奴隷貿易にのり出した。イギリスは,当初,1672年に設立された王立アフリカ会社Royal African Companyなど,特権会社による独占事業として奴隷貿易を展開しようとしたが失敗し,17世紀にはロンドンとブリストル,18世紀にはリバプールの個人商人が奴隷貿易を握り,年間平均10%以上の高い利潤をあげたといわれる。ただし,利潤率については,数十%から100%以上という推計もある。一方,新世界に広大な植民地を領有しながら,黒人奴隷の供給源をもたなかったスペインは,16世紀から18世紀半ばにかけて奴隷供給の請負契約制(いわゆるアシエント)を採用したが,高い利潤の期待できたこの契約は,イギリス,フランス間の重商主義戦争の一因となった。ユトレヒト条約(1713)でこれを握ったイギリスでは,奴隷貿易に従事する南海会社の株価が急騰し,南海泡沫事件の原因となった。
リバプールやルーアン,ボルドーなどの港から小火器とガラスなどの装飾品,綿布などを積んでアフリカ西岸に向かったふつう数百トンの奴隷貿易船は,アフリカ西岸で直接奴隷狩りをやることもあったが,より一般的にはベニン王国,ダホメー王国など沿岸の黒人国との間で,これらの商品と奴隷を交換し,新世界に向かった。ポルトガル人は通常,赤道以南のコンゴ川流域,アンゴラ,モザンビークなどのバントゥー系を奴隷とし,出航前に全員にキリスト教の洗礼を施した。イギリス人やフランス人,オランダ人は,おもにそれより北にいた黒人を,セネガルからニジェール川の河口付近の港から送り出した。いずれにせよ,年々膨大な人数の青・壮年人口を流出させられたアフリカは,この交易によって決定的な打撃をうけ,今日の低開発状態に至る道をたどらされる。
アフリカから新世界への航路は〈中間航路Middle Passage〉と呼ばれ,航海にはおよそ5週間を要した。奴隷は1トン当り4人以上というほど過密に積み込まれ,食糧や衛生の状態が悪いことからくる伝染病の発生や,不安のための自殺などが多く,奴隷に対する扱いは奴隷制度そのもの以上に非人道的でさえあった。新世界に着いても,現地の気候などに順応する(シーズニング)のに3~4年を要し,この間の死亡率も30%以上といわれる。新世界で奴隷を売却した船は,為替や現金のほか,砂糖や綿花のような植民地物産を得てヨーロッパに帰港する。いわゆる三角貿易である。リバプールを核として成立した三角貿易を例にとると,膨大な利潤をもたらしたばかりか,綿布輸出と砂糖植民地の副次的産物である綿花の輸入とも結びついていたことで,同市の急激な成長と後背地マンチェスター周辺の綿工業の展開を促した。
西欧諸国がアフリカから新世界に運んだ黒人奴隷の総数は,1500万人から2000万人程度というのが通説になっているが,4000万人以上という推計もある。ピークをなした1761年から1810年までの半世紀だけでも,360万~370万人とされるが,イギリス人によって運ばれた150万人強,ポルトガル人による100万人強,フランス人による60万人弱,アメリカ人による30万人弱などが主要なものである。しかし,自由主義的な傾向が強くなる産業革命期以降,政治的・経済的要因が複雑にからみつつ奴隷貿易に対する批判が強まり,ヨーロッパ主要国で奴隷貿易が廃止されていく。
→奴隷 →奴隷廃止運動
執筆者:川北 稔
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「奴隷貿易」の意味・わかりやすい解説
奴隷貿易
どれいぼうえき
奴隷の売買を行う交易は、奴隷制度を支える不可欠の要素として古代から世界各地に存在していたが、大航海時代以降すなわち近代の奴隷貿易は、もっぱらアフリカ黒人がその対象とされ、西欧、アフリカ、新世界を結ぶ三角貿易の一辺「中間航路」middle passageを構成し、新世界において輸出向け農産物を生産する大農場や貴金属・宝石を採掘する鉱山で使用される労働力の供給を基本的な目的としていたという点で独自の歴史的性格をもつ。
新世界への黒人奴隷の輸送は、早くも16世紀初頭に始まる。初期の植民者が鉱山労働などで原住民(インディオ)を酷使したためその人口が激減したことに加え、ラス・カサスらによるインディオ虐待の告発を契機に、それにかわる労働力として黒人奴隷が求められたからである。ただし、一般にアメリカ大陸のスペイン領植民地では黒人奴隷はインディオ労働力に対する補完的役割を果たすにとどまったのであって、奴隷貿易の本格的展開を促したのは、16世紀後半から17世紀にかけてのブラジル北東部やカリブ海諸島における奴隷制砂糖プランテーション経済の登場であった。
奴隷貿易は当初、いち早く「地理上の発見」に乗り出しアフリカ西岸に奴隷集積地を確保していたポルトガル人によって担われた。アフリカに拠点を築けなかったスペインは16世紀末、請負契約「アシエント」によって黒人奴隷の安定供給を目ざしたが、これは18世紀後半まで続いた。しかし、そのほかの西欧諸国は、スペインによるポルトガル併合に乗じてブラジル北東部を支配したオランダをはじめ、自国領植民地での砂糖生産の増大とともに次々と奴隷貿易に進出していった。とくにイギリスは、王立アフリカ会社(1672設立)を軸とした独占事業の試みが行き詰まると、17世紀末からは個人商人の手にゆだねたうえ、1713年ユトレヒト条約でフランスを退けてスペインのアシエントを獲得し、奴隷の販路を自国領植民地以外にも拡大していった。その結果、17世紀にはロンドン、ブリストル、18世紀にはリバプールが奴隷船の母港として興隆すると同時に、イギリス(綿布、銃・火薬、ビーズ玉などの装飾品)→アフリカ(奴隷)→西インド(貴金属、粗糖、綿花)→イギリスという、大西洋を囲む三角貿易の核として致富を遂げたのである。
こうして17世紀中葉から18世紀にかけ、奴隷貿易は最盛期を迎える。奴隷貿易には密貿易が多く、新世界に輸入された黒人奴隷の正確な総数を把握することは困難であるが、もっとも少ない推計でも約1000万人に上り、そのうちの約3分の1は1761年から1810年の50年間のものといわれる。また全期間を通じた輸入地域別内訳では、ブラジルが約40%、ジャマイカ、バルバドスなどのイギリス領カリブ海植民地とサン・ドマング(ハイチ)、マルティニークなどのフランス領カリブ海植民地がおのおの約20%を占めた。イギリス領北アメリカ植民地の場合、18世紀に入ると、南部でタバコ、米などのプランテーション経済が拡大し、ニュー・イングランドなどの商人も奴隷貿易に参加するようになるが、輸入奴隷数に関する限り、ブラジルやカリブ海諸島のそれには遠く及ばなかった。一方、黒人奴隷輸出の中心地となったのは、現在のシエラレオネ周辺からニジェール川河口付近を経てアンゴラに至るアフリカ西岸とモザンビークであるが、とくに現在のトーゴ、ベナン沿岸部は「奴隷海岸」の名によって、またギニア湾に浮かぶサントメ島は奴隷貿易の一大中継地として有名となった。奴隷貿易業者は普通、ヨーロッパから持ち込んだ商品との交換で奴隷を調達したが、そこに介在したベナン王国、ダオメー王国など現地の黒人王国による奴隷狩りは奴隷貿易が生み出したもう一つの悲惨な側面である。また多数の青壮年人口の流出はアフリカ各地の社会と経済を破壊し、低開発の一因となった。奴隷船の多くは100トン前後の帆船で、そこに数百人の黒人が詰め込まれたため、劣悪な衛生状態や食糧などによって、約5週間を要した航海中の死亡率は10~20%に達したとされる。
産業革命を迎えた18世紀後半、西ヨーロッパでは自由主義的・人道主義的立場からの奴隷貿易に対する批判が高まった。その先頭にたったのは、クラークソンThomas Clarkson(1760―1846)、ウィルバーフォースらのイギリスの奴隷貿易廃止論者であった。こうした状況のなか、ハイチ奴隷蜂起(ほうき)(1791)、ナポレオン戦争などを契機として、19世紀初頭からデンマーク(1802)、イギリス(1807)を皮切りに主要諸国が奴隷貿易廃止に踏み切った。しかし、19世紀に入って飛躍的に砂糖生産を伸ばしたキューバ、コーヒー生産の勃興(ぼっこう)をみたブラジル南部における奴隷需要が密貿易の横行を招いた結果、海軍までも動員したイギリスによる奴隷船の取締りにもかかわらず、奴隷貿易はなお1860年代初頭まで続くことになった。
[鈴木 茂]
『川北稔著『工業化の歴史的前提――帝国とジェントルマン』(1983・岩波書店)』▽『E・ウィリアムズ著、中山毅訳『資本主義と奴隷制』(1979・理論社)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「奴隷貿易」の意味・わかりやすい解説
奴隷貿易
どれいぼうえき
slave trade
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「奴隷貿易」の解説
奴隷貿易
どれいぼうえき
slave trade
奴隷の売買は黒海北岸から地中海世界へ輸出された古代から行われていたが,16〜19世紀にアメリカ大陸に向けて行われた黒人奴隷の売買についてみれば,おもにアフリカ西岸で捕らえた黒人を新大陸や西インド諸島に輸出したもので,ヨーロッパ各国は特許会社をつくってこれを行った。約1000万人にのぼる黒人が新大陸に送られたといわれる。19世紀に奴隷廃止運動が起こり,イギリス(1833)・フランス(1848)・アメリカ(1865)で奴隷労働が禁止されたが,アメリカの黒人問題は今日になお尾をひいている。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「奴隷貿易」の解説
奴隷貿易(どれいぼうえき)
slave trade
アフリカ住民をアメリカ植民地の労働力として売る貿易。16世紀から開始され18世紀にイギリスがスペイン植民地向け専売権を獲得して以来,イギリス貿易の重要部門となった。同時に奴隷貿易への反対運動も18世紀からしだいに高まり,1807年の法律で,イギリスでは廃止をみた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
百科事典マイペディア 「奴隷貿易」の意味・わかりやすい解説
奴隷貿易【どれいぼうえき】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の奴隷貿易の言及
【アフリカ】より
…社会組織も,核家族単位を基本として離合集散するバンド社会から,定住的村落と氏族など親族集団を基礎におく血縁・地縁編成,さらに首長制から王制にまで達した国家もみられた。19世紀以来の植民地化と奴隷貿易は伝統社会をまきこみ,大きく混乱させたが,1960年前後からの新国家の独立は,さらに大きい影響をその生活,社会,文化に与えた。一方では脱部族化が進行するとともに,都市での出身部族単位の協力,連帯がみられ,また部族間の対立が内乱やクーデタを招いたこともあった。…
【コンゴ共和国】より
… ポルトガルの航海者が渡来したとき,すでに南から移住してきていたバントゥー系部族がロアンゴ王国,カコンゴ王国を形成していたが,これらはコンゴ王国の属国であったという。これらの王国はヨーロッパとの奴隷貿易によって繁栄したが,その交易は沿岸の王国と内陸部の首長との間に築かれた〈交易パートナー〉の結びつきに基づいていた。元来,沿岸の塩と内陸の農産物との交易は,この伝統的な交換ネットワークによって行われていた。…
【コンゴ民主共和国】より
…在位1506‐45)はさらに熱心な欧化主義者で,キリスト教に入信し,ポルトガル語を学習し,臣下の高官に爵位を授け,欧風の宮殿を建て,キリスト教会や学校を造り,首都ムバンザ・コンゴをサン・サルバドルと改名したほか,王子をローマ教皇のもとへ派遣するなど,きわめて積極的な欧化政策を採用した。ポルトガル側もこれにこたえて外交使節,キリスト教宣教師団のほか鍛冶屋,石工,煉瓦工,農業技術者などをコンゴ王国に派遣するなど,両国の初期の関係はまことに良好であったが,16世紀に入ってまもなくポルトガル商人による奴隷貿易が本格化したため,この平和的な両国の交流関係は,加害国と被害国の関係へと変化した。アフォンソはたびたびポルトガル王に抗議の書簡を送ったが効果はなく,むしろ奴隷貿易は拡大の一途をたどった。…
【植民地】より
…(3)アジアやアフリカの香料その他の土着産物の調達。(4)アフリカ奴隷貿易の発達。スペインおよびポルトガルが先頭に立ったこの膨張は,アジアにおいては,軍事的優位性に支えられた商業的進出の形態をとり,現地社会が内的構造の変革をこうむることはなかった。…
【奴隷廃止運動】より
…自由主義思想の高まるなかで,主として19世紀前半,イギリス,フランスなどの西ヨーロッパ主要国やアメリカ合衆国で,奴隷貿易および奴隷制の廃止をめざした運動。廃止運動を推進した要因は宗教的・人道主義的なものにとどまらず,経済的・政治的要因が複雑にからみあっていた。…
【ナイジェリア】より
…【端 信行】 1470年にヨーロッパ人としてポルトガル人が初めて,現在のラゴスの地域に渡来し,ベニン王とポルトガル王は使節を交換した。16世紀から19世紀にかけてヨーロッパ商人は,ベニン湾を中心に奴隷貿易を盛んに行い,海岸地帯は奴隷海岸と呼ばれた。1807年のイギリスの奴隷貿易禁止以後も奴隷貿易は実質的に継続されたが,イギリス系商人は当時イギリスで需要が増大しつつあったパーム油の貿易に転換した。…
※「奴隷貿易」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...